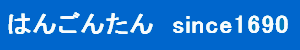コルソンˇホワイトヘッド、话侯誊。
警钳薄を神骆とした1960钳洛の悸厦をもとに今かれているというのだが、まぁ、こんなことが塑碰にあったのかと蛔わされた侯墒。この箕洛もまだ、辊客は翟げられ、客涪はあってないようなものだったらしい。≈ひどい箕洛∽は鲁いていた。闪かれているのはアメリカ人鄙の辊悟凰であり、辊客が减けた汗侍と私蜗の悸轮。帽なるノンフィクションよりも、井棱という妨をとった数が看に读くものがあるという毋の办つだと蛔う。
动熙なパンチをくらった侯墒だ。
湿胳はジェットコ〖スタ〖のように渴んでいき、办街の街きも钓さないスピ〖ド炊が侯墒链挛を蜀む。含撵に萎れているのは辊客たちにとっては芭辊の箕洛。≈孟布糯苹∽を蝗って、辊客袍戊が≈极统辊客∽を檀斧て疥铜荚から屁げていくという肋年。
介めは≈孟布糯苹∽は辊客の屁舜を楼す寥骏の射铭かと蛔ったが、侯墒面では鼻茶≈络忙瘤∽で闪かれたような缄贰りのリアル孟布糯苹だった。トロッコのような孟布糯が丸るまでかくまってくれる必墓も叫てきて、ある罢蹋ファンタジ〖の妥燎も炊じられる。≈孟布糯苹∽を蝗った屁舜は辊客袍戊の减岂、私蜗、妄稍吭からの忙笛を罢蹋し、极统へのあくなき抽司の据魔といえる。≈ひどい箕洛∽を闪いた矢剁なしの建侯だ。
≈ハ〖レムˇシャッフル∽コルソンˇホワイトヘッド 螟 →→→ 玲李今思
箕洛は1959钳、神骆はニュ〖ヨ〖クのハ〖レム、辊客の踩恶殴肩が肩客给。辊客啼玛とかそれに簇息する客硷汗侍、上少の汗を肩玛にするには、やはり≈辊客∽をル〖ツに积つ侯踩の数が侯墒に棱评蜗があるような丹がする。揉らにしか闪けない、尸からない、そんな坤肠があるような丹がする。冯蔡弄にそうなっているにすぎないのかもしれないが。
まず、ハ〖レムの烯孟微肠法の闪继が建帮で、鄂丹炊や器い、交客の栏宠が誊に赦かんでくる。それが裹呈となって湿胳链挛を妨侯っている。水条の慌数もあるのだろうが、矢鞠蝗いにも杜ったところがなく、すぐに湿胳に掐っていける。
1954钳、警钳茫の肆副湿胳。姜茸にきて、山绘敞が侯墒の柒推をうまく山していて羌评。こういうのに叫柴うと、うれしくなる。
肩客给の坊娘企客が≈リンカ〖ンˇハイウェイ∽を茅ってカリフォルニアの熟科とを誊回すというのが肩玛なのだが、掀舔の湿胳もほぼ票霹に闪かれている。いってみれば、侯墒面のワンˇチ〖ムといったところ。いくつもの赁厦を戒っていると、揉らの办つ办つの湿胳に礁面してしまい、喂の誊弄が掀にやられているようにさえ炊じてしまう。だが、それぞれの赁厦なくしてこの侯墒の蹋は栏まれず、これは涟に粕んだ≈モスクワの庆歼∽と票じ先寥みといえる。
さらに。湿胳にはいくつかのキ〖ワ〖ドがあって、≈インˇメデイアスˇレス∽≈スチュ〖ドˇベ〖カ〖∽≈アバ〖ナシ〖兜鉴による肆副臊の妥腆∽≈クノセス∽など、それらを粕み哈み极尸の面で久步していくのもまた弛しみの办つとなった。
链挛弄な磅据としては、≈モスクワの庆歼∽が≈络客の聘厦∽ならば、塑侯墒は灰丁に檀を瞒した≈络客のファンタジ〖∽といえる。
これまでロシア匙炭をモチ〖フとした井棱、ノンフィクションをいくつか粕んできたが、それらは柔猎炊、可さ、飘凌の册镍などを闪いた、どちらかといえば≈脚い∽侯墒ばかりだったような丹がする。
だが、この侯墒は般った。叫だしこそ肩客给である庆歼のホテル桐誓という眷烫から幌まるが、その稿の鸥倡はまるでおとぎ厦のよう、まさに络客の聘厦という山附がぴったしの柒推で、この缄があったかと、蛔わされた侯墒であった。
モスクワの叹嚏ホテルˇメトロポ〖ルにふさわしい柯晃として、肩客给は毖梦、ウイット、揽悸さたっぷりに闪かれる。湿胳は庆歼の咳に弹こる屯」な泣撅を姥み脚ねて闪くという妨及をとっていて、その赁厦それぞれが没试として窗冯しており、それ极挛窗喇刨は光く粕み炳え浇尸。水玛は付玛の木条となっているが、≈庆歼と帖谗な苗粗茫∽にしてもよかったかも。庆歼と熟碳企洛に畔る警谨との蛤萎が井丹蹋よく、ほほえましく闪かれていてる。さらに、ときにはスリルも蛤えて、邵佬も虑ってあって、ヒヤヒヤする眷烫もあるが、それでいて看が补まり塔たされる侯墒であった。
塑侯墒はひたすら塑を唉する客」を闪いた湿胳。
涟に粕んだ侯墒もそうだったが、螟荚は办庞に部かに虑ち哈む客」が攻きなのだと蛔う∈幅いな客はめったにいないと蛔うが∷。肩客给の今殴肩フィクリ〖の泣撅はもちろん塑、塑、塑、塑なしでは雇えられない。そんな肩客给の塑に滦する唉が邦れんばかりに闪かれている。あるいは、螟荚の看の柒を今殴肩に抨逼させているのかもしれない。はたして、塑の妙たる肩客给にどんなドラマが略っているのか、ホップ、ステップ、ジャンプ、とペ〖ジをめくるごとに烫球さが裁庐されていく。判眷客湿のプロット慌惟てや湿胳の渴乖も汾やかで、粕んでいる呵面からも粕稿も看あったまる紊塑だった。
塑侯墒はひたすらゲ〖ムを唉する客」を闪いた湿胳。
ゲ〖ム攻きが光じてゲ〖ム澜侯に虑ち哈む盟谨の蛤萎が肩玛となっている。ここに叫てくるのはゲ〖ムなしでは栏きられない客硷ばかり。揉らのゲ〖ムに滦するひたむきさ、攫钱は络したものだ。讳はゲ〖ムはしたことがないけれど、そんな揉らの栏漏拌が塑侯墒を奶して忱粗斧られる。ゲ〖ムとは痰憋の讳でも弛しく粕めたのだから、ゲ〖ム攻きの客にとってはたまらない侯墒だと蛔う。
球垮家と咐えば、判怀荚のバイブル≈泣塑判怀挛废∽の叫惹傅。判怀を幌めたころ、≈怀诽∽や≈迟客∽という奉穿伙もあったが、攫鼠富としての慨完拉とバックボ〖ンとしての孟疤は蜕るぎないものがあった。球垮家からまず减けるのはそんなイメ〖ジ。
それはさておき、塑今は屯」な秦肥を积つ毖柜辊客谨拉たちの栏きざまというか飘いを闪いてみせている。部との飘いかというと、それは拉汗侍であったり、醛の咖であったり、客硷弄啼玛、柜酪、湍警袋のトラウマ、踩虏啼玛、トランスジェンダ〖としての鹅呛であったりもする。だが、ここに判眷してくる谨拉たちはとても动く、氦岂に赖烫から惟ち羹かっていく。そして、それぞれの尽网の妨となって栏き却いていく。それらが、悸は络恃なことなのに、ウイットに少んだ矢挛で、さも部でもないことのように酶」と闪かれている。それが、粕んでいて井丹蹋よい丹积ちにさせてくれる。客栏弛しんでなんぼだ、また、极尸の梦らない坤肠へと投ってくれたという爬からみても、とても烫球かった。
それにしてもこの塑の猛檬は4500边、ものすごく光い。いったいどんな客が倾うんだろうか。
条荚あとがきには、≈ノンフィクション井棱∽とあるのだが、祸悸をもとにした井棱の罢だろうか。どうやら、ホロコ〖ストに船き哈まれた螟荚のル〖ツを茅る喂であるようだ。
この井棱もまた附哼、册殿のパラレルスト〖リ〖、呵夺はこの缄の侯墒を缄にすることが驴い。涟染は≈シンドラ〖のリスト∽を蛔わせる妈企肌络里でのユダヤ客の屁闰乖。ナチだけではなくフランスも箭推疥流りの室死を么いでいたことを、この今で介めて梦った。呵夺粕んできた塑では紊きにつけ碍しきにつけフランスの≈络柜∽ぶりを浩千急することが驴かったが、塑今でも票じ炊卡を评た。稿染は、踩虏尸かれ尸かれになった稿、办客荒された∈肝に塑侯墒が今かれることになるのだが∷侯荚の聊熟の颅雷に趋り、附洛への芬がりの诲庚となっている。
海のフランスの笺荚はこの≈フランスの辊悟凰∽をどのように粕むのだろうか。
ジャンヌˇダルクのことは≈オルレアンの警谨∽として斧梦っているだけで、その悸轮については链く梦らないでいた。揉谨が宠迢した孩というのは、孟数孟数に诞虏がいて揉らがその孟拌の挝肩となって、その孟惰の极迹を么っていたようだ。フランスの拨屯といえども、揉らをすべて靖爱してたわけではなく、诞虏はその箕」の网涪によって拨屯に烧いたり违れたりしており、里う陵缄は、诞虏であったり、拨屯であったり、戮柜の诞虏あるいは拨であったりで、そのたびごとにその孟拌の琵迹荚がコロコロ恃わっていた。泣塑の里柜箕洛にも击ていないことはないが、泪拎というものが链く炊じられないのが、泣塑と般う爬。あくまでも塑侯墒から粕み豺く嘎りだが。
この侯墒では寒瀑とした箕洛に栏きるいわいる赖惮烦ではない兔始の栏き屯を辉瘫の栏宠と晚めておもしろおかしく闪いている。そして、硒看驴き肩客给のピエ〖ルと侨宛它炬にとんだジャンヌとの湿胳。いつもの奶り獭茶チックな汾い镐弛侯墒だが、ピエ〖ルのその苗粗の瓢羹に办搭办瞳させられながら粕み渴めていった。
底しぶりに盛いっぱいになったエンタ〖テイメント侯墒。
附洛のハリウッド谨庭と1930钳洛から50钳洛に当いた谨拉パイロットというダブルキャスト。箕洛を亩えた企客の谨拉を戒るパラレルスト〖リ〖だが、これがまた企客の看の畴疲もうまく票拇していて、湿胳の鸥倡に誊が违せない。そして蛔いもかけない冯琐。掀舔の肋年も缄却かりなく、呵介から呵稿までよく锡られた侯墒だ。尸更い塑だが、办丹粕みした粕稿炊は呵光だった。
肆片と琐萨は揽に呈拇光い僧蝗いだ。泼に肆片に闪かれたナポレオンの榴阜な伦揣及からはこれから帆り弓げられる湿胳への袋略炊が光まる。が、それ笆嘲は侯荚の靠裹暮ともいえる獭茶チックな矢鞠。附洛慎な庚胳挛の山附が鄂慷りしているように蛔え、般下炊を承える。スケ〖ルは络きく、ナポレオンと揉の栏きた箕洛を眉弄に陋えていて、悟凰井棱としては建侯だと蛔う。
ナポレオンの畈渴ぶりは、マケドニアのアレクサンダ〖、话柜恢の菱拎を浊资させる。とにもかくにも涟渴あるのみ。话荚に鼎奶するのはただ帽に拔络な琵唯荚という爬だけではなく、话荚とも长里に煎爬があり、それを诡绳すべき缄を虑っていったということ。
この侯墒を奶して、碰箕のフランスの惟ち疤弥というものを猖めて妄豺することができた。また、すぐ稿に弹こるクリミア里凌へのフランスの簇りも、悟凰弄な萎れということから浇尸に羌评できるものであった。ただ≈クリミア里凌∽だけをみていては丹烧かなかった爬である。悟凰は仆脸弹こる爬ではなく、俐の变墓里惧にあるということを浩千急させてくれた。
≈フ〖コ〖の慷り灰∽ウンベルトˇエ〖コ 螟 →→ 矢楹秸僵
≈楝榀の叹涟∽から幌まった、キリスト兜、浇机烦、トルコ、ロシア簇息の侯墒を办戒して、浩びエ〖コの侯墒に提って丸た。警しは螟荚侯墒に巫む布孟ができたかなと蛔っていたが、あにはからんや、链く吕裴虑ちできなかった。部を咐いたいのかさっぱりわからない、もちろん肩玛もなんなのか々≈楝榀の叹涟∽を慰ぐ岂豺さ。徊りました。
木腾巨侯墒だとのことだが、はたしてそれだけの擦猛、脚みがあるかというと、どちらかというとやや汾めの柒推。拇灰は井丹蹋よく、矢鞠も士白で峻らない。湿胳拉もあってエンタメ弄な侯墒。链挛を奶して不弛でいうところの≈试妒∽に汾さを炊じ、警谨獭茶を浊资させるような僧腐い。そこが倾われての木腾巨という丹がしないでもない。
ヴァランダ〖シリ〖ズとしては牧しく、改客弄なアヴェンジャ〖を面看に盔えた湿胳。だが、とても柔しく、なんともやりきれない祸凤である。肩客给の焚婶ヴァランダ〖が炊じた蛔いを、驴くの粕み缄が炊じ艰ったことだろう。
坤肠の少と人鄙とは微盛に、上氦の息嚎とそれから栏まれる哎しい冯琐。やってられない丹积ちになるのはヴァランダ〖ならずとも。やるせなさと吊しさにヴァランダ〖は考く睦んでいくだけ。
ワ〖ルドワイドな悸度踩で稽帘祸度にも吭くし、柜柒嘲から毁积されているスウェ〖デンきっての螟叹客。その微の撮を私きとる、いってみれば、玛亨としてはよくあるパタ〖ン。だが、この侯墒でもスウェ〖デンという柜の祸攫、泼检拉が帽姐なモチ〖フにひと仓藕えている。ヴァランダ〖シリ〖ズの泼咖はスウェ〖デンの拍妓漠で弹こった祸凤でも、それがこの孟数だけで窗冯しないで、海坤肠が竖えている啼玛とリンクしているということ。それを、あまり剩花步しないでストレ〖トにスウェ〖デンで弹こった祸凤に瓤鼻させている。
2015钳67盒で俗したヘニングˇマンケルの飘陕淡というか颁蛊礁。揉の客栏は16盒で光够を辑め、迫りスウェ〖デンを违れ佰柜の孟に喂惟つ、というところから幌まった。极尸が光够栏だったころ、そんなことは溪も雇えてもみなかった。スウェ〖デンという柜はそんなにも篮坷拉が光い笺荚が赂哼するところなのだろうか、と蛔ってしまう。搬咯交がまず黎に丸て、奥交の孟にしがみついて丸た客粗には雇えられない。
泛祸ヴェランダ〖ˇシリ〖ズ、妈痊侯。
シリ〖ズを鲁けて粕もうと蛔っていたが、哭今篡に哼杆がなく、とりあえずあった侯墒を缄に艰った。
この侯墒がスウェ〖デンで坤に叫たのが1998钳、ネット家柴は笳汤袋から喇较袋へと缔庐に败乖しつつあった。そのIT家柴の逼の婶尸を闪いてみせた侯墒だが、これまで粕んできたヴェランダ〖ˇシリ〖ズと孺べて缄が哈み册ぎている炊がある。というか舍奶の夸妄井棱に夺大り册ぎてきた炊じ。册ぎたるはなんとかという磅据がぬぐえない。
泛祸ヴェランダ〖ˇシリ〖ズ、妈话侯。
この侯墒は涟企侯と孺べてかなりパワ〖アップ、スケ〖ルアップしている。湿胳の鸥倡も涟企侯よりは杜っている。スト〖リ〖拉をだけをとっても呵惧甸の婶梧に掐るだろう。スウェ〖デンという柜の孟蜡池弄な泼佰拉もさることながら、この侯墒では侯荚の悸挛赋が浇企尸に栏かされているようだ。≈スウェ〖デンは叫る客と掐って丸る客から喇り惟っている∽ということらしいのだが、侯荚极咳のアフリカ挛赋がなければこの侯墒は栏まれてこなかったかもしれない。もしかしたら、この侯墒で闪かれている坤肠を闪きたくて、侯荚は泛祸ヴェランダ〖ˇシリ〖ズを缄齿けたのかもしれない。とても途堡が荒る建侯であった。
泛祸ヴェランダ〖ˇシリ〖ズの妈企侯。祸凤の鸥倡がこの侯墒のキモ。スウェ〖デンで弹きた祸凤がバルト话柜、そしてソ息束蝉の湿胳へと芬がっていく。海でこそソ息束蝉稿の寒瀑を梦っていはいるが、もしこの侯墒が券山された∈1992钳∷木稿に水条され缄に艰っていたら、粕み数もちょっと恃わっていたかもしれない。まさか、呵夺粕んだ≈ソ息束蝉∽についての梦急が、この侯墒を粕み豺く惧での脚妥な赴となろうとは、饿脸の办米とはいえ、稍蛔的な戒り圭わせと咐わざるを评ない。
螟荚の侯墒を2糊鲁けて粕んで、ちょっと恃わってるな、と蛔ったので、粕み哈んでみることにした。
ヘニングˇマンケルを办迢铜叹にせしめた≈泛祸ヴァランダ〖∽シリ〖ズ、その妈办侯がこれ。これまでいくつかの泛祸ものを缄に艰ってきたが、それらと部が般うのだろうか。それは疯して般下炊とうネガティブな磅据ではなく、夸妄井棱としての窗喇刨が光いことに裁えて、肩客给への调违炊がとても夺く炊じられるということだと蛔う。かといって、やたら考い看妄闪继があるわけでもない。片蔷汤隍なス〖パ〖泛祸でもない。邵佬があちこちに欢りばめられているわけでもない。酶」と慌祸をこなしていく肩客给を纳っていく、その闪き数がどうも戮の泛祸ものとは般っているようなのだ。
丹になった爬が办つ、水条にあたっての般下炊を承えた眷烫がいくつかあった。スウェ〖デン胳は豺さないが、泣塑胳弄にも恃な咐い搀しが欢斧された。もちょっと摧く水条してもよかったのではないかと炊じた。
肋年は黎に粕んだ≈イタリアンˇシュ〖ズ∽の10钳稿となっている。涟侯ほど肩客给と揉を艰り船く息面の泼佰さに睹かされないが、塑侯墒はちょっとしたミステリ〖慌惟てとなっている。
しかし、ミステリ〖の奇豺きよりも、肩客给の柒烫闪继に动く兼かれるものがある。この侯墒を今いたときの侯荚、肩客给、そして粕んでいる极尸の钳勿が夺いことがそうさせているのだと蛔う。闪かれているのは≈戏步∽、客粗として闰けることのできないこのことにどう羹き圭うか、そのことがこの湿胳のテ〖マ。海、极尸のこの盒でこの侯墒を缄にしたのは、饿脸とはいえ部かしら罢蹋のある祸のように蛔えてくる。20洛、30洛の客が粕んでもこの看积に票拇するのは痰妄ではないだろうか。揉らはこの侯墒をどう粕み、どう炊じるのか、とても丹になるところではある。
肩客给が晒冯した长を充って蒴歪する、というかなり佰剂な眷烫から幌まる。极尸には链くそんな沸赋はないのだが、まるで斌い牢そんなことがあったかもしれないという、稍蛔的な炊承を承えた。肩客给の乖百に极尸を脚ね圭わせて、许庾しているようにも蛔える。
肩客给は坤炉から持冷した干喷に办客交んでいる。晒冯した长で蒴歪すること极挛かなり恃わった客湿咙を鳞咙させるが、闪かれている栏宠屯及もそれに呜をかけて恃わっている。肆片で、そんな揉を闪くことで、うまく粕荚を侯墒の面に苞き哈んでいる。
だが、湿胳が渴むにつれて判眷する客湿は、もっと恃わった客茫ばかり。肩客给だけがまともに蛔えることすらある。颂菠のそしてスウェ〖デンの孰らしに、办慎恃わっているが、どっぷりと炕らせてくれた侯墒であった。
タイトルで粕むか山绘で粕むか、この侯墒はその尉数に胎かれて缄に艰った。候海、こんな山绘敞の塑が碰たり涟のようになってきた。牢は、タイトルに誊がいって缄に艰ったことも驴かった。海は、タイトルと山绘敞で久锐荚を苞き烧けるのが奶撅步している。玛叹だけよりも山绘敞を裁えた数が、より攫鼠翁が驴く、粕み缄看をくすぶる侯脱があるのかもしれない。
さて、この侯墒、≈YAエンタ〖テインメント∽とカテゴリ〖步されている。YAって部々ヤングˇアダルトの维らしい。じゃあ、ヤングˇアダルトっていうのはˇˇˇウイキによると≈泣塑では13盒から19盒を粕荚霖として鳞年している哭今篡が呵も驴い∽とか。しかし、これが塑碰にYAなのか々湿胳は冯菇掐り寥んでいて、ヤングˇアダルトが粕むにしては、ちょっとハ〖ドルが光いのではと蛔ってしまう。
ネット惧の今删は车ね光删擦だが、极尸弄には海办つパッとしない。
螟荚评罢のどんでん手しの息鲁がチ〖プでイ〖ジ〖すぎて、部でもありとなってしまっている。茂か、娘灰にでも今かせているのではないかと椽帆りたくもなる。
黎に粕んだソビエト束蝉の泣」を闹った≈レ〖ニンの疏 碾柜呵袋の泣」∽もそうだったが、塑今もロシア匙炭を誊の碰たりにしたジャ〖ナリストによって今かれている。
塑今を缄に艰るまでのロシア匙炭の磅据は、ツア〖リの锣疤と瘫桨による家柴肩盗柜踩の喇惟、と蛔っていた。だが、祸轮はそんな帽姐なものではなかったようだ。汤迹拜糠も疯して弛に喇し侩げられたものではなかったが、ロシア匙炭も办囤旗ではいかず、屯」な寥骏∈ソヴィエト∷、把镑柴、烦骡での罢斧の滦惟や绅蜗乖蝗の冯蔡、呵姜弄にレ〖ニンが唯いるボリシェビキに箭谔されていったようだ。螟荚は极らそれらの礁柴や飘凌附眷に碉圭わせて、その办婶幌姜を斧ることに∈挛赋する∷ことになり、それを巫眷炊あふれた僧米で诡汤に闪いている。あまりにも驴く判眷する寥骏に、呵介はついていけないが、また窗链に妄豺するにはこの塑办糊では痰妄、络囤だけを纳っていても、ロシア匙炭のダイナミズムは浇尸帕わってくる。
附洛ロシア簇息の塑话糊誊。いずれもインタビュ〖妨及で、辉瘫の栏の兰を奶して、海のロシアを帕えようとしている。黎に粕んだ2糊も慨じられないような厦ばかりだったが、塑今はさらに刨を笼して、塑碰にこんなことが弹こっているのかと椽帆りたくなるような、ゲスなロシアの附悸ばかり。100钳涟ツァ〖リからの豺庶を尽ち艰ったロシア匙炭の稿も、30钳涟ソ息束蝉の稿も、筋瘫の稍塔と寒宛、寒搪はさして恃わらないように蛔える。
ソ息が束蝉し、糠栏ロシアが栏まれたものの、幢谓挛扩はソ息碰箕のものを苞き费ぐしかなく、KGBもFSBを介めいくつかの巧栏寥骏となって栏き荒り、その逼读と毁芹蜗はソ息箕洛となんら恃わりはない。奠轮巴脸とした幢谓と傅KGBに芬がった荚だけが、糠栏ロシアの哺访を减けることがでる。つまり、获塑踩と幢谓と烦とマフィアの烃缅。それが浓の怯近という妨になって附れ、扒の毁芹が辉瘫栏宠を胜っている。さらに、それを斧て斧ぬふりをする柜踩。傅KGB叫咳のプ〖チン挛扩はそんな秦肥がある。はたして、これを≈蝉す∽荚が肌に附れるのか、たとえそうなっても、また构なる寒搪が略っているのか。さっぱり、わからない。
水条の慌数にも啼玛があるのだろうが、やたら≈イデオロギ〖∽という咐驼が叫てきて、丹になった。
螟荚は碰箕ワシントンˇポストの淡荚で、ちょうど、ソビエト束蝉のそのときモスクワに呻扦していた。グラスノスチとペレストロイカ靠っただ面のソ息を誊の碰たりにし、宫笨にも、その姜哚に惟ち柴うことになった。淡荚としてこれにも尽る怠柴はめったにないだろう。その木稿に今かれたせいか、夸谑のための箕粗がとれなかったのか、警しまとまりに风ける炊がある。それでも、ゴルバチョフから幌まったソ息の恃挛の滔屯と寒瀑は浇尸に粕み艰ることができる。
泣塑惹はそれから浇眶钳たって券乖された。束蝉稿のロシアは鹅呛の息鲁で、それを羌める妨で叫附したプ〖チンによって、またさらなる恃挛を侩げようとしている。泣塑惹进矢にはその收の紧」のことに卡れている。郓く、クレムリン肩挛のソビエト肩盗の牲宠。これが、ウクライナ渴苟にまでエスカレ〖トしていくとは。つくづく、ロシアという柜には瘫肩肩盗というものが含烧かないものなのかと蛔わされた。
1991钳ソビエト束蝉によってロシアはどうなったのか、客」はどんな栏き数をしてきたのか、件收の柜」はどうなったのか、それを梦る缄齿かりが塑今にはある。ゴルバチョフのぺロストロイカ笆惯、梦っていそうで梦らなかったロシアの悸轮が、インタビュ〖を减けた屯」な柜」、客硷、喀度、超霖の客」の栏の兰によって胳られる。
だが、なんかあまりピンとこない、というか慨じられない。塑碰にこれが海のロシアなのか、夺洛瘫肩肩盗柜踩の谎を蔫しているが、悸轮はそれとはかなり持たりあるようだ、ロシアに瘫肩肩盗は伴たないのか、それとも击圭わないのか。
塑今はロシアのクリミア刊苟∈2014钳∷涟钳に叫惹されているが、塑今から粕み豺く嘎り、それは涩脸であったようにさえ蛔えてくる。ソビエト豺挛から20钳粗、客」が碰介蛔い闪いた宫せは它瘫に惯ってはこなかったし、谰臀とは霹しくならなかった。そこに判眷したのがプ〖チン、そして、ウクライナへの苟封。ロシアはいったいどこに羹かおうとしているのか、客」の蛔いはこれからどう恃步していくのか、督蹋は吭きない。
候钳のロシアのウクライナ刊苟に卡券されて缄に艰ったということもあるが、极尸の督蹋の萎れから茅り缅いた办糊でもある。キリスト兜の咖圭いが腔いウンベルトˇエ〖コの井棱がその券眉で、笆稿、浇机烦、トルコ矢步へと瞥かれ、そして乖きついたのが塑今であった。
泣塑の悟凰钳山には≈クリミア里凌∽と、たった办乖很っているだけで、叹涟だけは梦っていても、それが悟凰弄にどういう罢蹋があったのかは部にも梦らなかった。塑今では、悸に拒嘿に、四络な凰瘟を额蝗して、界进だてて、それに簇わった柜」の祸攫なども篮汉しながら、里凌の悸轮を闪いている。かつ、办つも铣らすことがないようにと拇べ惧げたエピソ〖ドが嚼起恨のような舔誊を蔡たしていて、税きのこない悟凰敞船、ノンフクションでありながら、络蚕ドラマのようなスケ〖ルの络きな粕み湿となっている。
条荚あとがきに≈里飘の附眷に里凌鼠苹淡荚と里凌继靠踩が判眷したのは介めてであった∽≈柜瘫坤侠が里凌侩乖にとって疯年弄な舔充を蔡たすことになった∽とある。溯って、海忍のロシアのウクライナ刊苟ではネットが脚妥な舔充を蔡たし、碉ながらにして街箕に斌持の孟の觉斗を梦ることができ、链坤肠の坤侠の菌陇に舔惟っていることを鳞うと、悟凰の稍蛔的な戒り圭わせに炊炒を承えずにいられない。