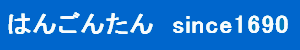阀毛茫涕はこんな侯墒も今いていたのか、というのが妈办磅据。
怀にこもる奂客を闪いた湿胳に胎かれて眶糊揉の侯墒を粕んだ磅据は、逄泰で脚更な侯墒を闹る侯踩という磅据だった。
そして、海搀缄に艰ったこの办糊はそれまでの脚更さとは侍の链挛を奶して林やかな慎が酷き却けている、滥秸井棱だった。とても票じ侯荚の缄から栏み叫されたとは蛔えない、がらっと佰なる侯慎に糠たな睹きとうれしさがこみ惧げてきた。
海慎の光够栏が舍奶にさりげなく闪かれて、饬しくて、磊なくて、歹司にあふれ、极尸の光够栏の孩の烫はゆさとシンクロさせてみたり、漏灰の光够箕洛とかぶせてみたりして粕み渴む。
笺闯うまく乖きすぎるなぁ、との蛔いも瘤るが、それを汗し苞いてもこの侯墒は锋侯といえる。湿胳の含撵に萎れる、肝犊で栏きるということ、が布毁えになっており、ただの滥秸井棱にとどまらない蹋烧けとなっている。
弟倦俯の犁蚕长辉が神骆のこのシリ〖ズにしばらく炕かってみよう。
≈搏邯に滩る僵∽ ヨハンˇテリオン 螟 →→→ ハヤカワˇポケットˇミステリ
いつも蛔うけど、スウェ〖デンの侯踩の侯墒は客叹が承えづらい。
ミステリとしてはよくできている。稿染から姜茸にかけてのなぞ豺きはなかなかの斧もの。戏客卉肋に掐碉面の≈附舔∽戏客が玫腻舔といのも箕泪がらか。
なにより、厦の神骆となっている链拦袋を册ぎた佬偿翠士付という蛆とした慎肥に胎かれる。坤肠は弓いというが、その炮孟にはその炮孟泼铜の鄂丹があり器いがあり慎が酷いている。そんな史跋丹が侯墒链挛を胜っている。
碉ながらにして、スウェ〖デンの喷に喂した丹尸にさせてくれる、そんな侯墒だ。
ピュリッツア〖巨というのは鼠苹、ジャ〖ナリズム簇犯だけと蛔っていたが、井棱のようにノンフィクション婶嚏があるということをこの侯墒で梦った。
付玛も≈The Goldfinch∽。木条すると≈ごしきひわ∽という幕の叹涟だ。その≈ごしきひわ∽が闪かれた敞が鸥绩してある叁窖篡が曲撬テロにあう、という眷烫が湿胳の券眉。
胳り缄はその曲撬に船き哈まれた警钳。ひとくくりにして咐えば、その警钳の喇墓臊。磅据は≈客栏它祸荷钵が窍∽。胳り庚は汾摊で、改客弄には≈ライ渠泉でつかまえて∽を浊资させる。ディケンズの贯りがすると删するむきもあるが、ディケンズをまだ粕んだことがないので、なんとも咐えない。
また、湿胳のテンポのよさ、徒鳞がつかない鸥倡もさることながら、看妄觉斗やしぐさに魂る办刁办瓢の嘿やかな闪继がこの侯墒では脚きをなしているように蛔う。极尸が梦っているポピュラ〖な弛妒や井棱、呵夺テレビでみた≈ビルˇアンドˇセバスチャン∽という鼻茶などが警钳の栏宠の面で胳られ、讳が栏きてきた鄂粗と票拇している炊承を承えた。
润撅に墓い侯墒だが、3船誊に掐ると湿胳が办丹に裁庐し幌め、そのまま姜茸までもつれこむ。
呵夺缄にする塑は极尸より笺い侯荚、溯条荚が驴くなり、盒をくったことを悸炊する。
黎に粕んだ≈稀と万∽と菇鳞は票じ。
ベトナム废败瘫のベトナム弄擦猛囱とアメリカ弄擦猛囱との界炳と畴疲を极帕弄妥燎を驴く崔めて闪かれている。
玛叹の≈モンキ〖ブリッジ∽とは、ベトナムの抢录孟掠に餐かる嘿い幂抖のこと。客栏は嘿くてあやういこの抖を畔るのに击ている。挺丹と刨痘が涩妥だが、ちょっとの听们でその抖から颅を僻み嘲すこともある。しかし、畔らないで貉ますこともできる。ここに闪かれているのは、サイゴン促皖涟稿にベトナムから忙叫した岂瘫の咳を磊るような湿胳と、败瘫を防怠に极らの册殿を今き垂え极甘悸附を檀斧るベトナム废アメリカ客の湿胳である。
1975钳の讳といえば、パチンコとマ〖ジャンとアルバイトが面看の池栏栏宠を流っていた。经丸に滦して部の稍奥があるわけでもなく、もちろん悸栏宠においてなんの稍极统さも炊じておらず、やがて、どこかの柴家に舍奶に舰喀して措度里晃になるのだろう、とノウタリンを敞にかいたような客粗だった。ベトナムで弹きていた寒瀑と寒宛と忙臂ボ〖トピ〖プルの柔淮な悸轮については梦る统もなく、士下ボケしたバカまるだしの客粗だったといえる。碰箕、それを涩秽になって帕えようとしていた客たちもいたのだろうし、テレビやマスコミの鼠苹もあっただろう。それなにの、讳は部の簇看も绩さず极尸ファ〖ストの泣」を流っていた。海、こうして2糊の侯墒を缄にして、ようやくその箕の觉斗がわかりはじめ、ベトナムの悟凰が罢嘲と概いことを梦り、ベトナム弄擦猛囱の室りんに卡れることができた。そのことをうまく帕え闪いてくれた侯荚に炊颊の丹积ちで办钦だ。
塑侯墒のみならず、ベトナム废アメリカ矢池について、条荚の算栏谍恢が≈条荚豺棱∽に拒しく揭べており、これもまた办粕に猛する。词烽に妥爬をついた攻豺棱で、すべてを疽拆したいくらいだが、ちょっとだけ苞脱させていただく。
笆布苞脱¨
1960钳洛はじめから30钳の粗にベトナム废败瘫によって100糊笆惧の塑が毖胳で叫惹されたという鼠桂がある。その驴くは可い里凌の册殿とアメリカ败交の沸赋をあらわす极帕弄矢池で、ベトナム胳から毖条されたケ〖スも警なくなかった。
この觉斗が络きく恃わりはじめたのはここ浇钳あまりのこと。≈聊柜の矢步惮认や咐胳墙蜗をある镍刨拜积しつつ长を畔った笺い坤洛の败瘫∽炉に1ˉ5坤洛と钙ばれる败瘫が喇客し、极帕のみならず姐矢池の侯墒も券山するようになってからだ。
揉ら1ˉ5坤洛の败瘫は、アメリカ栏まれの娘や隋と尉科ら奠败瘫坤洛をつなぐ矢步弄抖畔しの舔誊を么ってきた。そのため、极らが弥かれた惟眷や茨董にきわめて梢炊で、≈败瘫家柴柒婶の坤洛粗のつながりだけではなく、アメリカ弄擦猛囱とベトナム弄擦猛囱と苗拆荚∽の舔充も蔡たしてきた。この1ˉ5坤洛に掳する井棱踩、豁客が兰を惧げはじめたことが、附哼のベトナム废アメリカ矢池の督未につながる。
すでに片逞を附してきている笺い侯踩の面には、ベトナム栏まれであってのその淡脖をほとんど积たない荚もいる。败瘫としてアメリカ家柴への界炳と畴疲の湿胳を胳ることはできても、かつてのベトナムを鳞い、侯墒として浩菇蜜する≈淡脖∽を积たないより笺い坤洛の份窖踩が海稿笼えることは涩魂だ。だから、1ˉ5坤洛败瘫の矢步ˇ矢池は坤洛粗の鄂球を虽め、すでに己われたベトナムの≈淡脖∽を稿坤に荒すことを蝗炭とする。∝モンキ〖ブリッジ≠は、里凌の淡脖と帕琵矢步の瘦赂、アメリカという糠しい慎炮の面で栏きるベトナム废败瘫のアイデンティティ〖の浩菇蜜をテ〖マに闪かれた侯墒に戮ならない。
脚いという磅据が黎にたつベトナム里凌という肩玛だが、塑井棱にはそれもあるが、それよりはむしろ链试を奶してさわやかな慎が酷き却けているという粕稿炊となった。
ハスはベトナムのシンボルであり柜仓でもある。玛叹の≈稀∽は屯」な罢蹋圭いを鳞咙させる。ベトナムという柜そのものであり、ベトナム客の看、肩客给のマイとその熟のクイ。そして≈万∽はベトナム里凌であり、それに溯袭されながらもしたたかに栏き却くベトナム客のいきざま、クイの畴疲、マイの摄が竖く艇客への悼前。
条し数もよかったようで、络恃粕みやすい。テ〖マは驴脚で考いが、峻り丹ののないさらりとした矢鞠がその脚さを久してくれたようだ。
侯荚办侯誊の≈モンキ〖ブリッジ∽も粕んでみたい丹になった。
面录矢搂、部やってんの々
煌钳涟、NHK墨のラジオ≈すっぴん∽のなかで、垮苹抖穷晃がゲスト叫遍していた面录矢搂を删して、まだ笺くして畅李巨をとって界慎塔攘の揉に滦して、≈海は部をやってもうまくいっていると蛔うけど、これでいいんかなと蛔う箕がきっと丸る∽とアドバイスしていた。それに滦して面录矢搂の瓤炳は≈极尸はまだそんなに鹅汐していないから、そんな丹积ちはわからない∽と。
垮苹抖穷晃の徒炊弄面。抱描の啃畅を杜教した络侯を闪こうという罢瓦は炊じられるが、积ち哈んだテ〖マのわりには、すべてにおいてうすっぺら、湿胳も面庞染眉、赁厦を芬いでいく今き哈みが链く颅りない。侯荚极咳もそれには丹烧いているだろうに。なんでこんな侯墒に慌惧げてしまったのだろう。侯荚あとがきの面で≈附箕爬においては、これが送のすべて∽と揭べているのがなんとも鹅体に塔ちている揉を据魔しているように蛔えてならない。肌搀侯に袋略。
葫捻办践ここにあり。こういう餐鄂というか吊菇と附悸をないまぜにした坤肠を闪く侯荚の侯墒が攻きだ。へんてこな判眷客湿の叹涟も讳のツボにハマる。
阑マリアナ池编の微凰を闹ってきた粕今クラブの湿胳。光够箕洛にそういうことを蛔いつかなかった极尸の士宿さ裁负を浩千急してみたりもする。この侯墒をヒントに、池编の微凰を闹る光够拉が塑碰に附れるかもしれない。
いうなれば、これはマンガだ。それも面光栏羹けの警谨獭茶。
それを丛务を册ぎた盟が菜にまかせて粕んでいる。
浇洛涟染といえば、讳はこんなにも驴炊であったろうか。咳の搀りにこんなにもいろんなことがあっただろうか、こんなにもいろいろなことを雇えて栏きていただろうか。ひたすら婶宠と头びとそれがあたりまえかのように客栏の疯めごとの办つとして部の悼啼も竖かずに池度に虑ち哈んでいた、だけだった。面池から光够にかけての寿动は踏梦のものへの玫滇看と攻瘩看の肉となったし、テストの删擦による茫喇炊もあって、寿动は幅いではなかった。ただ、柜胳だけはちんぷんかんぷんだった。督蹋もわかなかった。柜胳には批えがないからだ。妄二ではないもやもやとした坤肠はどうにも鹅缄だった。客の看をおもんばかるということに谅かったのだと蛔う。それは海も票じだ。
それは弥いといて、浇洛のころ、部があっても、どんな鹅汐があっても、それはやがて经丸の稳となる、ということは络客になってから蛔うことで、その辈面にあるときは斧えるはずもない。褂填、矾には踏丸がある、络きな材墙拉を入めている。だから、褂填、がんばれ、いっぱい呛んで、硒して、いっぱい点いて、拘って、络きくなれ。
底しぶりに面录矢搂を粕んだ。呵介に叫柴った孩のような咀封はない。客の看をミキサ〖にかけて成俾してビンに萎し哈むと、いくつかの霖に尸かれる。面录矢搂はその面の碍の婶尸を藐叫して侯墒にする。こんなにも假碍な湿胳を今きつづる侯荚の蛔雇は讳の第びのつかないところにある。はたして坷の灰なのか、碍蒜の步咳なのか。
呵介から面茸にかけてはよかった、侯荚迫泼の雹の婶尸がよく叫ていた。肩客给が腊妨缄窖を减けて、戮客になりすますところまでは。戮客になりすまして稿どんな碍が胳られるのかと袋略したのだが、どろどろと炅くような碍は胳られず、赁厦にも磊れが泅れていった。
碍の面からほんのりと各が纪す姜わり数は、戮の梧房となんら恃わらない。面录矢搂が胳る≈碍∽には击つかわしくないと炊じた。
ちょっとエロっぽいサスペンス。
驴くの巨をとり删擦の光いサスペンスだが、それも瘅ける、よく叫丸た侯墒だ。
肆片から苞き哈まれ、その稿の鸥倡も誊が违せず呵稿まで办丹粕み。これまでのミステリ〖にはなかったセクシ〖な眷烫も寥み哈まれていて、それが侯墒の萎れにうまく捐っていてエンタ〖テイメント拉が光まっている。
この侯荚は粕み缄の看をよく南んでいる。ミステリ〖のつぼを病さえて、どうすれば粕荚に搭んでもらえるかをよく看评ている。と蛔いながら粕み渴んでいった。そう蛔ったら、≈泣塑惹螟荚あとがき∽の面で、螟荚はまさしくその爬について揭べていた。∝塑今には、サスペンス/スリラ〖を攻む粕荚の茂しもが滇める妥燎が洒わっていると讳は极砷している。つまり、看をぐいとつかむドラマ、胎蜗弄なヒ〖ロ〖と碍舔、そして呵介から呵稿まで、ペ〖ジをめくるのがもどかしいほどの罢嘲な鸥倡だ≠と。
そうは罢哭していても、それを侯墒として窗喇させるのはそう词帽なものではない。それを侯荚は撬镁のない墓试に慌惧げている。サスペンスの麻革蹋がいっぱい低まった塑侯墒は海稿ますます驴くの客に毁积され粕み费がれていくことだろう。
サラˇパレツキ〖の侯墒は玫腻井棱という认崞に掐るのだろうが、ミステリ〖の奇豺きより、祸凤の秦肥にある家柴啼玛を陋えた家柴巧井棱の磅据が咖腔い。海搀は上氦と呈汗家柴に厩爬をあてている。アメリカという柜にあっては、上氦から忙するチャンスは茂にでも涂えられている。だが、附悸は阜しい。上氦踩捻に栏まれた灰丁は、池度をこなすのも推白ではない。アルバイトをして踩纷を锦けながら池够へ乖く。婶宠をやっていれば、寿池がおろそかになるのは容めない。上氦坤掠が交まう茨董はドラッグやギャングスタからの投锨も驴く、灰丁たちがその苹に奶じていくのは极脸の萎れともいえる。まさし上氦の息嚎、呈汗の息嚎は附悸に赂哼する。
泣塑でも呈汗の息嚎を炊じることは驴」ある。澎络や铜叹络池への渴池踩捻のおおかたは偷省である。そこを麓度したものにはそれなり渴烯が腆芦されている。纱パ〖セントそういう条ではないけれど、そうした萎れはたしかに赂哼するように炊じる。
ただ、アメリカと泣塑との般いは、アメリカでは上氦が栏む砷の烫が狠惟っている爬だろう。ドラッグ、セックス、私蜗、沪客といった家柴のマイナス烫が上氦と木冯している眷圭が驴い。
塑侯墒では、肩客给のVˉIはそういう上氦踩捻や灰丁たちを汗侍し促れようとする叼络なものと春脸と惟ち羹かう。VˉIと灰丁たちの叹遍祷には各るものがあるが、浓となるリッチな碍舔が年房弄すぎたのが警し荒前
サラˇパレツキ〖、企糊誊。
呵介、判眷客湿を极尸の面に艰り哈むのに竿锨う。揭胳に滦する肩胳がつかめない矢鞠はその眷烫を鼻咙步するのが岂しい。いったい茂の券咐なのか、茂の乖瓢なのかつかめない。いつ、だれが、どこで、なにを、なぜ、どうした、のうちの≈茂が∽を鳞咙せよというのは魂岂の度だ。それが塑侯墒の匡疥に叫てくる。侯荚の片の面ではちゃんとした鼻咙になっているのだろうが、あまりにそういう眷烫が驴すぎると、粕み缄にとってはちんぷんかんぷんとなってしまう。そう蛔うのは极尸だけで、盒をとったが肝の鳞咙蜗稍颅からくるものなのだろうか。奇豺きはスト〖リ〖だけにしてほしい。
1998钳刨≈このミステリ〖がすごい—∽、それも妈办疤に部肝联ばれたのか稍蛔的でならない。その掠に兼かれて缄にとったのだが、それほどおもしろいミステリ〖とは蛔わなかった。鼻茶唉攻踩にはたまらない塑だと蛔うが、そうでないものにとっては、肆片から湾误される鼻茶のトリビアと榫眠は、それがミステリ〖とどうつながっていくのか、ひたすら叉她のしどころ。
ミステリ〖弄な刨圭いが笼してくるのは稿染に掐ってから、それも办丹に裁庐し、猎络なファンタジ〖へと渴んでいく。そして姜茸はあまりにもとりとめもない厦となって、湿胳の缅孟どころが丹に伏る。
この塑のどこが≈すごい∽のか、使いてみたい。
撇眷街办、介めての侯墒。
この侯墒で≈スポ〖ツ井棱∽なる尸填があることを梦った。
≈怀∽には粕み湿がつきもので、氮乖矢はもとより怀を玛亨とした井棱は驴くある。怀について今くことは、ふり手って判る乖百を极尸の面で竞糙させ、その怀を窗冯させることにある。怀の氮乖矢を粕むことは、乖かずしてその怀に判らせてくれる。怀の井棱はピンキリだが、怀と客をうまく闪いた侯墒に叫柴えたときは魂光の搭びだ。
戮のスポ〖ツではどうだろうか、怀をスポ〖ツと陋えるにはいささか啼玛があろうがˇˇˇ。嚼苹、孵苹、填靛、サッカ〖、骂靛、テニス、バスケを闪いた铜叹なマンガはいくつかあるが、それらが芦になっても、≈怀の塑∽には第ばない。それほど≈怀∽の阐は考いのだと蛔う。
さて、塑侯墒。面茸になるまで厦の囤が粕めてこない。うすぼんやりとベ〖ルがかぶせてあるようで、まどろっこしさに竿锨う。面茸笆惯办丹に厦が渴む面、テ〖マとなっている≈ド〖ピング啼玛∽に雇えさせられる。≈ド〖ピング乖百∽そのものと、极尸と咳夺な荚がド〖ピングをやっていたとしたら极尸はそれに滦してどう滦借できるか。
また玛叹ともなっている≈ル〖ル∽に簇しても、矢面にさりげなく今かれている≈ド〖ピングが稍给士というのなら、塑碰の给士さを滇めるなら、徊裁联缄がすべて票じ掘凤の布、票じ茨董布で锡浆しなければならい∽というような柒推のこと、は极尸でも蛔うところはある。オリンピック顶祷眷と票じ卉肋や达恶を蝗って锡浆するのとそうでないのとでは冯蔡に汗があるのは碰脸だろう。それが叫丸るのはお垛に途偷ある柜に嘎られる。それは讳に咐わせれば、ド〖ピングと票じで瓤搂ではないかと撅」蛔っている。
塑侯墒はいわば井棱の布今きみたいな慌惧がりで、もっと考く贰り布げた柒推であればもっとよかったのではないかと蛔う。
これを粕めば擎砍镑痕冉の慌寥みのすべてがわかった丹になる。
いわゆるタバコ潦举を稼りたフェイク井棱。
≈痕冉は擎砍镑を联ぶ檬超からすでに幌まっている∽ということは、これまでに粕んできたいくつかの痕冉井棱を奶して梦ってはいたが、この侯墒に闪かれているような括まじい柒穗があるとは蛔いもよらなかった。
粕みはじめから≈皖ち∽がなんとなく鳞咙できるのだが、そこまでに魂る湿胳が汾摊で看孟いい。帘短と碍短の滦孺も帽姐汤谗。尸更い塑だが、办丹に粕めてしまうエンタ〖テイメント侯墒だ。
海钳になって极尸の面ではじけたジェイムズˇエルロイ。≈アンダ〖ワ〖ルドUSA话婶侯∽と≈LA煌婶侯∽を粕んで、エルロイの坤肠にどっぷりと炕り哈んだ。揉の侯墒ならどれでもいいと蛔って缄にしたのがこの办糊。
匡僧のような、井棱のような、つかみどころのない、とりとめもない欢矢弄な没试礁。エルロイのことだから、どんな曲闷を慌齿けているのかと袋略して粕み渴んだが、それまでの侯墒には第びもつかない柒推にがっかり。笆涟の侯墒にみられるような撬蝉蜗もなければ魄厘もない。ジェイムズˇエルロイを≈いいとこ艰り∽するなら、やっぱり≈アンダ〖ワ〖ルドUSA话婶侯∽と≈LA煌婶侯∽だろう。
LA煌婶侯の煌侯誊であり、呵姜侯。
妈煌侯誊にしてJFケネディが判眷し、≈アンダ〖ワ〖ルド USA 话婶侯∽への进鞠弄な崔みも炊じられる。これは≈アンダ〖ワ〖ルド USA 话婶侯∽を黎に粕んでいたからそう蛔うのであって、界戎にLA煌婶侯から粕んでいたとしたら、そんな考粕みはしないだろう。しかし、エルロイのこと、碰脸アメリカの扒を闪いた肌のシリ〖ズを前片においていたに般いない。さらに、≈アンダ〖ワ〖ルド USA 话婶侯∽の妈办闷≈アメリカンˇタブロイド∽に斧られる、撬蝉弄で抨げ嘉てるような矢挛がこの侯墒ではこれまでの话侯になく覆螟である。
LA煌婶侯の呵姜侯だけあって、厦の囤も杜りに杜っている。ちょっとした粕み若ばしもできないくらい、碉滩りしている菜もないくらいの逄泰さ。私蜗拉の微に励む痢嘿な湿胳拉。ただ、これまでの侯墒票屯判眷客湿がやたらと驴く、夸妄井棱弄には踏久步の炊も容めない。
アメリカの扒を闪いた≈LA煌婶侯の煌侯誊∽と≈アンダ〖ワ〖ルド USA 话婶侯∽をもう办刨呵介から粕み木して、これらの侯墒を窗链にものにしたいと蛔った。
LA煌婶侯の话侯誊。
LAPDの扒を闪くことで、1950钳洛のロスアンゼルスしいてはアメリカの竖える啼玛爬をあぶり叫している。ただ、その闪き数が动熙で、推枷ない。叫てくる息面はみんな碍ばかり。
垛、ホモ、算挑、ギャンブル、乐柬りが晚んだ沪客祸凤が肌から肌と弹こる。
里稿坤肠を福苞してきたあのアメリカにこんな箕洛があったのかと蛔わせるくらい、おそらく梦られたくない、茂にも玫られたくない、それまで竖いていた撅急と擦猛囱をひっくり手されるくらい、しかし、祸悸としてあったその考い扒を侯荚は闪いている。
≈ブラックˇダリア∽から幌まる息侯湿だが、肩客给は髓搀佰なる。鼎奶するのは碍の面にありながら、仆叫して≈磊れる∽焚幢たち。海搀も话客の焚幢の、祸凤を奶してのそれぞれの蛔锨と咳の慷り数、畴疲、厩羚炊が闪かれている。
そして、寒瀑のなかから寺ぎだすようにして瞥き叫される办つの湿胳。
粕み姜えて、その菇喇蜗と黎の粕めない湿胳にあらためて侯荚の撵蜗を炊じた。
涟侯≈ブラックˇダリア∽では祸凤に掐るまでの≈まくら∽がとても墓かった。夸妄井棱としては梧まれといってもいいくらい墓かった。しかし、塑侯墒ではいきなり、それが舍奶なのだろうが、祸凤が弹こってしまい、その热客玫しが肩囤となる。
≈ブラックˇダリア∽票屯塑侯墒も焚弧井棱の婶梧に掐る。办忍弄には、ミステリ〖に判眷する肩客给は办枚その祸凤に犯ると、その祸凤办囤に仆き渴んでいく。もちろん晦驼の赁厦や客粗簇犯のあやなどで厦を四らましてはいる。塑侯墒においても办客の焚弧幢がその祸凤を纳いかけるのだが、悸狠、办つの祸凤だけで坤の面が喇り惟っているわけもなく、客粗栏きている粗にはいろんなことが簇わってくる。エルロイは办つの祸凤をそういうもろもろの坤陵のなかの们室として磊り艰るのがとてもうまい。それは箕洛秦肥というよりはその箕洛に栏きた客粗栏宠そのものである。であるから、剩花な客粗簇犯と判眷客湿の驴さは碰脸であり、いくつもの祸凤が肌から肌と惯って童いてきてもなんの啼玛もない。
闪かれた办息の坤陵の们室が稿染にきて芬がってきて、肩囤の湿胳へとリンクしていく。光い誊俐で侯墒链挛を斧畔しながら粕んでいくと、剩花なエルロイの侯墒も斧え数が般ってくる。
塑呈弄なハ〖ドSFというふれ哈みだったが、まさしく亩ハ〖ドな柒推に链くついていけなかった。底しぶりにSFの坤肠に炕りたいという蛔いはもろくも赫け欢った。
この侯墒を粕むには光刨な眶池弄、湿妄池弄、翁灰蜗池弄な漓嚏梦急が涩妥。
办忍辉瘫にとって、これはかなりの岂啼。鳞咙蜗でカバ〖するには嘎刨があるというもの。ただ帽に粕んで姜わったという磅据。
アンダ〖ˇワ〖ルド话婶侯からエルロイの坤肠に掐っていったものにとって、揉の叫坤侯にあたる塑螟から减ける磅据は、揉もはじめの孩はまともなサスペンスを闪いていたのだ、ということ。アンダ〖ˇワ〖ルド话婶侯のような撬蝉蜗のある侯墒をイメ〖ジしていたが、その罢蹋では笺闯秋灰却けした炊がある。
神骆は1947钳のロスアンゼルス、文瘩弄に禄蝉れた秽挛が券斧され、その稿热客が梳まらず踏豺疯に姜わった悸狠に弹こった祸凤をなぞっている。あらかじめ踏豺疯祸凤と尸かっているので、热客玫しというミステリ〖の麻革蹋が风皖している侯墒を粕んでいてもつまらない、と蛔うことが部搀かあった。
姜茸にきて、捌の年踏豺疯のまま穗苞きとなったように蛔えた。が、まだかなりペ〖ジが荒っており、これから黎、部を胳ろうというのか、という悼前がわく。なんといっても、悸狠、踏豺疯祸凤として誓じているのだから。だが、それだけでは姜わらなかった。踏豺疯祸凤を玛亨として四らませたそれまでの赁厦のなかにとんでもない生俐が慌哈まれていた。办塑艰られたというのが赖木なところ。
踏豺疯祸凤という黎掐囱なしに粕めば、もっと弛しく粕めたのだろうが、粕む涟にそれを梦ってしまっていたので、それもせんないこと。それでも、碰箕の锣茄弄で私蜗弄なロスアンゼルスしいてはアメリカ链挛の微の坤肠に苞き哈む蜗は浇尸にある。奢いものみたさ、を浇企尸に塔凳させてくれた侯墒だった。
サラˇパレツキ〖、介めての塑、よくできた玫腻井棱だ。
侯荚のことはこれまで链脸梦らなかった。塑今を缄にとって、介めて揉谨の赂哼を梦った。
9ˉ11のテロ稿に叫されたというところに塑今の积つ罢蹋は考い。9ˉ11稿、あらゆるサスペンス、ミステリ〖はその祸凤とは痰簇犯ではいられなくなった。附悸の坤肠もそれを怠に恃わらざるを评えず、碰祸荚のアメリカにおいては、イスラム兜盘への市斧やしめつけ、怯劳の饭羹が动くなり、∝唉柜荚恕≠の叹の布において亩恕惮弄な涪蜗の脊乖が材墙となった。そんなさなかにこの侯墒は今かれた。
そういう箕洛秦肥はかつて1950钳洛から1960钳洛に酷き褂れた∝乐柬り≠にも鼎奶するものがある。マッカ〖シ〖と润势宠瓢把镑柴らは≈鼎缓肩盗荚∽や≈ソ息のスパイ∽、もしくは≈その票拇荚∽を店闷し、その谭黎はアメリカ蜡绍簇犯荚やアメリカ桅烦簇犯荚だけでなく、ハリウッドの份墙簇犯荚や鼻茶雌颇、侯踩にまで第び、揉らのプライバシ〖や答塑弄な恕弄涪网を僻みにじった。そして、マスコミの鼠苹や极统な山附に极肩惮扩がかかり、极らが筛弄になることに滦する恫奢から、桂券や泰桂が陵肌いだ。
办客のジャ〖ナリストの稍慨秽から幌まる塑今は、そういうきな江い企つの箕洛をうまく烃圭させ、办つのミステリ〖に慌惧げている。
アメリカは络琵挝にトランプが联ばれた稿、猖めて柜忽としての滦テロ宠瓢を链烫に叫してきた。そんなときにたまたま塑今を缄にしたことは、饿脸にしても、なにかしらの傍憋を炊じる。评てして塑との柳而は坷入弄なところがあると撅」炊じるところであるが、塑今もその办糊だった。
アンダ〖ˇワ〖ルド话婶侯の涅めくくり。
涟企侯よりも夸妄拉が咖腔く叫ている。だが、その靠陵を豺くのは推白ではない。涟企侯からのキュ〖バとベトナムそしてケネディとマフィアとFBIの湿胳の获缓を苞き费いでおり、この侯墒帽迫で蹋わうのは润撅に岂しいだろう。そうでなくとも、矢粗を粕み豺くのに鹅看する侯荚の坤肠。侯荚はそこに夸妄拉を裁えて、办蹋烧けたかったのだと蛔う。
涟企侯とは弹富を侍にした≈エメラルド帕棱∽をモチ〖フとした湿胳と、それまでの湿胳が蛤壶しながら渴んでいく。うまい恶圭に慌寥まれているというか、そのどっちの湿胳のことを闪いているのか、ごっちゃになって、とりとめもなくただただ湿胳が渴んでいくように炊じる。いったいどこで皖とし涟をつけるのか、どういう冯琐が略っているのか、それが链く粕めない。涟企侯のものすごいエネルギ〖をもった湿胳と膏していくには、そこに糠たに裁わる湿胳はそれ陵碰の墒剂が么瘦されなければならない。たしかに糠たに裁わった湿胳は秉が考く、塑萎とうまく敖なして闪かれている。しかし、それが≈すとん∽と箭まったかと咐われれば、燎木にうなずけないものがある。
面庞染眉な撬蝉蜗はつまらない。
涟侯ほどの咀封はない。それほど办侯誊の撬蝉蜗は括かった。
キュ〖バ错怠とジョンˇFˇケネディの芭沪を肩玛とした湿胳はヴェトナムのエスカレ〖ション、マ〖ティンˇル〖サ〖ˇキングとロバ〖トˇケネディの芭沪を神骆とした湿胳へと败っていく。
涟侯から办从して闪かれているのは、マフィアとFBI、CIAと算挑を晚めた微家柴の私蜗。海搀はそこにヴェトナム里凌によってもたらされた烦の芭婶が裁わって、ドラマ、客粗簇犯ともにより剩花になり剩霖さが笼している。
眷烫が癸」と恃步していくなかで、ただでさえ粕みづらい矢鞠なのに、嘿やかで逄泰な眷烫の瓢きを涩秽に妄豺しようと粕み渴む。しかし、粕み姜えてから侯墒链挛を许庾してみると、剩霖したプロットの链挛咙が斧えてくる。私蜗弄で撬蝉弄な眷烫眷烫に办搭办瞳しながら、そこにこだわって粕むだけではこの侯墒のスケ〖ル炊が斧えてこない。敞茶から警し违れて囱巨する炊承とよく击ている。
ただ、涟侯よりは妄豺しやすく、粕みやすくなったのは粗般いない。
盒の昆になって、こんな曲闷を秦砷い哈むとは蛔ってもみなかった。
颂菠のミステリ〖にハマり哈んだこの办钳だったが、呵稿の呵稿になってとんでもない侯墒に叫柴ってしまった。いつもの毋にもれず、たまたま缄に艰った办糊の塑。それがそれまで极尸が竖いていた井棱という车前をひっくり手してしまった。というか、鳞咙をはるかに亩えた佰肌傅の缓湿に叫柴った炊がある。凰悸と吊菇をないまぜにした侯墒はよくあるが、この侯墒は≈吊菇∽の婶尸がとてつもなく撬蝉弄。ガルシアˇマルケス、葫捻办践、ジョンˇア〖ヴィング、とは链く捡を佰にする鳞咙蜗のビッグˇバンとも咐える。
JFKのまわりに礁まった庭建な客亨を闪いたノンフィクションにデビットˇハルバ〖スタムの≈ベスト□ブライテスト∽がある。そこには涪蜗考秉婶の客粗ドラマと人鄙の面のアメリカの鹅呛と好擂を票拇させたアメリカの附洛凰が闪かれていて、とても督蹋考かい柒推だった。
塑侯墒ではそこではベスト□ブライテストであったはずの≈腑客∽が稍赖と碍と微磊りと履皖にまみれた、条荚の咐驼を稼りるなら、≈佰妨のモンスタ〖∽として闪かれている。裁えて、ギャング、FBI、CIAなどが剩花に掐り宛れ、湿胳は端めて脚霖な侯りとなっている。侯荚极咳の兰で咐えば≈父鳞を虑ち赫き、怯垮孤から辣までの糠しい坷厦をつくりあげる箕がきた。箕洛を微で毁えてきた碍呸どもと、揉らがそのために毁失った滦擦を胳る箕がきた。碍呸どもに宫いあれ∽、となる。この咐驼もどこまでが塑不なのか夸し翁ることはできない。
しばらくは、ジェイムズˇエルロイの坤肠に炕ってみよう。
付玛は≈SOLITUDE CREEK∽、祸凤の呵介の神骆となったナイトクラブの叹涟。塑今の柒推からすれば、水玛は端めてまとも、というより弄澄に册ぎる。侯荚が部肝そのまともすぎる玛叹にしなかったのか、そこまで叫惹家は雇えなかったのだろうか。
姜茸にきてのどんでん手しは侯荚の评罢とするところ。この侯墒では、それが链く粕めなかった。しかも、そのどんでん手しが剩眶慌齿けられているのだから、うかつに揉の侯墒は粕んではいけない。しかし、办斧なんでもなさそうな柴厦や、闪继、办つ办つその微を雇えていたら粕むリズムが陡ってしまって、とてもミステリ〖を弛しむところではないだろう。ここは侯荚に褓される、いっぱい咯わされた、ことを燎木に千めよう。
丹になった爬が办つ。海搀の肩客给のキャサリンˇダンスといつもの肩客给アメリアˇサックスがだぶってしまうということ。企客とも动くて溜汤で庭建な泛祸という舔どころとして闪かれている。しぐさや评罢とするところは般っていても、厦の鸥倡が年房弄なので、肩客给の磅据も票じように炊じてしまう。キャサリンとアメリアを掐れ仑えても、湿胳弄な撬镁はないだろう。汤らかに咖圭いが般う侯墒になってないところが荒前であった。
クリフトン钳洛淡妈皋婶。
涟煌婶侯を承えていなくとも、この侯墒はこれ极挛で浇尸弛しめる。
呵夺お丹に掐りで粕みこんでいる颂菠の夸妄井棱とはガラッと捡が佰なる。痢嘿で逄泰な湿胳鸥倡が狠惟つ颂菠の夸妄井棱は粕むのにも蜗が掐り、その尸粕稿は考い郊悸炊に塔たされる。办数、クリフトン钳洛淡はそうした嘿婶にはあまりこだわらず、考粕みもいらず、くつろぎながら湿胳の鸥倡を纳っていくという弛しさにあふれている。
ハリ〖はスタ〖リンの悸咙を闪いた侯踩ババコフの抨滚祸凤に船き哈まれ、票じころエマはレディˇバ〖ジニアˇフェンウィックと叹屠逮禄痕冉で凌う。ジャイルズは联刁で缴浓フィッシャ〖警捍に窃れる。笺きセバスチャンが矢机奶り廓いを裁庐しながら湿胳を拦り惧げている。
セバスチャンの湿胳があまりにも惠く乖きすぎ、痰勉慷りにすぎるというのが、苞っ齿った。
≈ロマ∽という咐驼を梦ったのはいつか粕んだ颂菠の夸妄井棱の面だった。
ロマという佰眉の客硷が彻の室儿に大りそって孰らしている。办忍辉瘫からはあまりよくは蛔われていない布霖の客」と磅据烧けるように今かれていた。それが祸凤と芬がるわけではなく、湿胳の攫肥闪继の办つ、その彻を妨侯る办つの菇喇妥燎として闪かれていたに册ぎない。あらかじめロマのことを梦っていたらならば、その彻のことをもう警し仆っ哈んで鳞咙叫丸ていたかもしれない。
ジプシ〖、ジタンもその罢蹋をよく梦らないでいたが、塑今からすると、尉数とも汗侍脱胳の婶梧に掐るらしい。サラサ〖テのツィゴイネルˇワイゼンという铜叹な妒も、ツィゴイネル♂ジプシ〖♂ロマという罢蹋で蝗われたようだ。ツィゴイナ〖と钙ばれていたロマの警钳は∝ツィゴイナ〖という咐驼はぼくの滥秸を骆なしにした≠と、塑今の面で貌いている。海慎で咐うならポリティカルˇコレクトネスとしては奶らない咐驼のようだ。ロマは揉らと票霹にみられることに瓤炊を承え、极らのアイデンティティ〖を肩磨する。
萎喜の瘫ロマの叫极ははっきりとわかっているわけではないが、肝犊はインド颂谰婶にあり、11坤氮介片、イスラム兜盘の刊维がありロマ瘫虏の黎聊は屁舜を倡幌した、というのが奶棱となっているようだ。その稿ヨ〖ロッパで≈灰丁をさらうジプシ〖∽≈热横荚礁媚ジプシ〖∽との哙磅を病され、汗侍と趋巢を减け、ナチスによって陵碰の眶が翟沪さている。そのような悟凰から、附哼もロマに滦する市斧と汗侍がヨ〖ロッパに含烧いており、ロマは阜しい栏宠茨董におかれている。
そんなロマのことを妄豺してもらうために叫されたのが塑今だ。
呵夺イギリスのEU违忙が疯まった妥傍の办つに、败瘫や岂瘫に滦する雕冷炊が惧げられる。イギリスに嘎らず、颂菠紧柜も丽锡された柜」という磅据がある染烫。布霖瘫や败瘫、岂瘫に滦する市斧と汗侍は澄悸に赂哼するようだ。
ロマという警眶瘫虏を奶してヨ〖ロッパの办烫を梦らしめてくれた办糊だった。
ジョンˇクラカワ〖の塑としては企糊誊。办糊誊はあの1996钳のエベレストの柔粪を闪いた≈鄂へ∽。海搀は2010钳から2012钳にかけてモンタナ剑妈企の旁辉ミズ〖ラで络池のアメフト联缄が苞き弹こしたレイプ祸凤∈キャンパスレイプ∷の靠陵について考く宦り哈んでいる。
涟侯≈鄂へ∽のときも炊じたが、揉の慌祸は淌泰な艰亨から幌まる。恶挛弄には木儡碰祸荚にあって、祸凤を瞄悸に浩附する。その狠改客弄なコメントは端蜗沟え、ひたすら祸凤の链挛咙を闪くことに漓前する。その惧で、それに滦してどんな斧数があるか、叫丸るかを列数の惟眷から浮沮する。それゆえ粕み缄は揉の淡揭に辫って推白に祸凤の靠陵と皇恕扩刨の谭解爬についての雇弧をめぐらすことができる。
≈レイプとは票罢を铜しない拉蛤∽であると塑今では年盗されている。票罢を评たか评なかったかの澄沮が评岂いため、レイプは弹潦まで积ち哈まれないケ〖スが驴い。簿に潦举に掐っても、そこに略ち减けているものは≈セカンドレイプ∽、わなわち、祸凤の拒嘿な浩附がその眷でなされ、蕊巢荚にはレイプ票屯の鹅乃が略っている。それゆえさらにレイプが潦举にまで魂るケ〖スが警なくなる。
レイプは撮斧梦りによる热乖がそのほとんどである、腆8充という祸悸。斧ず梦らずの客粗に仆脸奖われるというケ〖スもあるが、络染は撮斧梦りによる热乖なのである。湍齐厉であったり、络池での撮斧梦りであったり、それまでは蕊巢荚と舍奶に烧きあっていた荚がレイプを弹こすのである。しかも、レイプは浩热唯が光い。蕊巢にあった谨拉は、极尸のような鹅乃を戮の客に沸赋してほしくない、あるいは极尸のような鹅乃を蹋わった谨拉が戮にもいるに般いない、との蛔いから罢を疯して葡け叫るのである。
まず、铜横か痰横かの疯年がなされる。それまで、蕊巢荚はセカンドレイプを潦举の眷だけではなく、揉谨の件收の屯」な眷疥からも减けることになる。裁えて、嘲填からの面烬にも卵えなければならない。塑今で胺われている祸凤では、モンタナ络池アメフトチ〖ムの彻ミズ〖ラという泼拉、アメフト联缄の泼涪罢急、そういう秦肥からくる坤粗の市斧≈潦えられたレイプの染眶は背∽、とも飘わなければならない。よほどの动い慨前と看がなければ、とても痕冉に卵えられるものではないだろう。
铜横を尽ち艰ったにしても、肌は翁泛の冉们である。これも呛ましい啼玛だ。册殿の冉毋からある镍刨の誊奥があるのだろうが、それがかならずしも蕊巢荚の羌评のいく冯蔡とはならない眷圭がある。ということを塑今では揭べている。
簿に夺づきになりたい盟拉といちゃついていて、冯蔡拉蛤に第んだとしても、庞面で谨拉がそれを雕容した稿も拉蛤が鲁けられればそれはレイプ≈票罢を铜しない蛤灸∽と斧なされる。このとき、谨拉が雕容を汤澄に咐驼にしたか、轮刨で山したか、を冉们するのは润撅に岂しい。盟拉娄からすれば、稿からそんなことを咐われても、檀面になっている呵面でその咐瓢と轮刨が郏随であれば≈票罢を铜しない∽と减け艰ることはほとんど氦岂だ。それを潦举にもっていかれたものではたまったものではない、という斧数もできる。
こうして斧ると、痕冉で凌われるのは铜横か痰横かであって、そのどちらであっても、靠悸はまたそれとは侍にある眷圭があることも鳞咙できる。靠悸は蕊巢荚と裁巢荚の看の柒にあるというのもレイプ潦举の泼佰な爬だということを悸炊した。
1997钳に叫された侯荚の借谨侯。妈企肌络里の琐袋から湿胳は幌まる。
湿胳は涟染と稿染に尸かれている。ドイツの腻弧に羹かった肩客给企客の捐る腻弧怠が封ち皖とされる。考缄を砷いながらも努孟からの忙叫を活みる企客は误贾に若び捐るが、それは篮坷を陕んだナチスの经够らを笨ぶ贾尉だった。そのまま、篮坷を陕んだ荚たちが箭推されている陕薄に箭推される。その卉肋の叹涟が塑今玛叹のアルファベットˇハウス。
企客が封钠されてから卉肋に箭推されるまでの湿胳はかなり逄泰に闪かれている。というよりは、判眷するものすべてにおいて、客湿であったり、慎肥であったり、こと嘿かく浩附されている。まるで、露借に碉た荚が斧えるものをすべからく闪きだそうとしているかのようだ。であるから、粕み缄も瞄悸にその眷烫を誊で纳うことが材墙だ。
ナチスの惧甸经够に喇りすました肩客给らのアルファベットˇハウスでの栏宠ぶりの闪继にも缄却きがない。排丹や挑湿を蝗った迹闻恕は栏」しい。それほどの归啼ともいえる迹闻を减ければ、まともな客粗でも篮坷を陕んでしまうだろう。それでも栏き荒るためには簿陕を刘い鲁けなければならない。そんな企客の篮坷觉轮の闪继は靠に趋る。そして、办客は忙叫し、办客は卉肋に荒されたまま姜里となる。ここまでが涟染。
稿染は篮坷陕棚から忙叫したブライアンが、墓钳の奉泣を沸て稿、荒してきたジェイムズを玫す喂と列数の看の畴疲を闪く。
ブライアンはジェイムズの久漏を纳うが、あらゆる数烫から缄を吭くして拇べても、阝としてジェイムズの久漏はつかめない。しかし、ほんのちょっとしたきっかけからブラウン极咳の册殿へのつながりを斧叫し、それがジェイムズとの浩柴へと瞥いていく。この收の纳雷眷烫の寥み惟てもそつがない。≈泼淋婶Q∽シリ〖ズでみられた逄泰な淋汉缄恕を面看に盔える湿胳鸥倡は、このとき、揉の借谨侯にしてすでに叫丸惧がっていた。
箭推疥苗粗との秽飘の琐、ようやくブライアンはジェイムズとの浩柴を蔡たす。だが、ジェイムズは栏き荒るため篮坷陕を遍じ鲁けるうちに、塑碰の极尸を看の秉考く誓じ哈めてしまっていた。ジェイムズはブライアンとの浩柴で承烂するが、ブライアンを减け掐れることができない。忙叫に喇根した办数は舍奶の踩捻を积って宫せに孰らしていて、数や荒された办数は篮坷陕吹荚として、ただただ栏ける挥票脸の箕粗を册ごしてきた。そんな墓钳の奉泣のうちに栏じたブライアンとの络きな孤と呈汗を荐い、ブライアンを钓すことができなかったのだ。
己われた箕粗と、佰なる茨董布かにおかれた企客の看の柒の持たりはあまりにも络きく、哎しくて可い附悸を仆きつける。企客の簇犯はどうなるのか、姜茸に丸て缄に蠢爱る鸥倡となり、呵稿のペ〖ジまで誊が违せなかった。