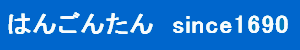�ǽ��ϡ����֤ξϡס����κǸ�κǸ���ܤ������Ǯ�����������ɤ�ʤ���������
�����ɤߤʤ��顢�������Ϥ���ǰ����ˤ��褦���ȴ��ٻפä����Ȥ������줬����ʽ�������줿�ΤǤϡ��ޤ������ˤȤäƤ��ޤ������ʤä���
�ֿ������פ������������о줷�Ȥ���������ĻҤ��蘆�˴ؤ��ˤϿ�ʬĹ���äˤʤ�Τ������ʡ��ޤ����͡��Ȼפ��ʤ����ɤ�Ǥ�������������»��������Ȥʤäơ���Ũ�ط��ξ�Ƹ�Ӥ��襤��ĩ�ࡣ�����»����������������»����ʪ��Ǥ��롣
Ƹ�ӤȤ��襤�����Ȥ����������������δ��Ȥʤ롣���虜��Ȥ���;����Ĥ����ޤޡ��������Ǥ��ڤ�ˤ��Ƥ�褫�ä��Ȼפ��Τ�������ԤϤ������ʤ��ä���
�ֿ������פǤ����Ԥ����פȤ�����ؤ�ȿ���������������»���ζ��Τ����襤�֤꤬����Τ��ä������������פǤ�Ƹ�Ӥ�Ƥ�ä��塢�»�����������λ�褫�����ޤޡ������ȯŸ���������פ����ФΤ�ΤȤ�����������ΤĤ��Τ��������ڤˤ����ƺǶ��η��ĤȤʤäƤ��ޤä����Ϥ����ơ���Τ����»���Ϥɤ��ʤ�Τ�������Ϥ��θ�ɤ����������Τ��������˶�̣��Ū��������
����ϸ����ֲ��ϡ���ͳ�Ծ줬���̤λԾ�Ǥ��ꡢʪ��˭����ή������ꤿ��������Ϥ⤦����Ȥϸ�����Τ��⤷��̤����Τϡ�ʪή�����������¡�����ι�����Ф����ɸ椬�濴�ˤʤ�ס��ȡ�����Ϥ⤦���ߤι������Τ�Τ����ۤ��Ƥ��롣
�Ϥ���������ι�Ť���Ϥɤ�ʷ�����ޤ���Τ������줬�ڤ��ߤǥڡ������äƤ��ä���
���쥯����ȤϿ������͡���ʪ���ƤĤʤ���碌���ֽ����פΤ��Ȥ��Ȼפä��顢�����ǤϤʤ��ä����֤꤬��ä��̡֣פǤϤʤ��֣ҡס����ʤ���ֽ����פΰդ��ä���
����ʥ��ե�������ܡ���äȤ⡢����ɤ���֥ե����פ�ꤳ�����������˽�Ƥ��롣�֥ե����פ��ɤ��ľ�塢�פ�̤Ȥ����ǺƤӥե��κ��ʤ˽а��ä������μ�δ�����١��ä�����뤳�Ȥ����롣�ͤȤνй礤���ܤȤνв��ԻĤʤ�Τ���
���ʤȤ��Ƥϥ�����������Ȼ���ʷ�ϵ���������졢ʸ��Ū������ʬ�ˤϰ��֤Ĥ��Ƥ����ʤ�����κ�����
�֥ե����פ��ϡ������������ʪ��Ū�ˤϤ��⤷�����褦�˴��������֥ե����פϡ����⤹�����¯���⥮�ꥮ��δ������ä����䤿��ֿ���ס֥��å����פȤ������դ��ФƤ��롣���ˤˡ��ɤ����ǤϤʤ�����ˤ���˾��ʪ����ä����֥��쥯����ס֥ե����פȤ⡢���ȡ��Ÿ����ڤ���Ȥ������ϡ��ֲ��äȿ��𡢤������������̩�����̡פ˰������ޤ��Ȥ������ʤ����֥��쥯����פǤϤ�������������������˥��ȡ�������̣����Ƥ��ơ�����ߤ˾���ȴ�������
���ʤǤ�Ϸ���ؤȤ�����ͤ�©�Ҥ�̼���������ޤ�������Ƥ��롣������Ǥ⡢�ѡ������������¤�Ǥ����פȡ������פ��դ�ź���ͤ�ʪ�줬�Ťߤ������Ƥ��롣�䤬�Ƽ�ʬ�ˤ���뤫�⤷��ʤ�Ϸ��������������������ˤ�����̩�������Ф��Ƥ��롣�ޤ��ޤ��ȸ����Ĥ�����Ϸ���θ��¡���������Ǥ����Ͻ�ʬ�������˻��ͤλҶ��������줾���ʪ�줬�ä�ꡢϷ���ؤ���餷�ȥ����������Ǥ������ΤΥХ�⤦�ޤ��Ȥ�Ƥ��롣
��������ǯ�����ƿ�ޡ����ƽ�ɾ�ȶ���ޡ��ԥ��åĥ����ޡ��Уţ�/�ե������ʡ��ޤ˥Υߥ͡��ȡ���ɡ����ƿ�ޤ˵�������������������ƤϤ���Ȼפ����ʤ���
�������������κ��ʤ��ˤȤä���
�����������ǽ������ɤ��ڤ�뤫�Ȼפä����������۹ͫ���ɤߤ����Ƥ����˿�������
�������ɤ�У������������ɤ�У����ȡ�������ʪ��˰������ޤ�Ƥ������äˣ�����������Ϥޤ��»���ȶط��ξ�Ƹ�ӤȤ�������ϰ��������֤�˺��Ƥΰ쵤�ɤߤ��������Ƥ��ä���
Ũ���ݤ��������ά�ˤ��͡������Ǥ����߹礦�����η��Ϥ�ʬ�ϡ�ʼ��Ĵ���Ⱦ������֡�ĵ���ʼ�롣�������ä��»���ȴ������ɤ߹礤�Ȥ���������ʪ��Ϥ�������Ǥ⽽ʬ���⤷��������������������������Ƥ���Τϡ��ޤ������������������ͤ�ʪ��Ǥ��롣���������Ԥ��������Ω��ľ�����ᡢ�ɤ�ʿͤ����ޤꡢ�ɤ�ʱѷ椬�о줷����餬����פä���äơ����Ǥ��ä����������ꡢ�ʤ�Ȥ��äƤ⤪�⤷�����Τϡ��������Ω�����������Ȥ��˲����Ǥ��롣���Ǥ�����Ū��������餬�����λ֤Τ�Ȥ˰�ݤȤʤäƴ���Ω��������������ۤɽ�̱�ο����ɤ뤬��ʪ��Ϥ���ޤ���
�פ��С��Τä������Ȥ�����ϡ�Ʊ�����Ȥη����֤��ǤϤʤ�������������������äơ�������ΤȤ��⤷���ꡢ����˻�äƤ�����ȺۤΤ�ȤǤ����ŷ���»���κ��Ⱦ������Ѥ�äƤ��ʤ���
����Σ������ڡ�����������������ߤΤ���ʬ�����ܤ��ɤ߱�����ʬ��
�褭�ˤĤ������ˤĤ����奢��ꥫ�λѤ������ˤ��Ĺ��������̤��Ƥ���Ȼפ��롣�ʤʤˤ�����ꥫ�ˤϹԤä����Ȥ��ʤ��Τ����顢��������Ǥ����ʤ��Τ�����
��ʬ���Ф�����¤������褦�Ȥ������ء��Ȥ��β�²�������Ƥ��μ���ο͡����˽��֤Ρ���˾�ο����Ⱥ���Ҷ�����ͤȤ��Ƽ�Ω���Ƥ��������������������ơ����������ʤ��Τ��Ȥ�������Ȥ�Ķ����������ȴ����ʪ�켫�Τ�ڤ��ޤ��Ƥ�����Ϥ����κ��ʤˤϤ��롣Ĺ�Ԥʤ���⡢��Ƭ����Ǹ�ޤǰ�Ӥ����ɤ߱���������ñ���ɤ߿ʤळ�Ȥβ�������³���롣����������˼����Ȱ������ޤ�Ƥ��ޤ��Τϡ������˼�ʬ�λѤ���Ƥ뤫��Ǥ�������
�������ȡפΤ褦�ʤ����ޤ����ߥ��ƥ���Ȼפä��פ���顢�����ǤϤʤ��ä���
�����Ф�������ι��ˤ����ž�������Ȥ��Ƥ���Τˡ��������Ԥ���Ť��Ȥ��ä���Τ��������������ʤ������Ȥ���Ŭ�ڤǤʤ����⤷��ʤ����������Ȥ��������������������������Τϻ��������������
�Ż���ι�褫����äƤߤ�ȡ�ͽ�Ƥ��ä���ۤ��ܤ��Ϥ��Ƥ��������ߤ�������ˤȤ�ˤ��äƤ���Ƥ����Τ��ä������ƤӤä��ꡢʬ���������Υܥ�塼��˰��ݤ��줿���������ֵѴ��¤ޤǤ�ä�����ɤ�Ǥ����ʤ������ˤ�Ԥ�������������顢���꿽���顢�������顢¾�ˤ���������ʤ��㤤���ʤ����Ȥ�ί�ޤäƤ��롣�֤����ܤϿ͵������äơ����Ȥ�ͽ�ͤޤäƤ��뤫�顢���¤ޤǤ��֤��Ƥۤ�����Ǥ����ɡפȡ����ֱ�Ĺ�Ϥ������Ǥ�Ƥ��롣���äơ�ι��ޤǤϻ��äƤ�����ʤ��������Ѥϼ�ȴ���Ǥ�äĤ��ơ��Ƥ�ι��˽и����ޤǤ�û���֡��֥������ε��ڡפ��ͥ�����Ȥ��뤳�Ȥˤ�����
�����ᤫ�����뤤��¾�ˤ⿼���ơ��ޤ�����Ǥ��ơ�Ϣ³���ͤؤȿ�Ÿ�����Τ��Ȼפ碌����Ƭ���ɤ߿ʤद���ˡ���˴������ǯ��Ʊ���ع����̤��������ˤϿ��¤��ͤ��ߤ�褦�Ȥ��뵡���������夬�ꡢ����Ҥ�ʤ���ư�˽Ф롣���졢��ǯõ���ġ��ȻפäƤ���ȡ����ˤ��餺������������ǯˡ��ؤ�ʪ��Ͽʤ�Ǥ��ä���
����륵���ڥǤϡ������åȡ��ȥ������䥸���ե���������㡼��������������������ܿͤˤϤ���ʾ���Ͻޤ����Ⱦ�פäƤ�����������������ʼ꤬���ä��Τ����Ȱ��ܤȤ�줿��ʬ��
���κ��ʤν�Фϡ־��⿷Ĭ�ס������褽��������������ɼԤ��оݤȤϤ��Ƥ��ʤ�������ϳع����ꡣʸ�Ϥ�ʿ�פǡ��ɤߤ䤹�����ֶ��İ쾯ǯ�λ������פ��̾õ�女�ʥ�פΥΥ��������Ƥ��롣�����顢������������ɤ�Ǥ⽽ʬ�ڤ���롢����ɤ����������ˤ⤼���ɤ�Ǥ�餤�������ơ�����ʤΤˡ��ʤ�����ԤϤ��κ��ʤ�־��⿷Ĭ�פ˷Ǻܤ����Τ��������⡢�¤ߤΥܥ�塼��ǤϤʤ�����ʬ�λҰ�Ƥ��̤��ƤǤⴶ�������Ȥ��������礦�Ӥ�������ϡ���ͤ��פäƤ���ʾ�ˡ��褯ʪ����ͤ��Ƥ���Ȼפ����Ȥ����롣�����ơ�����ȯ���˥ϥäȤ���������̤�¿�������κ��ʤǤϤ��줬ǡ�¤���Ʊ�����ˤ��̤�Ʊ�����ޤ���Ʊ��ǯ�����̤餬����������λ�ο�����Τ뤿���Ω�������롣���ο��¤��Τ뤳�Ȥ���������������ˤĤʤ��ꡢ���줬�ʤ���������̤��Ϥ������ʤ�����ǯˡ��η���Ȥäơ�����¿���ʿ����֤��Ƥ��������ޤ�ˤ��������Ǥ�������ε������������־��⿷Ĭ�פ��ɼԤǤ�������ͤˡ��ɤ�ǡפ�餦���Ȥ�����Ԥΰտޤ������ȤǤϤʤ��ä������ع�������ΰ�Ĥλ���Ȥ��ơ�
�����ơ�����Ƥ��줬������ä�ñ���ܤȤʤä����˽Фơ��Ƥ���ͤ���˼�롣������������������������ط��Ԥ��ɤ�褦�ˤʤ��������������äơ���������ʤ�����֤ΰջפζ�ͭ���Ϥ����Ƥ�����ǽ�������Ƥ��롢����ʺ��ʤ��ȴ�������
��ǯ���ܻϤ�ϡ�����롦���졣
�ȤӤä���Υ����ȥ����ڥ�����櫓�ǤϤʤ����ޤ�������͡פΥ��ѥ�����Ȥ��ä��Ȥ�����ˮ���λ����ˤ⤢��Τ����������ʤ�Ȥʤ����쥤���ɡ������ɥ顼�Ρ֥������åɥХ��פ�ʷ�ϵ����Ƥ��ޤ��Τϻ��������������
���ѥ������Τ��������Τ��Ȥ��Τ�ͳ��ʤ������������ߤ�Ω�Ƥ��������Ǥ��뤳�Ȥˤϴְ㤤���ʤ����ͤϡ��ʤ�ǡ����ѥ������̥�Ϥ���Τ�������ϡ���äѤꥹ�ѥ����餸��֤���ɤ��פ˥ɥ��ɥ��������뤫��ǤϤʤ�����������
�ܺ��ʤϤ��Ρ֤���ɤ��פ��龯����Υ�������ѥ�����ȤʤäƤ��롣

��ǯ���ɤ�Ǽ��ϥ������ॺ���ܥ�ɡ�
�֥ܥ�ɤϤդ����ɳ���������ʤ����㳰�ϥ���Хåȥ֡��Ĥ�ɬ�פʤȤ��ȡ�ɳ�η�Ӥ����ˤ�ä���֤Υ���������Ȥ˰��ۤΥ�å�������������Ȥ��˸¤����
�����ʤ�ۤɡ�
�����ե���ǥ����������������ܥ�ɤϤ����ˡ������餯�����ե���ǥ����������ե���ʤ�ФۤȤ�ɤοͤ������פäƤ��κ��ʤ��ˤȤä��ΤǤϤʤ�����������
�������餤���ȡ���Ϥꤳ��ޤǤΥ���饤�ॷ����μ�ˡ�Τޤޥܥ�ɤ�Ƨ���������ʤȤʤäƤ��롣�֣�������ǯ�˥���ե�ߥ����߽Ф���������ͭ̾�ʥ���饯������ɴ�����ɼԤ�˾�����뤳�Ȥʤ�������ɤ餻�뤳�ȡפ�������Τ��ȤǤϤʤ���
��Ƭ���ܥ�ɤδ�����ȱ����Ϥޤ륢���������ϡ��Dz�Τ�������ʤ����롣����ͭ̾�ʽФ����Υ�����ڤ�ʹ�����Ƥ��������ޤ�������ӥ����饤���ꥹ����������եꥫ�Ȥ�ޤ��뤷�����椬�Ѥ��Τ�ܥ�ɱDz�Τ���ޤꡣ�������ܥ�ɥ�������о줹�롣
�ޤ��������ե���ǥ�������������ݤ����������äơ�����Υ�٥�ˤ�ã���Ƥ��롣������������饤�ॷ����Υѥ������ɤ�Ƥ�������ˡ��¿����˷礱����ݡ��ڤ�̣�Ȥ������Ǥ⡢�⤦����äȡ���äȰ�ä�ɮ�פΥܥ�ɤ��ɤߤ����ä���
���٤��Ӱ�ͽ�Ϥ��Ĥ�Ȥϰ�̣�㤦��
�������������ŵ���ҥ��˥å��λҲ������ŷ�����ҤȤ����ȿ����͡��������ͭ���Ρ������ˤϤ��줾���Ω�졢���줾��������������롣���Τ��줾��λŻ��˷Ȥ��ȼҰ���͡ɤ�˥Х��������֤�ʤ��顢���ΤȤ��ư�Ĥ�ʪ��˽��뤵���Ƥ��롣���Τ��ꤲ�ʤ����Ȥ����������ä��ܶڤι�����̯������������ʤ����ȡ���ƥ�Τ��ޤ�����Ω�äƤ��롣
��ҤȤϲ������Ż��Ȥϲ��ʤΤ�����ˤ����������줿�Ȥ����ɤ��ʹ֤�ư���Τ���
�ʤ�Ȥޤ����ȥ졼�Ȥ���̾����
�ɤ�������˾褸������Ĵ�����äڤ�����Ƥ��ܤ��ȻפäƤ����顢���줬�ޤ������⤷�����ä���
��λ��郎�ʤ��ä��ʤ�С�����ۤɶ�̣���ʤ��ä�������������ס�
�ڹ�˲ä������Ȥ���̯�ʳ�������̯�ʥ��å��������Ƥ��롣�ޤ�ǡ����ξ�ȸ����̤�İ���Ƥ��뤫�Τ褦�ʿ��Ϥ褵���ƥ�ݤ��ɤ��Ϻǽ餫��Ǹ�ޤ�³����
��ȯ��ȯ�ζ�ĥ���Τ������ۥåȤ������ߥ���ǥϡ��ȥ������ߥʥ����ڥ��̤��ơ��䤵�����⤤�Ƥ���Ƥ��롣�����ڤȤϸ��դ��פʤ�ۤɡ��褤���ٶ��ˤʤä���
���ࡢ���Ĵ�ʤ��ʤ����ʡ����ˤʤ�¸�ߤ���
���Ƥ����Ϻ��
���ûҺ�Ȥκ��ʤϤɤ�ʤ�Τ��������Ȼפäơ���ˤȤä���
�ȥޥɤߤ����ʤ�Τ����������Ƥ�������������äƤ������ɤ��餫�ȸ����Хե������˶ᤤ��
�٥�����ɤ��⤿�餷���������ܤˤޤǰ���ĥ�ꡢ�ե�������Ω�Ƥο�������˻ž夬�äƤ��롣�����ơ������äѤ��û���ޤȤ�Ƥ��롣����褫���С��褦�ˤ�äƤϡ���äȽŸ��ʺ��ʤ˻ž夬��Ȼפ��Τ����������Ƥ������ʤ��Ȥ��������Ϻ�����ʤʤΤ��⤷��ʤ���Ʊ��������դǹ�¼�������ʤ顢���ˤ�����Ȥ�����ʤˤʤ�Ǥ��������ȻפäƤߤ��ꤹ�롣
���ϥ٥��ȥ��顼���ɤ�Ǥߤ褦��
����Х�����ޥ�ΥХ��֥�Ȥʤä��Ӱ�ͽ�κ��ʡ��������Х��Ǥʤ��Ȥ⡢�ڤ���롣
��������Ԥ���Ҳ�Ҥξڷ���Ҥ˺������줿Ⱦ�������ɣԴ�Ȥ�������ᤰ�ä��ܼҤȿ��ø����顣���¦�����ԿԤʤ�����Ⱦ�������य���֤��줿�����֤�����
Ⱦ�����������ޤϼ¤˥��å��������������˲�����Ⱦ�����������˶�����Ф���Τϻ�����ǤϤʤ����������Ӱ�ͽ�ϲ�ҿʹ֤��ᰥ�������Ĥġ��ͤȤ��Ƥʤ����ƤϤʤ�ʤ�������о��ʪ�˸�餻�Ƥ��롣���Ȥ���ʬ�ιͤ����������ȻפäƤ��Ƥ⡢������Ƥ����Ԥ����ʤ���С��ʤ��ʤ����˹Ԥ��ʤ���Τ����⤷����ǯ�����Ӱ�ͽ�Ƚа��äƤ����ʤ�С���ʬ�ˤϤޤ��̤ο��������ä����⤷��ʤ���
�Ƕ�Υ����ե���ǥ����������κ��ʤϡ��͡��δؿ������������˸����Ƥ��뤫���桹������οȶ�ʤȤ��������ܤ�������餬�⤿�餹���äȤ���¦�ˤ����������ơ��ޤȤ��Ƥ��롣
�֥����륳�쥯�����פǤϡȥǡ����ޥ��˥ɤ����Ȥ��ơ��Ȥβ���Τ�������ǥ�����ǡ���������Ƥ��븽��Ҳ�������భ�Ф��Ƥߤ����������ơ�����Υơ��ޤϡȥ��ͥ륮������ɡ����ǤϤ����ɬ���դ��Ƥޤ����̾������إ��ͥ륮������ɤΡȻųݤ��ɤ����Ĥ����Ƥ��롣���ޤ��˽ܤκ��ʤȤ����褦��
ʪ������פ��ȿͤ����ꤵ�졢�ܺ��Ϥ����ߤ�����褦�ʥ��ԡ��ɤ��ȿͤ����롣������������������饤����ɼԤʤ顢���Τޤޤǽ����Ϥ����ʤ����Ȥ��ΤäƤ��롣���줫�顢�ɤ���ä��ɼԤ�ڤ��ޤ��Ƥ����Τ����ɤ��Ÿ�����ޤäƤ���Τ����������Ԥ��ʤ����ɤ߿ʤࡣ�����ޤ�������饤�ॷ����Τ���ޤ�ȤʤäƤ��롣
�ܺ��ʤ�����ޤǤκ��ʤȼ㴳�㤦�Τϡ��ܺ���λ���;���ޤ������Ƥ�������������Ȥ�ľ�ܴؤ��礤�Τʤ������ʤ����ä��Ǹ�κǸ�ˤ��������Ƥ��롣����η����ˤ���⤦��Ĥ�ʪ�졣����ޤ����Ȥ�������ե���ǥ����������Ϥ���������������Ϥޤ��ޤ���ǯ�������Ƥ��ʤ��������ڤ��ߤ���
����⤽�Τޤ�ޡ�Silent Spring��
�����ܤϣ�������ǯ�˥���ꥫ�ǽ��Ǥ��졢����ľ�壱������ǯ��ˮ������Ƥ��롣���衢ʿ������ǯ�λ����ǣ��������¤�Ĺ���ˤ錄�äƻٻ������ɤ߷Ѥ���Ƥ��롣
���Ǥ��������Ҥ��Ф���ͤ���¿���ο͡��δ֤Ƕ�ͭ����Ƥ��ꡢ�Ȥ��ˤϲ��ҤȤ����פ����̤⸫�������롣�������������ܤ��줿���Ϥޤ�������ͭ�����Ф��꤬��ˤ���������ͭ�����ˤĤ��ƤϤۤȤ���������Ƥ��ʤ��ä���
���κ��ʤ��Ф��줿�طʤΰ�Ĥˡ���������������ǯ����������ѤȤ������Ȥ����롣����������ñ��̵�̤��뤤����ɬ�פȻפ�����֡ʻ���ˤν����ʪ��ʹ֤ˤȤäƤ���ʤ�����³���ζ���Τ��ᡢ���ߤ䤿��Ȳ������ʤ����Ѥ��줿�����Ρ֥��ץ졼�פΤ�������Ҿ�ǤϤʤ��ä��Τ���������̤ȹ��ϰϤˤ錄�ꡢ���̾ʬ��̾�Τ�Ȥˡ��ʤ�դ깽�鷺���ʤ��Ф黵����Ƥ��������줬�������ˤɤ����٤�Ϳ���뤫���ޤ�����ˤ�äƿʹ֤��ɤ�ʤ��ä��֤������������ޤ��ʤ����Ȥꤢ������������פ�������С�������ɤ��Ȥ�����
���ԤϤ��μ��֤�ðǰ��Ĵ�پ夲���Ԥ�줿��Ԥ��İ�Ľ����Ƥ��롣�ܽ�Ϥ��μ¾ڥǡ���������Ȥ��äƤ����ǤϤʤ�������Ǥ⤫������Ǥ⤫�ȡ���䤯�ɤ����뤯�餤��Ϣ�ͤƤ��롣
����ϲ������ʤ����Ѥ��������̤��ؤηپ���Ĥ餷�������������ܽФ���Ƥ��飵��ǯ����ä����������Ϥɤ��Ǥ������������ܤǤϥ��֥ɥ��ʤɡ��ۤȤ�ɤβ̼����ݤˤϲ��Ȥ�פ���ۤɤ��������ۤ��礫���ʤ������̿�����ˤʤ뤯�餤�β̼��ࡢ�����������ǤϤʤ��������ޤǤ��ʤ��Ⱦ���Ԥ˹��ޤ��̼¤����ϤǤ��ʤ����¡��ե���ԥ�ʤɤΥץ��ơ������Ǻ��ݤ����Хʥʤ⤷���ꡢ��ȼԤη������餤�����������Ѥ���Ƥ��롣�Ȥ����������Ϥ�Ư���ͤ����ε����ˤ�äƲ桹�ϰ²��ǻݤ��Хʥʤ�������Ƥ��롣���֤ϤҤȤĤ��Ѥ�äƤʤ��褦�˻פ��롣
�ֲ������ʤϤʤ�ǤⰭ�Ǥ���פȤ��ɤ����Ϥ��ʤ������������˸¤餺�����٤Ƥˤ����ƶ�������ѥ��Ȥ�Ϳ�����Τ�ɬ������Υ���ѥ��Ȥ�⤿�餹��ǽ�������롣�����ͤ��Ƥ����ƴְ㤤�Ϥʤ���������
�ְŹ���ɡס����ذ��ŤΥȥ�å��פ�³���ơ����������Ȥ��Ƥϻ����ܡ�
�ͥåȾ�ν�ɾ�����˹⤤���ۤȤ�ɤ��ޤ���������������ʬ�Ȥ��ƤϺǽ���ɤ���ְŹ���ɡפΥ���ѥ��Ȥ��礭���ä������ˡ��������Ӥ��Ƥ��ޤ������Ȥ��ɤ������ʤϤ���ۤɤΥ���ѥ��ȤϤʤ����⤷���ǽ�ˡ����ذ��ŤΥȥ�å��פ��뤤�Ϻ����ɤ���֥ե���ޡ��κǽ������פ��ˤȤäƤ����ʤ�С������Ȥ�ְ㤤�ʤ����ޤĤȤʤäƤ���������������Ǥ�ְŹ���ɡפΤۤ������⤷�����˾��äƤ���Ȼפ���
���ȤʤäƤϲ������줿�Τǡ֥ե���ޡ��κǽ������פ��������Ƥ��뤬����������ǯ�ˤ��줬���������ޤǤϡֺǽ�ͽ�ۡפȸƤФ��٤��Ǥ��ä�������Ǥ⡢���줬�ʤ�Ǥ��뤫���Τ�ʤ��Ƥ�ֺǽ������פȤ������դϤ���ޤDz��٤Ȥʤ����ˤ��Ƥ�����
�ܽ�ǥ��������Ϥ��Ρֺǽ�ͽ�ۡפ��ɤΤ褦�ˤ��Ʋ��˻�ä�������������ˤ��Ƥ��롣�����ơ��������о줹���ʪ�䤽�λ����طʤ�ޤ�Ǹ��Ƥ����褦�ʸ����������Ƥ��롣����Ū��̿��˥��ȡ������������������촶��̣�碌�Ƥ���롣������������ñ�ˡ֥ե���ޡ��κǽ������פˤĤ����ǿ������⤤�Ƥ��������Ȥϼۤʤ롣
�ե���ޡ���ͽ�ۤ��Ƥ��顢�¤ˣ�����ǯ�θ�ˤ��Ƥ褦�䤯�������줿����������¿���ΰ���ʿ��ؼԤ�ĩ��Ǥ��������줾�줬�����˰��⤺�Ķ�Ť��Ƥ����Τ����������ޤǤˤϻ��ʤ��ä��������ˤߤ���Τ��������Ѥ߽ŤͤǤ��ä������ʤ�������Ȥ�³������Τ������Ԥ������ޤ�������Ǽ��Υ��ƥåפ˿ʤ�Ǥ��������켫������ɾ�������٤�����ʰ���Ȥ����������Ф��ꡣ����ʻ�Ժ��������äơ�����˲����ؤȶ�Ť��Ƥ��ä��ΤǤ��롣�����ơ��Ǹ��ĺ���Ω�ä��Τ�����ɥ�塼���磻�륺���ä���
������ͤΤ��뤤�ϥ�����ˤ������Ū���ä��ȻפäƤ��Τ���������ۤɷ�Ū��Ÿ������Ĥ��������ˤ��ä��Ȥϻפ�����ʤ��ä��������ΰ�����������ʥɥ�ޤ˻�Ω�Ƥ��ޤ����������κ��ʤϰ��̸����ʳؽ�Ȥ��ƤϽ���Ǥ��롣
�����ذ��šפȤϡ��ּ�ή�ɤΰ�դ���Ⱦ����������Ƥ��ʤ�����ˡ�פ��ܽ�Ǥ��������Ƥ��롣�������ʸ��θ��դǸ���ɽ���Сֲʳ�Ū����ˤ�ȤŤ����šװʳ��Τ��٤Ƥΰ��Ź٤Ȥ������Ȥˤʤ롣�ܽ�Ǥϲʳ�Ū����ˤ�ȤŤ��ʤ����Ť����Ǻᤷ�Ƥ��롣�����ơ��ʤ�������ĥ����Τ����ʳ�Ū����ʿ������ι⤤�ǡ����ˤˤ�ȤŤ��Ʋ��⤷�Ƥ��롣
���Ԥ��Ȥ����Ǥϡ�����ͤ����Ԥ������ϡ����������ڤ��Ƥ������ذ��Ťᥫ�˥��ब�ʳ�Ū������Ǥ��ʤ�����Ȥ��ä�Ƭ�������ꤹ�뤳�Ȥˤ���ΤǤϤʤ��פȸ��äƤ��뤬�������δ�����Ȥ��������μ�ĥ�ϸ¤�ʤ�����˶ᤤ���ֲʳ�Ū����ˤ�ȤŤ��ʤ���Τ�ǧ���櫓�ˤϤ����ʤ��פȡ�
�����Ǥϼ��פʡ�瑱ס֥ۥᥪ�ѥ����ס֥������ץ饯�ƥ��å��ס֥ϡ�����ˡ�פ˾����ơ��ʳ�Ū�����̵����������Ƥ���ʰ������ꤵ�줿���̤ˤĤ��Ƥ�ǧ��Ƥ�����ʬ�⤢��ˡ����������ʤ�����ˤ⤫����餺������ˤ�����¿���˿͡���ǧ�Τ�����ŤȤ��ư����Ƥ���Τ��������������ˤϲ��餫���װ�������Ϥ����������ǡ����̤���������Ƥ��ʤ����ޤ���ȿ�ڤ��줿���Ť��Ǥ�Ԥ��о�Ȥʤ롣������Ǥ�ԤȤϡ��֥���֥�ƥ��סְ��Ÿ���ԡס���ءס����ذ��Ť�Ƴ�դ����ס֥�ǥ����סְ�աס����ܤȵ���ô���ɡס������ݷءʣףȣϡˡס���Ǥ⥤���ꥹ�Υ��㡼�륺�����ҤΡȹ��ɤˤĤ��Ƥε��Ҥϼ긷������
�ʳؼԤ餷����������˰��夻�ʤ�ʸ�Τǡ����ġ��ǿͤˤ�狼��䤹�����⤷�Ƥ��롣�������ֲʳؤ������Ǥ��ʤ�����ʬ��ǧ��ʤ����ȤϿ��¤Ǥ���Ϥ����ʤ��פȤ�����ĥ�ˤʤ�Ȥʤ����ä������Τ����롣���Ȥ��ʳؤˤ�ä����ذ��Ť������ꤵ�줿�Ȥ��Ƥ⡢���ذ��Ť����䤹�뤳�ȤϤʤ��Ȼפ����ʹ֤ο��ˤ���ȹ��������˳���ڤ�ʤ���ʬ���������롣���줬�ʹ֤ƿʹ֤��餷����ʤǤϤʤ��������������ͤ���ȡ��ܽ�ϤϤ��ʤ��Τ褦�ˤ�פ��Ƥ��롣
�ѻष���ʤΰ���ȯ����������ޤǶ���ΰ��������δ֤˲������ä��Τ���
���������Ȥ��ƺۤ����Τϡ��פΥ饹�ƥ������ӥå������ʺ�Ƚ�����Ƚ�������ǹ��Ƚ��Ƚ�������������ǯ���ֿ���̵��פǺۤ���Ƥ��顢�Ƥӥ��ӥå������Ȥ���ˡ���Ω�ġ�
���䣶���Фˤʤä����ӥå�����Ĩ���ʤ�����Ʊ�����Ѥ��Ȥ��Ƥ��ޤ��������⡢��������ϣ����аʾ��㤤�����֤�Ĥ��κͽ������Ĥ�ʤ������ǯ�ˤȤäƤϤ����ޤ����������������Ѥ�����λ���ȴط�������Τ��ʤ��Τ������ӥå��Ϥ��Τ���˺ʤ����Τ�������������Ȥ�ï��¾���ȿͤ�����Τ������뤤�ϼ����ʤΤ���
�ֿ���̵��פǤϥ��ӥå���̵���Ƚ�褬�����줿��ΤΡ���������Ϥ�äƤ��ʤ��Τ�����������ʬŪ�ˤϤ���ʵ��Ǥ��̤����ڤ�ʤ����������ǽФ��줿����κ��ʡ����ӥå��Ϥɤ��ʤ�Τ���������ƨ���ڤ��Τ�������������ʻפ����ɤ߿ʤࡣ
�ֿ���̵��פ��ɤ�Ǥ��ʤ��Ƥ�ڤ����Ȥϻפ��������ӥå���¾����Ԥο�ʪ����Ƭ����ˤ������ٽ���Ƥ�����������ꤪ�⤷�����ɤ��Ȼפ���ˡ����̤����̤��촶�����ơ��������Ȥ����������������Ȥξ����̤�ʤ��ʤ��ɤޤ��Ƥ���Ƥ��롣
�ֿ���̵��פȽŤͤ��ɤ�Ǥ��ޤ��Ȥ�����������ߤ����������롢�ȤȤ�ˡ������������ɤȤ�������Ʊ����ʨ���Ƥ��ơ��ʤ�Ȥ��ԻĤʺ��ʤȤʤä���
������ä��ܤϤʤ��ʤ��ΤƤ��ʤ������Ĥ����ˤ��ޤ��ɤൡ����������ȡ��ȤäƤ���Τ����������Ǥʤ���Ф����ξ���ˤ��������ʤ��ʤäƤ��ޤ���
���ĤޤǤ���ê����ˤ��Ƥ����Τ⤷�㤯���������Ȥ��äƼΤƤ��Ǧ�Ӥʤ����Ƕ�ˤʤäƤ����椫�������ļ��Ф����ɤ��֤��Ƥ��롣�ܽ�⤽�ΰ�ġ�
��ǯ�֤�κ��ɤȤʤ롣
����ɤ���֥٥��ȡ��֥饤�ƥ��ȡפȹò��Ĥ�����������
��ͤθ��Ϥȸ������ǥ����ˤĤ��ơ�����ꥫ�Ǥ��ֶ����٤ȶ�Ǻ�ˤĤ��������줿�Υ�ե��������ʹ�仨��饸�����ƥ�Ӥ������ˤ��λ������ˤ������������̱�ȴؤ�äƤ�����������طʤȤȤ�˼������ޤ����줾��Υ�ǥ�����ô���ꤿ���οʹ�̣���դ��Ѥ������Ф��Ƥ��롣���쵭�Ԥ����̤������������ơ�������⤷������������������ǥ������ۤ��夲���ȼҼ�ɤλѤ���¿���Υ��ԥ����ɤ��̤��ƤȤƤ⤦�ޤ�������Ƥ��ƶ�̣������
�ܽ�Ǥϡ��亮��ȥ�ݥ��ȡ�������饤�ա��˥塼�衼�������ॺ�����������륹�����ॺ���ã£Ӥ��ɤäƤ��줾��Υ�ǥ����ΰ������ڤ��äƤ��롣
�äϥ��ͥǥ�������˥����������Τλ�����طʤȤ����٥ȥʥ����衢��������������������������Ȼ���������Ȥ��Ƽ��夲�Ƥ��롣
�ɤΥڡ�����ȤäƤ⿷�����äФ��ꡣ�������ä˰��ݤ˻Ĥä��Τϡ���ʹ������饸�������θ��Ϥ�̩�ܤʴط��ˤ��ä����ȡ��Ȥ��ˤ������Ȥ����ۼԤ��Τ�ΤǤ��ä����Ȥ⤢�ꡢ�ޤ����줬��ǥ����ΰջפǤ⤢�ä��Ȥ������ȡ��ƥ�Ӥλ���˰ܤäƤ���ϼ���ˤ��η����������ʤäƤ��������դ������Ȥ��ƥ�Ӥ����Ѥ��Ϥ�롣��������ǯ�����������ǤΥ��ͥǥ��ȥ˥�����Υƥ��Ƥ���Ǥϡ��ޤ������ƥ�Ӥ�����Ū���Ϥ���Ĥ��Ȥξں��Ȥ���ǧ������뤳�Ȥˤʤä������ȤΤ����ͥǥ�¦����Υƥ�ӱǤ��褯���뤿��ˤ�������֥ޥå����ե��������Υ����ѥաפ����ξ��Ԥ�����ȤϺ�������ˤʤäƤ��롣���θ塢�ƥ�Ӥ����������Ȥ��ڤäƤ��ڤ�ʤ��ط��ȤʤäƤ��ä���
�ޤ������������������Ȼ�����ƻ��¦�ˤ��ä��ä�¤˶�̣���������λ������줾��Υ�ǥ����Ϥɤ�ư�����Τ������쵭�Ԥȥ�ǥ����ȥåפȤΤ���ꡢ�����Ʋ�Ҥα�̿����뤳�Ȥˤʤ뤫�⤷��ʤ���������ƻ���Ф���ȥåפη��ǡ�����餬�촶���äפ��ɮ�פ�������Ƥ��롣
��ǥ�������ʹ�ꥫ�ʾ��ʤ��Ȥ⤦��ʬ�����ܤΤϤ뤫���ԤäƤ���ȻפäƤ����ˤΡ������Τꤨ�ʤ��ä�������������������Ƥ��롣
�⤷�����ơ�����ϡ�LOST�פߤ�����ʪ��ʤΤ����������ɤ�Ǥ��뤦���ˤ���ʻפ���Ƭ��褮�롣
�ƥ�ӤΥ�����ӥ���Ǯ�����ǥ����ʡ��������������ϡ����뤳�Ȥ�������ڤ곫���Ϥˤʤ����롣�����������ڤ곫�����Ǥ���פ��⤤�Ƥ�����
��������κ���ϲ������䤿����ī�����Ƥ��顢�뾲���夯�ޤ��͡�������ȷ��Ǥ�Ȱռ������˲����Ƥ��롣������������ξ�硢�ä˺���ʾ��̤����������Ȥ������餫�ˤ��줫��ʤ�٤�ƻ�����������졢�����ռ����롣
�����˽ФƤ������Ϥ�������Τ��ɤ������Ω�������׳ؤ˵��롣�����ʤäơ������ʤäơ���������ȼ��˵����ꤦ������ޤϡ������Ƥ��γ�Ψ�ϡ�����������������ʬ���ȤǷ��Ƥ����Ϥ��ι�ư��������Ū̵�ռ��˺�������Ƥ����Ȥ����顣
�����������ܤν����䡢�ݡ�����������ʤɤ��Ω���Ǥ䤵�����Ҥ���ꤷ�ơ����ؤ�ʪ���˶�̣�Τ������ˤϤ�������ܤ��⤷��ʤ���
����ȡ������Ρּռ��פ���Ԥο����������Ƥ���褦�ǹ����ݤ���������
��������ǯ�˽�Ƥ��뤳���ܤϡ����Ǥ˥���֤ȥ���ꥫ�Ȥ��᱿��ª���Ƥ�����
����ꥫ�Υ����饨��ؤ���ﶡͿ���Ф���ѥ쥹���ʥ�����������
�ƥ��μ��Τϥѥ쥹���ʥ���餫�饤����ึ���������ɤؤȰܤäƤ�����
���������λ���Ϥʤˤ������˹ߤä�ͯ������ΤǤϤʤ����Ȥ餿��ƴ����롣
�ѥ쥹���ʥ����ȼ���֤Τϡ����ȤΤ����Ǥ˰������Ƥ�����̾�⤭�����ե��纴�������ƥ٥ȥʥ��������κ�Ȥʤä��������������Ф���ϥѥ쥹���ʥ�����ǰ�����ɤäƥ���ꥫ�ˤ�ä��褿�⥵�ɤ�ĵ����������������������Ƥ��Τ��������ˤ�������Υեåȥܡ�����Ǥ�����̵���̻��͡�
ʪ�����̩�ǥ��ȡ��Ū�ˤ���þ�Ϥʤ�����Ԥ���ǫ���������ޤ�Ƥ��롣���̺��⿽��ʬ�ʤ��������Ū�ˤϻ���������뤬����ή�Ԥ�Υ����åȥ����������������ڥȤϰ�äơ��Ҥ��Ҥ������꤯���ĥ�������ޤ�ʤ���
�ܤ����˽Ф�Ȥ������Ȥϡ����֤�ˡ������ˤ��Ȥ���������ΤǤϡ��Ȼפ����Ȥ�¿�����롣
�ܽ�⤽�ΰ�ġ����ޤ��ޤ��κ��ʤ�¼��ռ����ܤˤȤޤꡢ�बˮ�����뤳�Ȥˤʤä���
�ܤ�ɽ��ˡ�¼��ռ����ɤȽ�Ƥ��ʤ���С���ʬ���ܤˤȤޤ뤳�Ȥ�ʤ��ä���������
¼��ռ������Υ��ꥸ�ʥ�Ϥޤ���Ĥ��ˤȤäƤ��ʤ��Ȥ����Τˡ���������������Ϥ���ǻ����ܡ��༫�Ȥκ��ʤ������ν�ê�ˤʤ��櫓�ǤϤʤ��Τ������ʤ�����Τ��Ƥ��ޤäƤ��롣
���ܸ�ʳ��ǽ줿�ܤϡ�ˮ������Ƥ��ޤ��ȡ����λ����Ǥ��Υ��ꥸ�ʥ����Ϥʤ��ʤäƤ��ޤ���¼��ռ��Τ褦����̾�ǰ���ʺ�Ȥ������Ȥʤ�ȡ����κ��ʤϤ��κ�Ȥ��������ܤ����顢�����ɤ���ͤ���Τ��������Ȥ������ȤǼ�ˤȤäƤ��ޤ����ºݡ�����ޤǤ��ɤ��¼��ռ����κ��ʤϡ����δ��Ԥ餮�뤳�ȤϤʤ��ä���
���������ä����Ȥ����������������٤ˤ⣴���٤ˤ�ʤ���̤Υ��٥ꥢ���������档
���ҤȲ��������ȥ��٥ꥢ�θ����������Ȥμ���碌��̯�˥ޥå����롣
�������줿���ǤΥ��Х��Х��ϣ����������ʡ��ȽŤʤꤢ����
����¼��ռ������κ��ʤ�ˮ���ˤȤ꤫���ä��Τϡ�������������ǯ�����κ������ǤΤ��λ��ࡣ�֤��κ��ʤ������η����Ȥ�����������ΤǤϤʤ��פȡ����Ȥ����ǽҤ٤Ƥ��뤬�������ż����������Ƥ�����ΤϳΤ������������ΰ��פ�ª����ʤ�Ф���ޤǤ����������ǤϤʤ��ԻĤʰ���Ȥ�����Τ����ϻ�����ǤϤ���ޤ���
���������ơ�����������˽Ф���뤳�Ȥˤʤä����κ��ʤ��Ϥ�פ鷺�ˤϤ����ʤ��ä���
�ʤ������ǼԤ����Ǥȿʲ�������ӤĤ��Τ���
��㡼����Ǥϣ�������ǯ��Ǹ�ˣ����ǼԤ��ФƤ��ʤ��������Ϥ�����Ϥθ�����Ф��ơ��Ƿ⤬�ɤ��Ĥ��Ƥ��ʤ�����ʤΤ�����Ψ������Ū�ʤ�ΤǤ��ꡢ��������ȥ����ʤɤΤ褦������Ū�ʵ�Ͽ�Ȥϰۤʤ롣�����������ϤϤ������١�����Ū���ͤ�¬�뤳�Ȥ���ǽ�������顼Ψ�ʤɤ�����Ū�ˤߤ�ȳμ¤˾��ʤ��ʤäƤ��Ƥ���ʤ���ˤϥ���֤θ���ʤɤ�����Ƥ���ˡ�
������ʿ����Ψ�ϡ���㡼�������ˤˤ����ơ��ɤλ���Ǥ⤪�����2��6ʬ����פ��Ƥ��ꡢ�礭����ư�Ϥʤ����ܡ���οĤ�Ť������ȡ��������֤褦�ˤʤ롣����Ϥ���ǴѵҤδ�ַ�̤ˤʤ���⤢�뤬����礽�Τ�Τ���̣�ˤ��ƤĤޤ�ʤ����Ƥ��ޤ�������ȡ��ԥå��㡼�ץ졼�Ȥȥۡ���١����֤ε�Υ�Ф����Ȥˤ�äơ���Ψ�Ϥ������ٸ�������������Ƴ����롣
�Τϥ����֤ȥ��ȥ졼�Ȥ��餤�����ʤ��ä�����������ǼԤ�ͭ����Ư������������������֤θ��夬�����Ϥ�����̤�⤿�餹���Ȥˤ�Ĥʤ��ä����ΤΥ���֤ϵ��������ȥ����ɤʤɤĤ��Ƥ��ʤ��ä��Τ������Τ�������郎�����Ƥ���ȡ�����¦��ͥ�̤ˤʤäƤ��롣���������ǼԤ��Ƿ�Ѥθ���ˤ�äƤ�������Ŭ������褦�ˤʤ롣
�褦����ˡ������椦���ȤʤΤ���
����κ��Υ�㡼����ǤϤޤ��������Ƿ�Ȥ�˵����ϤϤޤ�ȯŸ�ʳ��ˤ��ä�����Ψ������ϤϸĿͤ���ŷŪǽ�Ϥ˺������줿��ʿ����Ψ����2�䣶ʬ�Ǥ��äƤ⡢����ˤϺ������������ޤǡ��礭�ʤФ�Ĥ���¿�����ˤ��ߤ�줿��4���ǼԤ�Ф�����ˡ�1��������ǼԤ�¿���ä��櫓�������줬�����夬���ĤˤĤ�ơ��Ƿ⡢���������˵���Ū���夬�ʤߡ����ΤȤ����礭�ʤФ�Ĥ�����¿�������˾��ʤ��ʤä��褿������Ψ�Ǹ�����ɸ���к����������ʤäƤ����ˡ������ο��줬���ʤ��ʤꡢ��Ψ���Ѱۤ�����ȤȤ�˶Ž̤���Ƥ��������������α�ü�˰��֤���4��Ȥ�������⺸��ư����4���ǼԤ��Фˤ����ʤäƤ����Ȥ����櫓�����������������4���ǼԤ����줫���衢�Фʤ��Ȥ������Ȥ����ȤˤϤʤ�ʤ�
�ʤ�Ȥʤ�ʬ���ä��褦�ʡ�
����ޤǰ���Ū�Ǥ��ä������������̿���Ȥ���ȿ����¿�����θ������᱿¿���ब�ʲ��λѤ��Ȥ���������ɤ���ˤ϶��ĤǤ��롣4���ǼԤ����Ǥ���ͳ�ϡ������ϸ���ˤ��¿�����θ�����ɸ���к��ν̾��ˤ���Ƴ����롢�Ȥ������Ȥ�ʬ���ä��������������ɤ��ʤ�4��Ǥʤ���Фʤ�ʤ��Τ�������ˤĤƤ��Ϥ��ް�IJ������ʤ��ä��褦�ʵ������롣
��������ǯ�����ʥ����֥�ƥ��å��塦������ӥ�������ü�˰��֤��륫�ʥǥ�������å��������ƥ������Ϥι��٣���������ȥ�μ��̤�Ϫ�Ф��Ƥ��륫��֥ꥢ����ʣ�������ǯ���ˤ��Ǵ��ؤ���ưʪ���β��Ф�¿�����Ĥ��ä���
��������ǯ�夫�顢���β��з��κ�ɾ�����ʤ��졢��������©���Ƥ�����ưʪ�ϸ��ߤ�ʬ�ෲ�ˤ��ƤϤޤ�ʤ���Τ�¿�����뤳�Ȥ�Ƚ��������
�������顢���ԥ�����ɤϿʲ����ˤĤ��Ƥκƹͤ�¥���ȼ��μ�ĥ��Ÿ�����롣
���ʤ����
�ظ�����ʪ�˸�����ѥ������Ϣ³Ū��¿����������ȿ������ˤ�äƤ�ä���ȿʲ������櫓�ǤϤʤ����ʷ���Ū�ǥ����ǽ�˵�®��¿�Ͳ�������˵����ä��ˤȤ�Ǥ�ʤ��᱿¿����ˤ�äƤ��Ĥ館��줿��ΤʤΤ���
����ϡֶ�ȯ����Ż뤹����³Ū�ʲ����פǤ��ꡢ����ޤǰ���Ū�˾������Ƥ����ʲ����μ�ή���ּ��������κ��Ѥ����¤˽Ż뤹������Ū�ʲ����פ���ȿ���롣
�ܽ���ɤ�����������ʪ���¿�������ԻĤ˻פäƤ��������Ȥ��С������ȩ�ο��䡢�ܤο���ȱ�ο��ΰ㤤�ϸ���é��Ȥɤ��˻Ϥޤ�Τ�����������褬���ͥ��ߤ�Ʊ���ȤϤȤ��Ƥ��פ��ʤ������ϲ����䡢�Ф�ȩ�οʹ֤⤤���ΤǤϤʤ������������ä�¿��¿�ͤ���ʪ�����ơ������ΰ��������Ǥ��Ƥ��ޤä������Ĥ꤬���ߤ���ѤʤΤǤϤʤ������ȻפäƤߤ��ꤹ�뤳�Ȥ⤢�ä���
�ܽ�ϡ�����������ޤ������Ƥ��������ޤ����Ȥ��������Ф��Ƥ��줿������Ǽ�ʬ���и��˼��Ȥ����Ƥ����ޤ���ȯ���γڤ��ߤȴ�Ӥ����������Ф���Ƴ���Ф����ʲ����ιͻ��β������ǿͤˤ�褯�狼��褦�˽�Ƥ��롣
�ѥ���μꡩ���λؤϣ��ܤ���Τ������������Σ����ܤοƻؤˤߤ���ؤȤ����Τ����¤ϼ��ι��ΰ������Ѳ����ƤǤ�����Ρ��������դäѤ��Ϥ�Ǥ���ޤ����˱��٤�褦���ȿƻءɤμ��դˤ϶�����ȯã���Ƥ��롣
�����狼��䤹�����⤹���ΤȤ��ơ��֤��ι��ϼ翩���륵���٤뤿��˾������ġ�����Ū�ˤ˿ʲ����Ƥ��ơ����ߤη��ˤʤä��ס��Ȥ����Τ����롣
�����������ˤ���Ǥ����Τ���������������ɤϵ�����褹��
���������ּ�ε����פ�ȯɽ�����Τ�1859ǯ����ʬŪ�ˤϿ�ʬ�ΤΤ��Ȥ��ȻפäƤ��������ºݤϤޤ�150ǯ���餤�������äƤ��ʤ����ʲ����Ϥ��Ǥ˳�Ω���줿��λפäƤ��������ºݤϤ����ǤϤʤ��褦����
�ܽ�ϥ���������ʹ߽������Ӹʲ�����ƹͤ���ҥ�Ȥ�Ϳ���Ƥ���롣
�����ܤ���Ƽ�˼�ä��Τ���ǯ�������κ��Ϥޤ���ʬ�˴�˾��̤�褬���ä����������ȱ���Ӥ⡦������
��ϡֱ���˥��㡼�ʥ롢����˥ޥ�����פ����夫�龯���٤����ͤˤʤäơ��Ҳ�ͤȤʤä�����Ȥ��̤Ȥ��ơ����Υե졼���Υ��å��褵��ƴ��ơ�ī�����㡼�ʥ�Ф��֤��Ƥ����������餯���κ��ʤϤ���ī�����㡼�ʥ�˾Ҳ𤵤�Ƥ��ơ��㤤����Τȵ������롣
������ǯ�λ���ФƤκ��ɤȤʤä���
�إ٥��ȡ��֥饤�ƥ��ȡ٤Ȥϥ��ͥǥ������������Ѥ����ֺ��ɤˤ��ƺǤ������ʡͺ�����仿���줿�͡���ؤ�������ʥ����ã���äƤ��Ƥ⡢����ꥫ�ϥ٥ȥʥ�����Ȥ���ť�¤ˤϤޤ����Ǥ��ä������Υ���Ȱ�Ͱ�ͤ��ɤ�ʿ�ʪ�ǡ�����ΰ�ڡ����Τɤ���ʬ��ô�äƤ��������������Ȥˤ�äơ������Υ���ꥫ�Ȥ����Τ�Τ֤�Ф��Ƥ��롣
��̱�δ��Ԥ�����ä��㤭�������Ȥ����о줷�����ͥǥ��Ⱥ��Υ��Хޤ��Ťʤꤢ����
���פʹ�ΰջ��꤬�ʤ��������ˤ����ơ���餬�ɤ������餸�Ƥ�������������������Ƥ��롣���Ҥϳ��ͻ��ּ��˱�äƤ��뤬����ͤ���Ԥ��о줹��Ȥ��ο�ʪ�����٤��ơ���������Ȥ�����ˤޤĤ���̤���Ԥ�ʪ����̤λ��ݤθ��ڤؤȰܤäƤ������ʤΤǡ��ä����ä���������ꤳ�ä���������ꤹ�롣�������٤Ƥˤ����Ƥ���ʴ���������ʥ����Х��˻��ּ��Ȼ��ݤȿʹ֥ɥ�ޤȤ�������䵡ɤ�פ��Ĥ��ޤ�Ž���դ��Ƥ��äơ�����餬ͭ��Ū�˷�Ӥ��äƽ���Ƥ��롣
������������Ƥ���Τϡ����Ͽ������οʹ֥ɥ�ޤ��˱ɤ���Υ���ꥫ�ζ�Ǻ�Ⱥ��ޤ�ƱĴ������������ꥫ�θ���ˡ�����ꥫ����Ԥ˵ڤ���ȷаޡɤȡȤ櫓�ɤ����Ⱥ٤���������Ƥ��뤬������Ǥ�ʤ�����������������ʤ��ä��Τ��������ܤ��ɤ�Ǥ���桢�������ɤ߽���äƤ���⡢����˶줷�ࡣ
ɴ����äơ��٥ȥʥ�˲�������������ʤ��ʤä��Ȥ��Ƥ⡢�����⺣��Ƕ��η������ĥ���ꥫ���ʤ��٥ȥ�����̥٥ȥʥ�ˡȾ��ơɤʤ��ä��Τ����������ʤ����Х��饯�Ǥκ������������ܤ�������ˤ��Ƥ���Ȥʤ����餽���������롣�������٥ȥ���¦�ˤ��ä��Ȥ������Ȥϴְ㤤���ʤ��Τ�����ɡ�������
�ϥ�С������बɬ��ˤʤä��������������ष��餵�εͤޤä����ʤ������奢��ꥫ�ˤΥ��֥ƥ����ȤȤ��Ƥ⽽ʬ���Ѥ���Ȼפ���
��ǯ������˿�ۤ�ͽ�ơ���äȡ����äƤ����ܽ�˥說�說��ʬ��
��̾���顢�ʤ�Ȥʤ���Ω�Ƥ��������Ĥ���������Ǥ�ͽ��Ĵ�¤˴٤餺�����Ԥ��ڤ�ʤ��Ȥ������Ӱ�ͽ����
����μ������̩������¤�Ȥ�������ꡣ�����åȥ���Υ����ǥХ����Ȥʤ�Х�֥����ƥ��ᤰ�äơ����軺�Ȥ���������Ź��ȤȤ��Τ����롣
��Ĺ��̴���餺���ơ���ҷбĤϤ������ʤ���
��ʬ�ο�����ޤ����ꡢ���������ʾ㳲����ޤ����Ƽ��Ԥ�̣�襤�ʤ���⡢̴���ɤ������Ƥ����ο�������
�ȥǥåɡ����������饤�֡ɤȤϡ������फ�פΰ�̣���ȻפäƤ�������������鷺�פΰդ��ä������ʤ����Ƥ��餷�Ƥ�ְ㤤�ʤ���ԤǤ�������
����ֹ�ݥƥ��פϥ���å����饤���������������Ƥ��줿���������������ò����ɤδ����̤����ʤ��ä����ܺ��ʤϤ����������Ȥ��ä��Ȥ������Ϥ��������Ƥϡ�������
���ѥ�����������顼��ʬ��Ǥϡ��������ェλ�塢Ụ̃���ط��ι��ޤ��Ѥ�ꡢ�ƥ��ꥹ�Ȥ�����ꥫ�ΰ��������ФƤ��������������塢���η����ϸ����Ȥʤ롣
�ȥࡦ������Ϥ��κǤ����Ρ���Ϣ�κ�Ԥκ��ʤ��ɤ�Ǥ���ȡ�����ۤɤޤǤ˥�����ඵ�̡ʥ�����ึ���������ɡˤԤˤ��Ƥ�褤��Τ��ȻפäƤ��ޤ���
�����������Υ��ѥ�����ϡ�����ΤΥ����ƥ����ȤȤ��ơ�����Ϥ�����ɤߤ����������ä��������������λ��塢�ƥ��ϥե��������Ǥʤ��ʤꡢ���ζ��Ҥϸ���̣�Ӥ���Ƥ��롣�����ʤ�ȡ���������Ȥ�������Ϥ���ʾ�Υե���������������졢�ɼԤϤ�괰���٤ι⤤���ʤǤʤ��������ʤ���������
�ȥࡦ������������ȸ����ɤ⡢���Υϡ��ɥ�Ϥ��ʤ�⤤�Ϥ���
��ԤϤ��ι⤤�ϡ��ɥ�ۤ���饤������������ɽ�⤽��˴��Ԥ���������ϥƥ���Ω������������ꥫ�ȥ���å����饤����Ρ������ɤ�ʪ������ʤ�Ȥ�����̣��Ф����Ȥλ�ߤ��ʤ��ǤϤʤ��������Х���̤Ϥ���ޤǤκ��ʤˤʤ�¿�������������Хƥ���ʪ��Ͽ��ߤ˷礱���Ȥ�����������ޤǤκ��ʤΰ��Ķ���Ƥ��餺���ڤ��ߤ��Ƥ����饤����ȺʤΥ��㥷���������ʪ���ޤ����Υ������٤��Ƥ����ˤΤ�����ʤ����������ΤȤ��Ƥ����̤�礤�Ƥ��롣
����ۤɼ�˴����ꡢ�說�說�����ɤ������å����饤��������ǯ�������ݤ�ʤ��褦����
���ֵ��ղȤ�����פ��饹�ԥ��դ��ƤǤ������ʡ�
�Ϥä�����äơ�����ϥޥ���
���������Ʀ��Ʀ��Ļ����ּ�¼�ˤ�����Ŵ��Ҥμ�Ĺ��Ĺ����
����Фˤʤä���ؤ�����䤤�ʤ䡢��Ʀ�ϥХ����Τ��Ĥ˥��ߥ�ûҤ�褻���ļˤ�ƻϩ��Ѥ��顢�Ѥ���ȶȴ���롣��Ŵ���ɾ�Ʀ�ϥ�ǥ���������Ŵŷ�ȡפν�����Ĺ�Ȥʤäơ������륺ã����Ļ�衢���������硢���������Ƥ��Ƥ���
��������餺����̵�Τʥ��ȡ�������ʺ���ϥϥ��������ˡ���������ǯ�夫��λ����طʤ���������ޤ�������������̴ʪ����̤��ơ���Ĥλ�����ڤ��äƤ��롣�Х����˸٤�̴�˸����ä��ͤ��ʤ����ã�������������ν�褵�ϥ��饹�Τ褦���Ȥ������Ƥ��롣�������դ⤦�ޤ��Ȥ߹���ǡ������Υϥ������㥳�ߥå��ǤϤʤ��Ľշ����Ȥ��Ƥ��롣
�����������Ǥ���줬�ܽ���ɤߤɤ����ΰ�ġ����Ӥ�뤼����
�ؿ����֤�dz���褦�������ƻ����
��ϩ���������ϩ���˻ह�����줬����ʤ������ͤ�������
�ؤ������顢�ϥ��������������Ƥ롪���餫���ˤ㡢�����Ф��㤯������
���������á�����Ʀ��Ʀ�������ɤ������褦�ˡ��ϥ������������ˤʤ�á����줬���ޤ��λ�̿������á�
�ؤ�������������ǯ�Ȥ���äȡ����ޤνդޤ�ͷ���ݤ��Ρ���Ʀ�����Ȥʤ��Ϲ��ޤǹԤ��衣���ޤνդ˾ФäƤ��̤줷�褦������ޤǰ���ͷ�ܤ��衣�������Ǥ⤤�����餤��������̵�㤷�褦���͡������äƸ��äƤ��硼����
�饸���ϡ����Ĥ�Ż��桢�֤����İ���Ƥ��롣�����ΣȣˤǻϤޤä����֤פäĤ�פ���ʤ��ơ֤��äԤ�ס�������˥ѡ����ʥ�ƥ������Ѥ�ꡢ��������ô�����ⶶ����Ϻ���ʤ��ʤ�����̣�Ф��Ƥ���ʤ��Ȼפ��Ĥġ�İ���Ƥ��롣�ڤ����뤯�餤�ΡȥΥ�ɤǡ��桼�⥢�����äơ����䤫�����ɡ������������ա١���ȯ���Ƥ��롣
���Τ���٤꤬���ޤ��ʸ�Ϥˤʤä������κ��ʡ�
��Ū�ǡ���ʸŪ�ǡ���Υ�����Ǿ��굤�ޤޤ˼�ʬ�θ����������Ƚơ�
�֤���Ǥ����Τ��פȸ��äƤ��롣
�ܵ��ʤΤ�������������ʤΤ���
����ʤ���Ӥ������Ƥ���Ȥ������ȼ��Ρ��Իġ����äѤꡢ�狼���
����å����饤�����©�Ҥ��Хƥ���ư�˾��Ф���
���פ������פˤ����Ƥϡ����ο�����������ۤ��뤿��Τ�Ρ����Ĥ�Υ�����ˤϤߤ��ʤ�����������Ū�ʵ��Ҥ���Ω�ġ�
����ޤǤΥ饤������Ρֻפ�ɤ��褫���������줬���Ƥ����Τ��������ޤ��褫������Ƥ��ʤ���
�����������Ԥ�ɤ���꤯�ꤷ�Ƥ����Τ������줫���Ÿ���˴��Ԥ�������
�岼ʻ���ơ�1600�ڡ������Ķ����������ǯ�˽졢��������ǯ��ˮ�������Ǥ���Ƥ��롣�����ϡ�����å����饤��������ܤ��Ф����Τޤ��ޤ����ȡ��Ԥ�˾��Ǥ����Τ�פ��Ф���
�����ɤ��֤��Ƥ⤵�������ʤȴ������뼡�衣��������ǯ�Ȥ����С��Ѵ�������ȯ��ǯ�����ӥ��Ȥ���������ǯ�Ǥ⤢�롣���κ��ʤ��������ェ��Τ��Ȥ���̯��ɺ���������������������Ƥ��롣�ޤ������θ�ˤ��륢��ꥫ�ȥƥ��ꥹ�ȤȤ��з衢�����ˤ��������뤳�Ȥˤʤ�Τ�������ͽ�����Ƥ����ܤǤ⤢�롣�ֹ�Ȥ��岡������ƥ��ꥺ���������פȥ饤����ϸ��äƤ��롣
Ĺ�Ԥˤ⤫����餺�����Τ˾�����̵�̤�̵���������Τ�����̵�����ƥ��ꥹ�Ȥθ�����¤�β����ˤ����äƤϡ��ʤ�ۤɤȴ���������줿������ʤˤ⤿�䤹�����������褦���ΤʤΤ��ȡ������ƥ��Ρ����ѥ�������ϡ��饤����γ�ƣ�Ȱ��������勞�勞���ƥڡ������ä���