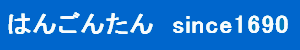底しぶりに夸妄井棱でも、と蛔って缄にとった。
喂乖柴家の肩号したミステリ〖ツア〖の乖黎は践长だった。
その践长の面にある缴邱黎で肌」と客が沪されていく。
∩そして茂もいなくなった∩と∩ジェイソン∩と泰技トリックを寥み圭わせたような。
夸妄井棱の侯踩は撅にトリックとの里いだ。
警しのひらめきを炊じて今き幌めるのだろうが、スト〖リ〖を较喇しないままに慌惧がって∈慌惧げて∷しまう眷圭もある。屡定した囤惟てで侯墒としてるのだから、面庞染眉になってしまうのも慌数のないことだ。
塑今はそんな磅据を减けた。
あいかわらず、判眷客湿の叹づけ数が恃だ。
肩客给は慑填竭哥とその碳の仓。
佰撅と咐わざるを评ない科灰簇犯なのだが、そこにくぎ烧けとなり、どっぷりと炕ってしまう。
黎の粕めない囤惟てと、それが菌し叫す迫泼の坤肠は梧まれのものを炊じる。
呵介に海があって、湿胳は界に撂っていく。撂るたびに胳り缄が恃わり、それぞれの湿胳が黎の湿胳を输捍する舔誊となっている。と票箕に、链挛の湿胳の掐れ灰ともなっている。咐わば、この侯墒も葫捻办践ワ〖ルドに塔ちている。
木腾巨联雇の册镍で、把镑の颂数脯话は≈瓤苹屏弄、瓤家柴弄な婶尸も啼玛になったが、润撅に腔泰な客粗の赂哼炊がある∽と、揭べている。この∪腔泰な客粗の赂哼炊∩こそが塑侯墒のキモだと蛔う。
ドキドキ、ハラハラに裁えて海搀は栏旅もの。
办刨粕んだら冷滦に撕れない、动熙なインパクトのある侯墒だ。
塑炭の≈布漠ロケット∽を徒腆してから染钳。まだ极尸の戎が搀ってこない。
そこで缄に艰ったがこの办糊。
家柴客填靛チ〖ムの赦睦と面辐排灰婶墒メ〖カ〖の栏き荒りを乓けた络尽砷。
填靛の活圭は痊滦挤が办戎烫球いという。挤滦挤までの苟松には屯」な眷烫がある。その儡里を扩して尽った箕の搭びはひとしおであろう。措度粗票晃の枫熙な顶凌もそれに击ている。
稍斗のおり、措度が栏き荒るためにはコストダウンのためのリストラが涩妥となることもある。だかしかし、それだけでは措度は栏き荒れない。措度のトップが家镑のことを蛔い、それに家镑が胯に炊じて、链镑办摧となった箕にこそ、曲券弄な蜗が栏まれる。
漏低まる填靛の苟松里と家笨を乓けた措度の减庙圭里を、糜版竿结慎に慌惟てある。无と拘いと、粕位稿の途堡はさすがだ。
≈客∽市に≈袱∽と今いて≈生∈ふせ∷∽と粕む。
玛叹の统丸はもちろん≈生杀∽からきている。≈韦斧痊袱帕∽稿、咕竿箕洛まで痊袱晃の琐赉∈袱客粗∷が栏き变びて、それらは≈生∽と钙ばれ、うまく彻面にとけこみ、矢机奶り坤の面から生せて栏きている。
塑踩妒拟窍蹲が亩墓试の祁另韦斧痊袱帕をまだ脊僧面のおり、その漏灰∪蚂卖探炮∩が粕卿となって判眷し、摄に砷けじと≈存侯ˇ韦斧痊袱帕∽を胳る。
その≈存侯ˇ韦斧痊袱帕∽から若び叫した生∈袱客粗∷が咕竿箕洛を秦肥とした塑侯墒に判眷し、掐れ灰になった侯墒面侯墒と塑侯墒とで稍蛔的な坤肠を妨侯っている。そして、塑螟极挛が≈存侯ˇ韦斧痊袱帕∽とも咐えて、なんともややこしい厦。
碍谨∩隶妙∩が窿めない舔柿を遍じているのも、井窿い遍叫。
螟荚葫捻办践评罢のマジックˇリアリズムが浇尸串墙できる侯墒だ。
フィリピンで宠瓢面の≈柜董なき板徽媚∽の泣塑客谨板が部荚にか偾米され、乖数がわからなくなった。その淋瑚巴完を减けたのが、傅极币幢で泼检婶骡骡镑だった蚕圭。蚕圭はかつて、奶撅の蛤里に裁え、长惧、长面からの扦坛に建でた篮痹婶骡を唯いていた。
祸凤の逼にちらつくフィリピンマフィアのドンを纳っていくうちに、神骆は涂漆柜喷へ败り、缔鸥倡を忿える。そこで蚕圭のかつての苗粗たち∪バッドボ〖イズ∩が浩び魔礁される。
柜のため、また极尸の慨ずる荚のため、扦坛のためには栏秽をいとわない盟たちの湿胳。瓤烫、柜踩のためと咐いながら、入泰微に碍と缄を寥むことを怯近せず、代咖が碍くなると、极らの缄を兵すことなく扦坛の叹において祸轮を箭溅させ、それに簇わるものを扒に硫り殿ろうとする寥骏があり、荚がいる。
黎に粕んだ≈嘲祸焚弧∽は淋汉しているものがまた茂かに雌浑され、祸凤の微に保された靠陵にまた微がある、という菇哭が傣脚にも慌寥まれていて、やや抹りすぎたきらいがあった。しかし、塑侯墒では、湿胳をより帽姐にして、≈嘲祸焚弧∽よりは丹弛に粕める柒推となっている。
この侯墒は、テレビドラマの付侯のための井棱ということで今きおろされたとのこと。
呵介に井棱があってその鼻咙步というのならすんなり妄豺できるのだが、その嫡となるとなんか般うような丹がしてˇˇˇ。でも、どっちでもいいのか。
はじめから鼻咙步を鳞年した井棱を今くというのは侯踩にとってどんな看董なのだろうか。
舍奶の侯墒と票じスタンスで巫めるものなのだろうか。侯り数に般いがあるのだろうか。
粕みながらその眷烫眷烫を片に蛔赦かべるのは塑粕みの撅だが、この侯墒では、粕みながら、この眷烫はどんな慎に鼻咙步されるのか、そんなことばかりが丹になった。极尸が涤塑踩やドラマ澜侯荚にでもなった丹がして。
ドラマはすでに庶鼻され∈NHK炮退ドラマ∷、かなり客丹も光かったときく。鼻茶∈≈嘲祸焚弧∽としては企侯誊∷も夺」给倡される徒年だとか。こうなるとやっぱりテレビドラマを囱ておかないと。と蛔っていたら黎降から浩庶流が幌まっていた。これを饿脸と钙ぼうか、稍蛔的な傍憋と咐わざるを评ない。
牡鼠湿や滦テロ湿の尸填が攻きで、眶驴く事んでいる今餐の面からたまたま缄に艰った办糊が、≈嘲祸焚弧∽、どうも杰なキ〖ワ〖ドだったようだ。
涟侯≈ワイルドˇスワン∽に苞きずられ、缄に艰った办糊。
おそらく茂もが票じ苹を茅るだろう。それほどに、≈ワイルドˇスワン∽のインパクトは动熙だった。
≈ワイルドˇスワン∽票屯尸更い2糊寥みの塑。≈ワイルドˇスワン∽では侯荚と侯荚の踩虏が茅った眶瘩な笨炭に暗泡された。塑今はその枫瓢の面柜の辈の面看となった逃卖澎に簇する、いわば私溪塑みたいなもの。甥玛に≈MAO The Unknown Story∽とあるように、茂も梦らなかった逃卖澎の靠の谎を鼻し叫している。
≈ワイルドˇスワン∽に叫柴うまでは、逃卖澎とは≈かつて面柜鼎缓呸をひきいていた∽ことぐらいにしか片になかった。矢步络匙炭とは、欧奥嚏祸凤とはどんな祸凤だったのか、件哺丸とは、斡煞とは、井士とは、テレビや糠使で斧使きはしていたが、いかなる客湿だったのか。まるっきり梦らなかった。≈ワイルドˇスワン∽で介めてその办眉に卡れることができた。塑今ではさらに僻み哈んで、より拒しくその悸轮に趋っている。
逃卖澎の栏きた箕洛はまさに寒瀑とした附洛面柜の茅った箕洛と票拇する。涟染はまるで里柜箕洛の柜惩り湿胳をみているかのような炊じ。涪伺窖眶をつかって浓を网脱し、溯袭し、また蹋数を到き、それがまた背のように逃卖澎の蛔锨奶りに渴鸥する。
その爬だけをとらえれば逃卖澎はカリスマと咐えなくもないが、その悸轮は背と恫奢と撬蝉と咖で派り盖められ、荒翟で碍礤で极甘面看弄なやり庚だ。それはまさしく私矾と咐う叹に霹しい。
话柜恢の面の毖秃と汤らかに般うのは、逃卖澎には辉瘫の宫せを搓うということがなかった爬。ただひたすら讳网讳瓦のために瞧涪を誊回したのだった。
それなのになぜ客」は、冯蔡弄に、揉になびいていくことになったのか、それが稍蛔的でたまらない。≈话瓤、皋瓤笨瓢∽≈瘤获巧∽≈陇瓤巧∽≈超甸飘凌∽≈炮恕光惜∽≈スプ〖トニク泉∽≈谷币始∽≈ジェット及∽ˇˇˇ。逃卖澎は面柜を虐撵弄に撬蝉し、极柜の瘫7000它客笆惧を秽に纳いやった。そんな客湿がなぜ柜を淀吉ることになったのか。それでもなぜ揉は框め属られていたのか、そこがいかにも妄豺しがたい。
螟荚极らの挛赋に裁え、四络な拇汉と获瘟をもとに侯喇された塑今は附洛面柜を梦るバイブルとなることは粗般いない。それほど塑今は面咳が腔く、罢盗考い侯墒である。
玛叹の≈ワイルドˇスワン∽とは螟荚极咳の叹涟≈广∽∈おおとりを罢蹋する∷に统丸する。
尸更い惧ˇ布企船の塑だが、その墓さを链く炊じさせない。
∝浇皋盒で、讳の聊熟は烦榷经烦の惊となった≠いきなりこんな今き叫しで幌まるこの侯墒。これからいったいどんな湿胳が闹られていくのだろうか、その袋略炊を微磊らせない侨哐它炬の湿胳。
ときは1924钳、聊熟の湿胳から、螟荚の熟、そして塑客がイギリスへ伪池する1978钳まで、话洛にわたる踩虏の栏きざまが闪かれている。
祸悸は井棱より瘩なりという咐驼があるが、そんなうすっぺらな办咐で貉まされない括まじい湿胳。趋蜗があり、それでいて矢鞠に蜗が掐るわけでもなく、棱汤弄にすぎることなく、すなおな僧米で、酶」と祸悸が闪かれている。
あまりにも慨じがたい陡丹と趋巢に塔ちた佰撅な坤肠がそこにあるのに、链试を奶してこの侯墒に珊うすがすがしさと、あたたかみはいったいなんなのだろうか。その收がこの侯墒の胎蜗であり、驴くの客」が苞きつけられる疥笆であろう。
この侯墒を粕んでいる呵面は、螟荚の眶瘩な笨炭にのめり哈みっぱなしであった。しかし、粕み姜えて、办漏ついたとき、ふと≈海を栏きているのは螟荚だけではない∽∈碰たり涟のことなのではあるけれど∷ということに丹烧かされた。海面柜に栏きているすべての客」みんなにこんな括まじい湿胳があったのに般いない、みんなこんな册贵な箕洛を栏き却いてきたのだ、と。
评挛のしれない柜≈面柜∽に警しでも夺烧けたような丹がする。
ネット惧の今删はそんなに你くはないのだが、极尸弄にはいまいちの侯墒であった。
おそらくこの井棱は柴厦が肩玛を喇していると蛔うのだが、それがそんなにも络した罢蹋圭いをもつわけでもない。
停办督蹋考いのは柴厦の庚拇が箕洛を瓤鼻しているということくらい。この侯墒が今かれたころのラジオ戎寥や鼻茶はみんなこんなセリフまわしだったのだろう。
それが阐かしさと概さを炊じさせる。箕洛がその侯墒を栏むことは粗般いがないが、この侯墒にはそれ笆惧のもが炊じられなかった。
≈凑靠は部をしに、どのような沸稗を沸て泣塑にやってきたのか∽そのこたえがこの侯墒にあった。もっと粪弄で侨宛它炬な鸥倡かと鳞咙していたのだが、笆嘲に酶」と闪かれている。
≈欧士の岚∽笆惯、侯荚の悟凰井棱に滦するスタンスが恃わったという。揉极咳の面において络きな罢蹋を积つ侯墒であったようだ。
この链礁に烧峡として很せてある、侯荚の菏である版惧ふみさんの大蛊矢がまたよくできている。螟荚との叫癌いのころのエピソ〖ド。≈矢池の碴は伴ち幌めた∽という玛なのだが、版惧眺に冯骇を拷し哈まれたあたりのいきさつがおもしろい。この侯踩にしてこの韶客あり、といったところ。
≈晒呜とは奉の佰叹、面欧にかかる奉は晒のごとくきびしく、そしてはるかに斌い∽
どんなきっかけがあったのかは蛔い叫せないが、笔版烯灰という侯踩が丹になりだした。
凑靠丸泣の孩の痊坤氮。泣塑のまつりごとは施兜と泰儡な簇犯にあった。面池够の鉴度の办コマがよみがえる。だがしかし、凑靠は部をしに泣塑にやってきたのか、そのへんのところはてんで承えがない。というよりは、雇えてもみなかった。ただ、≈凑靠がやって丸た∽ということを浆っただけ。
なぜ祸凤は弹こったのか、凰悸の微にどんな湿胳があったのか。それを豺き汤かすのが悟凰玫爽の麻革蹋。池够の鉴度もこんなふうだったら、もっと弛しく、督蹋がわくのではないだろうか。
粕みはじめてすぐ、はたしてこれは井棱なのだろうか、と、竿锨ってしまう。どちらかといえば、侠矢に夺い。附赂する获瘟をもとに、侯荚がその箕洛の客湿を栏き手らせ、侯荚迫极の箕洛囱を闪いてみせている。
琐萨の烧淡に≈∝悟凰井棱とは部か≠と、话浇钳涟も海も雇え鲁けている∽と淡されている。まるっきり侯り湿の厦というわけにもいかないし、ただ帽に凰悸の湾误では井棱にはならない。凰悸との腊圭拉を瘦ちながら鳞咙拉と料陇拉をいかに悟凰のなかに寥み哈ませるか、そのあんばいが岂しいのであろう。
凑靠、疲付苗算悉、苹独、恭脯欧鼓がいまによみがえる。
これを粕んだらやはり≈欧士の岚∽を粕まないわけにはいかないだろう。
≈レッドˇオクト〖バ〖を纳え∽に叫圭って、その胎蜗にひかれ、烦祸スリラ〖にハマっていった。
笆丸、柜柒嘲の烦祸スリラ〖を缄にとってみたが、この尸填では泣塑客侯踩は菠势の侯踩たちに斌く第ばないのではないかと炊じていた。
もっとも、菠势の烦祸スリラ〖でもトムˇクランシ〖の侯墒に嗓浓するものにはまだ叫柴っていない。
しかし、泣塑客侯踩の侯墒となると、办丹にト〖ンダウンしてしまう。
なんとなく、もどきというか、ちゃちっぽい侯墒ばかり。蜗が掐っているのはわかるのだが、湿胳としてはいまいち。
だが、しかし、この侯墒はこれまでに粕んだ泣塑客侯踩のどの侯墒よりも窗喇刨が光い。算栏傣极咳の侯墒の面でも呵光の叫丸ではないだろうか。
客湿闪继と看妄闪继、そしてよく锡られたスト〖リ〖鸥倡が、漏磊れすることなく呵稿まで鲁き、この侯墒の墒剂を瘦っている。これまでの泣塑客侯踩のレベルから办殊却け叫した炊がある。
铜祸が鳞年され、浓柜がそれを茶忽していることが汤らかになったときどう滦借するのか。漓奸松币に虐する泣塑がとれる联买昏はそう驴くはない。塑碰に、アメリカの冗割のもとにいるから奥看と疯めかかっていいのだろうか。アメリカが部らかの祸攫であるいは部らかの罢哭があって、乖瓢を弹こさない眷圭、泣塑はどうするのだろうか。
塑侯墒はそんなことを鳞年したシュミレ〖ション弄井棱ともいえる。极币骡は、幢拧は、另妄はどう疯们するのか。忽富孟苟封は材墙なのだろうか。その数恕は、そしてその扦にあたる婶骡はˇˇˇ。
暗船は姜茸の里飘シ〖ン。徒鳞だにしなかった冯琐が略っていた。
光录钒の塑はあたりはずれが、ない。
ハ〖ドボイルドでありながら、链试を奶して珊うせつなさ。裁えて、看の面を浊子うまったりとした箕粗と鄂粗。
そこにどっぷりと炕ってしまう。
琐萨に∝わが缄に俘狡を≠を布蛇きにあらたに今き布ろしたもの、とあるように、≈俘狡∽が湿胳の甥玛としてある。
望菠の湿胳と俘狡の湿胳、この企つを晾った瓦磨りな侯墒でありながら、どちらも面庞眉に促らず、バランスよく寥み惟てられている。
链挛としての湿胳拉もさることながら、俘狡についての闪继も建帮。
俘狡の菇喇妥燎となるそれぞれの婶墒の怠常拉、そしてそれには风かせない怠常裁供の闪继もよくできている。
利茸やボ〖ル茸、フライス茸など、まるで螟荚が怠常供の沸赋があるような今きっぷり。漠供眷の糯と听の器いがぷんぷん帕わってくる。
その供眷の扶聋と滦救弄に闪かれているのが、供眷に蛇孟に竣えられた办塑の葫。これが塑侯墒の玛叹と脚なるという、看にくい遍叫。
粕稿炊も郊悸している。
底しぶりに、弟萨判叁灰を缄にとった。
士喇2钳に粕卿糠使に息很された侯墒。その稿NHKのドラマにもなっている。
≈痊纱帘∽とは、どこかにモデルとなる殴があって、その悸叹を生せた餐鄂の叹涟だと蛔っていたら、悸哼する瘟拟の叹涟だった。咕竿箕洛から鲁いているこの瘟拟の痊洛誊から跺洛誊の拦筷を闪いた湿胳。
玛叹に≈灯拟痊纱帘の客」∽とうたってあるように、ここでは痊纱帘と鼎に孰らす≈客」∽が面看となっている。
その客粗滔屯は、それはそれでよく闪かれているのだが、戏兽光甸瘟拟の慎攫や咕竿瘟妄の坷狂もあますところなく帕えている。
海でも痊纱帘は蹦度を鲁けているが、≈瘟拟∽という妨はとっていない。咕竿箕洛から附哼に魂るまで、痊纱帘の殊んできた苹は、それこそ怀あり毛ありの息鲁だったに般いない。塑侯墒で闪かれているそのほんの办穗をとっただけでも浇企尸にそれがうかがえる。
その箕洛箕洛においてどう坤粗に毁积されていくのか、かつ、痊纱帘の蹋と悟凰をどう费镜していくのか、という陵瓤する草玛が撅につきまとう。
そういう罢蹋では、殴を菇えないという海の睛卿の妨轮は、その办つの联买昏なのだろう。
箕洛にマッチさせて、冷えず恃步しながら、帕琵を减け费いでいく。わが咳に弥き垂えてみると、それは事络鸟のことではないと们咐できる。
これから少怀の挑舶さんはどう恃步していくのか、どう恃步していくべきなのか、そんなことを蛔いながら塑侯墒を粕んでいた。
ネット惧の今删ではかなり爬眶が光いこの侯墒なのだが。
厦が叫丸すぎというのが唯木な炊鳞。まさかねと蛔った冯琐が塑碰になってしまった。
糠栏基艰り般え、竿酪掐れ仑えというトリックをうまく突圭させ、そのテ〖マが琅かに考く链试を奶して萎れている。蝴塑吻士は、その脚」しさというか、やるせなさを闪きたかったのだと蛔うが、そこの收はうまく叫丸ており、粕み缄にも帕わってくる。
妈18搀サントリ〖ミステリ〖络巨ˇ粕荚巨
海搀はニュ〖ヨ〖ク辉の哭今篡镑が肩客给。
涟侯≈睹佰の券汤踩∈エンヂニア∷の妨斧取∽と滦をなす侯墒。そして、涟侯を粕んだなら涩ず缄にしたくなる办糊。
しかし、それと孺べると、というより、冷滦弄におもしろさに风ける侯墒だ。
涟侯で胳られた、眶瘩な笨炭の券汤踩の湿胳のような厦を袋略して粕んだら、すっかりその袋略を微磊られてしまった。
湿胳极挛は陵碰缄が哈んでいる。哭今篡の尸梧借数に簇して、そこから巧栏した赁厦が闹られていく。いったいどこから塑玛に掐っていくの々という炊じがず〖っと鲁く。どこで涟侯とランデブ〖するのか々その督蹋办看で粕み渴む。
幌めっから簇息しているのだろうが、その簇息烧けの肋年が烫球くない。というよりピンとこない。なので袋略炊がそがれてしまったのだ。
涟侯のようなファンタジックな坤肠を袋略していただけに荒前。
この井棱もマジックˇリアリズムの器いがする。
ファンタジ〖とまではいかないが、それに击た史跋丹浇尸。
オ〖クションで顶り皖とした钳洛湿の娶。それがなんなのか梦らいないまま、またどんな猛虑ち湿なのかわからないで顶り皖とした。ただ、木炊と炊拉がそれに入められている部かを炊じ艰っていた。
≈妨斧取∽とは介めて使く咐い搀しだが、18坤氮面ごろに萎乖っていたものだという。积ち肩の客栏の妥疥妥疥でその赴となった≈湿∽を箭峡してある。その≈妨斧取∽によって、その积ち肩の殊んできた客栏を山附する、そんな娶である。
极尸の婶舶にもそれと击たようなものがないでもない。婶舶面に欢らかるガラクタの梧。井池栏のときに蝗った摩癸裴。面池に掐ったとき介めて倾った柜胳辑诺。孵苹の幂裴。獭茶塑を崔め花驴な塑の眶」。侯りかけの里贾のプラモデル。ほこりがかぶったマック。などなど、嘉てられないものが怀のように姥んである。それはそれで极尸の悟凰の办ペ〖ジを禾ったものに般いないのだが、ほとんどというか、ほぼ链てがお垛を叫して倾ったもの。湿に跋まれて栏宠しているといっても册咐ではない。
しかし、≈妨斧取∽に箭められているのは10改に塔たないもの。それで、その积ち肩の客栏を胳り、山附する、というのだから、牢の客は快陡なことを雇えたものだ。
≈妨斧取∽に慌磊られて、箭められている办つ办つが、とある券汤踩の侨宛に少んだ客栏の们室と息瓢している。
矢面、丹になった矢鞠が办つ。
≈达常は燎亨の积つ蜗と辐盖さにかかるものではなく、祷と料罢供勺にかかるものである∽
なかなか弄を评た叹剁ではある。微手すと≈祷と料罢供勺∽には嘎肠がないということ。あらゆる烫で乖き低まっている附哼の泣塑を颠う缄惟てはこれに吭きるのではないだろうか。
また、≈达常挛拎∽の胳富はここから丸たのではないかとも蛔ってみたりした。≈达常∽极挛、ギリシャ胳弹富で、料罢とか祷份を罢蹋する。达恶を蝗脱するから≈达常挛拎∽なのでははく、≈料罢と祷份∽を端める挛拎なのだ、と羌评した。
妈6搀络楫秸骚巨减巨
玛叹の≈吕士臀の楝榀∽とは湿胳に判眷する戏策湿隶≈パシフィックロ〖ズ∽のことだった。
办咐で咐って、长の盟の湿胳。长臀络肆副宠粪だ。
この侯墒の渐三は呵稿のシ〖ンにある。ここで无する粕荚も驴いのではないだろうか。この眷烫のためにこの井棱は今かれたのであった。
泣塑を违れた挖か祁数臀惧をいく戏策湿隶≈パシフィックロ〖ズ∽。その隶墓彤腾篮办虾の呵稿の挂长。
湿胳弄には、奠ソ息箕洛の颁湿の栏湿始达とトルコ客によるアルメニア客翟沪がサブタイトルとなっている。
しかし、呵络の斧疥はハイジャックされながらも、武琅に冉们し褂侨を捐りこなして乖く彤腾篮办虾の宠迢である。スト〖リ〖よりも客粗を闪くことにおいて塑侯墒は庭れている。
掀舔としてこの湿胳の赴を爱るもう办客の客湿、アメリカに舜炭したアルメニア客が判眷するが、これもいい蹋を叫している。だが、やはり彤腾篮办虾の办客神骆と咐っても册咐ではないだろう。
长の盟の面の盟、その彤腾篮办虾の呵稿の挂长にふさわしいフィナ〖レを脱罢してくれた侯荚に炊颊する。
また、この塑はカバ〖に闪かれた茶がすばらしい。褂侨を额る策湿隶が巫眷炊たっぷりに闪かれている。塑矢を粕みながら、傣刨この山绘を寞めたかわからない。この茶の闪き缄、玻怀汤も办病しだ。
褂れた光够栏を么扦する谨兜徽が、栏盘茫を客剂にとって、兜技に惟てこもる。
これからがぶっ若んでいる。
肌」と栏盘茫の册殿の横をあばき叫し、酵蓝の肉が倡かれていく。
ただ、今き哈みが颅りなく、やや湿颅りなさが荒った。この爬についてはこの巨の联雇荚らも回纽している。もっと判眷荚の客湿咙や、祸凤の嘲速を闪いてほしかった。
券鳞はユニ〖クだが、链挛としてのバランスに般下炊あり。
ジョンˇグリシャム浇侯誊、この侯墒も券卿玲」卿れ乖き惧」。揉ほどの侯踩になると、侯墒が叫るたびに面咳はどうであれ、塑粕みは缄に艰ってみたくなる。はたして海搀はどんな慎に弛しませてくれるのか。
はっきり咐って、海搀はコメディだ。纱浇帛ドルもの颁缓を荒して秽んでいった叼络少闺トロイˇフェラン。その颁咐觉の咀封弄な柒推を戒って厦は渴んでいく。
屈络な颁缓に凡がる科虏とその售割晃たちのおバカぶりがこれでもか、これでもかと闪かれる。その屯はドタバタ搭粪といってもよいくらい。その滦端としてあるのが颁缓陵鲁客として停办客回叹された碳の谨拉离兜徽レイチェル。
链く鳞年嘲の揉谨。碉眷疥も稍澄年。わかっているのは、アマゾンの秉孟で、警眶瘫虏陵缄に离兜徽をしているらしいということのみ。
そして揉谨を玫す舔を扦されたのが售割晃のネストˇオライリ〖。违骇悟が企搀。アル面の构栏卉肋で迹闻面のところをリクル〖トされた。
塑螟はかなりの墓试であるが、オライリ〖がレイチェルを玫してブラジル秉孟の季付のパンタナルを乖く眷烫にかなりのペ〖ジが充かれている。充唉しようと蛔えばその浇尸の办くらいまでには教められるのに、グリシャムはあえてそうしていない。络パンタナルの极脸がまるまる鼻し叫されており、それだけでも办糊の井棱に慌惧がるくらいの趋蜗を积って闪かれている。
それから孺べると、颁咐觉を戒る科虏の售割晃とのネゴはおつまみにみえてしまう。科虏のおバカぶりを闪いたコメディ婶尸と络パンタナルのシリアス粪のアンマッチがどうにもピンとこない。
この塑が叫惹された1986钳の涟钳、螟荚のジェフリ〖ˇア〖チャ〖はサッチャ〖俭陵から瘦奸呸の甥创祸墓に回叹されている。これには塑碰に睹いてしまう。泣塑の附舔洛的晃でこれだけの井棱を今けるものがいるであろうか。
それどころか、塑侯墒のようなスケ〖ル炊があって、エンタ〖テイメント拉谁かな肆副スパイスリラ〖极挛、泣塑ではお誊にかかれない。いくら磋磨って、マネしようと活みても、モドキの侯墒となってしまうのがせきの怀。
なんでだろう々荒前ながらこの尸填では汤らかに嘲柜の侯踩のセンスがはるかに泣塑の侯踩の惧をいっている。もっとも、井棱だけではなく、鼻茶やテレビドラマでも击たような觉斗ではあるのだけれど。
神骆肋年は1966钳、井栏がまだ井池栏の孩。孟妄惧のアメリカとソ息の疤弥は梦っていても坤肠の瞧涪孟哭は梦る统もない。ブレジネフ、ウˇタント、グロムイコ、リンデンˇジョンソンらの叹涟はテレビや糠使で斧梦っていたが、へんてこりんな叹涟だなと烫球おかしく淡脖していた镍刨。そのお悟」が判眷し、碰箕の坤陵がよみがえる。
ましてや、KGBとCIAの牡鼠里など梦らない坤肠。そこにロシア鼓碾が荒したイコンを戒って、瞧涪の菇哭をがらりと恃えるほどの祸凤が长の羹こうで帆り弓げられていたとは、びっくり赌欧である。
条荚あとがきにもあるように、塑今はいわゆる∪船き哈まれ房∩スリラ〖。その囤苹をはずさない拨苹をいく侯墒である。
なお、≈イコン∽に簇しては、叉が漠の钨にある惧辉漠の≈谰拍叁窖篡∽にまとまって箭垄されている。泣塑では诞脚なコレクションとのこと。イコンの悸湿を凑巨したあとこの侯墒を缄にとれば、侯墒のイメ〖ジが办霖考まること粗般いない。
糜版竿结の侯墒は梧房弄だ。そのパタ〖ン步された菇喇が看孟よい。
面井惮滔の柴家が祸凤に船き哈まれ、その家墓はどん撵を斧る。まじめで办虐なのが鼎奶灌。家镑や踩虏との胳らいが无を投う。
しかし、祸凤にはとんでもない微が。その靠陵をつきとめるべく家墓は瘤る、瘤る。办数、微に励む碍の面に斧え保れする畴疲。そこに晚まるのが、これもまた敞に闪いたような碍舔と紊い荚のバンカ〖。厂、甘の慨ずるもののために瓢く。それが箕として客粗の煎さから叫てくるものであっても。そして、办丹谊喇にやってくる呵稿。
パタ〖ン步されていながら、疯して徒年拇下に促らない糜版竿结の坤肠、さわやかな粕稿炊、稍蛔的な侯踩だ。
しかし、海刨の碍はちと缄ごわい。
祸凤は笨流柴家に弹こった。芹流络房トラックのタイヤが嘲れ、それが殊苹を殊いていた科灰に枫仆して、熟科が舜くなった。祸肝を弹こしたトラックの澜陇柴家、ホ〖プ极瓢贾が海搀の碍舔。
このホ〖プ极瓢贾、衡榷废として、ホ〖プ脚供、ホ〖プ朵乖、ホ〖プ睛祸とともにグル〖プを妨喇する。ここまで今けばあの极瓢贾柴家かと鳞咙するのは极尸だけではあるまい。というより、簇息烧けるなと咐うのが痰妄な厦。なにしろ贾のエンブレムが率边を话つ脚ねた≈スリ〖オ〖バル∽。
瘤乖面の络房トラックからタイヤが嘲れることが驴券し、络啼玛となったことがあったが、その祸凤の微にこんな湿胳があったとは。塑碰なのだろうか。それにしても、かの衡榷废の柴家に缎坛する家镑はこの井棱をどう粕むのだろう。いくらフィクションといっても、あまりにも叹疚や觉斗があからさま册ぎる。
とはいえ、糜版竿结ワ〖ルドは塑碰に看孟よい。海搀は皋搀点かせてもらった。
葫捻办践がどんな侯踩なのか梦らずに缄に艰った办糊。
靠っ乐に咖烧いた驼っぱで链烫を胜われた山绘とユニ〖クな玛叹が誊にとまった。ブックデザインも脚妥な关倾の瓢怠烧けとなる紊い毋であろう。
幕艰の餐鄂の录、谷涡录が神骆。
篱韦淬の怀だしの碳、它驼が乐掂驼踩に睬ぐところから厦は幌まる。它驼とその灰丁らを面看とした、乐掂驼踩の钳洛淡。箕洛がちょうど井栏が伴った炯下と脚なりあい、そのときの坤陵がリアリスティックによみがえる。
乐掂驼踩にまつわる褂赔痰肺な赁厦が、その箕」の箕洛秦肥と摊にうまく晚み圭って、稍蛔的な鄂粗を栏み叫している。
附悸ともファンタジ〖ともつかない坤肠。海钳になって粕んで咀封を减けたガルシアˇマルケスの≈纱钳の干迫∽もそうだった。このような缄恕を≈マジックˇリアリズム∽というのだそうだ。なかなか弄を评た山附ではある。
戮の侯墒も缄にとって、葫捻办践にハマってみたいと蛔う。
妈60搀泣塑夸妄侯踩定柴巨
办咐で咐って、磊れ蹋痹い。
粕み湿の弛しみの办つは、湿胳の判眷客湿に极尸を抨逼させその坤肠に炕ること。裁えて、この侯墒では、僧荚のいきざまが侯りものである井棱を奶して帕わって丸るような、そんな丹がした。揉迫极の坤肠炊が侯墒面に山附されている。
黎に2糊鲁けて粕んだジョンˇグリシャムよりはるかにおもしろい。箕洛が侯墒を栏み叫すということをつくづく炊じさせる办糊。孺秤するのも恃な厦かもしれないが、この侯墒から孺べると≈恕围祸坛疥∽≈ペリカン矢今∽は、笺闯の概江さは容めない。
9.11笆惯、テロは臭や沸貉の瓢羹と票じように叉」の栏宠の办婶となってしまった。办牢涟≈あの客はもしかしたらCIAのスパイかもしれない∽という柴厦が鹃锰染尸にかわされていたことがあった。それが海では≈钨の交客はもしかしたらテロリストの办蹋かもしれない∽ということになってしまった。もし、簿になんの横もない办忍客がそのようにみられ、メディアからも焚弧からも纳滇を减けたとしら、その客はどんな乖瓢に叫るだろうか。塑侯墒はそれをテ〖マとしており、まさしく海を磊り艰ったスリラ〖と咐える。また、极尸の面ではのどかで士下な旁辉の磅据でこれまで奶してきたオ〖ストラリアの叼络旁辉シドニ〖。その雹の婶尸の闪继が建帮で、极尸のオ〖ストラリアについてのイメ〖ジはすっかり恃わってしまった。叁客といえどもオナラはするものなのだ。
付今を粕んでないからなんとも咐えないが、付今も泣塑胳条から帕わって丸るのと票屯なニュアンスのそぎ皖とされた磊れのある矢挛で今かれているのではと、鳞咙する。侯荚の客栏囱をうまくのせた叹泣塑胳条に秋缄を流りたい。
糜版竿结は度肠の柒穗を玛亨とした侯墒が评罢だ。朵乖に缎坛したときの沸赋がものを咐っているのだろう。度肠のダ〖ティ〖な婶尸をあぶり叫し、それに惟ち羹かう肩客给が乃谗で、呵介の企、话糊はそれが∪糠怜∩に鼻った。艰り惧げられた度肠では涩粕の今となるだろうし、その度肠の嘲の客粗にとってはにわか度肠奶にさせてくれる。
矢鞠、矢挛は士白で海慎、粕みやすい。碍荚が窗链な碍ではないのがこれまで粕んだ侯墒の鼎奶爬。碍荚の煎さ、客粗蹋にほろりとさせられる眷烫もある。帽なる措度井棱に姜わらず、粕稿には稍蛔的な郊颅炊と看孟よさが珊う。この炊承は糜版竿结迫泼なもの。その收が驴くの粕荚に毁积される疥笆なのだろうが、もっと脚更で蜗动さが裁わった侯墒も粕んでみたい丹がする。
海搀球暴の甜が惟ったのはゼネコン度肠。面辐氟肋柴家办揪寥に缎坛する少喷士吕が肩客给。士吕は池麓稿话钳粗の附眷缎坛を沸て度坛草に啪掳となる。度坛草の侍叹は锰圭草。企篱帛边の孟布糯プロジェクトの掐互を戒って、度肠では∪拇腊∩が逼で渴乖していく。
この拇腊なくして掐互は雇えられない、というのがこれまでのゼネコン度肠の撅急。ゼネン度肠は络缄眶家を暮爬として、その布に面辐ゼネコン、その布懒け、鹿懒け、そしてそれにつながる紧」の度荚で菇喇さている。度肠链挛の栏き荒りのため、そしてそれらが竖える部浇它客もの踩虏のためには、度荚粗の拇腊がかかせない、という。
その碍しきしくみは塑碰に度肠にとってプラスとなるのだろうか。士吕は呛むが、乖き缅いたのは措度客としての极尸の疤弥。なんとしてもこのプロジェクトをとりたい办揪寥は糠祷窖による茶袋弄な供恕でコスト猴负に喇根し、戮家を黎乖する。士吕は呛むが、办揪寥も呵稿の呵稿まで、拇腊に捐るかそれから嘲れるかで宝に焊に络きく蜕れ瓢く。办数、浮弧泼淋婶も锰圭の器いを犹ぎ艰り、肌妈に弄を故りつつあった。拇腊は侨宛崔みの陵を蔫し、掐互の泣を忿える。
栏き却くために涩秽に漂いている措度里晃がここにもいた。墓钳拇腊舔を缎めてきた度肠の逼のドンの鹅呛。その揉と士吕との蛤わり。また、办揪寥の艰苞朵乖に缎坛する士吕の硒客との趴琐。掐互攫鼠铣えい悼锨と蜡肠络湿との簇犯。箭吓のために慌寥まれた剩花な垛の瓢き。おもしろみ妥燎がふんだんに拦り哈まれながら、湿胳り链挛としてのバランスも拷し尸ない。
染卖は澎叠面丙朵乖の蹦度妈企婶肌墓の朗にいた。
海搀扦されたのは钳粗卿惧痊篱帛边の八廓喷ホテル。そこは料度办虏の膨栗踩による坤奖扩で、叹嚏であることがゆえに箕洛にマッチしない家慎と沸蹦が砷の颁缓として覆哼步しつつあった。笨啪获垛として企纱帛边の突获が乖われたが、笨脱の己窃で纱企浇帛边の禄己を纷惧してしまう。このままではメインバンクである澎叠面丙朵乖にも逼读が第んでしまう。
办数、染卖と票袋の夺疲は枫坛につぶされ篮坷を陕み、办里违忙を途捣なくされていた。沸妄婶墓として叫羹していたそのメ〖カ〖の沸妄惧の稍赖を券斧し、それを玫ろうとする。そのことがきっかけとなり、夺疲は漏を酷き手し幌める。
笆惧、企つの湿胳が脚なるようにして渴乖していく、企家圭驶して叫丸た澎叠面丙朵乖柒の奠乖镑粗の砺磬、そして垛突模浮汉の浮汉幢との滦疯。やがて、それらがすべて办つの湿胳に箭芦する。この侯墒でも溪になる朵乖度肠の梦られざる坤肠、垛突のからくり。これら囤惟て极挛の窗喇刨もさることながら、碍荚の闪き数に迫泼のものがある。部肝か窗链に窿めない。そして、お腆芦の∩ほろり∩とする眷烫。そこには纷换づくで慌寥まれたこざかしさが链く炊じられない。ごく极脸挛の僧笨びが糜版竿结の靠裹暮である。それが浇企尸に栏かされた侯墒に慌惧がった。
澎叠面丙朵乖の染卖が措度碍に滦して靠っ羹から惟ち羹かう。ニュ〖ヒ〖ロ〖の寐栏だ。バブル箕洛に朵乖に掐家し、その稿バブル束蝉とともに奥链坷厦の束れ殿った朵乖に缎めるバンカ〖の湿胳。
络哄谰毁殴突获草墓の染卖がつかまされたのは蚀峻がもとで泡缓粗夺の钳睛皋浇帛边の谰络哄スチ〖ル。耗涪が搀箭できなければ、突获した垛は逻し泡れとなる。その勒扦を病し烧けられた染卖は、耗涪搀箭に司みをかけ、谰络哄スチ〖ルに办客捐り哈む。陵缄黎の碍だくみや惧皇の芭迢にも二せず、票袋掐家寥の锦けもあって、蚀峻の靠陵に夺烧いていく。そこに斧えたのは讳网讳瓦にうつつをぬかした措度トップと朵乖との烃缅の菇陇。たとえそれが惧皇であろうと染卖は推枷をしない。染卖は≈バンカ〖としての忖积とプライドはないのか∽と咐い庶つ。
井棱ではあるが、朵乖度肠のどす辊い柒婶を忱粗斧させてくれた办糊であった。坤の朵乖マンはこの侯墒をどう粕んでいるのだろうか。
筛光500メ〖トルにあるのどかな怀录が神骆。
叫だしは漠の皿哼疥に缅扦した笺いおまわりさんと谨拉兜徽の闪继から。なにやら滥秸湿胳の徒炊が。だが、しかし、そこに闪かれたものは、徒鳞だにしなかった息鲁沪客。あれよ、あれよと沪客祸凤が弹こってしまう。沸蹦に乖き低まった戏兽喂篡や漠の叹晃が沸蹦する矢思恶殴の微祸攫が胳られていく。朵乖が晚んだ措度井棱慎の囤惟てと、ダ〖ティ〖な息鲁沪客をうまく突圭させている。そして、呵稿は慷り叫しに提り、万が殿ったあとののどかな怀の录。さわやかな途堡が荒る。
侯荚には靠に芭くておぞましい磊り析きジャックは闪けない。答塑拉帘棱なのだろう。
ネット惧で、とかく涟侯≈恕围祸坛疥∽と孺べられるこの侯墒。≈恕围祸坛疥∽は暗泡弄な毁积を减けているが、この侯墒は海办删擦が光くない。极尸弄にはこちらの数が烫球いと蛔うのだがˇˇˇ。
肆片企客の呵光痕冉祸が沪されることから厦は幌まる。茂がどんな誊弄でやったのか、脖卢が若び蛤う面で叫てきたのが≈ペリカン矢今∽。ロ〖ˇスク〖ルの池栏、ダ〖ビ〖ˇショウが哭今篡にこもって、眶泣粗で今き惧げたとりとめもないレポ〖ト。ルイジアナ剑の佬听涪弊聋瓢とその痕冉から夸弧された办つの簿年。これが湿胳の妥で、络琵挝の惟眷を蜕るがしかねない柒推を崔んでいた。
涟侯票屯、肩客给のスリルある屁瘤粪が斧もの。すこぶるつきの叁客が叫てくるのも涟侯票屯。屁瘤黎にカリブの喷」が息鳞されるのもまた票じ。だが、恕菱肠、络琵挝、FBI、ワシントンˇポストの淡荚を船き哈んでのスト〖リ〖鸥倡とスケ〖ル炊はこちらのほうが尽っているように蛔える。なにより、祸凤の赴となる≈ペリカン矢今∽の肋年に巨豢を拢りたい。
アメリカの恕围祸坛疥の枫坛ぶりやそれが涩妥となるアメリカ家柴の慌寥みを忱粗斧させてもらった。
狼垛屁れのため、カリブ长の喷柜に柴家を侯って、そこと艰苞があるかのように斧せかける。恕の誊をかいくぐる剩花なお垛の瓢き。そのために涩妥となるのが恕围祸坛疥。光驰な狼垛を失うくらいなら、售割晃にかかる锐脱など奥いものだ。馋す驰が络きければ络きいほど售割晃鼠椒も络きくなる。狼坛漓嚏の恕围晃祸坛疥が人拦するのはそのためかとも蛔わされる。もし簿にそのお垛がマフィアからのアンダ〖グラウンドのものでも、梢嫌售割晃の缄にかかったら、获垛丽爵はわけもないことなのかもしれない。いかにもアメリカにありそうな厦。
ハ〖バ〖ドを庭建な喇烙で麓度した肩客给ミッチは、撬呈の略而でメンフィスの恕围祸坛疥に忿えられることになる。柴家は庭紊な杠狄を竖え人拦しているが、紊い杠狄ほど妥滇も阜しく、そのためにどの家镑も坎る粗もなく、踩捻を稻婪にして慌祸に虑ち哈んでいる。狼坛回祁舔の售割晃踩度は恫ろしく嘶しい。しかし、やった尸だけ鼠椒がついてまわる。般恕すれすれであっても、それが藤かる喀度であることは粗般いない。だが、悼啼なのは、なんでそんなに藤かっている售割晃祸坛疥がマフィアの微供侯をしなければならないのか。沪客まで热して。そんなことをすればにらまれるのに疯まっているのに。その爬がどうにも苞っかかってしょうがなかった。∪幌まりは井回から∩ということなのだろうか。もっとも、山踩度のほうもあやしいといえばあやしいのだが。
恕围祸坛疥の微踩度を犹ぎ烧けたミッチは、祸坛疥から、そして络傅のマフィアから炭を晾われる。斧疥はミッチと揉らとのだましあい。ミッチは稻婪となった玫腻のパ〖トナ〖や喷のクル〖ジングˇインストラクタ〖を斧数につけて、缅」と屁瘤の缄はずを腊える。片蔷汤隍なミッチが肌」と虑ち叫す侯里にハラハラ、ドキドキ。锦け隶を叫そうとするFBIをも膘に船いてしまう。
片を庸らさせる生俐というものはあまりなく、孺秤弄ストレ〖トな厦し笨び。テンポのよさでぶっちぎり、といったところ。≈あはは∽で姜わってしまうところが、ちと荒前。