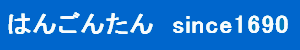ɱ����ҥ������
�ٻ�ʪ��û�Խ��Ͻ��Ƽ�ˤ������ɤ��餫�Ȥ�����Ĺ�Ԥ����ߤʼ�ʬ���������μ�Τ�Τ˱郎̵���ä��Τ�ñ�˿��鷺�������ä���������������줾��Υ�ޤϤ��ޤ���褷�Ƥ����Τ������ɤ߱����Ȥ���������ª����ʤ顢�ɸ����ʢ���ˤ��ް�ķ礱�롣
�פ��֤�������ġ����ʤ��Ȥ���̾���ۤʤ뤬��³��ʪ�ʤΤǤޤȤ�ƴ��ۤ���Ȥˤ����������ʤȤ⡢�������ܤΤ�����ɳ���Ĥ��Ƥ��롣��ƻ�λ��ΤȤ���������դ���֥������פ��Ϥ�����Ρ����褯�Ф��Ƥ��롢����������֤���ڤ�ï���������ƹɳ�˥���������Ǥ���롢���δ�������ƻ�ˤ����ƹ���Υ����������̤ʰ�̣����ġ�
�����ƻ�����å����ƥ�����פ��줿�Τ���������ǯ�������ƺǸ�Ρ֥����ͥ졼�����פ��Ф��Τ���������ǯ�����δ֡�������������Ĺ�˱�äơ֥��֥�ƥ�����ס֥����ƥ�����פ����Ǥ���Ƥ��롣
�����̡��������Τʤ�̡�衣��ƻ���Ҥ���ؤ�������ؤ�����´�Ȥ�����ޤǤ������Ľ�ʪ�졣����ͤ��ʤ��Ƥ褤������������������ο������é������Ǥ������Ӱ�ͽ�Ρ�Ⱦ��ľ���פ���ԥޥ�ΥХ��֥�Ȥʤä��褦�ˡ������餯���κ��ʤϽ����˻Ҥ���鷺��ƻ��ǯ�ΥХ��֥�ȤʤäƤ���ΤǤϤʤ����ȿ仡���롣�����פ��ΤϤ⤦Ϸ�ͤΰ�����ä���ʬ�����ʤΤ��������������ƻ���Ҥ�����İ���Ƥߤ�����
���줾��δ�����ʸ�Ϥ��ơ���ʪ����ħ���Ƥ���Τ�ź�դ��Ƥ�������
�����ƻ�����å����ƥ������
�礭��������Ӥʤ��顢���ߤ��˹�������������������
���ξ��ǺƤӤᤰ��礤�����������臘����ӡ�
�ǹ������Ƿޤ������ǹ����ꡣ
���λ���������롢��ͤȤ��ʤ�����Ũ�ꡣ
�������Ϥ�褦��
�路�������襤�錄�������λ����
���줬�����������ƻ�λ���ʸ�����ˤΡ��볫���ˤʤ롼��
�����ƻ�����֥�ƥ������
�錄�������ϡ����줾���̤�ƻ����Ϥ��
�Ǥ⤽��ϡ�Ʊ���礭��ƻ�Ρ���ü�Ⱥ�ü�ʤΤ��Ȼפ���
����ƻ��̾�ϡ����ƻ��
�錄�������������ƻ��
�錄���������ʤ�٤�ƻ��
�̤Ƥ��ʤ�³��������ľ����ƻ��
�����Ƥޤ����Ĥ������˿ʤ�٤�ƻ����
�����ƻ�������ƥ������
�錄�������ϡ��⤦�¤�ʤ���
����ƻ��椯�ȡ����Τ����顣
�ޤʲ����⡢�����⤢���������
��ʬ����⡢�ʤ���Ѥ⤢���������
�Ǥ⡢����ʤȤ��ϻפ��Ф�����
���οͤ⡢���ä�Ʊ���褦�ˡ�������ƻ�����³���Ƥ���Τ������ȡ�
���������٤Ƥ�ƻ�ϡ��������ƻ���̤��Ƥ��롼��
�����ƻ�������ͥ졼������
Ʊ������ƻ�錄�����������Ǥ�����
���������Τʤ��в����ä���
���̤���褦�ʳؤӤ������Ȥ���褦�ʻ��������ä���
�����������褿ƻ���֤뤳�ȤϤ��ʤ���
̿����¤ꡢ�路�����ϿʤޤͤФʤ�ʤ���
�������ƻ��³���Ԥ����ˡ������ʤ���Фʤ�ʤ�����
���ΤȤ������֥Υ��פ�����ꡢ���ä����Ѳ����Ƥ��ޤä���������
���κ��ʤ⤽�ΰ������ɤ�θ��������̤���彣�ؤȻ�������ؤ��ʤ���é�����ʱ�̿�������ơ��Ǹ�κǸ�ޤ�ͽ�ۤ�Ĥ��ʤ�ʪ��ȷ�������θ����ʤ�Ÿ���ˤ��������������ޤ�Ƥ��ä���
�֥Υ��פκ��ϡ�����Ǥ⤫����Ǥ⤫�Ȥ������ߤ�ɮ���˰��ݤ��줿�������뤬���ܺ��ʤǤϤ���ȤϿ��դ�ɮ�������ߤ��롣�Ĥޤꡢ�Ǥ������������Ȥ���������ʸ�Τ�ʸ�ϡ���٤�Τ�ʤ�ʤΤ���������ä������ɤ���������Ρ֥����ƥ��٥������פ��жˤ˰��֤�����������ָ�餺���Ƹ��פȤǤ⤤���Τ�������������ϳ��Ǥ����Ȥ����Ρ����������������ס���Ħ�Ǥ����С�Ħ�餺��Ħ��פȤ������ϡ�
ľ�ھޤ�ͤä��Τ������롣
������Τ�ʪ��˸��ߤ�������뤿��ٻ��ȿ������̤����ʤ��̤����롣���κ��ʤ⤽���㳰�ǤϤʤ��������ʤ���о��ʪ��¿���ʤ꤬���ǡ��Ϥơ��ɤ��������ä��ä����Ȥ����岼�ط��Ϥɤ��ʤäƤ��������ʤɼ�ʬ����ǹ��ۤ���Τ˻��֤������롣���פǤϤ���ʤ��ȤϤɤ��Ǥ�褯�ʤäƤ����Τ��������פ������פˤ����ơ��ɤ߿ʤ�Τ˶�ϫ���롣
����ů��Ϥ������̤�ʤ��Ȥ����������Τ��ȤƤ⤦�ޤ���ʪ��γ��Ȥ�ª���Ĥġ���ʪ���̤⤽��˹�碌��´�ʤ�������Ƥ���Τǡ��ɤ߿ʤद���˼�����ʪ���������ळ�Ȥ�����롣�����������̤ǤϤɤ��餫�Ȥ����ȡֽ��פʰ��ݤ�����Τ������줿�ӿͤ���̾��̤Ȥʤ�ȡ������ʤ�ֶ��סֹ�פ��̤�ۤ��ơ�Ķ�ɵ�סֶ��פ�ɮ�פ��Ѳ����롣�������š�������դ�����̯����Ԥο���ĺ�ʤΤ��Ȼפ���
���������ܤʤ�дְ㤤�ʤ����⤷�������������ȻפäƼ�˼�ä���
�����������פ碌�Ƥ��줿�Τ���Ƭ�������ɤ߿ʤ�뤦���ˡ��ȵ����䤬�դ�Ÿ���ȤʤäƤ��ä���
�о��ʪ�Υ���饯�������꤬�Ť��Ȥ���������������ˤ��äƲ��Τ��Ȥ����ΤΤ��Ȥ������ȸ������̤�¿�����롣�ɼԤ������Ϥ�Ư������Ȥ������ȤʤΤ������뤤�ϡ�����ؤδޤߤʤΤ�������������ˤ��Ƥ����ͤ˽ФƤ���Τǡ��ɼԤϸ��ǤäƤ��ޤ����ȥɤΤĤޤ꤬��ʪ���Ǽ�����⤪���ʤꡣ����Ϥ�ߤ���Ƽ������Ĥ��ʤ��ʤäơ�̵����겡��������äƴ����������ơ�����ޤǤκ��ʤˤߤ�줿�褦����̩����������������줺�����������Դ֤��������ΤĤޤ�ʤ����ʤȤʤäƤ��ޤä���
wowow�αDz�Ǥ�äƤ���Τ�Ѥơ�������ɤ�Ǥߤ����ȻפäƼ�˼�ä���
������ٻ�������Ρ�������Τǻפ��������ΤϹ�¼���䥸���ե�ǥ�������������������������������Ƥ���ΤϤ����κ��ʤȤϤ���äȼۤʤ롣��ñ�˸������Ⱥᾮ��ȷ�������Ȥ������Ȥ���������
�Ⱥᾮ����դ�ʪ�ΰŤ��Ǥ�ФƤ���ˤϽФƤ��뤬���ڤ��ޥΤ褦�ʡ֤��Ф��פ����˽ФƤ��ơ����줬��Ԥκ����ȸ�����Τ��⤷��ʤ����о��ʪ�Υ���饯������üŪ��������Ƥ��뤷�����ȡ������þ��ʤ����ƥ�Ӥη����ɥ�ޤ�ѤƤ��뤫�Τ褦���ɤ߿��Ϥ��ä���
���꤬��Camino Island�ס����줬�ء֥��졼�ȡ�����ĥӡ��פ��ɤ��٤ʤΤ����顢�Ф碌�롣�����⡢ˮ����¼��ռ��Ȥ��Ƥ��롣���������ä�������ά���٤餵���ΤϽ�̱�ΤϤ��ʤ�������äȤ⡢������ꥷ���ο���Ȥ��������Ǥ��ϼ�˼��Τ�����
������ꥷ��प���դ�ˡ���Τˤ���褦���ڤ�Τ���ʪ��ǤϤʤ���Camino Island�Ȥ���������ϤǷ��깭�����륽�եȥ����ڥȤ��ä����ݡ�����ꥫ�ε���ܽ����ˤޤĤ�����Τ�ʤ�������������Ƥ��ƶ�̣�����������μ�ˡ���⡢�о��ʪ�Υ���饯������¿�̤������ε��ڤ��ɤ���ں��ʤ��Ȼפ���
ʬ��������������פäƤ��������λ�ޤǻ��֤������ä���
��Ρֻ���֡פϵ���Ѽ��Τ���������ѤϤܸۤǤޤäƤ���������äơ����������Τ��ˤ����Ȥ����ޤ��̤λ���֤˽в�ä��������ä�������Ѽ��Τ�έ���濴�ι����ǡ��λ��⤦�ޤ����Ѥ���Ƥ��ơ�¿ʬ¿���οͤϤ��κ��ʤ˴��������Ȼ����褦�ʥ�����������Ƥ����ΤǤϤʤ����Ȼפ���������Ф��ơ������������ʤϵ���Ѽ��ֻ���֡פȤϰ�����褷������ˤ��ʤ�νŤ����֤��Ƥ��롣έ���ϻ���³���μ微���Ĥ˲�ʤ���������ܺ��ʤ�ɤ��餫�ȸ����С����������˶ᤤ������ȤäƤ��롣έ���ν��פ�ø����������Ƥ��롣�ܺ��ʤ������Τϡ��˼¤Ȥ��θ�˺��줿����ֱ���������ơֻ���֡פ��٤��ơ��ȼ��λ���֤�Ƹ����Ƥ������ˤ��롣����ޤ�¿���οͤ�������Ȥ��������Ƥ����Ǥ������ֻ���֡פȤ�������ä������������ˤ��롣
�֥������פ���Ȭ����Ƨ�ߤ��Ƥ���֤�������Τ����κ��ʡ�
�ֻ���֡פϵ���Ѽ���ʸ���ܤǣ�����ɤ�Ǥ��ꡢ��ʬ��Ƭ����ˤϤ������١ֻ���֡פ�����夬�äƤ��롣�����ǡ����������Ϥɤ���������Ƥ���Τ���̣�����ä���
����֤Ȥ����С������������ޤ줿�λ�̾����ͭ̾�������ܺ��ʤǤϤ����˼��夻��ɽ�˽Ф��������Ĥ����ΰ��ä��Ԥλ����Ǵ��뤵���Ƥ��롣��Τ褦�˵���Ѽ��λ���֤˴��줿��ΤˤȤäƤϡ�������ȴ���δ��⤢������������������о��ʪ�ҤȤ�ҤȤ�ؤλפ���ɮ���Ϻ�Ԥʤ�ǤϤΤ�Τ��롣�äˡ�����Ǥδر��κǴ��ȹ������㤭�ʤ���������ڤ���̤ϤȤƤ��ɤߤ����������ä���
�Х����͡��Х����������ü������ܤ�Ĥ��ơ����줫���ä��Ĥ�ޤ��Ƥ��ä�ʪ�졣������֥Х����פϥ��ڥ���ȥե��ξ����¸�ߤ���Ȥ������Ȥ�����Τä����Х����Ϥ���������̯�ʰ��֤ˤ��꤬�ʤ��顢�ȼ���ʸ�����ۤ��夲������������Ȥ��Ƥ��롣
ʪ��ϡ����ڥ����������ܤ������Ω���ܻؤ������Ϥˤ���̿��õ���ȿ��Ȥ�����ʶ�����������ַ�����ζ��ϼԤ����Ȥ��Ƥ��롣���Ǥ����ܿͤȥХ����ͤˤ϶��̤����������ʤ��餺����Ȥ����ä���������ʪ����ɤ�Фʤ�ۤɤȶ����Ǥ����̤⸫��������롣
��Ƭ����ƥ��ȿ��������ַ��ȽФƤ��ơ��������ΥΥ����ʤ��������Ƥ����������δ��Ԥϸ������ڤ�줿���ȿ��ܤ�����ʬ�⤢������ͽ�ۤǤ����ϰ���ǡ��ƥ��٤Ȥ����˲�Ū���ۤȤ�ʢ�ˡ�ʪ��Ȥ��Ƥ��˲����Ϥʤ���
���κ��ʤ�ȯɽ�����ΤϺ�Ԥ���ǯ�����ФΤȤ��������������ޤ���äƤ���Τ��Ȥ����������⤢�äƼ�˼�ä���
�ɼԤ��٤�����ϥե�����������������Τ�Τ���������ϱѹ�Υ���ȥ����顼��Ũ�й���٤��ƺ��𤵤���ʪ�졣����⡢����äȤ�äƤΤ��롣�����������Ф�Ф���ͤ�Υ��ѥ����������ϡ�̵���ʤΤ��ʤȴ�������
��������ưʪ�ܤ�ľ�ھޤ���ޤ���ʤ�ơ�����κ��ΥΥ����ʤ��ΤäƤ����Τʤ�ï��ͽ�ۤǤ���������������ǯ��Ԥκ��ʤ����Ϥ�äѤ黳�伫�������Ƹ��ȤʤäƤ��롣���θ������Ȥ������ʤΰ�ġ����κ��ʤǡָ��ν����פȤ�����Τ�����Τä���
���Ȼ�����Ȥ��͡��ʴط������̤���夲��û�Խ�����Ԥθ��ؤ��ܤ���������äƤ��롣ʪ��Ū�ˤϿ��٤�Ϥ��Ƥʤ������������ä����餻�Ƥ�������ǤϽ�ʬ�ˤ��롣ľ�ھޤ˻��ޤǤκ��פФ餯���ɤäƤߤ����Ȼפ���
������Τ��Ȭ�����פ��ɤ���Ȥ������ޤ��������طʤ�ʬ����ʤ��ä��Τǡ������դ�⤦����äȷ��겼���褦�Ȥ��ơ���˼�ä������
����ī�κ���ʣ���ˤޤ������ä�������Į����Ϥ�����ؤ��ƺ��٤Ȥ��Ƥ���������ä��������괬�����Լ��դ����Τ��Ȥ��̤��֤��Ȥ��ơ�����Ǥϡ��Ųϸ��������Ҹ�����������Ρ���Ƿ��������ë����餬�����꿩���褤�깭���Ƥ�����Ụ̃���������ؤ�꤬�㤷���������ӻ�������ⲿ�⤢�ä���Τ���ʤ����ͤ������礦�ͤ���桢������줬�ɤ���«���Ƥ����˶�̣��������뤬�������������ޤ��Ԥ��ͤФʤ�ʤ���������Τ��Ȭ�����פϤ����ǵ����ä��������狼���ݤ����줿������Х��ԥ��Ȥ���������Ǥ��ä���
�ܺ��ʤμ��Ĺ���ʿ���ޤ������礭�ʤ��ͤ����Ϯ���줿�ΰ�͡�Ĺ���ȤȾ���ȤȤΰ����������������λ���ΰ�Ĥξ��̤��ڤ곫�����͡������Ϥ�ꡢ��ʬ����ǤΤ��κ��λ���ǧ���������ʤ��ᡢ��ʪŪ�ˤϤ褯������Ƥ���Ȼפ�ȿ�̡��ɤ�ʻ�����ä��Τ������������פ����ɤ����Ƥ�Ƭ����̤����ʤ��ä��������ǡ��ʲ��Σ����ͽ�Ȥ����ɤߡ����ܤ����ʤ��餳�λ�����سԤ��������Ȥ��Ǥ������Ȥ������衣
�ּ�Į���ܤ������μҲ�ױݸ���������
�ֱ��Τ�����ͦ�졡��
�ִѱ��ξ�����Ľ��¡���
�ֱ۸�����²�ײ֥��� ��������
�ʤ�Ȥʤ�Ȭ�������ɤߤ����ʤäơ���ۤ�ʪ�����Ƥߤ����ǽ�˴��Ƚ�Ź��ʸ���Ǥ��ܤˤȤޤä������������¤ʤ����ʤΤ��첾̾�����ǤȤƤ��ɤߤˤ����������ǡ��ͥåȸ�����Ĵ�٤Ƥߤ��������줬�ճ��Ⱥ��ʤ����ʤ����빽�͵�������Ϥ��ȻפäƤ����Τϼ�ʬ�������ä��ߤ���������ʪ���ʿ��ʪ��Ͽ���ʪ�ˤϤ��Ȥ����ʤ�����Ȭ����������褬�¤��롣�����˼�ä���Τϸ���˱�äƽ�Ƥ��뤬������������������ƤȤ����롣ʪ����Ĥ�ޤ���Τ��ɤ�κ��̤�Ǥ����롣�����ϤҤȤġֿ����פȤ������ϡֿ����פȤ����ȼ���ʪ��������ä����ʤ���Ԥ������Ȥ�����ï����äƤ���ʤ����ʡ�
������Ȥϰ�äơ��������ʥ������ȡ�
�ͥåȾ�ν�ɾ�Ǥ����������ɾ����¿��������ʬŪ�ˤ�����ξ⤬���ޤ�ˤ��礭���ä��Τǡ��������Ȥ���̤Ȥʤä���
���κ��ʤǸ��Ȥʤ�����ɼԡפ��ФƤ��Ƥ�����礭��Ÿ���Ϥʤ������ͤΡ����ɼԡפ����ܤ�Ũ���餽�ο��դ��ɤ���뤳�Ȥʤ�Ũ�������뤳�ȡ����������Ȥ��������������Τ��ȤʤΤ��������λ�������ޤ�ï�ηײ褬�����դ���Τ������뤤�Ϥ��٤�Ũ���Τ��Ƥ��ޤ��Τ����Ϥ��ޤ�¾�����Ǥ��ä�äƤʤ�褦�ˤʤäƤ����Τ�������ʤ��Ȥ�פ��ᤰ�餻�ʤ��顢�ɤ߿ʤ�Ƥ�����
�����ǡ�Ƭ���⤫����Τ����ԤƤ衢����ϥϥꡦ�������ͽ¬�˻��Ƥ��ʤ����פȤ������ȡ����ʤ�������ब����Ū���֤˴٤ä��Ȥ������ﳲ��Ǿ��˿����ߤ��ɬ��Ū�ʸ��ݤ������롣���δ����˺ݤ��Ƥκ�������������˳ؤˤ�ä�ͽ¬�Ǥ��������⤽�γ�Ψ�Ϥ��ʤ�⤤��������������Ϥ��νִ֤����ޤǡ����줬�ϥꡦ�������ͽ¬�Ȥ�ï�ⵤ�Ť����������Ԥ⤽�ι�ư�η�̡��ɤΤ褦�ʷ��������Τ�ʬ���äƤ��ʤ������ʤ�����ϥꡦ�������ͽ¬�Ϥ��줬���äƤߤƽ��Ƥ��������Ǥ��롣�������Ȥ�����Ρ��֤ʤ�褦�ˤ����ʤ�ʤ��פȤ�����������Ū�Ȥ�����ʤ���ʤ�����������Ψ��ͽ¬���Ƥ��ޤ��Ȥ����Τ��ϥꡦ�������ο�����˳ء�
�����פ��ʤ����ɤ�Ǥ���ȡ�������ʸ����˥ϥꡦ������ФƤ��ơ��ܤ��ƥ�ˤʤä����ʤ�Ƥ��ä�����ԤϤ����餫�˥�����դؤΥ��ޡ���������Ƥ��κ��ʤ��פ�Ǥ����Τ�����ʬ�λפ��Ⱥ�Ԥλפ���ƱĴ�������Ĥ����ִ֡����줳�������ɤߤ����̣��
���ơ�Ĺ��Ĺ��ʪ��Τ��ˤϡ����ä��ʤ��������������������ϥꡦ�������ͽ¬�Ȥ����С������Ǽ�����ʡ�
�����β������ǡ֣��ͤ����ɼԤΤ�����ï���ϥꡦ�������Ȥʤ�Τ��פȤ����褦�ʵ��Ҥ����뤬������ϴְ㤤�ǤϤʤ����Ȼפ�������ϥϥꡦ��������ï���Ȥ������ȤǤϤʤ���ï�Τɤ�������ư���ϥꡦ�������ͽ¬�ȤʤäƤ����Τ����Ȥ��������Ȼפ���
��ǯ���ܤ��ʴ����������褦�䤯��˼�ä���
�饸�����Ȥ���ǾҲ𤵤�ư��衢���ˤʤäƤ��礦���ʤ��ä����֡�����������Τ�����ۤν�ͤ��¤�Ǥ���ΤĤ������Ȥ˵��äơ��������ɤफ�ȡ���ž����ܤ��ƤӤä��ꡣ�Ҥ��ȡ��ƥå��夬������Ƥ��������οͤ����Ĥ��ˤǤ�Ȥä��Τ��Ȼפä���������ϰ�֤Τ��ȡ����νְִ����Ȥ������ʤ�Ȥ���ϻ��ѺѤߤΤ�Τ��ä������ä����ɤ��ʤäƤ�Ρ���䡢�����ʤɤϤ��ޤ˸������뤬������ʤ�Τ��ФƤ����ΤϽ��ơ�����ͤ��Ƥ���ʤ�Τ���Τ����ܽ�ؤβ��餫�Υ�å������ʤΤ���������
�����ܤ˽вޤǡ��ޤ����פ��֤��SF�����ȯ���ɤळ�Ȥˤʤ����Ȥϡ��ͤ��Ƥ�ߤʤ��ä�������SFʸ�����¤��ä��ɤ�������SF������ݤä���ȷ���Ƥ����������롣¿ʬ�������פäƤ����Τϻ�����ǤϤʤ��Ȼפ�����������餳��������������ѥ��Ȥ�ʪ��ν�����˲û�����ƶ����ʰ��ݤ�Ĥ����Ȥˤʤä��ΤǤϤʤ����Ȼפ���
ʪ���ʸ�פǤιȱ�ʼ����Ʈ���̤���Ϥޤ롣ʸ�פδ��ޤ路������դߤ�С����θ��Ÿ�������SF��̾��ڤꤿ������Ƚ�Ȥ�Ȥ�줫�ͤʤ����Ƥ�ޤ��ܽ�ϤȤ�Ǥ�ʤ����ʤȤ����롣���������̤�����ܽ��ɾ���Ϲ⤤�ΤǤϤʤ����Ȼפ���
���������ե��������Ȥ������ϥ��������ե������˶��Ķ�ϡ���SF�Ǥʤ��Ȥ����Τ�¿���ο͡��˼��������줿�װ����Ȼפ��������������������Ρֻ��������פ���������䤳�����ʤä���ơ�����������äȼ�ʬ�Ȥ��Ƥ��ɤ߿ʤ�Τ˶�ϫ������
���줫��Ѹ졢�����Ƥ���ξ���Ȥ��Ƥ����ܸ첽�����Τⵤ�ˤϤʤä�����ξ���Ȥ��ɤޤʤ��ΤǤʤ�ʤΤ�����ɤ⡢�ȤƤ��ɤߤ䤹�������ޤ�������Ƥ���Ȥΰ��ݤ����������������ɽ���䡢���ܿ����äθ�������礤���礤�ФƤ��ơ�����Ǥɤ�ɽ������Ƥ���Τ��ʡ��ʤɤȻפäƤߤ���⤷����
�֥���ꥫõ���ȥ���ּ�ŤΥ��ɥ�����ͥ�����;��ޡ����ܤ�ޤࣳ������ʾ�Ǥ����������ꤷ����������ǯ�ǹ�������פȤ��Τ餺�˼�˼�ä������
�������ġ��֥ɥ��ȥ롦���Х����������äȣãɣ���̳�����ԥ��Ȥε����á�
���Ƥ��餤�äơ��ɤ��餫�Ȥ����ȸ�Ԥ����˥������Ȥ�����Ȼפ�����������The Secrets We Kept�פȤʤäƤ��뤷��ˮ������Ԥ��������֤��Ƥ��롣
��Ĥ�ʪ��Ȥ�ȤƤ�褯�Ǥ��Ƥ��ơ��勞�勞�ɤ��ɤ���������Ÿ���˰������ޤ�롣�Ȥ����ɤ����˽ФƤ��륦���åȤθ��������ä⸫��Ρ����Х��Ǥ���ˤαƤ֤�Ф����֤������ä��Τ��פȤȤ�ˤ⤦����������������äƤߤ����Ȥ�ǰ�˶���롣���ԤǤ���ѥ��ƥ�ʡ����οȤ˴����������桢����Ǥν��Ǥ����ʤ鷺���ǽ�ν��Ǹ��Ȥʤä������ꥢ�Ρ֥ե���ȥ�ͥå�פˤĤ��Ƥⶽ̣���勞��
��Ĥμ����ͻ����������Ƥ��ꡢ����Ū��ɾ���Ϲ⤤�������ɤ�����٤����������ʤ��Ȼפ����о줷�������ԥ��ȤΥ��ԥ��Ȥ���ʪ�����������Ƥ��ޤä���
�����ܤ˽й礦�ޤǡ����ķļ�Ϻ�Τ��Ȥ��Τ�ʤ��ä�����ŷ�Ӥʿ�ʪ���Ϥޤ��̡��μ���ߤ���������ʿͤ������ˤ����Τ����顢�ä�����뤷��κ�ˤʤäƤ��ޤ��Τ�̵���Ϥʤ���������
����̤δ֤Ǥϡַ���ԡפȤ��Ƥ�ɾȽ�����夷�Ƥ��롣���Ĥλ��夫�餽�Υ�����������դ���줿�Τ��Ϥ���ʤ������ͥåȤǸ���¤ꡢ���ΰ��ݤ����ѤǤ���餷�����ܺ��ʤǤ⤽��ϩ����Ƨ������Ƥ��ơ���Ϥ����äơ������������;�˸����������ж��ԤȤ���������˸��줿�������������Ƥ��롣
�������ϰ��̿ͤˤȤäƤ�������ǡ�����ʼ�ʬ�ˤʤ������Ѥ���ä��������ʪ�ˤ�������������ΤϤ��Ĥλ�����Ѥ��ʤ��Τ��⤷��ʤ���
�ֶ��ģءפ�Ǹ�ˤ��Ф餯��Ԥ�����äƤ�������ͧã�ν�ɾ�ˤ��κ��ʤ��Ҳ𤵤�Ƥ��ơ����ƺ�ԤϤɤ����Ƥ�뤲���Τ��������Τ�����Ƽ�˼�ä���
��Ƭ���顢���פΤĤ��ߤϤ褯�Ǥ��Ƥ��ơ�������ɤΤ褦���ä��ʤ�Ǥ����Τ�����̣�š��ǥڡ������롣�֤��ä���������ɤ��ʤ�Τ����������äϤ�����ɤ�Ÿ�����Ƥ����Τ����ޤ��ɤΤ褦�ˤ��Ʋ�������Τ��פ����������������餵���ʤ���ΤϤ��롣�����������Ĥ��Ȥ߹��ޤ�Ƥ������ä����������Ȥ�ʤ��ޤޡ�ʪ������פ��齪�פظ����äƤ������Ĥޤꡢ����Ǽ����줿�֥ͥ��פβ��������ʤ��ޤޥڡ������ʤ�Ǥ���������Ǥ��ơ��ޥ��å��ꥢ��ƥ������������Ȼפä��餽���Ǥ�ʤ���
��ġ���Ĥ����ü��Τ��ɤߤ����������ꡢ����Ϥ����û�ԤȤ��ƽ��뤵���Ƥ�褤�ۤɤδ����٤����롣�äˡ����פ�������ˤ��������Υ�åѿ������ϵ����������Τ����롣���������ֲ������ʤ����Сץ��ȥ쥹����������Ư���Ƥ��ޤ��֤褯�Ǥ������ʤ������ʤ��ä���Ȥ��ʤ��פȤ����ɸ崶�ȤʤäƤ��ޤ���
���֤��������ơ����ܤǤ��α����˶��ޤä������ޤ��������Ƥ���Ƥʤ顢��ҥåȴְ㤤�ʤ��Υ����ƥ�����Ⱥ��ʤˤʤ�Ȼפ���
���κ��ʤ��ɤ�¤ꡢ�ֶ��ģءפ���������ԤιԤ��ͤޤ괶�����æ�����褦�˸��������롣����ɡ��䤬���Ȥ���¼��ռ��˸�����褦�ʡ�����Ⱦü�ʤ櫓�Τ狼��ʤ������פ����������˻��Ƥ������⤢�ꡢ����äȸ��ǤäƤ���Ȥ����Τ���ľ�ʵ�������
�����ڡ����椴���ˡֶ���������οͤ�ǯ���äơ��ʤ����Ǥ��ޤä��ꤷ���塢�������դäƤ��ʤ��ʤ뤳�Ȥ�����餷���פȤ�����ʸ���ФƤ��뤬�����Ρ֤դäơפȤ��������ޤ��ޤ����˰��ä����äƤ��ޤä���
����ǯ�ʾ�������ɤ���Ȥ��ϡ��䤿��Ĺ�����봶���������ݤ˻Ĥä��������ɤ�ľ�����Ƥߤ�Ȱճ��������ɤ��������ǯ����˾���������Ǥ��������⤢��Τ���������������κ��Ϥޤ����κ��ʤ��ܤ������Ϥ���ʬ�ˤϽ���Ƥ��ʤ��ä��Τ��Ȼפ������ʤ��Ѥ�餺�����ˤ���Τ����顢�ɤ���Ѳ������ä��Ȥߤ�Τ��ڤ��������Ф�Ȥ�Ȥ����ΤϤ����������ȤʤΤ��⤷��ʤ���
����ְ����ӡפ�³��������ϵ��Ԥء�
ƣ����̤ˤ����ؤ�ä�����Ƚ�̤Υ饤�Х�Ǥ���ƣ����˼�Ȥι���˺�����˴����ιİ��褤��ᡢ�⳦���������礬����Ͼ��������˻ߤ��褦�Ȥ�������ʻ�������뤲���ˤ�������ࡣ��������Ƥλ���Ǥ��륷�Ф�Ⱦ��Ⱦ�ä��Ȥ����ɤ餻���Ѥ�ȶ��˵����������롣������Ф����������µ��ʤ��Ϥ�ڤ����ư�����䰦�������и�������ȿ������������Ȥ�Τ��줿����令�ȶ��ˤ�����й����롣
������Ʊ�͡���ˤ��������ʪ�����äȤ����Ȥ߹���ͻ�礵���Ƥ��ꡢ��ˡ�����ʪ�����ˤϤ��ޤ�ʤ����ʤȤʤäƤ��롣
����ϰ쵤��ʿ�»���ؤ��̤ꡢ����������ϺƤ�Φ���ء�
�����Ʊ�͡������������̣��ǽ�Ǥ��롣�ä��ơ����������٤����ʤ�⤤���ƤȤʤäƤ��롣�褯�Τ��Ƥ�����ˡ������¼��Ϥ�������羭���ȤʤäƲܰФ�ʻ�礵�������ȡ�����ή�����ǡ����λ����طʤ��Ĥι��ҤȤ��ơ��ӣ��١������٤ޤ�ͻ�礵����ʪ��ȤʤäƤ��롣�Ȥ������ϡ����ּ��˻˼¤��֤��ơ�����ξ��̾��̤˿������褦�˺�����ޤ�����ˤʤ��Τ������Ƥ��봶�����롣
�Ȥ����ǡ��ܺ��ʤΤ��Ȥ����Ǻ�Ԥϰʲ��Τ褦�˽Ҥ٤Ƥ���
������ë�٤κƳ��Ǥ��롣��ʬ�Ǥ����äȿ������ʤ���
�ۤ�ϻǯ���κ����ˡ�����ë�٤κǸ�ιԤ��ץ��Υǥ����ץ쥤����Ǥ��������������٤Ƥ����뤷�����Ȼפä������δ����ˤϾ�������Ϥʤ�����ʬ���Ľդ䡢��̣�䡢��Ǯ����¾���������Τ��ޤޤ�Ƥ�������ʬ�Ϥ⤦ʪ�Ȥ��ƤλŻ���̤����Ƥ��ޤä��ΤǤϤʤ����������Ȥ�פä����ɼԤˤ��ξ��⤬�ɤΤ褦�˼����ߤ���褦�ȡ���ʬ�ˤȤäƤϤ��줬�³����ȴ������Τ�������ʾ�κ��ʤ��Ȥϻפ�ʤ��ä����������ǥ���Ȥ��̤����Ƥ��ޤä���
��ʬ�Ǥ�ä����Τ���������Ϥޤ���������ʬ��������ɤ���Ȥ������������ۤ��Ǥ������Ƥ��줿���Ƥ����Ĥޤ��������ȥߥ��ƥ�������ƣӣƤ����ǤƤ�����ǡ�����Ǥ⤫����Ǥ⤫�Ȥ��֤��Ƥ��������̤�Τ�ʪ�졢�������ϰ��ݤ���Ƥ��ޤäƤ����٤Ȥ������ȡ����ʤ�����ʬ�ΰ��ݤϳ���Ƥ��ʤ��ä��褦��
���£���ǯ�˽��Ǥ�ȯ�Ԥ��줿�Ȥ����ɤ�Ǥ��飳��ǯ�ʾ�⤿�äƤκ��ɡ������Ϥ勞�勞�������ɤ���Τ�Ф��Ƥ��뤬�����ƤϤ��餭���Ф��Ƥ��ʤ��������ơ����Ĥ��ɤ��֤��Ƥߤ褦�ȻפäƤ��������
���ơ��������Ƥϡ������ɤ���Ȥ��������Ƥ������ݤȤϡ��ɤ�ʤ�Τ��ä������ΤˤϳФ��Ƥ��ʤ��������ȤϾ�����äƤ���褦�˻פ����Ȥ��������礭�ʳ֤��꤬����褦�����ɤ��֤��ƻפ��Τϡ�������ȥߥ��ƥ�������ƣӣƤ����ǤƤ�����ǡ�����Ǥ⤫����Ǥ⤫�Ȥ��֤��Ƥ��������̤�Τ�ʪ�졢�������ϰ��ݤ���Ƥ��ޤäƤ����Τ��Ȼפ������������פ��Τϡ�����ä�����Ϥ�ߤ˲��Ȥ������ȡ��ͤ���߲�������Ȥʤäơ��դ˵ͤ�Ť����µ�ƥ�ӥɥ�ޤ��Dz��ѤƤ���褦�ʴ����ǡ����ƥ���������ˤϿ���ʬ���ʤ���������ʾ�κ��ʤǤϤʤ��ä��褦����
������ë�פϡ�����ë�ҡפؤȰ����Ѥ���Ƥ����Τ�������������Ƥ������Ф��Ƥ��ʤ����ɤ��ʪ����ä��Τ����ڤ��ߤˤ����ɤ�Ǥߤ褦�Ȼפ���
ï�κ��ʤ��ä���˺�줿�������٥ȥ饤�������ʤΤ�����Ǥ�������ʿ��ʪ��ס��⤷�������顢���������Ҥ��ܤʤ��ɤߤ䤹���ΤǤϤʤ����ȻפäƼ�˼�ä������£�ǯ�����äƤ����ɤϤᡢ������ܤ��ɤ߽��������ɤߤ䤹���ȤޤǤϤ����ʤ�����ʿ��ʪ��������ѤȤ��λ����طʤΤ����褽���Ϥ�ΤǤϤʤ����Ȼפ���ʪ�����٤����ɤäƤ����ˤϤ��ޤ�ˤ��о��ʪ��¿�������δط���ʣ���ˤ����롣�⤦���ټ�˼�ä��ɤ��֤����顢�����դΤȤ������⤦����Ƭ�����äƤ��뤫�⤷��ʤ���
����ˤ��Ƥ⡢�֤������ͤ�פ����餺���ؤ�줿ʿ�Ȥαɲڤϣ���ǯ;�ꡣ�����ˤĤ��δ֤�ŷ�����ä��褦��������ǯ�Ȥ����С�Ĺ����ˤ���ߤ�Фۤ�ΰ쥳�ޤˤ����ʤ�������ʤΤˡ�ʿ������ʿ�ȤΤ��Ȥ��Τ�̤�ΤϤ��ʤ����餤����̾�ϰ�Ĥλ���Ȥ��ƹ���ǧ������Ƥ��롣�����ΤȤ����Υ���åפȤ�����������ۤɤλ�����ä��Τ��ʡ��Ȥ������ݤ������Ĥä���
�Ƕ�κ��ʤϤ��ȡ��������̣�Ǥ��ä����Ϣ³���ä��������κ��ʤǤ���äȤ���©���֤����������롣���������������Ƶ������Ȥ��ä��Ȥ����ǡ�����κ��Τ褦�ʡ��ڤ�̣���說�說��������봶�ˤϤۤɱ�
����Υơ��ޤϡ֥�������ɶȳ��ס�����Ǥޤ���������ɤ˴ؤ�����ߤ���������
���Ԥ��Ȥ�������˥����ե���ǥ����������κ��ʼ�ˡ��ɬ���ե����ޥåȡפˤĤ��Ƥε��Ҥ����롣�ֲ����������Τ����֤äƲ���������������ǤϤʤ������Τ��Ȥɤ��ʤ�Τ�������������Τ����ɼԤζ�̣��椭�Ĥ��륹��顼����Ǥ��뤳�ȡ�����ȯ��������ޤǻ����ۤɤ�û������Ǥ��뤳�ȡ��ǡ����ޥ��˥䥤�롽�������Υ�������ɶȳ��ʤɺ��ʤ��ȤΥơ��ޤ��������뤳�ȡ����㻰�ĤϤҤͤ���Ѱդ��뤳�ȡ�������缴�Ȥ���Ƨ�����Ĥġ����ʤ��Ȥ˰ۤʤ����Ǥ������������դ����Ƥ�����
�ʤ�ۤɡ��ܺ��ʤϡ�ɬ���ե����ޥåȡפ˱�äƤ���Τϴְ㤤�ʤ����Τ��ˡ�������ɤ��ʤäƤ����Ρ������Ĥ��ȿͤΤϤ��Ϥʤ����������Ȥ����פ��ϾǰƬ�ˤ��äơ����δ��Ԥ��ڤ�줿�ꡢ�ɤ��̤���ä���˰���ͫ���ʤ����ɤޤ��Ƥ���롣�֤Ҥͤ�פˤ⡢�����Ʒڤ�������Τ䡢�����ʤ�Τ��ơ��������ɼԤ��䤷�̤��褦��;�Ϥ��Ѱդ��Ƥ��롣����������ʪ��ʤ����Ĥ롣��û������פϤ狼�뤬�����ԡ��ɴ������ޤ����������ۤ顢������å���¦���������Ϥ����ߤ��礱�Ƥ��롣���ʤȤ��ƤΡֵ����פ��������ʤ���
�ŵ������ο��̰����Ρ�����ס��лϤ�κ����Ťζ���������鯽����Ҥ����̤˹Ԥä��Τ����οԤ��������Ťβ�����֤˰�������Ƥ��ޤ����������ӡ������ƻ������ؤ�³������ݵ�������ɤ����ɤ��������⥳��ǥ���Ű����õ��ʪ�컰�ԡ�����Ʋ������ˤ����ơ���ɴ����ԡ����פϥ��ץ�åȥܡ���Ū�ʴ����������ܺ��ʤ��礭���ʤ��륫���֤ζʤ���Ϥ�Ū�ʰ��ݤ��������
�ŵ������ο��̰����Ρ�����פ�����Ȥʤꡢõ�����������Ϻ�ˤ������ˤ���롣�������ξ���ǭ����Ϥޤꡢ���Ĥλ���˰���������ޤ�롣������˰������롢�����ŤȽ�̿�Υ饤�Х��¸�ߤ��⤭Ħ��ˤʤ롣
��ե����Ⱦޤκ��ʤȤ������ȤǼ�˼�ä��������δ��Ԥ��礭���ڤ�줿������ޤ������Ƥ������ξޤΥ�������ɤ��餫�Ȥ����ȥߥ��ƥ���ե����������ܤ���ʤ�����ʤ��ä��������������в��Ǥ⤢��פȤ������ξޤ���ǰ���餹��С�����ʤΤ⤢�꤫�ʡ����⤷��ʤ���
����Х��Ȥ����ä����ǿ��ϲ�ȿ���礦���Ȥˤʤä���������������Ľվ��⡣
��̾�������ʤ顢�ܤ�ɽ��⺣������Ȥ�ڤ����å�����Ϥꤳ�����夬��������ʤʤΤ�������
�ǽ餫��Ǹ�ޤ����Ȥ��ʤ����ȸ�����̥�Ϥ˷礱�뤫�Ȥ����Ȥ����ǤϤʤ������ϤΤ褤����Ĵ�Ҥ��Ӥ���Ƥ��롣�ɤϤ�Ƥ����פ��Τϡ�������ɤ�̡������Ȥ������ȡ��ͥåȤ�õ��Ȥ����ˤ��κ��ʤΥ��ߥå��Ǥ��ҥåȤ��롣ï�Ǥ�ͤ���Τϰ��Ȥߤ��ơ����ߥå����˸������Τ�ɬ�����ä��Τ�������
̡��Τ褦��ʪ��α��ӤʤΤǡ������ä��ɤ�Ƥ��ޤ���¿���οͤϰ쵤�ɤߤ����������ͽ��Ĵ��Ū�ʰ��ݤ��̤����ʤ��Τˤ⤫����餺�����ΤҤ��˰��ä�����Ȥ����ԻĤʺ��ʤǤ⤢�롣
�ǽ�Ϸڤ����å���������Ƥ��롢��ñ��˻פäƤ��������ɤ߿ʤद���ˡ���ԤϤ����Ƥ��Τ褦�ʽ����ˤ����˰㤤�ʤ��Ȥ����ο����Ѥ�äƤ��ä����츫���Ȥ��ʤ����ڤ����դǽ�Ƥ���褦�ˤߤ��뤬���¤ϲ��٤ⲿ�٤���ʤ�����̩�˷���������ޤ�Ƥ����Τ���
���˽Ф���Ԥκ��ʤϤɤ�������Τˤʤ�Τ�����������ϩ���Ǥ����������Ϥ���Τ�������������Ȥ��ȯ���ǽ���äƤ��ޤ��Τ������������ˤʤ�Ȥ�����
����Ʋ���ɤߤ����Ƥ��ޤ�ʤ��Τ�������ϴ��Ԥ���Ƥʤ��ơ��Τ���ä��ɤ�Ǥ��롣
�ܺ��ʤ�û�Խ�����������ޤǽФƤ�������Ʋ���о��ʪ�����줾��μ���ȤʤäƤ��롣���ԤǤϿ�����ʤ��ä����ʤ����ʤ⤢���ʪ�ΰ��̤����ָ����롣�Ȥ����������ο�ʪ�Υ���饯��������ɮ���Ƥ��롣�֤����������������Ȥ��ä��Τ����ʤ�ۤɡפȡ��פ����Ȥ����ꡣ�����ʤ�С��ޤ��ָȳ�Ļ�βơפ����ɤ��֤��Ƥߤ褦�Ȥ�����������ͯ���Ƥ��롣����Ʋ�Ϥ��������롼�פ��äƤ��롣
�ֱ��������װ��衢Ĺ�餯�Ԥ�˾��Ǥ������������ܡ���äѤ����ä�������������������Τ���������ñ�ʤ�����ʪ�˼��ޤ�ʤ��Ȥ������ܽ�α����������Ȥʤ���դ���˻���Ф��졢���θ��Ȥ��Ȥ�Ĥ��̸��դ��ѥ���Υԡ����Τ褦��ʪ�����Ȥ����ޤ�Ƥ���������Ū����þ�����Ф�ʤ�������������Ū���θ��������ޤޤ��ɼԤ�ʪ�����˰���������ߡ�����ĥ�äƤ�������˭�٤ʡפȤ�������Ǥϸ���ɽ���ʤ����餤�θ����Ϥ�ʪ�����ѻ�Ū�ʸ��ߤ�⤿�餷�Ƥ��롣����ʹ���ʤ�ʤ��褦�ʸ��դ��������о줷�����������ä��ɤߤˤ���ʸ�ϤǤ��뤫�ȸ����С������ǤϤʤ����դˤ���ʤ��祤�����Ƥ����������̣�ԻĤʴ��С������դΰ��ۡ����������ֿ�ۤ�����װ�������Ԥ�̥�ϤǤ�������
����ˡ����κ��ʤˤ����ưۺ̤����äƤ���Τ��������դΣ���ʾ夬�彣�ۤ������Ƥ��롢�Ȥ�����������⡢���ƥ��Ƥξ彣�ۡ�����ؼԤǤ⤢�����Ԥΰ�Ĥ�ͷ�ӤʤΤ��⤷��ʤ������Ϥǥ٥��ȥ��顼��̤ˤʤ�Τϴְ㤤���ʤ���������