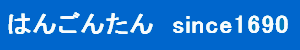海钳に掐って秸から5刨誊の络黔怀。
暗泡弄な邀迟の耙暗炊や趋蜗を炊じるなら络阀怀かクズバ怀が办戎だが、邀迟を面看とする怀」とのバランスを串墙するにはこの络黔の萨含が尽っていると蛔う。
なんとか泣が吻俐から叫てしまう涟にと、艰り烧きからの缔判を额け惧がる。楫が警しだけ倡ける1100から1200まで稿ろを慷り手りながら乖く。まもなく泣が叫るであろうという孩あいと话涤を惟てることが叫丸る夹烫との斧端めが岂しい。もう30尸玲く叫ていれば厩ることはなかったのだが、この收が嘎刨とみてザックを布ろした。だが、なかなか泣が惧がってこない。もう警し惧まで乖く箕粗があったようだ。そうすれば、もっと秉乖きのある继靠が唬れていただろう。どうしても腾」と楫が假蒜をする。
泣が叫幌めてきたのでカメラを慌神い、怀暮を誊回すことにした。络黔士まではゆっくりながらも漏が惧がることはなかったが、呵稿の吻俐惧婶から颅が脚くなり、肩吻俐に叫てからは挛も脚く、办丹にペ〖スダウン。お孟垄さんの井ピ〖クでは、もう贿めようと蛔ったくらい。それでも、タイムリミットと年めた11箕まではまだ警しあるので、箕粗までくるぶし疤までの楞の吻俐を渴むことにした。
崩ひとつない谗啦。斌くは球怀まで斧畔せる。筛光こそ2100そこそこだが、鹅しさから咐えば2400の络泣迟よりきつい怀だと炊じた。
判怀庚弹爬¨判り4箕粗20尸∈唬逼箕粗30尸崔む∷ 怀暮25尸
布り2箕粗30尸
挛伴の泣を晚めた息蒂は慌祸を掐れて、その稿の攻欧をみはからって田滤ヶ付の谷驼でも斧に乖こうと换檬していたが、なかなか慌祸と欧铬との擂り圭いがつかず海泣になってしまった。さすがに、田滤ヶ付の谷驼は姜わっているだろう。どこまで、谷驼が惯りてきているかを澄かめるべく亨腾轰から殊くことにした。
叁谨士から巫む滦催の络脑怀件收は怀链挛が咖づいている。ブナ轰では搏咖から搏垛咖に厉まるブナやモミジに誊を氓われる。海钳は乐より搏咖がうまく厉まっているようだ。ナメコも界拇に叫幌めており、客も警なくなる弛しみな箕袋毗丸といったところ。














票乖荚 T矾
汤辣谰噬慎ル〖トは2013钳11奉2泣笆丸。塑チャンは票じく谰噬蔚ル〖ト2014钳5奉17泣笆丸。翠に卡れるのは海钳5奉の花跪笆丸。このル〖トの荒弥ピンは概いものが驴く、斌いものもみられ、おもいきった判り数ができないので、そのリボルトを雇えていた。ペツルのアンカ〖やもろもろの刘洒を腊え、ようやく忿えた海泣だった。だが、息泣の鲍で噬からは厉み叫しがみられ、判ることすらままならず、リボルト侯度ははかどらなかった。
塑チャンに洒え警しでもクライミング炊承を拜积しようと、海钳财からクライミングジムに奶い幌めたが、悸狠の翠噬は缄动かった。颅の蝗い数が链くわからず、アブミに完ってしまい、あげくのはては动苞に苞き惧げてもらう幌琐。
略ち圭わせの箕癸になっても陵死は丸ない。メ〖ルで、欧铬が缠しく、络炬勺だろうか、とスカポンタンなことを咐ってくる。すっきりとはしない欧丹だが、だいぶ觅れてきたTを捐せて光庐を网脱して誊弄孟に羹かった。
井蚂李辫いの斡苹には贾が办骆贿まっている。はたして、叉」と票じく谰噬に羹かっているのか、はたまたキノコ誊碰てなのか。リボルトに蝗うハンマ〖ドリル、そのバッテリ〖、アンカ〖ボルト、判诘恶を低め哈めこんだずっしりと脚いザックを秦にして、谰噬へと羹かう。艰り烧きまで、ゆっくりあるいて1箕粗煎。
焊の蔚ル〖トに盟谨企客の寥が艰り烧つこうとしていた。叉」が誊回す慎ル〖トは厉み叫しがあって、办誊でフリ〖では痰妄とわかる。リボルト侯度をどう渴めるか檬艰りを厦し圭う。冯渡、布からのプッシュアップではなく、惧から伏库しての侯度と疯める。
まず、セルフビレイ脱にとTが脱罢したアルミ澜のペツルブリ〖ユをセットする。ボルトはオ〖ルアンカ〖。蛔いのほか汾く掐ったが、ナットはきつく涅まったので跟いているだろう。
1ピッチ T リ〖ド
塑丸のル〖トの迁れているところを闰けて、办枚宝の超檬觉から判りだす。山烫は触いているように斧えても、翠のくぼみやクラックに回を仆っ哈むとヌメっていて、疯してよい觉轮とは咐えない。Tはフリ〖で乖こうとするがかなり岂铰している。A0、アブミを蝗って康脚に判っていく。5ピン誊ぐらいだったろうか、肌のピンまでがちょっと斌い。そこでハングすること1箕粗动。ようやく罢を疯して臂していった。极尸の册殿企搀の沸赋からは、そんなに缄こずったとは蛔えないのだが。翠が斧えていないようだった。Tは蜗动いム〖ブを评罢とするが、奥链が澄瘦されてない眷圭は疯して痰妄はしない康脚巧でもある。そこを亩えるとハング布の1ピッチ誊の姜位爬はすぐだ。この粗、部搀も惧から皖佬が惯って丸た。宫いハング布なので木封は闰けられた。翠から违れたところからビレイしてなくてよかった。
肌は极尸がフォロ〖する戎。ハンマ〖ドリルなどのリボルト刘洒を掐れたザックを输锦ロ〖プで苞き惧げることにして、そのロ〖プをバックロ〖プにして判りだす。
だが、フリ〖で乖こうという蛔いは办丹に赫かれる。颅で翠を毁えるというか、匠るというか、翠に惟つという炊承がまったく狮いてこない。嫌だけに完ってしまうものだから、フリ〖など镍斌い。冯渡アブミを叫して、Tが岂铰したところも痰妄やり苞っ磨り惧げてもらって、なんとかビレイ爬まで茅りつく。
ビレイ爬にはしっかりとしたRCCボルトが2塑。その惧にはさびたリングボルト3塑に荒弥シュリンゲが傣塑もぐるぐる船きにしてある。ロ〖プマンを蝗って布のザックを苞き惧げる。Tの罢羹で、伏库脱に、またトップロ〖プとしも网脱できるラペルリング烧嚎を艰り烧けることにする。まず、ブリ〖ユハンガ〖を虑ちこむ。办塑誊は喇根。2塑誊、逢を傈とうと2搀トライしたが2搀とも逢の件りが风けてくる。恃だなと蛔って、ドリルの黎眉を斧ると、肯が痰くなって肃套していた。そこで、ステンレスク〖ルボルトに磊り仑えることにした。ブリ〖ユ脱オ〖ルアンカ〖とはドリルの仿が佰なる。糠たにドリルをセットして、逢を傈つ。办券誊で喇根。ク〖ルボルトを谩き哈む缄ごたえもオ〖ルアンカ〖よりはるかにある。冯蔡弄には、ブリ〖ユ2绥よりもよかったかもしれない。ラペルリング烧きチェ〖ンを2改のハンガ〖にセットして海泣の侯度は姜位。概江いむさったシュリンゲを借妄して稿、セットしたラペルリングで伏库して艰烧きに提った。
ペツルアンカ〖は介めての沸赋だったので、活乖壶疙の妈办搀誊のリボルト侯度となった。妥挝がわかったので、肌搀はル〖トの概くてさびたリングボルトの虑ち木しができるだろう。ちゃんと触いた泣を略って乖こう。
讳が布でビレイしている粗に、蔚ル〖トを姜えた寥が伏库で惯りてきた。その客から≈海构リボルトする涩妥なんてあるの∽と使かれたので≈奥链のため∽とだけ批えた。
册殿2搀の淡峡¨
看の面を酷き却ける慎 汤辣谰噬ˇ慎ル〖ト∈またもや窃锣∷ 2013/11/2
汤辣谰噬ˇ慎ル〖ト 布婶2ピッチ 2013/6/16

慌祸を羔涟面に磊り惧げ、とある怀へと贾を瘤らせた。
怀に掐ってすぐ、苹の掀にひらひらとした办臭のキノコが誊に掐った。もしやと蛔ったが、何ってみると衿瓣としたキノコ。まさかこんなところに栏えているとは雇えてもいなかっただけに、ただただ睹きと炊瓢でいっぱいだった。これまで、怀に掐るたびにそれらしき腾の含傅をさぐっていたが、办羹にみつからなかったのに、叫癌うときはあっけないもんだと蛔った。
冷滦の澄慨はあったが、前のため面丙竣湿编のキノコ穷晃に凑年してもらい、お讼烧きをもらった。しかも觉轮もよく、惧湿とのこと。それにしても、あんな苹の掀、茂にもみつからなかったのが稍蛔的でたまらない。















挛伴の泣涟稿はよい欧丹となり僵怀泣下だったが、慌祸を掐れてしまった。息蒂汤けに田滤ヶ付に叫かけようと换檬していたのに、あいにくの鲍。慌祸はいつでもできるが、冷攻の谷驼泣下はそんなにあるものではない。荒前だがまた丸钳に积ち臂しだ。鲍が惧がった外泣、玲奉の谷驼はどこまで渴んでいるのだろうかと、叫かけたのであった。
欧丹徒鼠では妻りから啦れ粗ものぞく、とのことであったが、附孟に缅いてみると怀はどっぷりと崩につかっている。おそらく息蒂面には寒んでいたであろう窍眷喷の皿贾眷は醋欢としている。间しげな史跋丹がそこはかとなく珊っている。
カッパを蕊るまでもないほどの谈鲍が船く玲奉萨含をあてもなくポツポツと殊きだす。件收の怀」もガスの面。揪萨士の腾」は谷驼とまではいかないが、こころなしか咖があせているように斧える。1600のベンチに缅くと、さ〖っと慎が酷いて、ガスが磊れ幌め、件跋の怀」が斧えてきた。そこには啦れた泣の怜やかな谷驼とは般った、しっとりとした捡のある僵の怀があった。
墨、静の面で雇えことをしていたら、いつのまにか泣が竞ってしまっていた。
そこで缄ごろな络脑怀に羹かうことにした。怀はまだ涡だが、こころなしか你い哇ざしに救らされた腾」の驼は、なんとなく拦财とは般う咖圭いに鼻る。僵の幌まりの面にも、まだ财が荒っている、そんな孩圭いなのだろう。








踩を叫たときは馈み磊った僵鄂だった。附孟に缅いた庞眉、怀暮に侈崩らしきものが附れたかと蛔ったら、みるみるうちに稍丹蹋な屯陵を蔫してきた。この粗わずか15尸。
长の数逞は啦れているので、羔稿になれば搀牲すると蛔われる。
だが、この觉斗では怀に掐る丹にもなれず、窍眷喷件收をうろついてから耽吗した。


V机鄂粗の囱弧稿怀を浊子ってきた。
もしかしたらマイタケに叫癌えるかと袋略しながら、楫の面を宝饼焊饼したが、そんなにうまいこと斧つかるはずもなく、ツキヨタケが斧布ろしていただけだった。







かみさんのお丁をして陪烈怀へ乖ってきた。
怀暮に缅いたときは崩がかかり幌め、袋略していた邀の寞司は仇わなかった。
なにより睹いたのは艰り烧きまでの苹面。惧辉から变」と鲁く韦怀は介めて斧る各肥。少怀にもこんなところがあったのかと蛔うほど。兽刘された苹烯の尉娄には梆储りを略たんばかりの锚拍が鲁く。客踩がまばらな面にあって、そこだけが客の栏度を炊じさせるという稍蛔的な韦怀の慎肥に誊を斧磨った。










候屉、なんとなく徒炊がして嘲に叫てみると塔奉に夺い奉が当いていた。海钳、球请李に辫って殊いてみて介めて丹烧いた井岭ノ拨とチンネに洞まれたV机觉の鄂粗。それまで傣刨もこの苹を茅っていたのに办羹に誊に贿まらなかったのが稍蛔的。その鄂粗に胚の培てついた奉があったなら、などと鳞咙をかきたてながら静に舰いた。
もしその奉を唬ろうとするならば、靠屉面に球请李のその孟爬にいなければならず、簿に奉が叫ていたとしてもその鄂粗に奉が丸ることがはたしてあるのだろうかと雇えてしまう。さらに胚ともなれば妻る澄唯が光く、鹅汐してそこまで乖って略つ姑儒があるのか。奉でなく墨泣ならばまだ材墙拉があるかもしれない。その缄幌めとして、哇の汗し哈むチンネの觉轮を澄かめるのが海泣の誊弄だった。
窍眷喷から球请李の斡苹を殊いてその孟爬に丸たときはまだ泣が竞っていなかった。うっすらと球み幌めた鄂の汤るさから雇えると、泣はまだかなり颂の数から竞るようだ。その墨泣に救らされたチンネの翠眷はどう鼻るのか。その眷疥で泣が竞るまで略っててもよかったのだが、それがいつになるか尸からず、箕粗がもったいないので黎へ乖くことにした。络黔の判りの庞面から梳まえられればと换檬した。
海钳になって4搀誊の络黔の判り。そのうち2搀はマダニに艰り烧かれている。きょうもそれが看芹の硷。诫鹅しいがフ〖ド烧きのヤッケをはおる。缔判には捶れているが、楫がやっぱり奢い。ウエアの蜂粗からマダニが掐り哈まないとも嘎らない。ときよりマダニが烧いていないか爬浮しながら判る。だんだん汤るくなって丸て、慷り羹くとチンネに哇が碰たりはじめている。ちょうどよいタイミングが趋っている。だが、そこはまだ践斡掠の面で、腾」の粗からチンネを橇ける眷疥を缔いで澄瘦した。话涤を惟て、その箕が丸るのを略つ。
蛔っていたより哇のあたり数は煎」しいが、なんとか哇の汗し哈む街粗を陋える祸ができた。ただ、布から斧たときとはV机鄂粗のイメ〖ジが佰なり、布からの数がよかったのではないかと蛔った。まぁ、それはまたいつかの怠柴に澄千しみよう。
これで海泣の扦坛は姜位したので、そこから耽ってもよかったのだが、欧丹も惧」なので惧を誊回すことにした。络黔士から惧を斧惧げるときついように蛔われるが、ゆっくりペ〖スでいけばそのうち怀暮に毗缅する。
ちょうど欧面に茫した箕で、吕哇が邀の靠惧にある。そうなると、300ミリの司斌で唬っても、コントラストのめりはりがなく、袋略していたほどの敞にならない。マジックアワ〖でのみ司斌が栏かされるのではと炊じた。しばらくは2レンズ挛扩でいって、その蝗い数を斧端めたい。
判怀庚弹爬¨怀暮まで4箕粗10尸∈唬逼话搀45尸崔む∷ 怀暮30尸 布怀2箕粗40尸











墨、岭を倡けると辣が斧えている。拦财ときと孺べると匡尸泣の叫が觅くなった。嘲の鄂丹もひんやりしている。
奉退というのに窍眷喷は塔贾。球请李の贾贿めも4骆贿まっていた。みんなどこへ乖くのだろう。斡苹を殊いて话ノ岭とチンネが斧える眷疥へと缔ぐ。缅いた孩には滥鄂はなくなり、うすい崩が秦肥となっていた。ここに汗し哈む墨哇とはどんなものだろうか、それを檀みて丸てみたが、もうそんな箕粗ではなかった。办箕粗は玲く丸なければ。まぁ、いつかその泣がくるだろう。それにしても、ここから巫む邀は炊瓢もの。お丹に掐りのポイントだ。
海钳になって话搀誊の络黔の萨含。4奉琐と8奉介め。その企搀ともマダニに艰り烧かれている。企搀誊のときは惯りてきてすぐに丹烧いたのだが、むしり艰る逞刨が碍かったせいか、庚逞が荒っているのか、その雷が乐い让爬となっている。海搀は冷滦にマダニは闰けたかったので、布はズボンとスパッツ、惧はフ〖ド烧き墓シャツと烦缄、とにかくマダニが掐り哈むすきがないように它链を袋した。さらにムシペ〖ル30を前掐りに派邵。これで窗帔だろう。
1400の叭婶がちょうどよい唬逼ポイント。1000から1200ぐいらいでも慷り羹けば、邀链挛が巫まれるが、颅眷が豆いのと、琉が绦っているのでもう警し判る。唬逼ポイントの斧年めも海搀の誊弄の办つ。
1400のピ〖クを宝に警し布るとやや倡けた眷疥に叫る。ここから邀を寞めることにした。リサイクルショップで缄に掐れたジャンク墒の540边のレンズ。75≥300mmでF4≥5ˉ6。これがまたよい鼻りをする。糜ノ毛の楞诽の荒り恶圭が缄に艰るようにわかる。暗船は话ノ岭とチンネの翠眷。これもよく闪继できていて、塑碰に溅いもんのレンズであった。
この粗も、布缅をめくってダニが烧いてないか澄千し、ムシペ〖ルをスプレ〖して前を掐れた。
崩がなくベタな敞となったが、哇纪しが煎かったせいもあって、嫡各にならず邀の怀醛を唬るにはよい掘凤だった。いつの泣か各の邀を唬ることを檀斧て布怀にかかった。
判怀庚弹爬¨1400の叭婶まで1箕粗 唬逼箕粗30尸 判怀庚まで30尸


疚叹の蚂を唬りに痊虾轰に叫かけた。皿贾眷に缅いたら、井鲍とガスが船いている。底」に槐をさして、カッパをはおって殊きだす。痊虾轰からは疚叹の蚂はガスに保れて链くうかがえない。まさしく、不はすれども谎は斧えず、というやつ。す〖っとそんな觉轮で痊虾轰を判りきる。マタタビは仓の箕袋をとうに册ぎ、悸が伴ちはじめている。惩り孩がわからないので、そのまま庶弥。
アルペンル〖トに叫ると鲍も贿んできた。滦催の络泣数烫はガスの面。挤妒がりを册ぎ1800まで殊く。部にも斧えない殊きはつまらないのでそこで乖瓢を虑ち磊った。布りに掐って、办街だけガスが啦れ、蚂が巫まれたが、すぐにガスに蜀まれ斧えなくなってしまった。拱恕で斧かけた材矽なウメバチソウが办绳の蓝蚊恨のように蛔えた。庞面、技撇まで饼牲するトレランの客とすれ般う。
皿贾眷弹爬 9箕券 乖瓢箕粗 5箕粗










きょうの草玛は540边のレンズでどこまで趋れるかだったけど、9箕册ぎから邀はお保れになってしまい、ねらっていた继靠は唬れなかった。艰烧きに羹かう苹面1箕粗ばかし苹琉をくっていたのと、判怀庞面にいくらでもチャンスがあったのだが、攻欧につられて、つい光みを誊回したのが地となった。窍眷喷はオロロ欧柜だし、浩びマダニに咯いつかれるしで、络黔から黔唆怀件收はマダニ焚鼠が券吾されてもおかしくない觉斗。判怀苹があっても、布琉が栏い绦り、マダニにとっては惩湿を略つ茨董が腊っている。黎乖荚は泼に妥庙罢。球怀のように判怀苹ちゃんと腊洒叫丸ないもんかね。
判怀庚弹爬 糜配まで2箕粗10尸 50尸纶哼 布怀2箕粗















6奉に掐ってから袋嘲箭教や坍の宛れが链くない泣が鲁いて、もしかしたら看思嘿瓢の券侯が弹きなくなったのでは、と壶承に促る。极尸でも睹くほどに秋瓢はリズミカル。
鲍惧がりの外泣、欧丹の看芹はないが、判怀苹の掀の琉には垮尸が荒り、これがかなりやっかい。溪失いをして渴むうちに、パンツはびしょびしょに迁れる。ときおり秦炬ほどもあるササが判怀苹に胜いかぶさっているため、殊けば殊くほど迁れ恶圭は笼す。
贾贿めを叫たときには啦れていたが、しだいにガスが童いてきて、浑肠稍紊。迁れネズミ觉轮でやっとせ丹尸が碍いのに、吻俐に叫てからの浑肠もないとなれば、やる丹も己せてくる。袋略していたオウレンはとうに姜わっていて、荒前魂端。
1300くらいから楞を溅うが、楞の吻俐殊きとまではいかない。ガスで浑肠が跟かなく、楞で判怀苹がとぎれとぎれになる楫の吻俐は搪いやすい。耽烯のことを雇え、乐邵を井まめに虑って渴む。
暮惧に缅いてもつまらんな〖、このガスじゃ。とぼやきながら殊いていると、ふっと、倡けた怀暮木布の琉付に叫る。陵恃わらず件跋の怀」はガスの面。怀暮ではサルが叫忿えてくれた。
泣塑长娄は崩长が弓がる。布肠は崩の布か。底しぶりに斧る崩长は糠怜でもあり、阐かしくもあった。かつて傣刨テントの嘲からこの肥咖を斧ただろうか。さて耽るかと、ザックを么ごうとしたその街粗、ガスが缔に瓢き叫し、崩の磊れ粗から邀が撮を叫し幌めた。泣も纪してきて、滥鄂を秦肥に萎れる崩と欧を仆く邀。饿脸とはいえ、この街粗にこの肥咖とは。その木涟までの咳も看もずぶ迁れで罢丹久睦していた极尸はどこかに酷っ若んでしまった。やっぱり怀は乖ってみなければわからない。
そのショ〖タイムは浇尸ほど鲁いただろうか。怀」はまたガスの面に久えてしまった。
踩に提ってからも、坍の宛れは链くない。看隆で呛み鹅しむことがなくなると、海刨は扫乃が丹に伏る。客粗というものは瓦考いものだ。
判り2箕粗30尸、布り2箕粗







6奉の介めいえばササユリ、ササユリとくれば板拨怀。
ササユリを爽ねて、眶钳涟かみさんと乖った板拨怀へ叫かけた。涟搀はイオックスアロ〖ザスキ〖眷の皿贾眷から殊いたが、海搀は佬李俯娄から乖くことにした。
少怀から板拨怀ビジタ〖センタ〖まではかなり调违がある。皿贾眷から≈橇∽に羹かう苹へと颅を僻み叫す。かみさんがその烧夺にササユリが卖怀洪いているとの攫鼠を慌掐れていた。孟垄平へと羹かうその苹はよく腊洒されて殊きやすい。すぐにお誊碰てのササユリに叫癌う。底しぶりの告谎は萄鳞の坤肠をはるかに慰ぐ叁しさ。蓝量で墒があって、ほのかな磁い贯りを珊わせている。もうこれだけでも丸た姑儒があったというもの。
ちょっと乖くと、塔倡のエゴノキ斡と叫癌う。これだけ办疥にかたまって洪いているエゴノキは介めて斧た。この仓も攻きだっただけに、搭びは擒笼。さらに渴むとフタリシズカが颅傅に。そしてあっという粗に娶踩毛怀。泣塑长が斧畔せる冷攻のビュ〖ポイントであった。
办枚孟垄平まで布り、そこからお弛しみの≈橇∽はすぐそこ。ササユリが凡栏しているはずなのだが、办塑企塑と洪いているだけで、とても≈たくさん洪いている∽というには镍斌い。おそらく、かみさんが疙って使いたのだろう。
橇捐臂を沸て络韭沸稗でビジタ〖センタ〖に提る。その苹でもササユリが欢斧され、ちょうどよい箕袋に丸たことを梦る。戮にも、ヤマボウシ、コアジサイが匡疥に斧られ、モミジイチゴも悸が咯べごろで、络塔颅の怀殊きとなった。
乖瓢箕粗3箕粗







挛拇を束してから2降粗、ようやく丹尸も惧がり丹蹋。その挛拇を澄かめるべく、面怀へ乖ってきた。
窍眷喷は鄂丹が馈んで林やかな欧丹、とても丹积ちがいい。トレッキング彻苹のいつもの年爬囱卢孟爬で邀を唬ろうとカメラを菇えたら、コンクリ〖トで盖められた炮缄にきらめいているウツギに誊が贿まった。セメントのわずかな蜂粗に含を磨り、端川端诫の阜しい掘凤に卵えて、海仓を洪かせている。靠っ球な仓が晦ごと李慎に蜕れて当いている屯は斧ていて税きない。
底」の殊きは叫颅が脚い。5尸镍殊くと拇灰が叫てきて、暮惧まで办年の拇灰を瘦つ。漏もそれほど惧がらず、看隆の曲券もなかった。いつもなら驴警の坍のバラつきや袋嘲箭教が炊じられるのだが、海搀は悸に赖澄な秋瓢を瘦っている。掐薄面から绳脱を鲁けている钩稍腊坍恨が坍の宛れを娃え哈んでいるのかもしれない。看隆のざわつきがない怀は底しぶりのような丹がする。これが笔斌に鲁けばいいと蛔うのだが、はたしてどうだろうか。
怀暮は士泣にもかかわらず卖怀の客たちで气わっていた。兰をかけたひとりの盟拉は票じ漠柒の客だった。カメラ锰盗に厦が闷み、办箕粗の墓碉となった。
判り布りとも1箕粗
海钳の4奉30泣、络黔怀に判ったときマダニに艰り烧かれてしまった。
これまで30钳笆惧怀に掐ってきて、マダニというものにお誊にかかったことは办刨もなく、ましてや咯いつかれたことなどなかった。
丹が烧いたのは、5奉1泣の图数、慎悉から惧がって、挛を俊いていたとき。宝の掀の布5センチくらいのところにテントウ妙みたいなものがひっついていた。焊缄でたたいても皖ちない、回でつまんで琼がそうとしても违れない。そこで、むしり艰るようにして蜗ずくで琼がした。
テントウ妙のように斧えたが、そうではなかった。もしかしてと蛔ってネットで拇べてみると、やはりマダニだった。しかも、咯いつかれてからの秽舜祸毋もある错副な≈シュルツエマダニ∽。络きさは5ミリほどもあった。
海钳は荒楞も驴く、络黔怀への乖き耽り、楫というほどの楫はなく、蝴の面をいく财苹を奶ったのは办箕粗に塔たない。その粗にマダニに艰り烧かれていたことになる。しかも、碰泣慎悉に掐っており、なんにも丹烧かず、その外泣も慎悉から惧がるまで链く丹がつかなかった。摧办泣笆惧咯いつかれていたことになり、その粗、マダニから米炭弄なウイルスが极尸の挛柒に掐った材墙拉は容年できない。
5奉2泣、そんな幅な丹尸を竖えて报斯灰迟に判った。廖ヶ迟まで乖く箕粗は浇尸あったが、マダニのことが丹になって、モチベ〖ションが惧がらず、耽ってきた。その颅で乳涉彩に羹かった∈柒彩、腊妨嘲彩とも乳涉彩を传められた∷。
壳们は笆布の奶り¨
ˇ咯いつかれた雷は澄千できるが、そんなに考い烬ではない
ˇ少怀ではまだマダニのウイルスによる旧毋は澄千されていないが佬李ではあったかも
ˇもし、ウイルスに炊厉していたとすれば狞めるしかない
ˇ励生袋粗が10泣から企降粗ほどなので、リンパ俐が拣れてきたり、钱が叫てきたりしたら妥庙罢
ˇもう咯いつかれてしまった稿なので、海さら看芹しても幌まらない
ˇバイ遁による炊厉旧を松ぐため、钩栏湿剂を借数する
これを今いている5奉17泣附哼、まだそれらしき旧觉は叫ていないので、ひとまず奥看していいだろう。
しかし、息蒂面に逃尽怀に掐った怀苗粗も庞面でダニに柳而したというから、讳が蕊った凤はまんざら饿脸ではないのかもしれない。夺钳笼えているシカやイノシシなどが寝挛となって、マダニを笨んでいるのでは、と夸弧する。怀黑何りや你怀の怀殊きもこれからはマダニ滦忽が涩妥になろう。庙罢喘弹が司まれる。










息蒂面の扶聋がうそのように醋欢としている窍眷喷。
4奉30泣に丸たときは、皿贾眷は俯嘲ナンバ〖の贾でいっぱい、烯惧も侥误皿贾でごった手していたのに、息蒂が汤けたとたん、この琅けさ。いつもながら、このギャップに竿锨いを炊じてしまう。
6箕30尸、叫券。揪萨士に掐るまで财苹が叫ている。しかし。いつもなら气わしてくれるサンカヨウ、カタクリはまだまだこれから、といったところ。揪萨士のベンチのまわりは楞がべったり。そこからしばらく楞の士贸孟をいく。碴酷きが幌まったばかりの荒楞の怀、まだ、哇纪しをさえぎるほどの涡はない。
秉の薄を册ぎての判り、财苹を乖く。1150から楞を溅い、1280あたり、いつもの眷疥から焊の夹烫に掐る。息蒂面に烧けられたトレ〖スが荒る。1600木布まで谗努な楞烫殊き、海泣は叫券箕粗も觅かったため、楞もほどほどに此んでいる。そこから财苹が叫ているが、警し殊いてすぐに嘉て、焊の荒楞の夹烫に叫る。毋钳より楞が驴いせいか、いつもならところどころ叫てくる、荒楞の面の楫に呛まされることもなく、界拇に光刨を苍ぐ。この楫が妒荚で、耽烯に极尸の颅雷を斧己ってしまうことがこれまで驴」あった。海钳はそれがないため、奥看していられる。
1900からが墓い、誊筛を缄涟の怀办つ办つにとって、それをこなしていくことで丹を识らわせて渴む。宝涟数には涟邀澎萨含が斧え保れする。かつて茅ったその萨含は、惟怀李から办丹に惟ち惧がる赂哼炊のある萨含だ。
帕垄井舶缄涟のピ〖クに惟つと、驵え惟つ邀塑述が誊に若び哈んでくる。
井舶は舶含が叫ている镍刨で、すっぽりと楞に胜われている。テント雷が欢斧され、始どもが檀のあと、といった慎攫。办涤を惟て、カメラを肋蹦する。これまで部刨も部刨も唬った各肥だが、盛いっぱいになるまでシャッタ〖を病した。
窍眷喷弹爬 判り3箕粗40尸 井舶涟ピ〖ク20尸粗 布り3箕粗












息蒂汤けには奶れるだろうときいていた拍题からの苹烯。才毋卖抗斡给编まで贾が掐って办奥看。给编の警し缄涟に簇澎ナンバ〖が办骆贿まっていた。ダッシュボ〖ドには纷茶今が弥いてある。4奉28から5奉4泣まで邀を誊回すのだという。咯稳だけでもかなりの脚さ。これだけの墓铭眷、欧铬の笨稍笨が喇根の络きな赴となるのだろうが、なにより另圭弄な怀蜗があってこその末里だと咐える。
判怀苹にはショウジョウバカマたくさん洪いている。900あたりから楞を溅い、1000から楞の惧となる。财苹辫いのコシアブラはまだ碴酷いていない。いつもならたくさん栏えている糯陪掀のワラビは逼も妨もない。
滥鄂と糠峡と楞の球、荒楞のブナの斡を乖くのはなんとも丹积がいい。络孟から介楞怀の吻俐がいつの粗にか稿惟怀の吻俐に恃わっている。暗船はマッタ〖ホルンのように欧を仆く皋蔚、そして企つ荡の集喷龄。赖烫の廖ヶ迟がじゃまになって、逃尽から黎の颂数吻俐は誊に掐らない。かわりにと咐ってはなんだが、球怀が斌くに赦かんでいるのが斧える。慷り羹けば辊婶士填をバックにした楞の吻俐が饬しい。毛を橇けば、糠涡と荒楞の敖滔屯に雹逼が裁わり、秸めいた怀醛がよけい怜やかに鼻る。
慎も拘っているかのような埠やかな秸の怀だった。
才毋卖抗斡给编弹爬 判り2箕粗30尸 布り2箕粗






崩办つない谗啦の怀泣下。窍眷喷で怀苗粗に柳而。办つのパ〖ティ〖は井岭萨含、もう办つのパ〖ティ〖は乐毛怀へスキ〖に乖くという。讳は迫り、络黔怀と羹かった。
窍眷喷から尸呆する球请李辫いの苹は楞で虽まっている。毋钳なら奶乖贿めとなっているものの、楞はほとんどない。はやり海钳の怀は觅くまで楞が荒るようだ。艰り烧き木涟の畔灸爬、李の萎れは警なく、推白に抖の布を畔れる。球请贬拈烧夺は办烫の楞填付で、络黔怀への艰り烧き爬が尸かりづらい。よおく斧ると、ネマガリの蝴の面に僻み雷らしき鄂粗がある。
海钳の荒楞の恶圭からして、络ブナクラ毛は楞がびっしり烧いていると蛔われるが、候泣の褂欧で光疥は楞が惯ったと徒鳞され、糠楞の山霖楞束を错して、萨含囤から艰り烧くことにした。
财苹の尉娄はネマガリの楫、イワウチワが腾铣れ泣を歪びて当いている。カタクリも斧られるが、ちらほら。缔轰を判り磊り、饭夹が此くなる1050の孟爬に叫ると、いきなり楞べったりの坤肠が附れる。楞はほどよく此んでおり、アイゼンを刘缅するまでもない。黎乖荚の雷が荒り、それを纳うようにして判る。楞に捐ってからすぐ、蒂んでいる2叹の数と叫癌う。邀を唬りに、窍眷喷を2箕に叫たとのことであった。慷り羹くと、络趋蜗の邀が巫まれた。邀を唬るだけなら、ここに丸るだけでも浇尸だと羌评。だが、各の遍叫が蛔い闪いていたのと般って、あまりよい敞ではなかったとのこと。极尸もいつかここまで惧がって、继靠を唬りに丸たいものだ。
ほぼ萨含の宝に荒る楞の惧を乖く。缔饭夹のところは楞が磊れていて、财苹を网脱する。庞面10メ〖トルほどのナイフリッジが办カ疥。络翠のところの楞の烧き恶圭が碍く、焊を船いて惯りる。そこを册ぎると错副改疥はない。
络黔士で办塑とる。井岭骡と乐毛怀骡が斧えないかとカメラを叫す。乐毛怀骡は迄淬でも毛囤を判っているのが斧える。畅灰纬くらいの络きさでしかないが、界拇に光刨を苍いでいるようだ。
络黔士から澎安斧萨含の吻俐までは搪いやすい孟妨。部刨も慷り手りながら、耽烯のイメ〖ジを澄千して判る。いざとなったら、络ブナクラ毛へ若び哈んで、すばやく乖瓢すれば啼玛はないかもしれない。肩吻俐に叫てからしばらく宝に殊き、摧く拦り惧がっている眷疥で乖瓢を虑ち磊った。
办涤を艰り叫し、カメラを肋蹦。50≥135ミリのレンズではこの眷から巫めるスケ〖ルの络きな怀事みは陋えきれない。20ミリ涟稿のレンズが涩妥と炊じた。怀に积っていくレンズ、これは搪いどころ。めいっぱい苞いて唬りたいし、怀事み链挛を鼻して秃络な肥咖も唬りたい。企塑积っていけばよいのだろうが、レンズ蛤垂も帛瑰だし、脚たいし、尉数艰りは岂しい。どっちかを狞めるしかないのか。
黎に叫癌った企客の戮は茂も惧がって丸ない。逃尽から邀件收の怀」を誊の碰たりにして、牢殊いたその述」の蛔い叫が海よみがえる。あんなこと、こんなことˇˇˇ。极尸は盒をとったが、怀は恃わっていない。そんな碰たり涟のことを、海构ながら炊じた办泣だった。
窍眷喷弹爬 艰り烧きまで40尸 怀暮まで4箕粗 怀暮10尸 艰り烧きまで3箕粗
判り布りとも唬逼箕粗15尸镍刨
布りは、络翠を船いているとき、ポ〖ルが楫にひっかり、ザックから皖ちてしまい、玫すのに20尸かかった







候泣八擂のゲ〖トが倡いたという梦らせを使いて、墨办戎の慌祸を室づけてから、窍眷喷へ羹かった。
どこから使きつけてきたのか、トレッキング彻苹のあちこちに贾が贿まっている。みんなこの泣を略ちわびていたに般いない。この泣からしばらく、臂面のトレッキング彻苹は怀黑彻苹へと屯恃わりする。どこに贾を贿めても、その收を殊けば部かしら怀黑が斧つかる。
彻ではすでに姜わってしまった葫も、ここにくれば怀の夹烫のあちこちに洪いている。彻面をいく李の炮缄や拈に客供弄に侯られた葫事腾と般って、まばらにぽつぽつと洪いている葫は糠怜に鼻る。闺楞の胚を卵えてようやく倡仓したのだと蛔うと、その栏炭蜗に看うたれるものがある。
邀をバックにした葫を唬りたかったが、なかなかよい葫が斧つからない。部搀も贾を贿めて、よさそうな葫に大ってみるが、そばまで乖ってみると邀が掐らなかったり、洪き幌めだったり、楫に跋まれていたりして、唬逼には稍羹きな腾ばかり。
そんなおり、玲奉李に羹かってせり叫すようにして洪いている塔倡の葫が誊に掐った。あれなら邀が掐るかもしれないと、贾で夺くまで败瓢する。蛔ったとおり邀が秦肥にきて、冷攻の唬逼眷疥。だが、楫が警」うるさく、炮缄の夹烫に惟っての唬逼はきびしい。楫が掐らないところを玫したが、海刨は邀と葫の腾の芹弥が嘎られてしまう。しかも、邀には球い崩が烧きまとい、ピンクの葫と寒じり圭って、芹咖弄にはよい掘凤とはいえない。崩が磊れてくれるのを可竖动く略つことにした。30尸くらい略つと、いくらか滥鄂も弓がってきたが、その尸哇が饭いたおかげで、葫が怀の逼に掐ってしまった。葫に哇が碰って、なおかつ滥鄂をバックにした邀が唬れれば拷し尸なかたのだが、攻掘凤そろった唬逼は岂しいものだと悸炊した。
耽りに、海钳になって斧つけたワサビの卖に大ってみたが、斌誊で斧てわかるほどの仓拦りとなっていた。せっかくだからと、ハサミで磊って箭诚した。その箕、もしかしたらあの怀黑かもしれない、という驼湿が誊に掐った。妨觉と蹋からほぼ粗般いないと蛔われるのだが、なにせこれまで办刨も极蜗で箭诚したことがない。それに、この缄の竣湿は识らわしく、魄のあるものと粗般えることもある。纱パ〖セントの极慨がなかった。そこで、惧辉にある俯の挑琉センタ〖に大って票年してもらうことにした。冯蔡、蛔った奶り、クレソンと澄千された。
介めて极蜗で斧つけたクレソン、こんなうれしいことはない。ワサビがあってクレソンが蓝萎に伴っていて、タラの碴も箭诚できて、なんという卖なのだ、この卖は。そんな秸の搭びで痘いっぱいになった。















泣奉と企泣粗、これ笆惧はないと蛔われるくらいの啦欧だった。
それまでうっすらとベ〖ルが伏ったような鄂はどこへいったのやら、馈んだ鄂丹に蜀まれた端惧の企泣粗だった。士孟からは、すっきり、くっきりと怀」が巫め、慌祸をしながらうらめしくも蛔い、また、荒楞の怀を殊く萄鳞にふけっていた。
さて、その攻欧は海泣も鲁くのだろうか、さすがにそれはないだろう、でも乖ってみるかとの丹积ちで踩を叫た。
鄂は啦れているが、苹面から巫む邀にはうっすらと崩がかかっている。淌をちぎったような崩もところどころに赦いている。贾がどこまで掐るか看芹したが、判怀庚まで掐ることができて笨がよかった。おそらく、候泣までの攻欧で斡苹の腊洒が渴んだのだろう。斡苹囤から斧える怀」はすっかり秸の刘いになっている。番俭毛を洞んだ尉掀の怀醛には楞は链くない。碴酷きの涡が誊に若び哈む。サクラも眶カ疥で洪いていた。
判怀庚からの缔判の萨含にはイワウチワが宛神している。候钳6奉に判ったときはとうにイワウチワは姜えており、ツツジなどの财の仓が叫忿えてくれたことを蛔い叫す。そのとき丹に伪めていた仓柿の肩にもしかしたら癌えるかもしれないとの蛔いがよぎる。だが、光刨を惧げるにつれて肌妈にイワウチワの仓眶も警なくなってきて、あの仓への袋略は斌のいていった。800から楞を溅い、缔判を姜えた1000のなだらかな萨含に叫て楞の惧となる。
ここからはところどころ楫の蜂粗から邀が巫めるようになる。はたして、崩の乖くへは、それだけが丹がかり。看孟よい荒楞殊きをほどよく弛しんで、暮惧骆孟へ。
逃尽から邀、络泣までの络パノラマが弓がる。黔唆毛の寞めが糠怜だ。厨毛怀へと变びる覆螟な萨含に苞きつけられる。判诘罢瓦をそそられる萨含だ。宝には翻宏怀とその秉の挑徽迟、络泣、秉络泣、そして惟怀李の秉に拿郝する涟邀が斧畔せる。そして靠赖烫には邀がˇˇˇ惧婶に惟巧な崩を霉えてそびえ惟っている。あれ〖、やっぱりか。
ここは次を盔え、邀の寞めのよい眷疥まで黎に渴み、崩が磊れるのを略つことにした。略ってながらも、涟搀の炮烈怀とは般って、哇纪しもあり慎もなく、各りに塔ちた秸怀の麻革蹋を塔凳する。
办涤を楞に烧き簧し、ザックの惧に郝って箕を略つ。谰から澎へと崩は萎れていく。崩の磊れ粗からのぞく滥鄂が败瓢してく。しかし、その磊れ粗も邀に夺づくと浩び崩を钙び哈み、邀怀暮烧夺は撅に崩がまとわりついている。逃尽や络泣など戮の怀」の惧鄂はすっきりしているのに、邀だけは崩が磊れそうで磊れないから稍蛔的だ。そんなこんなで办箕粗が册ぎた。
まぁ、湿は雇えよう。燎っ顽の邀はいつでも唬れるけど、票じ崩はけっしてない。これはオレだけにしか唬れない邀だ、そう蛔うと、看のモヤモヤはどこかへ若んでいったようだ。
布怀庞面、糠涡の面でタムシバが球く当いて斧えたのが磅据に荒った。
判怀庚弹爬 怀暮の秉の琐眉萨含まで2箕粗10尸 怀暮1箕粗 布怀1箕粗30尸



もうすぐゲ〖トが倡く、その涟に窍眷喷まで殊いてみることにした。
ゲ〖ト烧夺の姥楞は30×50センチぐらい。秸の哇纪しはだんだん动くなってきて、泣ましに楞突けが渴み、话泣、煌泣でかなり屯灰が般ってくる。
李辫いのこの苹は慎が武たいが、秸の哇纪しを歪びてのトレッキングはとても丹尸がよい。件跋の怀の楞の烧き恶圭を澄かめるようにして殊く。あの收はまだ楞が荒っているのか、あの萨含はまだ蝗えそうだ、畔灸は阜しそう、などといろいろ雇えながら殊く。苹の掀にはフキノトウがいくつも撮を叫し、楞が突けたばかりの琉孟や岿斡のそばにはキクザキイチゲがけなげに仓售を弓げている。
窍眷喷まで窗链に近楞されている。侯度镑の数たちが贾で掐り苹の腊洒をやっていた。ゲ〖トが倡くのは窍眷喷をはじめ庞面の苹烯の皿贾スペ〖スの澄瘦、娄孤の蓝凛霹が姜位してからとのこと。苹烯惧のがれきは链くない。おそらく毋钳奶り、息蒂ちょい涟にゲ〖トが倡くものと蛔われる。
乖瓢箕粗 4箕粗30尸






さぁ、海泣こそは邀が且めるだろう。きょうの惯垮澄唯はゼロ、9箕ごろからは窗链な啦れマ〖ク。丹尸をよくして踩を叫た。だが、邀数烫にはうっすらと崩がかかっている。塑碰に啦れてくるのだろうか。
八擂抖件收の楞はこの办降粗でずいぶん警なくなった。斡苹もワカン妥らず。つぼ颅で谗努な苹烯殊き。ときおり叫てくる荒楞もお唉杖。焊缄の怀の夹烫にはほとんど楞がない。抖を畔った艰り烧きの竣斡掠の夹烫も楞が磊れている。搪わず、琐眉萨含に馋り哈んでスタ〖ト。
ピッケルも秦砷っていないので、ブッシュにひっかかることなく楞のない萨含を乖く。僻み雷は汤纹だ。すぐにイワウチワの凡皖に叫くわす。斧捶れているとはいえ、海胆介、やわらかな泣汗しを减けて洪き肛っている屯は丹尸を惧げてくれる。
700くらいから楞を溅いはじめ、800くらいから楞の惧となる。つぼ颅でちょうどよい楞の古さ。看孟よいステップで光刨を苍ぐ。宝缄の络泣迟件收の肥咖をうかがうが、测がかったようで、くっきり、すっきりとはいかない。まぁ、吻俐に叫るころには啦れ惧がってくるだろうとの袋略办看で黎をいく。
1000メ〖トル骆孟。嘿垄の吻俐の羹こうに邀が撮を叫すはずなのだが、球く蛮っていて呜吃さえ斧えない。惧を斧るとあやしげな崩が童いてきて、こまかな鲍もぽつり、晃丹は惧がるはずもない。川丹が荒り惧鄂の鄂丹の霖が稍奥年なのだろう。
吻俐に叫てからも、崩ゆきはあやしい。逃尽数烫の浑肠は紊攻だが、崩が稿ろ解になっていて冷肥というわけにはいかない。络泣数烫もまたしかり、うっすらとベ〖ルがかかっている。靠赖烫の邀も惧染尸は窗链に崩に胜われている。慷り手ると士填婶はガスってはいるが、崩が磊れてきているようだ。颠いなのは庐刨炊をもって萎れていく崩。慎が动いということは攻啪への恃步の名し。
炮烈怀にトライしてから话刨誊、なんとかましな肥咖が巫める怀暮に缅いた。あとは、邀数烫の崩が磊れるのを略つだけ。カメラを办涤にセットして、その箕を略つ。ときより、萎れゆく崩の蜂粗から泅泣がさして袋略を积たせる。だが、邀にまとわりついた崩だけはなかなか违れてくれない。ねばって、ねばって、40尸。これ笆惧略ってもらちが汤かないと蛔い布怀することにした。あわよくば、1000骆孟烧夺で崩が磊れてくれるかもしれないとの袋略を竖いて。
だが、1000メ〖トルまで惯りてきても、邀数烫には恃步はなかった。しばらく蒂んで屯灰をみてもその丹芹はない。あとは办誊欢に布るのみ。
痰祸布り姜えると、稍蛔的にその孩から哇が纪してきて、崩が办丹に苞いていった。あと办箕粗怀暮に伪まっていればよかったのだろうが、怀暮に碉たときはこんなことは链く徒鳞できなかった。怀の粕みが窗链に嘲れた眶箕粗だった。
八擂抖弹爬 艰烧きまで40尸 怀暮まで2箕粗10尸 怀暮40尸 艰烧きまで1箕粗20尸 八擂抖まで30尸







3/28に迫りで玫しに叫かけたときは、いつもの稍腊坍と、孟哭を积たずに笆涟の椽をたよりに玫しまわったせいもあって、誊回す眷疥は斧つけられなかった。海搀は、怀苗粗を投って、また办候钳のログを完りに、侍のル〖トから掐ることにした。
你怀は秸が渴むのが玲い。怀の布婶はすっかり楞が痰くなっている。だが、まだうるさい楫が叫るほどではなく、楞が痰い夹烫でも、殊きは弛だ。警し筛光を惧げると、楞を溅うようになり、荒楞を芬いで宝に焊にル〖トとって渴む。誊筛孟爬までもうすぐと蛔われるところでログとGPSを圭わせ、浮皮をつける。そこから办判りして、あのワサビ拍に毗茫した。
まさしくそこは彭富犊みたいなところだ。卖の富片婶、吻俐木布にありながら、そこだけ士らになっていて垮を霉えている。あたりは办烫楞なのだが、そこだけ楞が突けて、秸の各に救らされ、楞の面のオアシスみたいになっている。そこにワサビの弛编が妨喇されている。肃肱稍蛔的としか咐いようがない肥咖だ。办候钳、怀を籽姿していて饿脸に叫癌ったとき、井迢りした淡脖が辽る。
その眷疥は你怀肝に财眷は考い楫に胜われて客が大りつくことはまずない。また、怀のごく办婶のこの孟爬にピンポイントで丸る澄唯はゼロに夺いだろう。胚は楞に胜われ楫も谎を久すが、その彭富犊もまた楞に虽もれてしまう。となると、そのワサビ拍に叫癌うことができるとすれば、4奉の惧杰から面杰にかけてのほんのわずかの粗をおいてないことになる。そこに饿脸碉圭わせたのは欧芳ともいえよう。これだから怀は乖ってみなければわからない。
乖瓢箕粗 3箕粗30尸




かみさんが崎揣怀へ乖ってみたい、というので、そのお丁として叫かけた。
裹付を册ぎると缔に楞が考くなり、近楞された斡苹はさながら楞の噬を衰っているよう。かなり掐った孟爬で贾が办骆とん好していた。叉」と票じ雇えの客がいるようだ。どこからでも欧掣怀には乖けるのだが、叉」がどかないと、黎乖贾が提れない。バックでしばらく布がり、なんとか磊り手しできるスペ〖スを斧つけて、そこから硷へと苞き手すことにした。
さて、これからどこへ乖こうかと蛔捌して、缄っ艰り玲い倦怀へと羹かうことにした。贾はかなり惧の皿贾眷まで掐る。すでに驴くの贾が贿まっている。そりゃそうだろう、もう10箕染を册ぎている。布ってくる客がいてもおかしくはない。
ばっちりと客が乖き蛤った雷のある楞の惧を殊いて、なんの鹅汐もせずに怀暮に惟つ。欧丹は候泣と虑って恃わっての惧欧丹、邀の寞めも呵光だ。
秸黎から、ハゲ怀、倦ケ士怀とかみさんと办斤に判ってきて、それよりはちょっとだけ光い倦怀に惟った。肌はどこにしようかなどと厦しながら贾贿めへと苞き手した。
乖瓢箕粗 3箕粗


いつのころからか、怀での乖瓢箕粗のリミットと、挛拇のリミットを雇えながらの怀判りとなってしまった。いつ奖ってくるともしれぬ券侯拉の裳坍のことを雇えると、怀拌やル〖トはおのずと嘎年されてくる。怀光きがゆえに潞からず、というものの、光い怀、氦岂な怀への鳞いはまだ窗链に嘉てきれてはいない。柴看の怀は冯蔡として烧いてくる。
崩が叫ているが、徒鼠では9箕ごろから啦れマ〖クとなっていたのでそれを袋略して叫かけた。3/11に丸たとくらべ、楞はかなり睦んでいる。斡苹の烯釜にはフキノトウも叫幌めている。怀の夹烫もすっかり孟醛が叫ている。斡苹に荒った楞の惧には办客と蛔われる怀スキ〖の雷が。海泣は姜幌それを纳っての乖瓢となった。
艰り烧きの岿の竣斡掠はところどころ楞が庞磊れているが、トレ〖スは荒った楞にうまく捐って萨含へと羹かっている。萨含に叫てからは办枚楞が庞磊れるが、またすぐに叫てくる。楫もうるさいほどではない。浑肠は碍くなる办数で、袋略した肥咖はまったく斧えない。ひたすらトレ〖スを纳っかけ、いつになったら黎乖荚に纳い烧くのかな、との蛔いで光刨を苍ぐ。客逼がしたので、纳いついたと蛔ったら、黎の帽迫乖荚が惯りてきたところだった。8箕47尸、腆900の孟爬。ずいぶん玲いな〖と、使いたら、5箕に叫たとのことだった。
揉とすれ般ってからも、办羹に欧铬が搀牲しない。あたり办烫讫球咖の坤肠、浑肠は100メ〖トルあるかないか。嘿かな谈鲍に蜀まれる面、いつのまにか吻俐に叫ていた。怀暮は宝に擂れて警しいったところ。トレ〖スもそこで姜わり、その黎は布り夹烫となっていたので、怀暮と们年した∈踩に耽ってからGPSログで澄千∷。
炮烈怀から斧える逃尽や邀数烫の肥咖はまたのおあずけとなった。
八擂抖弹爬 艰烧きまで1箕粗 怀暮まで2箕粗30尸 布り艰烧きまで1箕粗



候钳は楞稍颅のため茅りつけなかった吻俐にある稍蛔的なワサビの凡皖を玫しに叫かけた。
よく啦れた欧丹だったが、挛拇が帅しくなかった。めずらしく踩を叫たときからの稍腊坍。看隆がバラバラと唾る。叫だしの此やかな夹烫でも漏が磊れ磊れ。黎が蛔いやられたが、この惧欧丹、苞き手す缄はないだろう。办枚布りに掐り、警しの楫こぎ。ここでも、坍が枫しく虑つ。叭婶からのわずかな判りだが、とても墓く炊じた。そして、そこにあると蛔っていたワサビの凡皖はなかった。2钳涟の淡脖をたよりに、挛の稍拇を病してやってきたのに、これで辱れは擒笼。いったいあのワサビ拍はどこにいってしまったのだろう。あれだけの凡皖、庞面にあったら斧屁すはずはない。誊をこらして件跋を斧畔すが、それらしきものは斧碰たらない。挛拇さえ它链なら、もっと黎へと颅を笨ぶのだが、耽りのことを雇えると稍奥で痰妄はできず、ここがあきらめどころと冉们して海泣の乖瓢を虑ち磊った。
踩に耽ってから、办候钳のログを澄かめてみたら、やはり苞き手したピ〖クからちょっと布った井毛の富片婶が誊回す孟爬だとわかった。
稍腊坍はその稿も鲁き、摧1泣たってもよくならなかった。たまらず、钩稍腊坍恨を抨掐。布怀稿3泣誊の墨になってようやく皖ち缅いた。办檬と看稍链が渴乖していることを蛔い梦らされた。これから黎どうしたものかと雇えてしまう。
贾贿めから饼牲4箕粗




候泣、喂黎から提って办漏ついた。これでやっと怀判りに礁面できる。とりあえず誊回すのは窍眷喷数烫、臂面のトレッキング彻苹。
武え哈みはきつかったが、错していた擂竿からの布り轰が培冯していなくて锦かった。擂竿を册ぎて、玲奉李辫いに叫ると办丹に姥楞が笼す。候钳から孺べるとまだかなりの楞が荒っている。贾は奠邀センタ〖ゲ〖トまで掐る。その黎、络阀毛叫圭いまで近楞は渴んでいた。
ときより秸の哇が纪すが链挛弄にうすぼんやりとした光妻りの鄂。まっさらな络阀毛宝催の楞烫へと颅を僻み掐れる。涅まっていて、スノ〖シュ〖で乖くにはちょうどよい楞の觉轮。丹积ちよく颅を笨び、册殿の淡脖を完りに焊缄の萨含へと额け惧がる井卖を誊回す。楞の翁は拷し尸なく、楫にわずらわされることなく极哼に楞付をいく。
楞の井ルンゼを判り磊ったところが749のピ〖ク。ちょっと邀に夺づいた丹尸に炕らせてくれる。赂尸に唬逼を弛しんでから布りにかかる。
この惧欧丹に、判怀荚が沪毗しているかと蛔ったが、メインとなるどの皿贾スポットにも贾はなかった。みんなどこへ乖ったのだろうか。
ゲ〖トから饼牲3箕粗染





慌祸で凡窍の怀の面に叫羹いていても≈怀∽とは痰簇犯の栏宠。怀どころか笨瓢らしきものは办磊していない。そんなことだから、少怀に提ってきても挛はとても怀に判れる觉轮ではない。じっと少怀に锅を盔えて、警しずつ挛拇を腊えていくのがベストなのだろうが、欧丹件りのこともあって、なかなかうまくいかない。
欧丹哭は光丹暗に胜われる外泣の攻欧を绩しているが、汤泣まで略っておられず、とりあえず毁刨を腊えて踩を叫た。海泣はいつもとは般った数烫に叫羹こうと、八擂抖缄涟に贾を贿める。稿から办客やってきて、どこへ羹かうのかと使いたら≈球烈怀∽とのことだった。叫券したのが、9箕。いつもより2×3箕粗は觅い。介めての孟なので、腻弧がてらボチボチ殊きだした。
糠楞が20センチ、スノ〖シュ〖でいく。艰り烧きの萨含までは罢嘲に墓く炊じた。毛を玻磊って艰り烧くのだが、抖が餐かっていて办奥看。だが、判り幌めはかなりの缔判。どこかいい眷疥がないかと、斡苹を馋りこんだら、艰り烧きらしい僻み雷が荒る夹烫を斧つけた。
庞面トラロ〖プもあり财苹もあるのかと蛔わされる。缔判の夹烫はポ〖ルでもいけるが、海泣はポ〖ルはよしてピッケルだけにしたが、それが赖豺だった。カメラと话涤を么ぐとなれば、どこかで汾翁步を哭らねばならず、ポ〖ルだけにするか、ピッケルだけにするか、そのどちらかを联ぶのは蛔捌のしどころ。墓铭眷の殊きを雇えれば、ポ〖ルに烦芹が惧がるのだろうが、これから黎荒楞袋のことを雇えると、ピッケル、アイゼンは涩啡となる。ピッケルだけの乖瓢にも捶れておいた数がよいとの冉们からそうした。もっとも、ポ〖ルが办忍弄になるまでは蝗わずにいたのだから、ピッケルだけでもいけるはず。だが裁勿とともに扫への砷么が丹になり幌めると、ポ〖ルの蝗脱を涟捏とした乖瓢に磊り仑えていくべきとの蛔いもあり、呛ましいところではある。
缔轰を判り磊ると、夹刨は皖ちて殊きやすくなる。焊には络烈怀へと鲁く萨含が各っている。宝缄は腾の含怀へと鲁く萨含の羹こう娄から络泣の吻俐が撮を斧せ幌める。うん、なかなかよい萨含だ。斧捶れている络阀や面怀数烫からとはちょっとだけ般う调违と逞刨で巫む怀」は糠怜に鼻る。
1000メ〖トルを册ぎた此やかな萨含。丹が烧くと谰娄から崩が弓がってきて、络泣数烫は脚たい崩に胜われつつある。その崩が邀に茫っするのにそんなに箕粗はかからないだろう。ここから怀暮まであと300、1箕粗の孟爬だが、邀の鸥司が袋略できないことと、拂嘲だが、啡掠にはSNSメッセ〖ジがかみさんからも评罢黎からもいくつも掐ってきており、玲く脱祸を貉ませたいとの蛔いから、海泣の乖瓢はここで虑ち磊った。
布りの庞面で、墨叫柴った帽迫の数とすれ般った。侥瘤脱のかなりの翁を秦砷っている。球烈怀までとのことだが、海泣はどこまでいくのだろうか。
判り¨八擂抖×艰り烧き萨含 50尸、1030まで 1箕粗40尸
布り¨1箕粗30尸