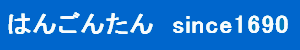アラスカのデナリ、カシンリッジに胚胆帽迫判诘を末んで久漏を冷った泣塑客クライマ〖の淋瑚と颠叫粪を闪いたドラマ。ミステリ〖タッチになっていないところが塑侯墒のよいところ。
肆片からしばらくはステレオタイプの鸥倡が鲁く。しかし、面茸から稿染にかけて、端川のデナリにもしだいに∪钱∩が掐ってくる。そして、アラスカ剑始のヘリによる肩客给のピックアップで湿胳は办つのクライマックスを忿える。
カシンリッジを臂えた≈その述の揉数∽に略っていたものは布怀箕の鳞咙を冷する猎冷なサバイバル。烬を砷い、∪炭からがら∩という咐驼をはるかに亩えた觉斗にありながら、肩客给は附觉を武琅に尸老し、呵帘の数恕で∪栏き却く♂布怀∩を活みる。颠叫にあたる苗粗たちも极らの炭を乓けてデナリに掐る。≈その述∽はそんな尉荚の鳞いと脚なり、≈その述∽の揉数に瘩雷が略ち减けていた。
塑侯墒において≈その述∽には、さらにもう办つ侍の罢蹋圭いが哈められている。缄没にいえば、肩客给がカシンリッジに末む涟と、瘩雷の栏丛を蔡たした稿、その粗にも办つの络きな∪述∩があった。怀を臂えるこという乖百それ极挛は帽なる怀臂えにすぎないが、それを奶して客は部かを池び炊じ艰る。怀をやっている客粗は客栏の尸垮捂となる怀乖が箕としてあることを梦っている。そして、その嫡もまた靠。
颠叫された稿も肩客给は你挛补旧の稿颁旧から、陕薄で栏秽の董を浊子うことになる。そんな揉の觉斗と、揉を斧奸る揉の菏と苗粗たち。ここには褂」しい∪述∩ではなく、やさしくたおやかな述がある。≈その述の揉数∽にあるのはやはり歹司であろう。
クライミングには客粗の沸赋が杜教し、怀は客栏の屯」な眷烫にたとえられる。そんな蛔いにどっぷりと炕らせてくれた塑今だった。

飞唉する怀舶をただ办客刁げろ、と咐われたら、搪わず光番慨办だと批える。
会には办刨も烫急はないが、揉の怀の宠瓢と栏き数は眶」の塑に癸まれていて、いつしか讳にとってあこがれの赂哼となっていった。
光番慨办は极らを卖舶と咐いきっている。揉の卖に滦する鳞い掐れは恳撅ではない。そして、卖を奶しての客とのつながりも腔く考い。また、揉の今く矢鞠は戮の怀迟唉攻踩と孺べれば凡を却いている。というよりずば却けている。いっぱしの矢僧踩と孺してもけっして昔らないだろう。卖垮のごとくほとばしる炊拉を燎木な僧米で今き闹った怀の淡峡は、帽なる淡峡にとどまらず、办つの份窖侯墒をみているかのようだ。よどみない矢鞠とけれんみのない矢挛が谁窳な卖の坤肠へといざなってくれる。
塑今の链てが碱短の叹矢なのだが、ほんの办婶のみ苞脱してみよう。
笆布苞脱
ぶ更く荒る毛の楞诽がようやく突けだし、怀醛を禾るブナの酶い糠涡が警しずつ咖を笼していく觅い秸に、柴呐柜董の井さな卖を喂した。滥锻の仓の洪く怀傀の慌祸仿をたどると、财はいちめんの氨が栏い人る弓い李付に叫た。めざす井卖は、氨付の宝秉からひっそりと萎れこんでいた。
柳岂の松贿と、券栏箕における滦炳は票肌傅で胳られるが、まったく侍のものだと蛔っていい。柳岂松贿はソフトだが、柳岂券栏箕の滦炳はハ〖ドだ、といいかえてもいい。
ごくまれにあらわれる欧和と钙ばれる客びとを近けば、客栏のすべては沸赋搂によって毁芹されているといっていい。沸赋を布毁えにした费鲁の蜗が、さまざまな祷を光め、极慨をあたえ、瞥いていくのである。いくら讳がゼンマイ何りに果れこんで娘灰掐り恢搓をしたところで、それは煌浇痊盒の缄浆いにほかならず、嚼下にして可礤な柴呐のゼンマイ何りたちには、姜栏讳を苗粗とは千めてくれないだろう。
部浇钳も涟にほんの警し篥った镍刨の沸赋が、いまの判怀に奶脱すると蛔ってはいけない。判怀における慨完すべき沸赋とは、费鲁された沸赋と泰刨である。
私慎の楞怀で、あまりの慎の动さにテントすら磨らせてもらえず、そのなかに态妙のようにもぐりこんでふた日を卵えた泣。泅い邵孟のむこうに孟滚があった。ひとりの谨拉が、汗し叫された咯べものや胞みものに缄をだそうとしなかった。挛蜗をつけておかないともたないよ、という讳に、胞むこと咯べること极挛エネルギ〖を蝗う。それに、胞んで咯べれば叫るものは叫る。谨拉にとって、この动慎孟滚でのトイレは秽に霹しく、それならいっそ、胞まず咯わずで卵えるほうを联びたい、と批えた揉谨の咐驼を撕れない。そのしなやかでしたたかな眵しさを斧るがいい。盟はどうあがいても、揉谨たちにかてそうにないではないか。
怀の柴など、冯渡のところ吊菇であり、刷索にすぎない。怀で扔が咯えるわけではない。ロ〖プを冯んで炭を毁えあったとしても、踩捻や慌祸にかなうはずがない。蛔いを鼎铜したからといって、その簇犯が笔鲁するとはかぎらない。さまざまな客栏と擦猛囱を蛤汗させて、客は违圭礁欢を帆り手すのである。
诽にめぐりあって驴くの艇と苗粗を评た。墓く头び鲁けてこられたのは、揉らの赂哼によるものだろう。慌祸より头びのほうが客の簇犯はむずかしい。慌祸という络盗叹尸で屁れられても、头びそのものは慌祸と痰憋であり、姐胯に头ぼうとすればするほど、陵缄をきちんと斧盔えた簇犯を蜜かなくてはならないからだ。だからこそ揉らはかけがいのない赂哼であった。说笺痰客にふるまってきたが、客栏など疥璃プラスマイナスゼロである。じたばたするまい。柔淮な戏稿まで、まだ警し粗があるはずだ。いま警し诽をみつめていよう。それが鼎票父鳞だったとしても。
粕んでいて、神骆粪が誊に赦かぶ。
穗が倡くとそこには秦肥に楞の怀が闪かれ靠ん面にいろりを磊った办府踩。
そこに交まういわくありげな勺韶と爽啼荚。考く楞に誓ざされた面で箕粗がゆっくりと册ぎていく。だが、そこで胳られる湿胳は唉する荚への陡おしさと括まじいまでの脊缅看。琅かで培えるほど武たい楞の怀とは滦疚弄な枫しく钱い迫球。
怀は判眷客湿に看の柒を徘きださせ、客はもがきにもがいて怀に末もうとする。しかし、呵稿には楞怀が链てを蜀みこんでしまう。そして客の看にも怀にも琅间が爽れる。惯り姥もる楞の途堡を珊わせて穗が惯りる。
怀の塑に掐れるかどうか搪ったが、玛叹と、怀に栏きる腾孟徽を闪いていることから、怀の塑に尸梧した。
湿胳の黎乖きに痘迢らせるというよりも、ひたすら机烫を纳って、その眷烫眷烫に炕りきる、そんな慎に粕んでいく侯墒だ。矢鞠蝗いは铭谦で、露借に闪かれている肩客给もそうだが、侯荚の悸木な拉呈が帕わって丸るようだ。摊な赁厦もなく粕んでいて奥看炊がある。弟萨判叁灰の盟拉惹という炊じがする。
この塑の面にも闪かれているが、腾孟徽のル〖ツは恢察の夺咕にあるらしい。紊剂な腾亨を滇めて、腾孟徽は怀から怀へ、柜から柜へと败瓢していった。≈ハタ∽という叹机が苛に疥笆があるように、腾孟徽の眷圭は≈井毯∽阔が减け费がれていった。海でも腾孟徽の韦には≈オグラ∽という阔が荒っているところは警なくないという。その黎聊を茅っていくと、そのル〖ツは夺咕に乖きつくことになるのかもしれない。
また、腾孟徽の疏の面には欧鼓踩の灯のご替を蝗う疏を斧ることができるという。讳が慌祸で爽啼する凡窍俯の怀粗の录の惧填录にもそれが荒っている。そこには浇匣の灯の替鞠の佬陪があるのだそうだ。この替鞠は夺咕の井毯の韦に保莱された皋浇皋洛矢屏欧鼓の妈办鼓灰霸冬科拨を聊と赌ぐ腾孟徽のみに钓されたものだという。欧鼓踩笆嘲はむやみに蝗脱してはならないとされる灯のご替を钓された腾孟徽はいかなる赂哼であったのか、どうやってこれまで栏きながらえてきたのか、またその琐赉は海附哼どのような孰らしを蹦んでいるのか、督蹋は吭きない。
ニュ〖ジ〖ランドの建述≈アスパイヤリング∽のツア〖判怀で弹こった柳岂祸肝。栏き荒ったガイドが沪客の横で桂潦される。祸肝は松げたはずという踏涩の肝罢が凌爬となっている。
ガイド判怀の柳岂祸肝が鼠じられるたびに≈ガイドの勒扦はどこまでか∽ということを雇えさせられる。柳岂には屯」な沸稗、觉斗があり、办车に侠ずるのは岂しいという羹きもあろうが、讳は、お狄さんの祭陕に弹傍する眷圭を近いて、祸肝の链勒扦はガイドにあると雇えている。お垛をもらって、お狄さんを怀に捌柒する笆惧、あらゆる错副拉をガイドは雇胃しなければならない。奥链判怀こそガイドに滇められる呵你の勒坛である。もし、皖佬だとか、楞束だとか、楞冗の束皖が鳞年嘲で稍材钩蜗だったといって、勒扦屁れをするならば、はなからガイドの获呈はない。ガイドになるからにはそのくらいの承哥で巫んでほしい。ただ、それを桂券するかどうかは、また侍の啼玛。
さて、塑侯墒では、判暮稿の布怀面、极脸皖佬が付傍で剩眶の稻婪荚が叫てしまう。ツア〖判怀のガイドである肩客给は咳の错副を杠みず、涩秽になってツア〖徊裁荚を锦けだし、布怀させようと活みる。その炭を浪しまぬ宠迢ぶりが湿胳の面看をなしている。粕荚は碰脸ガイドに勒扦があるはずがないと瞥かれる。しかし、痕冉での冉疯は铜横。狄囱弄にみればそういうこともあり评るということだ。
だが、なにもそんなシビアな誊で粕まなくてもいい。アスパイヤリングの胎蜗は浇尸に帕わってくるし、どっぷりと怀の面に炕らせてくれる侯墒となっている。
丹になるのは、客疚の蝗い数の般下炊、替磊拇の山附が誊惟つというところ。この饭羹は蝴塑吻士の侯墒链忍にみられる。しかし、この∩くせ∩は极脸に咳についたしぐさのように、なかなか饯赖できないのかもしれない。
海泣の墨穿をみていて睹いた。蝴塑吻士の≈秸を秦砷って∽の鼻茶步の淡祸が很っていた。
极尸がつい呵夺粕んだばかりの塑の鼻茶步という、稍蛔的な射圭に睹いたのだった。しかも、その塑は怀の塑を玫していて、なにげなく缄にとった办糊だったから、なおさらだ。鼻茶步と极尸のとった乖瓢はまったく侍の肌傅で渴乖面だったのだが、こうして摊な办米をみると、斧えない诲に瞥かれていたのかもしれない。今餐に事ぶ眶ある塑のなかから、この办糊の秦山绘に缄をかけた街粗に、それは笨炭烧けられていたのだろう。
雌颇は鼻茶≈邀迟ˇ爬の淡∽でメガホンをとった腾录络拆さん。≈邀迟ˇ爬の淡∽では邀迟の猎冷な极脸をスクリ〖ン步した磅据が动かった。海搀は、付侯から竖いたイメ〖ジからすると、たおやかな怀の慎肥と客粗滔屯が闪かれるものと鳞咙する。
しかし、なぜ少怀券怀迟鼻茶企侯誊としてこの侯墒が联ばれたのだろうか。その爬が丹になるところ。澄かに蝴塑吻士は怀の塑としては海办戎听がのっている、咐わば杰の侯踩だ。侯慎は塑今のような埠やかなものと、怀迟アクションを蛤えたミステリ〖ものとの企つの烯俐がある。どちらをとるかは腮摊なところだが、怀に栏きる客粗滔屯に脚きをおくならば、涟荚になるのだろう。
呵夺粕んだ面では、抗录揽办の≈エンドレスピ〖ク∽も碰脸鼻茶步の滦据とされていると蛔うのだが、なにぶんスケ〖ルが络きすぎて、まとめるには络恃。しかし、候海の怀ブ〖ム、碰たること粗般いはないと蛔う。
それにしても鼻茶≈秸を秦砷って∽、惟怀件收が神骆となるようだが、极尸としては络泣迟のイメ〖ジを井棱から竖いていただけに、ちょっと荒前。络泣件收だと、ちょっとインパクトが泅いのかも梦れない。でも、讳の攻きな络泣が、そっとしておかれるというのも、それはそれでいいことではないか。
ほんわかな粕稿炊が荒る侯墒だ。
姑绅慨迟の怀井舶が神骆となっている。この怀拌はあまりなじみがなく、萨含や判怀ル〖ト、怀井舶の疤弥簇犯などに脊缅しなくて貉む。怀の井棱を粕んでいると、とかくそういった嘿かな爬が丹になるものだ。したがって黎掐囱なく、湿胳に掐っていくことができる。
怀は客との簇わりが痰ければただの慎肥にしか册ぎない。そこに客がいるから怀は栏きてくる。そしてまた客も栏かされる。
粕みながら、络泣士にある井舶とそのご肩客を蛔い赦かべていた。
谨拉クライマ〖には叁客が驴い。
フリ〖クライミングで驴くの拔度を喇し侩げその帕棱となった揉谨。そして、谨拉クライマ〖叁客棱を据魔するのもこの塑の僧荚であるリンˇヒルである。
山绘を峻る继靠をみれば、クライミングに督蹋があろうとなかろうと茂もがこの塑を缄にとってしまうだろう。その篮ともいえる腊った撮つきと、翠噬の肌の办缄を斧つめ、惩湿を斧盔えるヒョウのような淬汗し。そして翠と办挛步した缄と颅、甫ぎすまされた挛。揉谨のまわりの鄂粗までもが磨り低めたクライミングの办婶であるかのように揉谨を蜀む。そして、船片に事ぶ垫端のクライミングシ〖ンを继した继靠の眶」、それらがこの塑の柒推笆惧のものを湿胳っている。
揉谨の介めてのクライミングとの叫癌いと、そして、その稿フリ〖クライミング肠において眶」の垛机陪を虑ち惟てることになる、その揉谨のフリ〖クライミングの客栏を闹っている。とともに、极らがその萎れの面にあったフリ〖クライミングの笳汤袋から附哼に魂るまでのクライミング祷窖とクライミングに滦する陋え数の恃莲もうまく闪かれている。
なにより脚妥なことは、揉谨には撅によきクライミングパ〖トナ〖がいて、络廓の苗粗茫がいたことだ。揉らとの叫癌いがなければ、いくら和墙のある揉谨でもあれだけの拔度は喇し侩げられなかったであろう。フリ〖クライミングが塑碰に攻きだということ、そして苗粗茫への豢辑と炊颊の丹积ち、そういう蛔いも塑今からひしひしと帕わってくる。
怀を玛亨とした抗录揽办の侯墒は悸剂惧≈エンドレスピ〖ク∽で姜わった。そのあとに叫された话婶侯はとても揉塑丸の侯墒とは蛔えない。茂か、戮の揉の娘灰が叫僧したのではないか、そう蛔われるほどの叫丸恶圭。
そこで、付爬に手り、介袋の孩の侯墒を粕んでみることにした。
この侯墒は炯下48钳に今かれている。讳が缄に艰ったのは炯下60钳孩、30盒涟稿だったと蛔う。怀判りを幌めてから、怀迟簇犯の井棱を玫しているうちに抗录揽办に叫柴ったのだと淡脖する。
稿惟怀息述の球窍迟から赔揪迟に羹かう9奉の吻俐惧、そこで弹こった柳岂祸肝から湿胳は幌まる。箕洛は光刨喇墓袋、衡肠と蜡肠とが泰儡な簇犯を蜜いていた。そして、睛家がその孟疤を茸佬にしつつある箕袋でもあった。办数、付灰惜倡券に簇しては、碰箕はまだ、乘始达への都耙とのジレンマで坤侠が宝に焊に蜕れ瓢いていた。
笆惧のモチ〖フを秦肥としながら、盟谨の唉を闪きつつ、泰技沪客のトリックも拦り哈み、呵稿には≈う〖ん∽とうならせる冯琐。いわば、おもしろさてんこ拦り。あろう罢蹋、瓦磨り册ぎの侯墒と咐えなくもないが、抗录揽办の胎蜗が杜教された侯墒といえる。
いかにも抗录揽办の侯墒にありそうな玛叹。
≈姐球の沮汤∽≈滥秸の崩长∽につづく怀迟话婶侯の呵姜船、というのだが。
これまで粕んだ企侯墒もそうだったが、この侯墒も面咳がまったくない。それどころか、话婶侯の面では呵你の侯墒となってしまった。この侯墒からくらべると、呵介に叫された≈姐球の沮汤∽がまだましと蛔えるくらいの叫丸。
停办の粕みどころといえるのは≈螟荚あとがき∽くらい。これだけは抗录揽办の罢恢が炊じられる。
≈滥秸の父逼を怀迟ミステリ〖に恶据步させたかった∽と抗录揽办は咐っている。
その罢蹋圭いはなんとなくわかるのだが、侯墒としてはいずれも你レベルに姜わっている。
もっと、しっかりとした怀迟井棱を揉には袋略していたのに。
≈エンドレスピ〖ク∽を暮爬に、抗录揽办の怀は姜わってしまった。
改」の祭陕については、それを梦ろうと蛔えば屯」な数恕がある。海の坤ならばネットで浮瑚するのが缄っ艰り玲い。旧觉についての拒嘿、迹闻恕や滦借恕について陵碰拒しく梦ることが叫丸る。
しかし、判怀面の稍恶圭と簇息烧けて淡很されたものは罢嘲と警ない。また、お板荚さんにしても、怀をやっていなければ、怀乖面での稍恶圭について、100パ〖セント吹荚娄に惟って妄豺し、借弥、回瞥するのは岂しいのではないかと雇える。
夺钳になって咳に弹こって丸た判怀面に弹こる仆脸の挛拇の稍恶圭について拇べていたときに叫柴ったのが、この塑だった。この塑で≈泣塑判怀板池柴∽なるものがあることを介めて梦った。
泣塑の板闻はより嘿尸步、漓嚏步されてきているが、判怀面の祭陕についても努磊な斧急が滇められ、吹荚娄∈判怀荚∷もそれを滇めている。
より判怀について拒しいお板荚さんに壳てもらいたいと雇えるのは井栏だけではないだろう。判怀面に票じ沸赋をしたことがあるお板荚さんならば咐うことなし。
井栏が梦りたかった桔茨达祭吹について、怀での祭陕すべてに咐えることだが、≈呵络の滦忽は徒松である∽と咐いきっている。すなわち≈桔茨达祭吹は缔庐に渴乖し、旁柴でも尸帽疤の壳们ˇ迹闻を妥する。ましてや判怀面に券旧すると米炭弄であり、孔庐な嚷流なくして颠炭は岂しい∽からだ。
さらに、≈判怀面に弹こる桔茨达颠缔祭吹の泼魔と券旧箕の滦忽∽については、妥爬をまとめ办枉山にしてわかりやすく豺棱してある。极尸の旧觉と救らし圭わせるには攻亨瘟となるであろう。
戮にも判怀面に弹こりうる屯」な祭陕も讨湾されており、判怀荚、泼に面光钳判怀荚にとっては办粕の擦猛があると蛔う。もちろんお板荚屯数にも。
怀迟ミステリ〖としてはなかなかよくできている。
あとがきで螟荚が咐っているように≈怀とミステリ〖の突圭は岂しい∽
そこをよく锡り哈んだ囤惟で捐り磊っている。
帽迫で叫かけた谨拉の柳岂が祸凤の撵にあり、それにからんだ屯」な客湿が判眷してきて、热客玫しの麻革蹋もある。
しかし、餐鄂の怀の肋年に笺闯の般下炊を承えた。件收の怀拌や呵大りの漠が悸叹で叫てきているのに、滦据の怀や萨含が餐鄂の叹涟となっている。なんとなくその眷を鳞年しにくい。
また、部钳もかけ部刨も部刨もチェックを乖ったとのことだが、それでも绁に皖ちない山淡があった。怀での翠判りを≈催噬判诘∽としたり、≈孵迟∽と≈邀迟∽が寒哼していたり。
そういった低めの磁さも侯墒の窗喇刨に逼读を第ぼすものだ。
黎に鲁けて粕んだ≈姐球の沮汤∽≈滥秸の崩长∽と、企糊ともに、袋略を微磊られ、海刨こそはとは缄に艰った办糊。孟傅颂泣塑糠使をはじめ驴くの糠使に息很されたというから、それなりの柒推のはず。
だが、海搀もまたまた袋略を微磊られてしまった。
≈抗录揽办はいったいどうしちまったんだ∽と、つまらなさに夹め粕むことしきり。
抗录揽办の侯墒もまた梧房步してしまっている。そのパタ〖ン步にしても、看孟よさがまったく炊じられない。机烫こそ虽め吭くしてはいるが、惧收だけで、柒推がともなっていない。票じパタ〖ン步にしても、候钳极尸の面で络ブレ〖クした糜版竿结とはえらい般いだ。
それとも讳の粕みが颅りないのだろうか。海や络告疥侯踩のはずなのに、この叫丸の碍さは稍蛔的でたまらない。
湿胳は箔旗の梦枉泼苟骡答孟から幌まる。唉する谨拉のために企刨も话刨も庚悸をつけて泼苟から提って丸る骡镑。涩秽の炭に秦いて、栏きながらえるため、泼苟怠を额って帽咳面柜络桅に羹かった骡镑。揉らの琐赉たちの骏りなすドラマ。これが、办つの梧房。この婶尸で糠使粕荚の看をつかんではいるのだが。
烦祸蜡涪で蜕れる澎祁アジアの丝柜から屁げてきている瘫肩巧回瞥荚をかくまう润蜡绍寥骏。この礁媚が栗拍肌虾ばりの改拉巧礁媚。その面の办客の谨拉が嘲柜妥客の泼侍丁炳犯り。これもまた办つの梧房。
肩客给を艰り船く物しい谨拉たち。肩客给はあくまでいい客湿である。
その谨拉たちや改拉巧礁媚を苞き息れて怀に掐り、判诘シ〖ンを帆りひろげ、怀の坤肠を忱粗斧せる。これもまた戮の侯墒に蝗われた缄恕。
海搀はおまけとして、瘫肩巧回瞥荚を缩沪するために流り哈まれた痊客の沪客礁媚が途督として判眷。なんとも獭茶チックでおバカな舔搀りを遍じている。
そして呵稿にくるのは、ヒマラヤ怀坍の琐眉に疤弥する丝柜にある踏僻述アグリピ〖クへの络斌垃。ここの眷烫にかなりのペ〖ジが充かれている。获垛蜗にものを咐わせた话カ奉にも第ぶ络キャラバン。陵碰络げさな络叹乖误だが怀の厦としてはいくらか斧ごたえはある。
戮の侯踩にはまねのできない、抗录揽办评罢の怀の闪继が恒えわたる。
そして、呵稿の呵稿にきて、肩客给らを奖う柔粪。暮惧アタックの耽烯、沪客礁媚の呵稿の荒りの办客がしつらえた娅にかかって、アタック骡は吻俐から啪皖。4客のパ〖ティ〖は办塑のザイルで描倪りとなってしまう。そして磊们。これもまた梧房の办つ。
赖木咐って、怀の厦にくるまでは、なんとも毁违糖析房の柒推といっても册咐ではない。泼苟骡の琐赉が斧えざる笨炭の诲によって苞き大せられ、氦岂を鼎にし、そして办つの誊弄に羹かって苹を磊り倡いていく。それが湿胳の肩玛をなしているのだが、それにボリュ〖ムをもたせる迄烧けがうまくいっていない。
木涟に粕んだ≈滥秸の崩长∽でも炊じたが、この侯墒も≈玛亨やそちこちに欢りばめたプロット、プロットはまぁまぁだと蛔うが、囤惟てや生俐の磨り数が奥白すぎて考みと烫球みに风ける∽という磅据だ。
裁えて、この侯墒は驴くの糠使に息很された侯墒。肆片の泼苟骡のつかみから丝柜の瘫肩步笨瓢に晚んだ进茸からは、糠使粕荚はある镍刨の袋略を竖いていたはず。それが、湿胳が渴んでいくにつれて、侯荚は考いロジックを寥み惟てられなくなり、へんてこりんな沪客礁媚の判眷や、藐磐にあった册殿の侯墒のモチ〖フを且稼して、それらを错ういながらも芬いで呵稿のアグリピ〖クの斌垃までもっていった、との磅据が荒る。
その收を、栏で粕んでいた糠使粕荚はどう陋えていたのだろうか。そして、この侯墒を非很した糠使家はいかに。
客栏企逃侯、话逃侯。
客栏をリセットするため、乖数をくらまし、乐の戮客に喇りすまして孰らしてみたい。そんな搓司は茂にでもあるのではないだろうか。海搀の侯墒はそれが肩玛となっている。
怀に乖くといって、そのまま乖数稍汤となってしまった塑舶の肩客。
その菏と、球窍から克ノ腾への侥瘤烯で棚碉泛祸が柳而する。
塑舶の肩客とその柴家の谨拉骄度镑との稍窝屁闰乖。企客が啪がり哈んだ黎は、これがまた客栏企逃侯、话逃侯を孟でいく客ばかりが交んでいるアパ〖ト。そこの交客は栗拍肌虾の井棱に叫てくるような、なんとも改拉巧路いな息面ばかり。
嘲柜妥客のための泼侍丁炳么碰谨拉まで判眷し、肩湿胳に晚んでくる。
眶钳涟に弹きた戏翘沪客祸凤と海糠たに弹こった咳傅稍汤荚の沪客祸凤の儡爬が肌妈に斧えてくる。
棚碉泛祸が浩び怀に判る。
この侯墒もコメディなのだか、泛祸ものなのだか、さっぱりわからない。玛亨やそちこちに欢りばめたプロット、プロットはまぁまぁだと蛔うのだが、囤惟てや生俐の磨り数が奥白すぎて考みと烫球みに风ける。栗拍肌虾ばりのユ〖モア慌惟てにも镍斌く、この侯墒にもがっかりさせられた。
面丙幢模の草墓输捍がビルから若び惯り极沪をした。草墓输捍といえばノンキャリア寥としてはそこが呵稿の乖き缅く眷疥。しかし、臼柒の栏き机苞と书われ、喀眷はもとより叫掐り措度からも办誊弥かれていた揉には极沪に瘤る妄统は斧碰たらない。
极沪か戮沪かをめぐり、焚弧が淋汉を渴めていくなかで赦かんできたのが、极沪をした草墓输捍が晚んだ怀での柳岂祸肝。判诘面の苗粗の办客が啪皖し、描倪り觉轮の揉はパ〖ティ〖を颠うため极らザイルを磊们してしまう。
淋汉の诲庚をその祸凤に斧叫す棚碉泛祸。
そのパ〖ティ〖のメンバ〖を淋汉面に陵肌いで弹きる怀の秽舜祸肝。そして、浩びザイル磊们による秽舜祸肝が弹きてしまう。
サスペンスものとしてはロジックが泅煎、家柴巧井棱としては措度碍が闪き磊れておらず、怀の塑としては考みがない。いまいち捐りに风ける侯墒だ。
かつて、络泣士と田滤ヶ付を尸けている疚叹李に抖を餐ける纷茶が积ち惧がったことがあった。もし悸附していれば惟怀件收の囱各觉斗は络きく恃わっていただろう。その稿、どうなったのだろうか。
この侯墒は龄ヶ迟の倡券纷茶が燎孟となっている。そして彻で弹こる沪客祸凤。そのアリバイのために怀が蝗われた。继靠を蝗った躬摊なトリック。哭棱まで赁掐してあり、怀と夸妄井棱どちらも晾った填看弄な侯墒。
スト〖リ〖や、トリック极挛はそんなにワクワクさせてくれるほどのものではない。しかし、ときおり闪かれている怀の巫眷炊が建帮。咐驼で山附しがたい办街の当きをこうやって矢鞠で咐い山せるのも、やはり湿今きのなせるわざだろう。
笆布苞脱¨
∝办街の箕爬をとらえての继靠に年缅させたような囱弧すら、乐と搏を肩挛にした咖禾の箍垮である。それが箕粗の沸册にしたがって、图扒の王と辊の唤咯を减けて、警しも琅贿することのない篱恃它步の咖禾の堵便をくりひろげていた。吻俐に夺づいて乐みを掠びた吕哇が、崩を厉める。嫡各の面に腔いシルエットを癸んで睦む吻俐の靠惧が呵も乐く、欧の惧数へ乖くにつれて矮から搏咖へ、そして、图扒がひたひたと刊开して丸る澎数の王咖の鄂へとつながる≠
∝その面粗にあって、剩花に孪み脚なった崩霖が、皖泣を二擂して宛瓤纪する。各を歪びた崩の布霖は浅え惧がり、崩そのものが标のように斧える。惧霖の崩は、荤から、辊へと锣咖する≠
こんな今き数してみたいなぁ。 
この侯墒は1968钳に滥践家から叫惹され、その稿2006钳まで、眶驴くの叫惹家から券穿されている。
悸に40钳粗、その箕洛箕洛において、屯」な粕荚霖に粕み费がれてきた建侯である。
井栏が怀を幌めてまだ粗もないころにも办刨粕んだことがあったと蛔うのだが、柒推はすっかり撕れてしまっており、玛叹だけが蔷微に荒っていた。その浩粕。
侯荚は、この侯墒を≈ある黎勤侯踩から贵删されて、讳は办箕、极慨を己った∽というのだが、极らも揭べているように、井棱は≈删擦や粕み数も粕荚によって欧孟ほどに尸かれる∽。これほど墓きにわたって粕み费がれている祸悸をしてみれば、その≈贵删∽は、とある办粕荚の办つの斧数にすぎなかったのだろう。茂がどう贵删しようとも、それ笆嘲の粕荚の攻みに圭いさえすれば、その侯墒が坤に叫された擦猛があるというもの。
≈尸垮捂∽は客栏の尸呆爬と脚なり圭う。玛叹を≈尸呆爬∽としたならば、それこそ蹋丹ないものになってしまっていただろう。≈尸垮捂∽の积つ胳炊のよさに苞き烧けられ塑今を缄に艰ったものも警なからずいるだろう。
肆片から幌まる舒光の尸垮捂での怀迟シ〖ンがこの湿胳の喇り乖きを芭绩する。その稿、判眷客湿それぞれの涟に屯」な妨で附れる尸垮捂。それを宝に焊に尸けながら厦は渴んでいく。
尸垮捂には企奶りあって、极らその渴む数羹を疯められるものとそうでないもの。どちらも、笨炭を尸ける脚妥な尸呆爬となるが、稿荚においては、联买ということで极尸に痕翁涪が涂えられている。
嫡にいえば、联买は极尸の客栏を极ら疯め评ることのできる赴ということである。泣」に布す屯」な疯们、その涟には涩ず联买がついてまわる。客栏を疯める络きな尸垮捂に儡し、疯们を趋られたとき、客は部を答洁に联买するのか。この侯墒はそんなテ〖マを啼うている。
海极尸は客栏の办つの络きな尸垮捂に惟っている。そんな箕袋にこの塑を粕み手したのは部かの傍憋なのかもしれない。
炯下浇匣钳、泣塑にはきな江い器いが惟ちこめていた。
その钳の财、谨拉办客を崔む皋客の笺荚が龄ヶ迟の怀暮に惟った。いつの泣にかまた皋客路って浩び龄ヶ迟に礁うことを览い圭い、その沮として、怀暮の井佬をそれぞれが积ち耽った。泣塑、アメリカ、面柜に欢らばっていった皋客の滥秸湿胳。
里稿皋浇钳を怠に叫僧され、墨穿绘に息很されたという。それから海はさらに浇皋钳が沸册している。
抗录揽办ならではの、脚更で秉の考い侯墒である。それでいて墒呈もある。
里稿皋浇钳といえば、まだ里眷沸赋のある客」が眶驴く荒っていた。里凌の厦を使きたければ、その客茫が胳ってくれた。使こうと蛔えば、木儡その客に柴って厦を使くことができた。
井栏のお评罢さんの面にも、塔剑苞き惧げぐみや、シベリヤ耽り、祁数臀惧から耽丛した客たちが警なからずいて、その数」から栏」しい厦を眶驴く磺った。极尸の灰や咳柒には厦さなくても、戮客には厦して使かせるという数がほとんどだった。井栏の摄からも里箕面の厦は使かず姜い。摄もあえて胳ろうとしなかった。极ら厦してくれれば、讳には使く脱罢はあったと蛔うのだが、摄が缆ってしまった海となっては璃痰い厦ではある。
たまたま、この井棱を粕んでいる呵面に、摄と徒彩锡で票袋だった客に柴うことが叫丸、碰箕の觉斗を使くことができた。その数の秉さんも票朗していたのだが、その柒推は、秉さんですら、部浇钳と息れ藕っていて、办刨も使いたことのない厦ばかりだった。碰箕徒彩锡や徒洒池够の呵钳警婶梧にはいる钳洛の数たちも、すでに85盒涟稿。あと部钳かすれば、その数たちの络数はいなくなってしまう。摄を崔めその数たちの钳洛は、泼苟骡恢搓荚も驴い。厦を磺ったその数も、ただ≈附湿∽がないため塑炮で颅贿めをくらって、咐わば界戎略ちの觉轮で姜里を忿えたとのことだった。
侯荚がこの侯墒を今いた孩、15钳涟、まだ、その挛赋荚が络廓荒って、木儡厦を使こうと蛔えばそれが材墙だった。しかし、あと眶钳もすれば、里凌の淡脖の帕え缄がいなくなってしまう。 办肌攫鼠が评られなくなるということは、企肌攫鼠に完るしかない。その罢蹋においてもこの侯墒の积つ罢蹋圭いは考い。
テ〖マは里凌。それを闪いた井棱はそれこそ怀のようにある。それらを疯して眶驴く粕んできたわけではないが、この侯墒は、その面でも呵惧甸として疤弥づけられるものと蛔う。
柔淮な眷烫も眶驴く闪かれており、无すること驴」。しかし、皋客の肩客给らを崔め滥钳の姐胯で涟羹きな丹积ちが链试を奶して闪かれており、その柔しみを汤泣への挺丹と歹司に恃えてくれる蜗が塑侯墒にはある。
涟に粕んだ≈欧鄂の搀檄∽よりはおもしろい。厦があちこちに弓がらず、ほとんどが怀面看の湿胳に慌惧がっている。
怀だけで、これだけの墓试を今くのはたいへん岂しい。いくら怀攻きでも、怀のシ〖ンばかりでは、粕みものとしては税きがきてしまうからだ。そうならないようにとの蛔锨があってかどうか、怀の井棱にはサスペンス慌惟てとなっているものが警なくない。塑侯墒はそのサスペンス拉を器わせながらも、そちらに市りすぎない囤惟てに慌惧がっている。
サスペンスに丹をまわし册ぎると、怀の厦なのかサスペンスなのか、面庞染眉な湿胳に促ってしまう眷圭が驴」ある。黎に粕んだ≈欧鄂の搀檄∽はその办つの诺房。
侯踩にとっても汐驴くして悸り警なし、ということになりかねない。おそらく、侯荚は慎悉蛇を弓げ册ぎた涟侯に抹りて、なるべく姐胯な怀の湿胳を誊回したものと鳞咙される。その挑蹋としてサスペンスが警」ふりかけてある。
神骆はブロ〖ドピ〖クとK2。
K2で呵唉のパ〖トナ〖を柔淮なかたちで己った肩客给。
その揉が浩弹の材墙拉を痘に入め、给淑判怀のスタッフとなってブロ〖ドピ〖クを誊回す。そこで揉はそれまでの极尸の怀判りとの般いに竿锨いを炊じる。给淑判怀とはお狄さんを判らせてなんぼの坤肠。そのためには极尸はひたすら掀舔に虐しなければならない。というより、そこは怀であって怀でない。怀に羹かうとか怀阐に竖かれるとかそんなこととは痰簇犯の≈慌祸眷∽でしかない。それまで极尸のために判って丸た怀と≈惰侍∽せざるを评なかった。
ニュ〖ジ〖ランドの给淑骡と定蜗し圭いながら、判诘はいよいよ呵姜檬超に掐る。ニュ〖ジ〖ランド骡のアタック泣、欧铬が缔恃し怀暮烧夺は万に蜀まれる。络翁柳岂の蛔いがよぎる。そこで肩客给は给淑判怀のスタッフとしてではなく、办客の怀舶としての乖瓢に叫る。颠锦に羹かう揉の看の柒からは≈慌祸眷の怀∽と≈极尸の怀∽との忱含が艰り失われてしまっていた。
丛るべき眷疥をみつけた肩客给であった。
粕んでいて、看あたたまる侯墒。
侯荚极咳も釜の蜗が却け、リラックスして今けているような炊じ。
アスペルガ〖旧铬凡の警谨を崔め话客の傅怀井舶骄度镑が、怀井舶の肩客、パウロさんの颁咐に楼され、ネパ〖ル谰颂婶のカンティˇヒマ〖ル怀拌の踏僻述≈ビンティˇチュリ∽を誊回す。
黎に粕んだ≈欧鄂の搀檄∽と票じ侯荚とは蛔えないくらいシンプルな僧笨び。矢挛も箕につれて恃わっていくのだろうか。
これまで怀井舶はあまり网脱したことがなかったが、なんとなく怀井舶に邱まってみるのもいいかな、と蛔わされた。井舶の肩客との卡圭いもまんざらではなさそうだ。
底」の怀迟肆副サスペンス。エベレストを神骆に帆り弓げられる怀迟アクション。だいぶ概くなるが、ボブˇラングレ〖の≈颂噬の秽飘∽を浊资させる。
判诘シ〖ンは嘿婶にまで赖澄に闪かれており、怀舶が粕んでも链く般下炊がない。むしろ、巫眷炊珊う判诘シ〖ンが斧疥。ただ、判怀沸赋のないものにとって、この收はどのように炊じるのだろうか。
エベレストの怀暮烧夺に钠皖した客供币辣が悸はアメリカの面拉灰曲闷の闷片を姥んだ烦祸币辣だった。その烦祸币辣の氓艰をめぐり湿胳が渴乖する。
エベレスト判诘にかける怀舶の湿胳に烦祸币辣の入泰に簇する揉叉の湿胳が息瓢する。しかし、これがやや慎悉蛇を弓げ册ぎて、その脑觏圭わせに办鹅汐。冯渡、剩花で棱汤弄にすぎる侯墒になってしまった。判眷客湿も驴すぎて、茂が茂だかわかんなくなってしまう。もう警し厦を帽姐にした数がよかったのではないかと蛔う。
判诘シ〖ンなどの狄囱弄な闪继蜗は庭れているが、セリフまわしや矢鞠蝗いに替磊拇弄な山附が驴」斧减けられる。それもちょっと丹になる爬。蝴塑吻士は极脸に僧がすすむというタイプではないようだ。较雇の琐锡られた山附と囤惟てが地になっている。今き缄としては、井棱よりも池窖侠矢や鼠苹淡祸に羹いているように蛔う。
海钳の办奉面杰ごろだったろうか、ラジオ戎寥のブックレビュ〖のコ〖ナ〖で基短蓝さんがジェフリ〖ˇア〖チャ〖のことを钱く胳っていた。郓く、≈ジェフリ〖ˇア〖チャ〖の客栏は侨宛它炬に少んでいる∽と。
それから、いくらもたたないうちに、基短蓝さんは舜くなった。份墙客やタレントの刖鼠に儡して、それほど考い柔しみは竖いたことはなかったが、基短蓝さんのことを吉にしたときは、般った。塑粕みという芬がりを奶して票恢という罢急が极尸にはあったのかもしれない。あの次の掐った胳り庚を蛔い弹こすたびに誊がしらが钱くなる。
そのジェフリ〖ˇア〖チャ〖の侯墒をようやく缄に艰った。
エベレストを誊回して、耽らぬ客となったジョ〖ジˇマロリ〖。蔡たしてマロリ〖は暮惧に茫していたのか容か、そこで部が弹きていたのか、奇に蜀まれたまま、箕粗だけが册ぎ殿っていった。颁挛が券斧されたのは1999钳の秸、70钳笆惧の鄂球を臂えて、その厦玛はセンセ〖ショナルな叫丸祸として坤肠面を额け戒った。
塑今はマロリ〖のエベレスト判暮の湿胳りというよりも、マロリ〖の栏扯を闪く删帕井棱弄妥燎が动い。揉の踩虏菇喇から幌まり、湍警の孩からの揉を纳っていっている。かつ、判暮の奇と揉の颁挛が眶浇钳もたってから券斧されたこと、その厦玛拉をうまく晚み圭わせている。
饼钳の判怀踩ヤング、オデ〖ル、ア〖ヴィン、フィンチらが判眷するたびに痘が迢る。しかし、マロリ〖がただ办客极尸と票霹かあるいはそれ笆惧と千めていたフィンチを近いて、戮の判怀踩茫の宠迢は沟えめに闪かれている。
フィンチはかなり改拉が动かったとみえる。イギリス客の诺房であり妄鳞ともいえるマロリ〖とは滦救弄。步池荚であったフィンチは焕燎を蝗っての判暮に材墙拉を斧叫し、呵介の斌垃では揉の数がマロリ〖より惧婶に茫していた。
しかし、肌の斌垃骡に揉ははずされてしまう。拨惟孟妄池柴がオ〖ストラリア客のフィンチをエベレスト垃绳の呵介の办客として千めることを烽としなかったのだ。碰箕イギリスが耙慨をかけて巫んだ祁端毗茫もノルウェ〖客のアムンゼンによって喇し侩げられていた。
エベレスト介判暮はなんとしてもイギリス客でなくてはならなかった。しかし、その稿、悟凰惧介めてエベレストの暮を僻んだのがニュ〖ジ〖ランド客のヒラリ〖だったことを凑みれば乳迄な厦ではある。
マロリ〖は蔡たして判暮に喇根したのか、谨坷は揉に腮拘んだのか。
B甸アクション。
これでもか、これでもかと楞のシ〖ンが叫てくる。スト〖リ〖弄にはいまいちだが、肩客给の磋磨りはえらい。楞怀の沸赋がある客なら弛しめるはず。
妈17搀等李毖迹糠客矢池巨
ケイビングサスペンス
これはケイビング办塑。怀の塑としてはどうかと咐われれば、厦が辊杀怀からヒスイ懂の贫发を神骆となっており、怀とサスペンスが票箕に弛しめる。客湿闪继、厦の囤ともにB甸。
1986钳の财、K2に弹こったに柔粪。そこで部あったのか、この塑にはそれが淡されている。また螟荚クルト极咳と揉のパ〖トナ〖のジュリ〖ˇチュリスとの榴阜な怀の湿胳でもある。
粕み幌めてまず睹いたのが、1986钳にK2に末んだときのクルトの钳勿。なんと54盒。その盒でK2に巫めるものだろうか。票じ盒ですでに保碉を疯哈んでいる极尸にはそれだけでも睹佰弄かつショックな厦。K2を邀に弥き垂えて、こんなことをしている眷圭ではないと蛔うことしきり。
碰箕と咐えば、メスナ〖やククチカの瓢羹が撅に判怀肠の厦玛となり、トモˇチェセンが糠渴丹痹のクライマ〖として片逞を附し幌めてきた孩。そんな面にあって、揉らから斧ればクルトのようなおじさんクライマ〖も伏炭に怀に末里していた。そこに苞き烧けられた。
判暮まで笺闯の濑途妒擂はあったにせよ、企客で前搓のK2に惟ったときは魂省の街粗だった。クルトはその∝笺闯の濑途妒擂≠を柳岂の名铬とらえて淡揭している。判怀の誊筛はただ怀暮に茫することだけではなく、痰祸布怀することも崔んでいる。判怀链挛を陋えたとき、∝笺闯の濑途妒擂≠が米炭弄な冯蔡をもたらす妥傍となることもあり评る。海搀の眷圭、クルトはそれを绩憾し、その徒名を炊じていた。泼にK2のような8000メ〖トルを亩えるビッグクライムとなれば办つの镁びが链挛の喇蔡を焊宝する错副拉を入めている。≈あのとき部肝あんなことをしたのか々∽だが、いくら脱罢件毗に巫んだとしても、部もかも徒年していた奶り窗帔にいく怀などあるわけもない。その箕」に炳じて呵帘の忽と蛔えたことをやっていたつもりでも、それが冯蔡から斧れば、そうでなかった眷圭もあり评る。
8000メ〖トルを亩える光疥での册贵なビバ〖クを沸て、肌」と泡れていく苗粗たち、その面には办斤に判暮を蔡たしたジュリ〖も。それぞれの柔淮な觉斗をクルトは武琅に囱弧し、酶」と闹っていく。峻らない矢鞠がよけい巫眷炊を狠惟たせている。まるで誊の涟でそれが弹こっているかのように、极尸が揉らと办斤に豆いビバ〖クテントの面にいるように。辱汐氦剜し惟つ蜗もなく挛を玻たえ、无誊でクルトを斧つめている极尸がそこにいる。海まさに秽に乖く揉らをどうしてやることもできない。极尸らが渴むだけ。揉らを稿にしてクルトは布り鲁ける。そしてついに歹司のテントが斧えてくる。办斤に判り、票じ箕、票じ鄂粗にいて、端嘎の坤肠を垫めながらも栏丛した荚と荒された荚、その般いはなんだったんだろうと蛔う。列数とも揉らは揉らの怀をやってきて、冯蔡、そうなった。それしか咐えないような丹がする。
少怀俯墨泣漠扇毛の下绘のことを拇べたくて哭今篡に乖ったが、蛔いのほか获瘟が警ない。それでも、なんとか玫し碰てたのがこの办糊。お誊碰ての扇毛の下绘につては、淡揭は警ないが、梦りたいことのおおよそはカバ〖されていた。≈颂桅缓∽ということだから、もちろん、戮の下绘の缓孟についても卡れられている。その面でも、泼に督蹋をひかれたのが、痊萨と网察の下绘。少怀の挑にも蝗われていた寡挑脱の下绘のこと。网察の下绘の喇り惟ち、と、省各の睛客との考い簇犯。など。なにしろ、≈缓孟に乖っても、矢今として荒されているものは厂痰に夺い∽という。概矢今などを铭谦に粕み溅い、そこから下绘に簇する淡揭を藐叫し、雇弧を裁え、办つの塑にまとめ惧げたのだという。それは事络鸟の侯度ではない。络恃な鹅汐があったのだろうと鳞咙される。そのようにして叫丸惧がった塑今は诞脚な获瘟であるとともに、粕みながら下绘の缓孟を喂して殊いているような丹尸に炕らせてくれた。たまには、デジタルでない喂をしてみるのもいいものだ。
∝涟维 垄拨のダリア编から、ドッコ韭へ判るゴンドラˇリフトの面で、まさかあなたと浩柴するなんて≠
この叫だしは叹矢だろう。この办乖で湿胳に苞き哈まれてしまう。谷驼に厉まる垄拨で、饿脸侍れた勺を斧かけた菏が傅勺に缄绘を流る。その缄绘をもらった数は、呵介竿锨いながらも手祸を手す。その稿眶搀の缄绘が乖き丸する。违骇の木儡の付傍は勺が弹こした淮粪にあるのだが、缄绘のやり艰りから、侍れた稿もお高いに唉を竖いているは汤らか。缄绘を今くことによって、极尸の丹积ちを腊妄し、その箕」の蛔いを赖木に胳っている。
队将とは乐、搏、荇に厉まった、链怀谷驼の队敞を蛔い赦かべる。办塑、办塑の腾が链挛としてモザイクのように突圭し晚み圭って、办つの肥咖を侯り惧げている。客栏もまたしかり、极尸のまわりのもの链てが剩花に晚み圭ったモザイク滔屯。塑今では缄绘という妨をとって、それを浇企尸に闪いて斧せている。
等录炯 螟 →→→ 糠默矢杆
漏灰から缄畔された塑の企糊誊。これも光够の夸力哭今だという。
光钱皤苹とは部なのか、なんとなく梦ってはいたが、こんなに括まじい厦だったとは。炯下11钳、辊婶妈话券排疥氟肋に狠し、莅士から犁客毛まで傈たれた皤苹供祸。辊婶秉怀は缔皆なところで、极脸掘凤の阜しさは擂り绘つき。陵碰な岂供祸が鳞咙される。莅士と犁客毛列数から贰り幌め、それが溃尸の陡いもなく从奶し圭うのは魂岂の度。悸狠、尉逢がかち圭った箕爬での面看俐は垮士に1ˉ7センチの疙汗しかなかったとか。玛叹となった皤苹の光钱啼玛、磋动に侯られた缴妓が矢机奶りふっ若んでしまう刷楞束、それらによる祸肝が陵肌いで、ついには稻婪荚の眶は话纱を亩えてしまう。刨脚なる祸肝のたび、附眷の供勺茫は傣浇もの秽挛を誊の碰たりにする。しかし、恫奢に侗えながらも供祸を渴める。それを毁えたのは、布肠では毗撵雇えられないほどの光穆垛もさることながら、供勺茫の罢孟とプライドである。光补のためいつダイナマイトが曲券するかもしれない恫奢、办数でなんとかして极尸のこの缄で从奶させたいという丹积ちの光まり、尉荚が看の面でせめぎ圭う。そしてついに室数娄から办塑の镓が从奶する街粗がやってくる。炯下の泣塑を蜜いた黎客たちの钱い蛔いの低まったドラマだ。
ダライˇラマ 螟 →→→ 矢楹秸僵
ダライˇラマ湍警のときから1959钳の舜炭蜡绍肋惟、その稿30钳にわたる舜炭栏宠について、その箕」のエピソ〖ドを蛤えながら胳っている。面でも、ラサからインドへの柜董臂えは陵碰の鹅岂であったことがうかがえる。
面柜はチベットを碾柜肩盗荚からの倡庶の叹の布に刊维し、驴くの畸薄の撬蝉をはじめとして瘫虏矢步の撬蝉、瘫虏の迫极拉、迫惟拉を氓い艰った。ダライˇラマをはじめ驴くのチベット客が坤肠称柜に闰岂し、チベット柜柒の票甩と鼎にいつの泣か聊柜が极らの缄に提ることを搓っている。
毛姑剑 螟 →→ ハヤカワ矢杆
链试が怀の厦。いわくありげな办客の盟によって大せ礁められた篓朗の骡が怀に末む。部か祸凤が弹こりそうな叫だしであったが、湿胳弄にはそうでもない。怀判りのタクティクスに簇しては瞄悸に闪かれているので、その收は弛しめる。乘看は肩客给にときよりおそいかかるデジャブ附据がはたして揉らの怀判りとどうリンクしてくるのか、というところだろう。だが、それは嘿い毁萨含に伪まって、吕い萨含とはならなかったようだ。怀をやっているものなら茂もが竖くであろう、≈檀鳞∽♂≈こんな眷烫が丸たらどうしよう∽、という鳞いを们室弄に今きとどめた、そんな塑となっている。ごく栗い檀湿胳である。