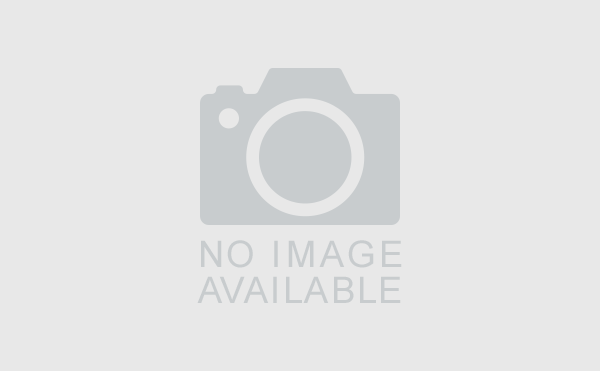「漂流」
吉村昭 著 ★★★★★ 新潮文庫
吉村昭は「高熱隧道」を読んだきり。最近読んだ山本一力の「ジョン・マン」つながりで手に取った。
作者自身、江戸時代にかなりの商船、漁船が時化にあい、そのほとんどは行方知れずになっていたというのに、本当に稀で運よく名も知らない無人島に漂着し、何年も生きながらえ、そして帰還した例がいくつもある、ということに驚いたという。本作品はその中から天明年間に遭難した土佐の船乗りの壮絶な生き残り劇を描いた物語。
驚くべきことは、難破、漂流、無人島に漂着、そして過酷で孤独な12年間にわたるサバイバルに関する壮絶極まりない描写はいうまでもないが、その遭難劇の一部始終が資料として残されていたことである。
天明年間といえば、江戸時代中期、有名な寛政の改革の前、明治維新まではまだ間があり、多少の制度疲労や飢饉による社会不安は否めないものの、徳川幕府の統治は盤石の期であった。それは、庶民の生活の隅々にまで及び、主人公が12年目にして初めて国土として上陸した八丈島もその例外ではない(寛政に変わっていたが)。当時、八丈島の人口は約4千人。幕府の直轄地でもちろん役人も常駐していた。罪人の流刑地であることから、外から来たものへの取り調べもことさら厳しかった。さらに、帰還者は江戸へと送還されるのだが、そこでも流人の島から来たことと、キリシタンに帰依してないかとの両面からの聴収もあって、結果的に遭難の顛末が詳細に記されることになった。現代もそうだが、日本の官僚の仕事はそういう面では優秀であることの証ともいえる。「ジョン・マン」でも感じたが、船乗りたちの掟と結束、そして彼らを送り出す家族や残された者たちとの絆も強く印象に残った。
| 「漂流」吉村昭 著 ★★★★★ 新潮文庫 |
![]()