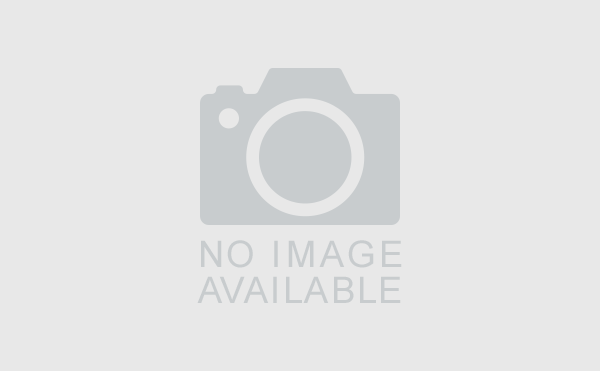「黒百合」
泉鏡花 著 ★★ 日本の文学 第四巻 中央公論社
泉鏡花を読むのは初めてだ。今が旬の富山が舞台の宮本輝の「潮音」に触発されて手に取った。いわく、泉鏡花にも富山が舞台の小説があるという。作品は明治32年(西暦1899年)に読売新聞に連載された。今から120年以上も前で、すでに版権は切れており、ネットを探せば、PDFで閲覧できるサイトもある。
この「黒百合」掲載の文学全集、本巻は三島由紀夫が編集委員で尾崎紅葉の「金色夜叉」、泉鏡花の出世作「高野聖」他二編も載っている。巻末には三島由紀夫自身による解説もある。
さて、本作品。昔の言葉遣いも手伝って、すぐには頭の中に入ってこない。舞台設定が凝りに凝っているし、登場人物の誰の所作やら言動やらが分かりにくい場面も多々ある。次第に先に打たれた布石が繋がり出すのだが。確かに富山の地名、総曲輪、新庄、桜木町、旅籠町等々出てきて親近感がわく。そして、題名となった「黒百合」、これは以下のごとく的確にうまく描写されている。
「その黒百合というのは帯紫暗緑色で、そうさ、ごくごく濃い紫に緑が交った、まあ黒いといっても可いのだろう。花は夏咲く、丈一尺ばかり、梢の処へ莟を持つのは他の百合も違いはない。花弁は六つだ、蕊も六つあって、黄色い粉の袋が附着いてる。私が聞いたのはそれだけなんだ。西洋の書物には無いそうで、日本にも珍らしかろう。書いたものには、ただ北国の高山で、人跡の到らない処に在るというんだから、昔はまあ、仙人か神様ばかり眺めるものだと思った位だろうよ。東京理科大学の標本室には、加賀の白山で取ったのと、信州の駒ヶ嶽と御嶽と、もう一色、北海道の札幌で見出したのと、四通り黒百合があるそうだ」
とあるのだが、富山の中心地と黒百合が咲いているという深山石滝がいくらも離れてないように書かれているのにはちょっと引っかかる。まぁ、劇のような作品と思えばそれもありかもしれない。
![]()