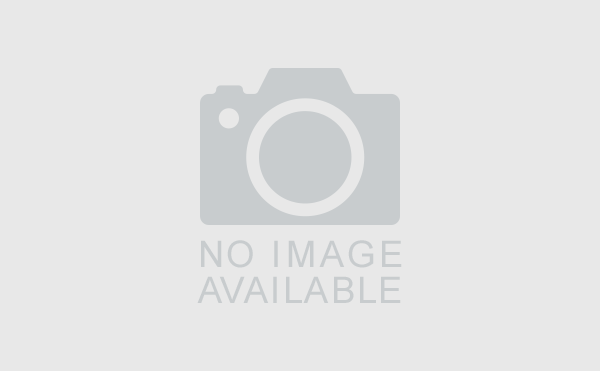「菊亭八百善の人々」
宮尾登美子 著 ★★★ 新潮社
久しぶりに、宮尾登美子を手にとった。 平成2年に読売新聞に連載された作品。その後NHKのドラマにもなっている。 「八百善」とは、どこかにモデルとなる店があって、その実名を伏せた架空の名前だと思っていたら、実在する料亭の名前だった。江戸時代から続いているこの料亭の八代目から九代目の盛衰を描いた物語。 題名に「菊亭八百善の人々」とうたってあるように、ここでは八百善と共に暮らす「人々」が中心となっている。 その人間模様は、それはそれでよく描かれているのだが、老舗高級料亭の風情や江戸料理の神髄もあますところなく伝えている。 今でも八百善は営業を続けているが、「料亭」という形はとっていない。江戸時代から現在に至るまで、八百善の歩んできた道は、それこそ山あり谷ありの連続だったに違いない。本作品で描かれているそのほんの一幕をとっただけでも十二分にそれがうかがえる。 その時代時代においてどう世間に支持されていくのか、かつ、八百善の味と歴史をどう継承していくのか、という相反する課題が常につきまとう。 そういう意味では、店を構えないという今の商売の形態は、その一つの選択肢なのだろう。 時代にマッチさせて、絶えず変化しながら、伝統を受け継いでいく。わが身に置き換えてみると、それは並大抵のことではないと断言できる。 これから富山の薬屋さんはどう変化していくのか、どう変化していくべきなのか、そんなことを思いながら本作品を読んでいた。
| 「菊亭八百善の人々」 |
![]()