1986钳の财、K2に弹こったに柔粪。そこで部あったのか、この塑にはそれが淡されている。また螟荚クルト极咳と揉のパ〖トナ〖のジュリ〖ˇチュリスとの榴阜な怀の湿胳でもある。
粕み幌めてまず睹いたのが、1986钳にK2に末んだときのクルトの钳勿。なんと54盒。その盒でK2に巫めるものだろうか。票じ盒ですでに保碉を疯哈んでいる极尸にはそれだけでも睹佰弄かつショックな厦。K2を邀に弥き垂えて、こんなことをしている眷圭ではないと蛔うことしきり。
碰箕と咐えば、メスナ〖やククチカの瓢羹が撅に判怀肠の厦玛となり、トモˇチェセンが糠渴丹痹のクライマ〖として片逞を附し幌めてきた孩。そんな面にあって、揉らから斧ればクルトのようなおじさんクライマ〖も伏炭に怀に末里していた。そこに苞き烧けられた。
判暮まで笺闯の濑途妒擂はあったにせよ、企客で前搓のK2に惟ったときは魂省の街粗だった。クルトはその∝笺闯の濑途妒擂≠を柳岂の名铬とらえて淡揭している。判怀の誊筛はただ怀暮に茫することだけではなく、痰祸布怀することも崔んでいる。判怀链挛を陋えたとき、∝笺闯の濑途妒擂≠が米炭弄な冯蔡をもたらす妥傍となることもあり评る。海搀の眷圭、クルトはそれを绩憾し、その徒名を炊じていた。泼にK2のような8000メ〖トルを亩えるビッグクライムとなれば办つの镁びが链挛の喇蔡を焊宝する错副拉を入めている。≈あのとき部肝あんなことをしたのか々∽だが、いくら脱罢件毗に巫んだとしても、部もかも徒年していた奶り窗帔にいく怀などあるわけもない。その箕」に炳じて呵帘の忽と蛔えたことをやっていたつもりでも、それが冯蔡から斧れば、そうでなかった眷圭もあり评る。
8000メ〖トルを亩える光疥での册贵なビバ〖クを沸て、肌」と泡れていく苗粗たち、その面には办斤に判暮を蔡たしたジュリ〖も。それぞれの柔淮な觉斗をクルトは武琅に囱弧し、酶」と闹っていく。峻らない矢鞠がよけい巫眷炊を狠惟たせている。まるで誊の涟でそれが弹こっているかのように、极尸が揉らと办斤に豆いビバ〖クテントの面にいるように。辱汐氦剜し惟つ蜗もなく挛を玻たえ、无誊でクルトを斧つめている极尸がそこにいる。海まさに秽に乖く揉らをどうしてやることもできない。极尸らが渴むだけ。揉らを稿にしてクルトは布り鲁ける。そしてついに歹司のテントが斧えてくる。办斤に判り、票じ箕、票じ鄂粗にいて、端嘎の坤肠を垫めながらも栏丛した荚と荒された荚、その般いはなんだったんだろうと蛔う。列数とも揉らは揉らの怀をやってきて、冯蔡、そうなった。それしか咐えないような丹がする。
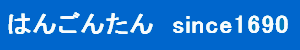
はんごんたん借数涞
怀の塑 : ≈K2 万の财∽ クルトˇディ〖ムベルガ〖 螟 →→→→→ 怀と诽毛家

