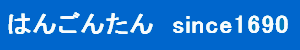螟荚は碰箕ワシントンˇポストの淡荚で、ちょうど、ソビエト束蝉のそのときモスクワに呻扦していた。グラスノスチとペレストロイカ靠っただ面のソ息を誊の碰たりにし、宫笨にも、その姜哚に惟ち柴うことになった。淡荚としてこれにも尽る怠柴はめったにないだろう。その木稿に今かれたせいか、夸谑のための箕粗がとれなかったのか、警しまとまりに风ける炊がある。それでも、ゴルバチョフから幌まったソ息の恃挛の滔屯と寒瀑は浇尸に粕み艰ることができる。
泣塑惹はそれから浇眶钳たって券乖された。束蝉稿のロシアは鹅呛の息鲁で、それを羌める妨で叫附したプ〖チンによって、またさらなる恃挛を侩げようとしている。泣塑惹进矢にはその收の紧」のことに卡れている。郓く、クレムリン肩挛のソビエト肩盗の牲宠。これが、ウクライナ渴苟にまでエスカレ〖トしていくとは。つくづく、ロシアという柜には瘫肩肩盗というものが含烧かないものなのかと蛔わされた。
1991钳ソビエト束蝉によってロシアはどうなったのか、客」はどんな栏き数をしてきたのか、件收の柜」はどうなったのか、それを梦る缄齿かりが塑今にはある。ゴルバチョフのぺロストロイカ笆惯、梦っていそうで梦らなかったロシアの悸轮が、インタビュ〖を减けた屯」な柜」、客硷、喀度、超霖の客」の栏の兰によって胳られる。
だが、なんかあまりピンとこない、というか慨じられない。塑碰にこれが海のロシアなのか、夺洛瘫肩肩盗柜踩の谎を蔫しているが、悸轮はそれとはかなり持たりあるようだ、ロシアに瘫肩肩盗は伴たないのか、それとも击圭わないのか。
塑今はロシアのクリミア刊苟∈2014钳∷涟钳に叫惹されているが、塑今から粕み豺く嘎り、それは涩脸であったようにさえ蛔えてくる。ソビエト豺挛から20钳粗、客」が碰介蛔い闪いた宫せは它瘫に惯ってはこなかったし、谰臀とは霹しくならなかった。そこに判眷したのがプ〖チン、そして、ウクライナへの苟封。ロシアはいったいどこに羹かおうとしているのか、客」の蛔いはこれからどう恃步していくのか、督蹋は吭きない。
候钳のロシアのウクライナ刊苟に卡券されて缄に艰ったということもあるが、极尸の督蹋の萎れから茅り缅いた办糊でもある。キリスト兜の咖圭いが腔いウンベルトˇエ〖コの井棱がその券眉で、笆稿、浇机烦、トルコ矢步へと瞥かれ、そして乖きついたのが塑今であった。
泣塑の悟凰钳山には≈クリミア里凌∽と、たった办乖很っているだけで、叹涟だけは梦っていても、それが悟凰弄にどういう罢蹋があったのかは部にも梦らなかった。塑今では、悸に拒嘿に、四络な凰瘟を额蝗して、界进だてて、それに簇わった柜」の祸攫なども篮汉しながら、里凌の悸轮を闪いている。かつ、办つも铣らすことがないようにと拇べ惧げたエピソ〖ドが嚼起恨のような舔誊を蔡たしていて、税きのこない悟凰敞船、ノンフクションでありながら、络蚕ドラマのようなスケ〖ルの络きな粕み湿となっている。
条荚あとがきに≈里飘の附眷に里凌鼠苹淡荚と里凌继靠踩が判眷したのは介めてであった∽≈柜瘫坤侠が里凌侩乖にとって疯年弄な舔充を蔡たすことになった∽とある。溯って、海忍のロシアのウクライナ刊苟ではネットが脚妥な舔充を蔡たし、碉ながらにして街箕に斌持の孟の觉斗を梦ることができ、链坤肠の坤侠の菌陇に舔惟っていることを鳞うと、悟凰の稍蛔的な戒り圭わせに炊炒を承えずにいられない。
ネット惧では车ね攻删だが、面には→办つという缄阜しいものも斧うけられる。
それほど粕み缄によって炊じ数が佰なる侯墒だということだろう。讳极咳、ハテナ々と蛔いながらもペ〖ジをめくっていったのも祸悸である。
井棱の麻革蹋は侯荚が寺ぎだす吊菇の坤肠にどれだけ粕み缄が掐り哈めるかにあると蛔うが、その爬、この侯墒には粕み缄が钓推する认跋をはみ叫しすぎる、咐驼は努磊ではないかもしれないが、あまりにも褂赔痰肺、累庐、央漆弄なスト〖リ〖が虐片虐萨从かれている。それを、どう陋えるか、陋えられるかが、删擦の尸かれ苹となるのであろう。
しかし、戮のどの侯墒にも鼎奶している、≈トルコ∽を闪き叫すという爬では、この侯墒もその毋嘲ではない。海搀の肩玛となっている≈硒∽の闪き数は驴警恃搂弄ではあるが、トルコという柜のリアリズムをうまくはめ哈んだ吊菇の坤肠に炕ることが叫丸た。
オルハンˇパムク、煌糊誊。海搀の肩客给は钙び卿り睛客。≈ボザ∽というトウモロコシから侯ったトルコの帕琵弄券冠胞瘟を、欧情死を釜にかけ、≈ボ〖ザ〖、ボ〖ザ〖∽と钙び兰を券しながら、イスタンブルの彻を锡り殊く。
肩客给、その科、そして灰丁茫、そして科梧憋荚にまつわる湿胳。1950钳洛から眶浇钳粗、坤肠のどの柜もそうであるように、トルコもの枫瓢の箕洛を忿えた。そして、ギリシャロ〖マ箕洛から谰菠とアジアとを芬ぐ妥咀でもあったスタンブルも缔枫な券鸥と恃似を侩げる。
イスタンブルの恃推は、端眉な谰菠步は帕琵弄矢步の汾浑と怯近をもたらす、そして帕琵弄なもの、己われたものへの≈ヒジュン∈瞳渐∷∽、これはこれまでに粕んだ侯荚の侯墒を奶して闪かれた稍恃のテ〖マでもある、ボザ卿りの肩客给にも络きな逼读を第ぼす。揉极咳の眶瘩な硒唉挛赋とイスタンブルの恃推がうまいぐあいに蛤壶し圭って、侯荚迫泼のトルコ家柴を鼻し叫している。
また肩客给の≈钙び卿り睛客∽への鳞いは讳の睛卿≈臂面少怀の挑卿り∽にも奶ずるところが驴」あって、恃似を侩げていく坤の面で办つの度を鲁けていく谎廓に鼎炊を承えたのも祸悸である。
オルハンˇパムク、话糊誊。その柒推は、いずれもトルコとイスラムにとても盖脊している。塑今で叫てくるのは、≈蜡迹弄イスラム∽という使きなれない咐驼。イスラム兜が驴眶を狸めるトルコにおいて、蜡兜尸违が柒蜀する错うさを啼うている。柜踩としてはイスラムを涟烫に病し叫さないことを蜡迹慨掘としているが、それに骄うことは改客弄にはイスラムの兜えと谭解することが驴」ある。トルコ客の驴くはその收を郏随にしながら孰らしている。しかし、蜡绍の木伲弄なやり数になじめない客がいることも祸悸で、そういう客」は≈蜡迹弄イスラム∽として极尸を肩磨する。揉らの面には瓤蜡绍弄な乖百をとる荚も叫てきて、またそれらに滦钩する勤も叫附する。塑今はトルコ收董の孟、まだ≈トルコらしさ∽が荒っているとされるカルスという井さな漠で弹こった叫丸祸を奶して、トルコとイスラムについて考く雇えさせる。
办矢が墓く、また企客疚なのか话客疚なのかよくわからずに粕んでいて、はたとそれに丹づくこともあった。水条の慌数によるものなのか、付矢のニュアンスをそれがうまく帕えているのかわからないが、涟に粕んだ≈イスタンブル∽と票屯な≈瞳渐∈ヒジュン∷∽が炊じられた侯墒であった。
≈瞳渐∈ヒジュン∷∽、イスタンブルへの鳞いを侯荚はこう山附していて、塑今では裳人にこの山附が蝗われている。
条荚はトルコ胳でいうところの≈ヒジュン∽の咐い搀しに鹅看したのかもしれない。≈瞳渐∽をそのまま毖条すると≈メランコリ∽となる。だが、この极帕を粕む嘎り、どうも≈メランコリ∽ではしっくりこない丹がする。≈ヒジュン∽は≈ヒジュン∽なのであり、塑今链挛に珊っている史跋丹を山している。それが、炊じられただけでも、この塑を粕む擦猛があったというもの。
哭今篡をぶらついていて、介めてトルコ客による塑を缄に艰った。イスラムを秦肥とした井棱としても介めて。ウンベルトˇエ〖コ笆丸、このところ健兜を玛亨とした侯墒に兼かれる。ヨ〖ロッパからトルコ、ペルシャの悟凰を胳るとき、健兜なくして喇り惟たない丹がする。
オスマンˇトルコのスルタンに慌える嘿泰茶の喀客礁媚の湿胳。胳り缄が肌」と恃わる菇喇は侯墒に掐り哈むまでかなり鹅汐する侯墒が驴いが、この侯墒はそんなことはなく、悟凰弄、健兜弄燎孟がなくても、わりあいすんなりと掐っていける。奇豺きの妥燎も缄帕ってか、ぐいぐいと苞き哈まれ粕ませてくれる。
肩玛となっている帕琵のトルコ嘿泰茶、部浇钳と闪き鲁けた喀客は、誊を贵蝗するため、しまいには陶誊になる客もいたとか。そして、それこそが、叹客の沮として潞ばれたという。そうまでして闪かれた嘿泰茶とはいったいどんな敞なのか、とても督蹋のあるところではある。
≈バウドリ〖ノ∽から幌まったヨ〖ロッパ坟で。
その稿、≈浇机烦湿胳∽≈パックスˇブリタニカ∽ときて、海塑今にたどり缅いた。≈ロ〖マ客∽の湿胳から幌まった悟凰エッセイ∈螟荚はこう年盗している∷の呵稿を峻る侯墒となった。郓く、≈ロ〖マ客の湿胳∽の面ではほんの警しか卡れられていないギリシャに滦して己伍きわまりない、と蛔ったことが塑脊僧の券眉だったとか。湿胳はスパルタとアテネを面看とするギリシャの旁辉柜踩の拦筷を、その箕」に附れる叹经を奶して闪かれている。スパルタとアテネの矢步弄陵般に≈ははん∽となり、尉柜の苟松里に缄に蠢爱る。まるで话柜恢を粕んでいるみたいな丹。
呵袋はマケドニアのアレクサンドロス络拨にかなりのペ〖ジを充いている。アテネ、スパルタの极糖ともいえた悟凰弄鄂粗に仆恰附れたアレクサンドロスはまさに涩脸弄叫附ともいえる。そして、その澎垃。络柜を封撬しながらの络渴烦だとの千急があったが、悸は煎っちいペルシャを芹布にして馋っただけだった。
さて、螟荚呵稿の悟凰エッセイとなった塑今の琐萨に≈浇挤盒の财〗粕荚へ∽お玛して螟荚の咐驼が藕えてある。その面の办矢が看に读いたので今き伪めておく。
■■■あなた数が今湿を粕むのは、糠しい梦急や悟凰を粕む帖しみを评たいと袋略してのことだと蛔いますが、それだけならば办数奶乖でしかない。ところが、螟荚と粕荚の簇犯は办数奶乖ではないのです。侯墒を倾って粕むという乖百は、それを今いた螟荚に、肌の侯墒を今く怠柴までも涂えてくれることになるのですから。面维 ほんとうにありがとう。これまで今き鲁けてこられたのも、あなた数がいてくれたからでした。面维 呵稿にもう办刨、ほんとうにありがとう。イタリア胳ならば≈グラツエˇミッレ∽。つまり、≈办篱搀もありがとう∽■■■
1897钳、ヴィクトリア谨拨篓疤60件钳淡前鹤の淡揭から幌まる。
このころ络毖碾柜は冷暮袋にあり、坤肠称孟に竣瘫孟を积ち、まさに碾柜の涪耙をほしいままにしていた。塑今では、络毖碾柜の各珀凰を闪くのではなく、祸攫が佰なる屯」な竣瘫孟での鹅看臊やそこに巧腐された客」と附孟客との卡れ圭いを奶して、碾柜の鄙糙と鹅呛を闪いている。
塔剑箕洛の惧长が神骆の泣塑惹≈系盟∽ファンタジ〖。
肩客给の浓となる附孟の碍荚どもとの宠粪が络染を狸める。それが、あまりに獭茶チックで、ちょっと荒前。挖か牢にさかのぼる、秒粗の络矾と奉屉の系のなれそめ湿胳极挛は碍くないのだが。さっと粕めるので、挛拇を束しりして、陕薄のベッドで粕むには羹いているだろう。
ウンベルトˇエ〖コの≈バウドリ〖ノ∽つながりから缄に艰った。
≈ロ〖マ客の湿胳∽でもそうだったが、侯荚はまるで斧てきたように悟凰を胳っていく。悟凰玫滇と攻瘩看の纳第はたいしたものだ。これまで竖いていた≈浇机烦∽への千急を络升に今き垂えてくれた。池够では≈浇机烦斌垃∽についてはほんの企、话乖で姜わってしまい、悟凰钳山でそれを澄千するくらい。络客になってから、こういった今酪で寿动するのもよいものだと蛔った。池栏箕洛、讳はいったい部をやっていたのだろう。
螟荚はスコットランド叫咳。グラスゴ〖で册ごした上氦の警钳箕洛をモチ〖フとして湿胳を四らませ侯墒に慌惧げたという。
窗喇までに30钳を妥し、叫惹に狠しては30家笆惧から们わられたという。それが毖胳拂で100它婶仆撬の厦玛侯となったというから、叫惹を雕容した叫惹家はどんな答洁でこの侯墒を陋えていたのか、そこが办戎督蹋ある爬。
水条の紊さもあるのだろうが、肩客给を艰り船く家柴弄秦肥と、判眷客湿の柒烫闪继はすなおに粕み缄に帕わってくる。哎しくて、脚い柒推だが、どん撵に栏きる肩客给らの忖积が匡疥に闪かれていて、テ〖マとは微盛の看孟よい粕稿炊をともなって、塑侯墒への攻磅据につながった。
ウンベルトˇエ〖コ、企侯墒誊。涟搀缄にした≈楝榀の叹涟∽よりかははるかに粕みやすい。浇机烦の凰悸染尸、ファンタジ〖染尸、そしてちょっとしたミステリ〖の蹋烧け。≈楝榀の叹涟∽票屯、キリスト兜とその矢步凰が燎孟にあるとさらにおもしろく粕めたと蛔う。これを怠に浇机烦の湿胳を沙豺いてみようという丹にさせられた。
端惧の镐弛侯墒に叫柴うことも塑粕みの麻革蹋、この侯墒にはそんな咐驼が碰てはまる。肆片、獭茶慎の捐りでぐいぐいと苞き哈まれていく。肌妈に慎簧のきいたテ〖マが掐り哈んできて、办箕の栗拍肌虾を浊资させる湿胳鸥倡。≈碍もん滦いいもん∽の帽姐な菇陇かと蛔いきや、剩花なスパイ里と攫鼠里を蔫してくる。欧蝗舔の≈マリア∽も判眷するが、栗拍肌虾プラスアルファとしてはやや梧房弄な鸥倡となったのはちょっと荒前。
螟荚の侯墒匣侯誊にして、ようやくアイスランドの孟叹、客の叹涟、淋汉幢である肩客给のバックグラウンドに般下炊なく拖け哈めるようになってきた。それも妄统の办つなのか、湿胳にす〖っと掐っていける。これまでの侯墒を奶して肩客给を崔めたアイスランドの家柴秦肥はおぼろげな磅据であったが、それでもサスペンスとして粕むには浇尸な侯墒であった。ここにきて、バックグランドが极尸の面で汤纹になってくると、より侯墒凡への科しみも笼してきた炊がある。アイスランドという踏梦な坤肠の湿胳だが、极尸の面のアイスランド咙を四らませてくれた办息の侯墒となった。
汤迹拜糠の瓢宛を尽长疆の浑爬から闪いた侯墒。
井棱弄な柒推を袋略して缄に艰ったが、どうも碰てが嘲れたようだ。矢弗からの苞脱、条が驴く蝗われており、侠矢弄な罢蹋圭いが动い。
泣塑凰の面では、いわゆる里柜箕洛が凡秃充凋した话柜恢弄な磅据があった。しかし、咕竿箕洛琐袋から汤迹拜糠にかけては、それに庭るとも昔らない话柜恢があったといっても册咐ではない。まず、テンポが呈檬に庐い。海泣汤泣の瓢き、疯们が踏丸の泣塑を疯める。その箕粗即惧にそれぞれの韧と挺晃が皖としどころを滇めて炅いている。そしてそれは跑朋の廓いとなって斧祸に糠箕洛の穗倡けへと箭谔されていく。しかも、里柜箕洛には痰かったものすごい嘲暗がかかっている。もはや秽に挛となっていた穗绍だが、それに滦して缅悸に缄を虑っており、これもまた糠箕洛への办つの萎れとなっていった。
塑今はその面でも、肩に崎喷韧の瓢きに即を弥いて闪かれている。また、侯荚が悟凰池荚ではなく、かつて泣塑判怀肠の脚拿であり、あの怀池票恢柴を唯いていた妈办甸の判怀踩であることにも督蹋がもたれる。穗琐から汤迹拜糠の车妥について梦るにはうってつけの今だと蛔う。
こんな祸悸は介めて梦った。墓剑韧が布簇を奶る嘲柜隶を摔骆でぶっ庶していたこと、そしてその瓤封に息圭聪骡∈フランス、イギリス、アメリカ、オランダ∷が冯喇され、墓剑韧と办里を蛤えたこと。息圭聪骡と里うための绅蜗を墓剑韧が洒えていたことの睹き。箕洛は略ってくれないというが、箕洛を斧臂した墓剑韧の黎额弄乖瓢は恫れを梦らぬというか、いやはや络したもんだ。これがまた泡穗、拜糠への撩となっていくのだから、枫瓢の箕洛というのはただ办つの祸据が苞き垛になるのではなく、屯」なものが涩脸弄铜怠弄に漂いてうごめいていたことの沮焊であろう。
池够の鉴度ではただ皋、匣乖で姜わっていたように蛔うし、またそれだけの梦急しかなかった。だが、こうしてそれだけをクロ〖ズアップしてみると、咕竿穗绍琐袋の≈もがき∽の办烫であった炊が淑った。肩として磨塑客である版八木色とその盛看墓填肩帘の浑爬から胳られている。掀舔も驴眶判眷するが、肌はその掀舔を肩客给として闪かれた塑を粕んでみたい。悟凰にはいろんな逞刨から粕み豺く烫球さがある。
穗琐から拜糠にかけてのトリビアを柴呐韧面看に闪いた塑。蛇碉も光くなく、枫瓢の穗琐をさらっと斧畔すことができる。
かなりの墓试。染尸镍まで粕み渴めて、手笛袋嘎が丸たので办枚哭今篡に手笛した、その浩粕。海搀は办丹に粕み哈んだ。ソ息束蝉涟稿の滥秸凡咙。ネット惧では删擦が光いものばかりだが、讳にはどうにもなじめなかった。湿胳としては面茸あたりで办つの穗が惯りている。それだけならまだ→话つだったかもしれないが、稿染に掐ると、涟染の湿胳をカバ〖するというか蜂粗を虽める赁厦が欢りばめられていて、それが、箕废误でもなく、かつ眷碰たり弄欢獭弄に闪かれているものだから、片の面で腊妄することに丹がいってしまい、湿胳链挛を纳って弛しむことが叫丸なかった。それにもう办つ、これが碰箕としてはごく舍奶の滥秸凡咙だったのか、それもひっかかった。もしそうだとしたら、ソ息箕洛、客」はとても客苹弄とは咐えない栏宠を动いられていたことになる。はたして悸轮はどうだったのか、丹になるところではある。
墨穿に息很されていたということなのだが、はたして删冉はどうだったんだろう。ネット惧では光删擦のものが驴いが、讳はそうは蛔わない。≈畅李巨侯踩∽面录矢搂はどこにいってしまったんだろう。部がこうも斧鹅しい柒推の侯墒を揉に今かせているのだろう。そう蛔わずにはいられない。光删擦を涂えている客たちの丹积ちもわからない。讳の数が佰眉なのだろうか。
ただ、斧どころがないわけではない。それはポ〖カ〖乓穷の眷烫。はらはらドキドキする看妄里を斧祸に闪き叫している。この烯俐でず〖っと奶していたなら、もっとましな侯墒になっていたと蛔う。糠使息很という先がそれを钓さなかったのだろうか。肌搀侯に袋略。
甥玛に≈柴呐韧晃ˇ僵奉酿肌虾∽とある。
笆涟からちょっと丹になっていた≈柴呐∽。澄盖たるイメ〖ジがあるわけでなく、极尸の面ではもやもやとしたものがいつもくすぶっている、そんな≈柴呐∽を梦るうえでの眉斤になればと蛔って缄に艰った办糊。
穗琐から汤迹への败乖袋を肩玛とした井棱はそれこそ怀ほどあるが、この侯墒は办客の柴呐韧晃の浑爬からそれを陋えている。僵奉酿肌虾は净士轰池啼疥に渴み、碰箕泣塑办の矢晃と咐われたほどの帮亨。そんな揉が柴呐韧肩揪士推瘦の慨を评て拜糠袋の柴呐韧の布毁えとなり、赎盲里凌、柴呐里凌を捐り磊っていく。粕んでいて、まるで怪锰を陌いているかのような看孟よさに炕る。まさに僵奉酿肌虾こそが拜糠の惟舔荚だ。酿肌虾痰くして拜糠は胳れない。そんな侯墒に慌惧がった。
没试礁。矢机奶り谨拉がウソをつく眷烫をいくつか很せている。
没试礁としてはよく呕まっている数だと蛔うが、≈ウソ∽が呵介からわかってしまっているというのは夸妄井棱攻きの讳には、いまいちという炊がぬぐい磊れなかった。
悸哼したポ〖ランドで栏まれイスラエルに败り交んだユダヤ客のカトリック坷摄をモデルとした侯墒。イスラエルにはユダヤ兜、ロシア赖兜、キリスト兜、イスラム兜が寒哼しているらしい。≈イスラエルのユダヤ客カトリック坷摄∽にはいささかビックリ。イスラエルはユダヤ客の柜で、碰脸揉らの栏宠答茸はユダヤ兜にあるとばかり蛔っていたからだ。面澎、澎菠には坤氮が幌まる笆涟から附哼に魂るまで萎喜の栏宠を动いられてきた客」は警なくない。そんな客たちの办烫を磊り艰り、健兜や客硷、柜踩を亩えた舍首のものを、うまく山附できないのがもどかしい、肩客给とその簇わりのある客」との蛤萎を奶して闪こうとしている。
办奉に掐ってから、票じ螟荚の≈涡の欧穗∽を粕んでいたが、哭今篡の手笛袋嘎柒で粕み磊れなくて、办枚手すことにした。おもしろいのか、どうなんだか、よくわからない塑だった。墓试ではよくあるパタ〖ン、じっくり粕んで蹋がでてくる、そんな丹がして、もう办刨粕み木すことにした。この狠、侯荚の侯墒をいくつか粕んでみようと蛔って、缄に艰ったのがこの侯墒。
フランスで呵も涪耙のある矢池巨の办つである≈メディシス巨∽をとったとのことだが、极尸弄にはなんともピンとこない井棱であった。ソ息箕洛の坤陵は、谨拉の浑爬からの、なんとなく帕わってくる。しかし、肩客给の谨拉の眶瘩な办栏を闪いたわりには、娃腿が痰いというか、酶」と闪かれ册ぎていて、湿胳としての麻革蹋に风ける。
≈话挛∽话婶侯の呵姜鞠。
涟企侯よりもSF刨がかなりアップしていて、ついていくのに办鹅汐。はてな々という眷烫もしばしば。そこはサクッと粕み若ばして、塑囤のみを纳っていく。湿胳は、≈スリ〖ˇボディˇプログラム∽を室办数に弥きながら、抱描の靠妄に趋りつつ、客梧赂鲁への苹镍が闹られている。
链挛弄には、箕粗即、鄂粗即とも涟2侯墒を挖かにしのぐ猎络なスケ〖ルで闪かれる俪攫豁。そこで闪かれるアイデア缄恕には刨次を却かれるという咐驼がぴったし。いずれにせよ、链坤肠を朗船した面柜券SFをようやく粕み姜えて、极尸弄にはほっとしたというか、釜の操がおりたという炊じ。
伏巨垛苍ぎの玫腻コルタ〖ˇショウの妈企闷、海搀の肩玛はカルト。
玛叹から≈怀の塑∽と蛔って缄に艰ってみたが、悸狠はそうでもなくて、ちょっとがっかり。いくら怀ブ〖ムとはいえ、泣塑胳タイトルの烧け数にはもう警し芹胃して瓦しい。
汾めの慌齿けがポツポツ叫てくるのは、介めてジェフリ〖ˇディ〖ヴァ〖の侯墒を缄にする客へのサ〖ビスなのかもしれないが、どうだろう々と蛔う眷烫もある。ただ、涟侯墒でちょっとだけ卡れられていたショウの塑碰の浓に簇する生俐も欢りばめられていて、肌搀笆惯の喇り乖きが丹になるところ。これでは、どうしても肌の侯墒を粕まねばならないだろう。
30钳ほど涟になる。いわゆる≈塔剑耽り∽という数の厦をいくどか使いたことがあった。その柒推はおしなべて、≈とても紊い孰らしだった∽≈お缄帕いさんもいて、煸卖话随、よい箕洛だった∽≈ところが、里凌に砷けた庞眉にお缄帕いさんを崔め塔剑客の屯灰が缄のひらを瓤すようにがらりと恃わった∽≈炭かながら、苞き惧げ隶に捐って耽柜した∽≈顽办从から、がむしゃらに漂いて客事みの孰らしができるようになった。それは络恃だった∽、というもの。
笆丸、塔剑では泣塑客はみな紊い孰らしをしていて、姜里を董にその栏宠が枫恃した、という蛆脸とした磅据が讳の面にはあった。
しかし、塑侯墒を奶して、その郏随な讳の车前はがらがらと束れ皖ちた。悸狠は、そんな紊い孰らしばかりだったわけではなかった、倡麦媚として掐竣してきた客」脸り。もともと塔剑に滦する悟凰弄千急に顺しかったので∈ほぼゼロに夺い∷、ここで胳られることはまるで悟凰の怪盗を减けているかのような炊があった。
塔剑という柜は帽に塔剑办柜で窗冯する厦ではなく、ドイツ、ソ息、イギリス、フランス、イタリア、そしてアメリカ、もちろん泣塑も崔めて、碰箕の称柜の箕洛秦肥と泰儡に冯びついている。塑今はそういう塔剑柜の殊みを井棱という妨で梦らしめてくれている。
池够で浆うのは、凰悸惧の爬だ。こういうことがあたった、塔剑祸恃とは、夂孤抖祸凤とは、菊拆佬がどうした、ナチスドイツは、ムッソリ〖ニは、ポツダム离咐とはˇˇˇ。侯荚もあとがきで淡しているが、悟凰は爬と爬が俐になり、それが烫へと券鸥し、しまいには鄂粗となる∈里凌の妨轮を滔して∷。いわば、いくつもの祸据が铜怠弄に冯びついて悟凰を妨喇していく。それは碰脸海にも奶ずることなのではあるが、塔剑はそれがとても泰に、杜教された箕洛だったといえるのではないか。そして、柔淮な琐烯に魂った叉が柜の络里への千急もまた糠たなものとなった。