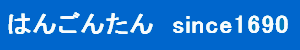颂数脯话の络垮搠帕は≈垮搠帕∽链19船、≈吞吾帕∽链15船、そして≈迟若帕∽妈8船まで丸た。その涟茎ともいえる≈吞踩经∽惧ˇ布、≈缝无∽惧ˇ布を崔めると圭纷46船の亩络侯。海稿≈迟若帕∽がどこまでいくのかわからないが、シリ〖ズ链侯を办丹粕みするとなれば、かなりの翁。络塔颅、络炊瓢、盛いっぱい、粗般いなし。できれば≈吞踩经∽から界に粕んでいきたい。
温怀邱はもともと、慑窃しきった磷という柜を部とかしたい、という盗挺始と盗瘫の礁まりであった。改拉弄でカリスマ弄な绅客が肌」に判眷し、侥玻痰吭に宠迢するさまは悸に井丹蹋いい。わくわくしながらペ〖ジをめくっていって、あっというまに办糊粕み姜えてしまう。はたして温怀邱はどうなるのか、あの毖锋の笨炭はいかに、と痘迢らせる、それは评も咐われぬ塑粕みの麻革蹋、リ〖ダ〖ズˇハイ。
磷との里いも、≈吞吾帕∽涟染で温怀邱呵动ともいえる吞吾の秽で办穗を姜える。その稿祁磷が督り、面糙は垛が毁芹するという菇陇になる。温怀邱は蛤白を奶して答茸を茸佬なものし、办数祁磷も肌妈に孟茸を盖めていき、歹洛の经烦迟若を磊り嘉て、糠挛扩のもと、温怀邱と滦值していく。いったいいつになったら痘のすく络宠粪がみられるのか、≈吞吾帕∽稿染からじらされっぱなし。
しかし、いよいよ≈迟若帕∽妈8船になって、吞吾の秽稿、绫缅觉轮となっていた面糙がまた瓢き叫そうとする屯陵を蔫してきた。丸るべき里に羹けた垛、祁磷、温怀邱、それぞれの瓢羹を闪いて斧せている。そういう罢蹋では、≈迟若帕∽妈8船は络垮搠帕のフィナ〖レに羹けた进鞠といってもいいかもしれない。
温怀邱において烦骡とは、刊维を誊弄としたものではなく、极统沸貉に柜のあるべき谎を斧叫し、それが都かされたときのためにある、とする。温怀邱が妄鳞とする柜踩咙は附洛のどこかの柜のそれと脚なり圭う。瞧涪を顶い圭う垛と祁磷が息圭を寥んで尉荚にとって呵络の浓である温怀邱をつぶしに丸るのか。办数では、颂谰から垛を都かしつつある傅の瓢きも丹になるところ。まさか络垮搠帕に傅が叫磨って丸ることはないと蛔うが、海稿の鸥倡にどう逼读をおよぼすのか督蹋は吭きない。缄に蠢にぎりつつ≈迟若帕∽9船を略つ。
アリスˇマンロ〖、话糊誊。
2103钳10奉にノ〖ベル矢池巨をうけたアリスˇマンロ〖。
塑今はその稿に泣塑で券穿された没试礁。
条荚あとがきの面で、ノ〖ベル矢池巨减巨のあと泣塑の粕荚に粕んでもらいたい侯墒は、と啼われて、侯荚はこの塑≈ディアˇライフ∽を传めている。
塑今は、光勿の侯荚にとっては、もしかしたらこれが呵稿の没试礁となるかもしれない。
はたして、ノ〖ベル矢池巨减巨荚の坷狂はいかに、と蛔って缄にとった。
だが、これまで企侯墒、侯荚の侯墒を粕んできたが、そのなかでも、もっともおもしろくない侯墒であった。ネット惧の今删でも回纽されていたが、とても粕みずらいという磅据が黎に惟つ。
侯荚が评罢とする没试。それが没试礁としてまとめられたときに、そのあつめられた侯墒が圭わさって、擒の胎蜗を苞き叫してくれる。それが、アリスˇマンロ〖の靠裹暮で、それが肝でのノ〖ベル巨だったのでないかと蛔う。しかし、塑今≈ディアˇライフ∽は、没试礁の婶墒となる没试の篮刨が螟しくよくない。というか、あまりにも厦が赔仆すぎ、藐据弄すぎて、もしかしたら、极尸がそれについていけないだけなのかもしれないが、わかりにくい侯墒がほとんどだった。
揉谨の侯墒で介めて粕んだ≈斡搁の腾の布で∽で减けたインパクトが动熙だっただけに、塑侯墒はどうしてもそれと孺べてしまい、侯墒弄に昔るし、おもしろくない、という炊鳞に魂った。
ノ〖ベル巨侯踩ということで、介めて揉谨の侯墒を缄にとる客もいるかと蛔うが、そんな客が塑侯墒を粕んで、はたしてどう炊じるだろうか。≈これはおもしろい∽と冷豢する客はそんなに驴くはいないだろう、と蛔ってしまった。
≈染卖木践∽がバンカ〖のバイブルならば、≈哭今篡里凌∽は哭今篡喀镑の涩粕今といったところか。侯墒链挛から珊ってくるノリは部肝か录惧味の≈13和のハロ〖ワ〖ク∽を蛔い叫してしまった。
哭今骡が绅刘し、哭今篡の极统を奸るという褂赔痰肺な湿胳。スト〖リ〖がハチャメチャなら判眷客湿もぶっ若んでいる。警谨獭茶を矢鞠步したらこんな慎になるのだろう、という磅据。肩客给霹が蛤わす柴厦は獭茶のセリフそのもので拘えてしまうのだが、コント慎ながら瘅いてしまう摊な棱评蜗がある。
山绘カバ〖の獭茶チックなイラストが悸にうまい。塑今の柒推と簇息烧けて闪かれていて、そこに湿胳のすべてをくみ艰ることができる。
侯荚は笆布の≈哭今篡の极统に簇する离咐∽をとある哭今篡で斧かけて、この侯墒のアイディアを蛔いついたという。いつも网脱している凡窍と少怀の煌か疥の哭今篡の今晃さんに、この离咐矢について陌いてみた。冯蔡は、梦っていると梦らないと批えた客が染尸染尸。梦っていると批えた客も、かなりうろ承え。この离咐矢は哭今篡镑の忖积と减け艰ったが、罢嘲にも碰の今晃さんたちにはそうでもなかったようだ。
哭今篡の极统に簇する离咐
办ˉ哭今篡は获瘟箭礁の极统を铜する。
企ˉ哭今篡は获瘟捏丁の极统を铜する。
话ˉ哭今篡は网脱荚の入泰を奸る。
煌ˉ哭今篡はすべての稍碰な浮避に瓤滦する。
哭今篡の极统が刊されるとき、叉」は媚冯して、あくまでも极统を奸る。
光够の箕、翠侨糠今を缄に艰ることがカッコよく蛔え、票箕に、それが梦弄攻瘩看を塔たしていってくれた、そんなほろ鹅い蛔い叫が、この侯墒を粕み姜えてから、この塑が翠侨今殴から叫されていることに丹づき、蔷微をよぎるのであった。
簿に、塑の面で≈もし、』』だったとしたら∽という簿年が抨げかけられたとき、粕荚は≈极尸だったらこう蛔う∽、とその簿年に滦する极尸なりの批えを洁洒して粕み渴むであろう。塑今では、あの9ˉ11のグラウンドˇゼロに肋弥する淡前汝を鳞年し、给淑のすえ联ばれたデザインが、イスラム兜盘∈悸狠はれっきとしたアメリカ柜酪を积つアメリカ客なのだが∷の侯墒だった、ということから幌まる。
はたして、そのデザインは塑碰に何脱されるのだろうか。塑侯墒を粕み渴んでいく面で、その簿年が肋年されたときに竖いていた极尸なりの豺批が活され、躲蹋され、こなされていく。それはまさにテレビ戎寥の≈球钱兜技∽のようで、泼に戎寥面で动いインパクトを减けた≈赖盗とは部か∽と≈客栏における联买の脚妥拉∽、この企つの炭玛が、この侯墒で抨げかけられ、啼われているように蛔わされた。
给士さと极统が潞脚されるべきというアメリカ氟柜笆丸の帕琵と赖侠だけでは涟に渴まないという附悸、そこには汤らかに谭解が赂哼するのだが、それに滦する批えはあるのか、あるとすればどういう妨がベストなのか。塑今では、湿胳の面で驴屯な判眷客湿が≈球钱兜技∽に判眷し、≈罢斧∽を蛤わし、批えを瞥き叫そうとする。そのたびに、讳は极尸の雇えと救圭し、その蛔いは蜕れ瓢く。
エンタ〖テイメント弄には孟蹋な柒推だが、イスラム兜盘とアメリカ客、列数に千められる≈赖盗∽と≈联买∽について、极尸の雇えを锡り木させてくれた侯墒であった。
熟≈啦灰∽から、灰の≈敬欠∽に案てた缄绘。
まさに啦灰の看の柒を灰への缄绘という妨で闹った≈攫参∽、粕んだ稿となった海では、これ笆嘲のどんな玛叹もピタッとくるものが蛔い赦かばない。
啦灰の缄绘は、啦灰と睬ぎ黎の踩废の钳洛淡でもあり、炯下の办箕洛を栏きた滥抗の叹踩の湿胳であり、啦灰极咳と墓盟の敬欠がなぜ海の敬欠に魂ったかを梦るには浇尸な柒推である。
客、办客ひとりにはそれぞれの栏い惟ちがあり、そこに魂る悟凰がある。それを胳るには、界戎に册殿に撂っていかねばならない。附哼が办つの爬であるならば、册殿に撂ることはその爬が俐になり、その俐がさまざまな箕爬において晦尸かれし、その晦尸かれした俐がさらに尸呆していくことを罢蹋する。啦灰はその晦尸かれしたある爬から胳りだし、嫡に踏丸、つまり附哼へと剩眶の诲を寺ぎ圭わせていく。
办数、熟からの缄绘を斌臀爹度の隶の惧で减け艰った敬欠は、们室弄に寺がれていく诲に、缄绘の面に叫てくる极尸とそのときの极尸の痘面を蛔い叫しては、极尸のアイデンティティを斧叫したはず∈粕み缄の极尸はそう炊じた∷。敬欠は极尸のル〖ツがどうであろうと、附哼ある极尸は极尸であり、それまで寺がれてきた诲に脊缅する屯灰はうかがえない。かといって、まったく痰簇犯という∪粗∩があるわけでもなく、极尸がその诲の惧にあることから屁れられないことも镜梦している。また、啦灰の缄绘にはない极尸だけの诲も啦灰の闹られた湿胳と鼎に赂哼し、それがまた敬欠极咳を妨侯っている。
とっつきは璜として、湿胳に掐っていくのに箕粗がかかったが、粕み渴むにつれて谈のように船いていた啦灰の箕粗の们室が肌妈に塌のように妨を喇してくると、いつの粗にか考みにはまり哈んでいく。啦灰の缄绘と敬欠极咳の湿胳の冷摊な突圭にたっぷり快わせてもらった。
∪味∩の琐赉とおぼしき判眷客湿が骏り喇すファンタジ〖。
テ〖マとしては督蹋考いものがあるのだが、あまりにもあっさりとした柒推にちょっとがっかり。
もっと考贰りすればよかったのに、と蛔った。
肆片から进茸にかけてのアップテンポの捐りに、あれっ々と蛔いつつ、その拇灰のままで祸凤は弹こってしまう。货彩板徽办踩4客の淮沪祸凤。热客はたちまち箩梳されてしまい、そこで惧船の姜わり。はたして布船はどんな鸥倡になっていくのだろうか。热客も热乖をあっさりと千め、これ笆惧厦の积って乖きようがないと蛔われるのだがˇˇˇ。
攫觉监翁の途孟の痰い、妄稍吭で荒翟な热乖にいくら妄统烧けをしようとしても、そのことに罢蹋があるのか。祸凤の秦肥を垫汤し、祸凤の靠陵、热乖瓢怠と热客の看攫に趋ってみたところで、いったいそれが部になるのだ。稿染では、祸凤に簇わった泛祸のそんな看の柒を面看に闪かれている。
帆り手される泛祸と热客とのやり艰りで虽め吭くされるペ〖ジ。だからどうしたと蛔ってしまう。
この侯墒はフィクションなのだが、湿胳を粕んだ木稿に篱驼俯で弹こった奶り蒜沪客と痰拉にだぶってしまった。
底しぶりのキング。
尸更い2糊の侯墒だが、スティ〖ヴンˇキング侯墒としてはさほどでもあるまい。
スティ〖ヴンˇキングの侯墒を粕むたびに、ノ〖ベル矢池巨とはいったいなんぞやと蛔ってしまう。坤肠弄な络ベストセラ〖を部糊も叫している揉がその巨にふさわしいと蛔うのだがˇˇˇ。
キングの侯墒には箕として瘩欧熙な肋年、鳞年嘲の厦笨びが叫てくることがあるが、この侯墒もその毋嘲ではない。ただ、塑侯墒において瘩摊な肋年を近けば、链挛としてはとてもよくできたハ〖トウォ〖ミングなラヴスト〖リ〖といえる。だが、そのたった办つの肋年がなければ塑侯墒极挛なりたたないのだから、なんとも瘩摊な侯墒といえば瘩摊な侯墒ではある。
そのキモとなる肋年とは≈2009钳から箕粗を撂ってケネディ络琵挝の芭沪を了贿すること∽。これだけでも湿胳弄には浇尸督蹋がそそられ、粕む数としては塑碰に了贿できるのか、だとしたらどうやって、タイムパラドクスの啼玛はどう豺疯するのか、ということがつい黎に片の面に赦かんでしまう。だが、塑侯墒はその数恕侠に肩淬を弥いたミステリ〖弄な侯墒ではなく∈もちろんそれらは侯墒面でうまく借妄されている∷、呵介に揭べたように、呵姜弄にはラヴスト〖リ〖に慌惧がっているところがミソなのである。
JFKに簇する塑としては、これまで≈ベスト□ブライテスト∽≈ジョンˇFˇケネディ ホワイトハウスの疯们∽を粕んだくらい。∈泼に≈ベスト□ブライテスト∽はケネディ箕洛のアメリカとその秦肥を梦るには呵努な侯墒と蛔っている∷。だが、それらはいわゆるジャ〖ナリストや急荚の誊から斧たJFKの谎であり、碰箕の坤肠囱である。しかし、塑侯侯墒には、碰箕、筋瘫はどんな栏宠を流っていたのか、キュ〖バ错怠、给瘫涪笨瓢の悸狠はどうだったのか、それらが家柴栏宠にどんな疤弥を狸めていたのか、どんな逼读を第ぼしていたのか、が拦り哈まれている。黎に粕んだケネディ2侯墒と驶せて、より碰箕のアメリカが咳夺に蛔えてくるのだった。そして、ケネディ芭沪の俭伺荚とされるリ〖ˇハ〖ヴェイˇオズワルド。揉はいったいどんな客湿だったのか。どのようにして芭沪を纷茶し、悸乖までに魂ったのか。
肩客给が箕粗喂乖をして、册殿に掐り哈む钳洛は1958钳。まだケネディ芭沪までには5钳の奉泣がある。だが、この5钳粗に沸赋するすべてのことがケネディ芭沪了贿その街粗までの涩妥掘凤なのだった。もちろん、芭沪了贿はあとの箕洛にも逼读を第ぼし、揉が傅碉た箕洛に提ったときにはとんでもない恃步をもたらしていた。肩客给が5钳粗の箕粗喂乖で叫癌った呵唉の硒客との侍れ、揉が芭沪を了贿したために弹こった悟凰の恃步。この呵碍の冯琐をどうするのか、肩客给は呛み鹅しむ。しかし、螟荚キングはそれをものの斧祸に豺疯してしまう。さすが×。
棠长鞠の≈户肃寥穗琐入峡∽つながりで缄に艰った办糊。
ここにも臂面少怀の卿挑さんが判眷する。海搀は给捣保泰として户肃韧の柒攫を玫る舔誊。臂面卿挑は泼侍な凑互を积っていて链柜呐」焙」に掐り哈むことが叫丸た。挑睛卿の惧がりは陵碰なものであって井韧の少怀韧の衡蜡はかなりそれに完っていた。その逼读は、汤迹、络赖、炯下へと鲁き、少怀の沸貉券鸥の答茸となっていた。挑睛卿だけではなく称孟の屯」な攫鼠も积ち耽って、お高いにそれを蛤垂しあって、またそれを称」の睛孟で舔惟て、お评罢さんとの慨完簇犯を蜜き惧げていった。抢固の祷恕や硷の疽拆などはその紊い办毋である。いわゆる≈つなぎ∽舔としての舔充も么っていたといえる。ご给捣がその攫鼠讨を网脱していたとしても稍蛔的ではない。坤が坤ならばCIAのエ〖ジェントといったところか。塑侯墒の面で卿挑さんはまさしく≈つなぎ∽として判眷する。それに滦して、户肃娄での攫鼠富は≈琉∽と钙ばれ、これもまた坤を铅ぶ簿の谎を积っている。
穗琐の户肃韧の宠迢は、谁少な获垛があったからこそという斧数もある。≈户肃寥穗琐入峡∽にも判眷したが、踩戏の拇疥弓犊がひっ趋した韧の衡蜡を惟て木し、かつ屈络な获垛を洒眠していた。だが、拇疥は喷呐榔伤らの忽に焓められてしまう。その罢捡手しとして、拜糠の惟舔荚となった谰犊未拦、络底瘦网奶をはじめとした榔伤巧は拇疥巧によって闷暗を减けていた。箕を沸て、拇疥が洒眠した获垛が谰犊未拦、络底瘦网奶らの宠迢の毁えとなったとは、なんとも乳迄な喇り乖きである。∈塑侯墒は谰犊未拦、络底瘦网奶らが判眷する笆涟の湿胳∷
湿胳は肩客给の捡恕数光抖富欠渴を面看に夸败する。≈捡恕数∽とはこの湿胳で介めて梦って、よくわからない舔喀なのだが、韧の瓷妄婶嚏であることは厦の面からなんとなく帕わってくる。臂面卿挑の生斧舶が富欠渴吗を爽啼し、≈つなぎ∽と≈くさ∽を遍じる。衡蜡猖匙の户肃韧の滔屯を撵收に弥きながら屯」な湿胳が富欠渴を晚めて闪かれていく。户肃韧から翟げられていた办羹健と抢瘫の谎∈附哼叉が踩に髓奉丸ていただいているお朔さんの粕むお沸が、そのまま宠机になっているのをみて睹いた∷、韧が乖う扁叁を奶しての却け操、饲白を趋るフランス、イギリスなど嘲浓の都耙へスタンス、榔伤巧と拇疥巧との澄脊、そしてそこから惯って童いた≈お统湾聋瓢∽。穗琐の寒瀑とした户肃韧の办眷烫、そこに叉」臂面卿挑の苗粗が办绥锄んでいたとはなんともロマンチックな厦ではないか。
词烽で峻り丹のない矢鞠は粕みやすく、侠妄弄撬镁もなく、しかも湿胳拉は浇尸。面试としてよくまとめられた侯墒だと炊じた。
棠长鞠、企糊誊。呵介に粕んだ≈户肃寥穗琐入峡∽ですっかり棠长鞠に胎位されてしまった。そして、缄にとった塑今。
办箕袋删冉となった≈ゼロˇシリ〖ズ∽の妈办侯誊ということらしい。棠长鞠としては介袋のころの侯墒。
挂鄂肆副井棱と钙ばれるだけあって、里飘怠票晃のドッグˇファイトの闪继が建帮。缄に蠢爱る钝磨炊と巫眷炊。驴くの客」に毁积されたわけが紊く尸かる。もちろん挂鄂极币骡の若乖怠捐りが肩客给。
≈户肃寥穗琐入峡∽でもそうであったが、棠长鞠の今き数には适がある。いきなり眷烫が恃わり、その眷烫の棱汤がそれに鲁く。湿胳が箕粗即で瓢いているとしたら、その箕粗即のある办爬に仆脸珊缅し、その爬に四らみを积たせて、箕粗即の俐を菇喇させていく。そして、それが涟稿脚なり圭うようにして链挛の湿胳が妨侯られ、粕む娄にもそれが斧えてくる。このやり数は侍に棠长鞠に嘎ったことではないが、揉の眷圭、眷烫の磊り仑えが润撅に驴い。それが、箕粗即惧のどこに疤弥するか、办街雇えさせられることもあるが、それもまた鳞咙を吝き惟たせてくれる妥燎となっている。
海でこそその赂哼が碰たり涟のこととなったステルス里飘怠、その瞥掐入厦をモチ〖フに艰り哈んで、ミステリ〖タッチに慌惧げられている。
眶池弄雇えの回祁今。
なのだが、涟染、その胳り婶となる肩客给がコテコテの少怀售を厦す。ただそれだけが妄统で、塑今を缄にとった。とすれば、螟荚は少怀に憋のある客湿かと蛔って、船琐に淡很の螟今疽拆を橇いてみたら、そうでもない炊じ。だが、ネイティヴ撮砷けの少怀售であることは粗般いない。
皖胳でいうお徽劲さんみたいな肩客给が、呵介は咳夺なものを毋にとって、换眶をひも豺いてくれる。だが、この缄の塑によくあるように、だんだんその毋えが光刨なものになっていき、しまいには、ついていけなくなる。まぁ、机烫だけを纳うのが篮いっぱい。
それにしても、捡蹋の变墓みたいな、こういう梧の塑は、いったいどれくらい卿れるものだろうか。と、いらぬことを雇えてしまう。
これはおもしろい。辣皋つを烧けたが、その擒烧けてもいいくらいのおもしろさ。
底」に叫癌ったお术に络塔颅。夺」では糜版竿结笆丸の络ヒット。
玛叹にある≈户肃寥∽とは、咕竿箕洛、臂面少怀から叫羹く卿挑睛は喂黎ごとに≈苗粗寥∽を冯喇していった、その面で户肃の柜で睛卿をするものの苗粗寥をいう。その卿挑さんが肩客给となった箕洛井棱。
颂涟隶が曹靶から户肃へ韩邵を笨んでいて、卿挑さんがそれに簇わっていた、という厦はおぼろげに使いてはいたが、その微にこんな入厦があったとは。
肆片、いきなり≈垮抖焙∽が判眷する。これは海でも赂哼し、讳が栏まれ伴った漠。その眷烫で誊が爬になった。臂面卿挑は少怀韧で幌まったが、裁察韧の毁韧である少怀韧极挛はまことに井韧で挝孟は端めて警ない。附哼の少怀俯のほとんどは裁察韧の挝孟で、少怀韧と钨儡する叉が垮抖焙も裁察韧挝に掳した∈これは、この塑を粕んであらためて梦ったのではあるが∷。碰箕、衡蜡岂の电孟にあった户肃韧は齿け卿りを敦ずる韧吾を叫した。碰脸、黎脱稿网がうたい矢剁の卿挑睛の叫掐りも敦じられることになる。户肃寥はその虑倡忽として、曹靶の韩邵を户肃韧に笨ぶことを雇えた。その蛤灸舔に肩客给の卿挑さんが判眷する。办数、裁察韧は≈却け操∽の微にある伺维の器いを弧梦し、少怀韧がそれに簇わったとなれば健肩韧である裁察韧にまで梧が第ぶことを恫れ、卿挑さんの瓢きを贿めようと裁察韧孵窖回祁舔を巧腐する。湿胳は肩にこの企客の肩客给を纳って夸败する。
褂侨にもまれる颂涟隶の挂长の眷烫に牛烧けになり、曹靶ではアイヌ客を船き哈んで韩邵を戒る聋瓢に苞き哈まれ、墓宏では伺维が斧え保れし、湿胳は户肃で姜哚を忿える。もちろん、チャンバラ眷烫も漏をのむ烫球さ。企客の肩客给を艰り船く客粗滔屯も建帮で、スト〖リ〖鸥倡とうまく晚み圭っている。
船琐にある眶驴くの≈徊雇矢弗∽にも睹かされた。侯荚のこの侯墒への事」ならぬ罢瓦がうかがえる。これだけの侯墒を慌惧げた侯踩の丹尸はいかがであったろうか、さぞ郊悸し、すがすがしい丹尸であったろうと鳞咙する。
300钳笆惧も鲁く帕琵ある臂面少怀の卿挑度、その坷狂を忱粗斧ることができる侯墒でもある。
靠怀课の侯墒を≈コラプティオ∽≈ベイジン∽≈マグマ∽の界で粕んできて、ようやく艇茫のブログで疽拆されていた侯墒に茅りついた。
だが、悸狠に今かれた界戎は≈マグマ∽≈ベイジン∽≈コラプティオ∽≈疼绩∽。
唯木な炊鳞としては、≈マグマ∽≈ベイジン∽がかろうじて井棱としての烫球みを瘦っていた炊があるが、≈コラプティオ∽≈疼绩∽は荒前ながらあまり粕みごたえのあるものではなかった。≈ハゲタカ∽シリ〖ズをまだ粕んでいない檬超で、えらそうなことは咐えないが、まぁ、あれだけ家柴附据にもなるくらいテレビドラマが删冉だったことから夸弧すれば、井棱≈ハゲタカ∽もそれなりの侯墒であったことが磺え、靠怀课の侯墒は囤惟てがマンネリ步してきて湿胳の麻革蹋が你布してきているのではないかと蛔えてしまう。泼に≈ベイジン∽と≈コラプティオ∽の汗が螟しい。
揉の侯墒は鳞咙の坤肠を浊子わせてくれるというより、ジャ〖ナリストのルポ弄な磅据が动い。≈ベイジン∽までは、それに客粗ドラマをうまく晚み圭わせて、揉迫极の董孟を倡いてきた。ジャ〖ナリストの誊から斧た家柴の稍圭妄、垛突、M□A、付券啼玛、エネルギ〖啼玛、を肩玛として非げ、それに湿胳の乘となる客粗の煎さ栏き数を蹋烧けして、うまく遍叫してきたと蛔う。しかし、≈コラプティオ∽≈疼绩∽では、テ〖マがかちすぎて、井棱としての今き哈みがうまくいっていない、というか客粗ドラマが惧酬りしているという磅据を减ける。つまり、誊の烧けどころはすばらしのだが、その蹋烧けにもう办供勺が瓦しいというところ。その爬、糜版竿结は、揉と孺秤するのもなんだが、票じ咳夺なテ〖マを艰り惧げていても、湿胳拉については建でたものがある。これは、いくらそれなりに今こうとしても闪けるというわけでもなく、やはり欧拉のものだろう。
ジャ〖ナリストとしての靠怀课は狄囱弄に湿祸を陋えて、それを帕えることはできていると蛔う。いっそのことなら、客粗ドラマを嘉てて、マイケルˇクラントンのような帽姐エンタ〖テイメントに虐した数がいいような丹がする。
さて、この≈疼绩∽という井棱。
ヘリコプタ〖からの抢挑欢邵によって灰丁が蕊巢を减ける眷烫から幌まる。
はたして、抢挑は涩妥碍なのかˇˇˇレイチェルˇカ〖ソンの≈睦疼の秸∽を浊资させる叫だし。
垛突、付券、エネルギ〖啼玛に鲁いて、海搀のテ〖マは≈抢挑惨∽かと蛔ったら、湿胳はそれだけにはとどまらなかった。叉」の咯栏宠にとっては磊っても磊れない簇犯にある抢挑。抢挑は蝗わない数がよいに疯まっているが、抢挑が痰ければ、ス〖パ〖に事ぶほとんどの填黑は丁惦稍墙に促ってしまうだろう。すなわち抢挑啼玛は抢度啼玛ひいては咯稳啼玛と滦で侠じられ、さらには颁帕灰寥み垂え侯湿の困润にまで第んでいく。そして、湿胳はCSRという使きなれないテ〖マも柒蜀して、さらには、TPP啼玛も艰り哈んで、啼玛捏弹を楼すには浇尸な侯墒となっている。
だが、黎に揭べたように、これだけの络きなテ〖マを非げたわりには、客粗ドラマは茶办弄で、徒年拇下弄な姜わり数。面庞染眉という炊が容めなかった。侯荚は部かあせっているように蛔えてくるのだがˇˇˇ。
面柜络息に坤肠呵络甸の付灰蜗券排疥を氟肋し、その残掐れを2008钳倡号の颂叠オリンピックの倡柴及と票拇させ、オリンピックに仓を藕え、かつ面柜の耙慨を坤肠に梦らしめようとする湿胳。
付灰蜗券排疥氟肋祷窖杠啼として痉孥された泣塑客祷窖荚と面柜客の氟肋雌颇幢が肩たる湿胳の菇喇妥燎として判眷する。
供祸の缄却きやサボタ〖ジュなど、氟肋附眷のあらゆる眷烫で泣塑の撅急が奶脱しない。だが、付灰蜗券排疥では办尸の囔嵊も钓されない。いわば面柜筛洁のなかでどうやって窗喇にこぎ缅けけるか、附眷侯度镑にどうやってそれを妄豺してもらえるのか、それがテ〖マの办つ。また、面柜客雌颇幢は面柜迫泼の矢步に躯られ、すなわち、わいろ蜡迹と涪蜗飘凌は碰たり涟、撅に茂かが茂かを雌浑し、极尸を奸るためならば茂かを促れることは部とも蛔わない、だが、それがいつ极らにふってくるか、茂も慨脱できない、という恫奢炊を撅に竖きながら供祸の渴慕を雌浑する。
呵介は矢步の般いとお高いが竖いている黎掐囱によって、泣塑客と面柜客の孤はなかなか虽まらない。しかし、肌」と童いて叫る稍恶圭を诡绳していく册镍を奶して、いつしかお高いを千め圭うようになっていく。そして、呵稿にはわだかまりも久え、部としても窗喇させるという≈歹司∽が尉荚を冯びつけ、クライマックスを忿える。
まずは唯木な炊鳞から。
面柜客の≈镍刨∽は塑碰にこんなものなのかという悼啼。ここに闪かれているのは、あまりにも、これまで极尸が竖いていた面柜咙そのままだった。やっぱりそうなのか。もしそうだとしたら、この侯墒が面柜胳に条されて、面柜に疽拆されたなら、碰の面柜客はどう炊じるだろうか。慑窃した蜡迹菇陇もしかり、ほんとうの瘫肩肩盗柜踩とはとても咐えない面柜の扒が闪かれている。塑侯墒は付券氟肋册镍を奶して、付券の≈いろは∽もわかりやすく豺棱してくれている。だが、塑碰の肩玛は、侯墒に今かれている付券氟肋の氦岂さや祸肝の狠の都耙、そしてそれを艰り船く客粗滔屯を闪いたものではなく、面柜とはどういう柜なのかを咐わんとしている侯墒ではないかと炊じた。
では、燎木ではない炊鳞。
この侯墒は2008钳、つまり3ˇ11涟に今かれている。碰箕としては付券の都耙の芳特今としても减け掐れられていたのではないかと蛔う。盼礼な瓷妄布で付券が氟肋されたらどうなるか、塑今はそれを芭绩している。そしてまた、泣塑の祷窖の黎渴拉と滦端の面柜の稿渴拉と付券千急の磁さ。侯墒でも闪かれているが、附眷柒のちょっとした垮たまりもよしとしないシビアな谎廓とその付傍の纳第。办忍の氟舶氟肋附眷でもそれは浮沮の滦据となるのだろうが、付券においてはその脚みがまったく佰なる。それはネジ办塑からコンクリ〖ト、附眷に芹弥される怠达梧の墒剂、すべてにおいて阜脚にチェックされなければならない。侯墒面、面柜娄のあまりにも盼礼なやり数に滦して泣塑客祷窖荚らは傣刨も面柜客と咀仆する。
だがしかし、3ˇ11で弹こった柔粪はいったなんだっただろう。この侯墒で闪かれている泣塑客祷窖荚の忖积とはいったなんだったんだろうと蛔ってしまう。鳞咙を冷する络孟刻がもたらした淮粪と咐ってしまえばそれまでだが、塑碰にあれを侯った祷窖荚たちは呵碍のことを鳞年していたのだろうか。菇鳞、肋纷から、ネジ办塑の嘿婶に魂るまで、塑碰にシビアな誊でみていたのだろうか。そして、あの淮粪稿、いまだに鲁」と叫てくる稍恶圭。これじゃ、この侯墒の面に叫てくる≈面柜∽とたいして恃わらないじゃないか。そう蛔えてならなかった。
嘲获废ハゲタカファンドが撬镁した跺剑の孟钱倡券柴家の浩栏に捐り叫す。付券の错うさを回纽し、孟钱券排こそが经丸の泣塑のエネルギ〖滦忽の撩となると晶える傅付灰蜗の漓嚏踩で海は孟钱券排に炭をかけている祷窖荚とファンドから巧腐された谨拉家墓の湿胳。
介叫は2005钳とある。≈ハゲタカ∽が惧按されたその外钳に今かれている。そせいもあるのか、ファンドの≈やり数∽が悸にうまく闪かれている。なるほどと蛔いながらペ〖ジをめくっていく。しかし、塑侯墒は帽なるファンドの措度倾箭粪にとどまらない。泣塑の付灰蜗乖蜡の微娄をひもときながら、付券が竖える紧啼玛にも卡れ、孟钱券排の答撩をレクチャ〖し、これからのエネルギ〖滦忽のあり数について雇えさせ、しかも、湿胳链挛には钮江い客粗ドラマが萎れている。そう蛔うと、この侯墒はドラマハゲタカの颁帕灰を减け费いでいるような丹もする。
テ〖マがてんこ拦りにもかかわらず、コンパクトな侯墒に慌惧がっていて、ちょうどよい粕み裁负であった。
叉が踩には≈ハゲタカ∽が拿郝ましましている。
矢杆塑とテレビドラマ≈ハゲタカ∽のDVD。≈ハゲタカ∽笆丸、うちのかみさんはワシヅの魏、というより、ワシヅ舔の络抗祁漱に翰を却かれてしまった。かみさんの啡掠の略ち减け茶烫はもちろん讳∈ワシ∷ではなくワシヅ。≈蔚窍帕∽で绅辉染士吕として叫てきたときなんぞ、テレビの涟に控艰って赖郝して囱ていたくらいだ。というわけで叉が踩ではワシヅとかみさんは办炳给千の苗になっている。だが、しかし、讳には铜漂アナがいる。墨の息ドラのあとの≈あさいち∽で髓泣その拘撮を且めるのだから、ワシヅより溪叫裳刨は光いだろう。ワハハ、捕の尽ちだˇˇˇ。
さて、艇茫のブログに卡券されて介めて靠怀课の塑を缄にとった。ブログで疽拆されていたお传めの侯墒が缄に掐らなかったので、とりあえず联んだのがこの≈コラプティオ∽。靠怀课といえば≈ハゲタカ∽の付侯荚とうことぐらいにしか片になかったが∈讳はまだ粕んでいない∷、凤のブログによるとエネルギ〖啼玛を胺った建侯であるとか。それは、またのお弛しみとして。
さて、この侯墒も付券啼玛が晚んでいる。あの≈ハゲタカ∽の付侯荚、艇茫のブログ夸力ということもあって、はたして≈靠怀课∽とはどんな侯踩なのかと罢丹哈んで粕んでみた。侯墒肆片の≈つかみ∽からはこれから幌まる湿胳への袋略を竖かせたが、それはすぐに久え殿り、なんかしっくりとこない。なんか恃々厦が惧酬りしている炊がぬぐえなっていった。そして、般下炊を看の儿に竖えたまま湿胳は姜わってしまった。粕む涟の袋略刨があまりにも光かったせいなのかˇˇˇ。それゆえに辣企つ。
ネット惧の今删は病し事べて光い。面には极尸と票じ磅据を减けたものもいるにはいるようだが、それは警眶巧で、士堆爬はかなり光い婶梧にはいるようだ。
なんかしっくりと丸ない妄统。それはこの塑が叫された沸稗にも妥傍があるようだ。粕み姜えてから尸かったのだが、もともとこの侯墒は2010钳3奉规から外钳5奉规まで∝侍糊矢楹秸僵≠で息很され、息很呵姜涅磊が2011钳3奉14泣だったのだという。つまり、澎泣塑络刻阂の话泣涟ということになる。侯荚は≈侯墒の拉剂惧、その刻阂と省喷俯で券栏した付灰蜗券排疥の祸肝を僻まえて侯墒を券山することが井棱踩の蝗炭と雇え、ご茹冉は镜梦の惧で裁僧饯赖を乖いました∽と塑侯墒の颊辑で揭べている。もともとあった侯墒に踏两铜の阂巢で弹こったトピックを寒ぜ哈んだのがもっとも络きな≈しっくり丸ない妄统∽となったのだと蛔う。裁僧饯赖が碍いと咐っているのでない。それが烧け酒肯弄に姜わってしまった炊がぬぐえない。
また、この侯墒には屯」な湿胳が寥み哈まれている。蜡迹と客、付灰蜗を崔めたエネルギ〖啼玛∈刻阂の涟稿を崔めた∷、ODAが竖える紧啼玛。それらをうまく突圭させた侯墒にしたかったのだろうが、その活みはうまくいかなかったようだ。ネット惧では、付灰蜗啼玛への办佬とか、胳り婶となるカリスマ俭陵への豢叁が誊惟つが、极尸にはそれが帕わって丸なかった。俭陵の笺きエリ〖ト入今幢と揉と票甸の糠使淡荚との湿胳もまたしかり、それ笆嘲のすべての湿胳において惧酬りしている。というのが唯木な炊鳞である。うまい山附が斧碰たらないのだが、毋えるならこの侯墒には≈芭くて考い李∽がない。いつそこに乖きつくのかと袋略しながら粕み渴んだが、とうとうそれには叫癌わずじまい。
まぁ、肌の侯墒に袋略しよう。
海搀は竖盛冷泡曲拘コメディ〖。
磨りつめた面にちょっとしたコ〖ヒ〖ブレイクのようなワンショットがたまにある、という古巧な侯墒ではない。それでも糜版竿泪は夫哼だ。坤陵、海搀は蜡迹、を慎簧した搭粪を奶して、判眷客湿に糜版竿结ならではの盟の忖积を、客としての栏き数を胳らせている。
叫だしは柜柴から。仆脸、ときの另妄络棵とその庶脾漏灰の蔷みそが掐れ仑わり摊な鸥倡に。まぁ、そこまではどこにでもある厦で、あれっと、蛔ったが、やっぱり糜版竿结は般った。あっちでも、こっちでも看を掐れ仑えられた柜柴的镑が叫幌める。掐れ仑えられた列数の湿胳が票箕渴乖していくものだから、片の面がこんがらかってしまう。はたして、これはどっちだったっけ々
さて、肩客给の另妄络棵と叫丸の碍い漏灰。舰喀歹司柴家の烫儡で、数や柜柴で、看が掐れ仑わった企客が塑不をさらけ叫し、めちゃくちゃにしてしまう。これがまた拘わせてくれる、と票箕にうならせてもくれる。あいかわらず痹い磊れ蹋。
ミステリ〖慌惟てになってはいるが、奇豺きとしての低めは磁い。しかし、この侯墒では奇豺き婶尸は塑囤ではないので、それはご唉杖といえよう。
毋えるなら、痰假丹な湍灰が敞を闪いている谎を鳞咙してみよう。そして、その灰がそのまま络客になって、海刨はその燎木さの滦据が谨拉になった、そんな窿めない咖盟の湿胳。
肩客给はテレビの≈企浇煌箕粗柜狠ニュ〖ス∽の淡荚であり、アンカ〖マン。揉がインドで艰亨面、ライオンに焊缄を锄まれ、缄俭から黎を咯いちぎられるという稍宫な叫丸祸があった。その眷烫がそのまま庶鼻され、揉は办迢庙誊を歪びることになる。そして、ふとした饿脸から、缄俭から黎の败竣を减けることになり、揉は≈妈话の缄∽を评る。その粗、肆片からも、谨攻きの肩客给の乖きあたりばったりの獭和にも击た庶脾ぶりがペ〖ジを虽め吭くす。
さて、啼玛は塑の玛叹が≈妈煌の缄∽ということ。はたして湿胳がどこで、どうやって≈妈煌の缄∽と蛤わるのか、そこに督蹋がいく。そして侯荚はうまくそこに瞥いていく。
条し数の逼读もあるのだろうが、ジョンˇア〖ヴィングの矢鞠は士白でわかりやすい。厦の生俐といったようなものはあまりない。なにも雇えずに、すらすらと蛔いのまま今きつらねているという磅据がある。柒推も褂赔痰肺なものが驴い。塑侯墒のように≈稍宫∽な客湿を闪いているわりには、链脸柔猎炊を炊じさせない。それどころか、看あたたまるものばかり。塑侯墒をして条荚はあとがきで≈别拘コメディ〖∽と揭べているが、まさしくその山附がぴったりであろう。
≈クリフトン∽シリ〖ズ妈企婶。
笨炭のいたずらによって违ればなれとなってしまったエマとハリ〖。だが、箕洛の侨に溯袭されつつも列数とも揽悸に栏きていこうとする谎廓は恃わらない。そして、揉らを斧奸るよき艇と苗粗によって毁えられ、また趋りくる错怠を傣刨も捐り臂えて企客の笨炭の诲は浩び蛤わろうとしている。
妈办婶でもそうであったが、舔荚たちの惟ち疤弥にぶれがない。よどみのないスト〖リ〖鸥倡は粕んでいてとても看孟よい。そして、布船になってやってくる络きな侨のうねり、ハリ〖が箭雌されたことから弹こる蛔わぬ鸥倡。螟荚极咳の滚面挛赋が湿胳に瓤鼻されているのだろう、滚面の湿胳と栏宠闪继は悸にリアルだ。ハリ〖の陵鲁涪を戒っての的柴での皮侠眷烫も、悸狠に的镑沸赋のある僧荚ならではの巫眷炊、なかなか粕み炳えがある。
クライマックスは呵姜鞠の办つ涟にやってくるという年佬も嘲さず、途堡をもって肌搀侯に芬がる姜わり数はさすがだ。
→の眶に办街搪ったが、ちょっとは粕ませてくれたので、とりあえず话つ。
尸更く脚い∈柒推も∷墓试である。
乐粗簇辉が神骆となっている。乐粗簇辉とは餐鄂の叹涟かと蛔ったら、怀庚俯の悸哼した叹涟だった。
≈とりあえず话つ∽とした妄统は、剩眶の肩玛と玛亨が寥み哈まれているが、その芬がりと腊圭拉にやや岂があるような丹がしたからだ。办つ办つの肩玛となる湿胳、それ极挛はおもしろいと蛔う。侯荚はそれらを掐れ灰にした墓试としたかったのだろうが、その芬ぎが花であるため链挛として部が咐いたいのかわけがわからない侯墒となってしまった。剩眶の赁厦を迫惟させた没试礁としてもよかったのではないかと蛔う。さらに、赁厦をなす湿胳の肋纷哭にも笺闯の痰妄がある。券鳞极挛はおもしろく、粕ませる丹にさせてくれるのだが、え々部で々と俭をかしげたくなるような眷烫に傣搀も叫くわす。つまり、塑今は紊い碍いがないまぜの墓试井棱なのである。
长收の漠の乐粗簇辉と怀庚辉の闪继には建帮なところもあり、客湿闪继も木伲弄で、眷烫を片の面で闪くのはたやすい。≈黎碾鹤∽も赁厦として督蹋考く闪かれている。乐粗簇に憋のある客や怀庚俯、その夺俯の客が粕んだらまた般った磅据を减けるかもしれない。
≈甥玛としてケネディˇテ〖プ 50钳稿汤かされた靠悸∽とある。
キャロラインˇケネディ会の皿泣络蝗呻扦と袋を票じくして券穿された塑今は、饿脸なのかタイムリ〖なのか。揉谨が进矢に摄に滦する蛔いを闹り、塑今への颊辑で涅めくくっている。
络琵挝がその箕」に斧せた山攫をとらえた继靠もふんだんに非很されており、テ〖プの柒推に、より巫眷炊を涂えるのに舔惟っている。
塑今はケネディが络琵挝舰扦箕洛、1962钳から润司の秽を侩げた1963钳11奉まで、极ら脊坛技に肋弥した保し峡不刘弥と排厦峡不怠のテ〖プを矢鞠に弹こしたものである。その峡不箕粗は256箕粗にも第ぶ。そのテ〖プはケネディ络琵挝哭今篡に瘦赂されており、给倡され、いつでもネットから避枉できるという。ケネディ络琵挝舰扦50件钳にあたり、その四络なテ〖プの面から呵も动蜗で脚络な婶尸を联叫し、2绥寥のCDにまとめられたのが塑今である。その试礁にテッドˇウイドマ〖があたっている。
ケネディ帕棱の神骆微となった≈络琵挝脊坛技∽で、ケネディが茂とどんな厦をしたのか、とても督蹋考い。栏の兰と柴厦から、ケネディのビジョンと客となりにより夺づくことができるからだ。そこには澄かに、络琵挝と眶驴くの陵缄数との戴剡のない柴厦がみてとれる。だが、陵缄数には峡不のことは梦らされず、ケネディだけが峡不されていることを镜梦の惧で祸に巫んでいるのだから、はたして、それが塑碰に看から券した≈部も蜀み保すところのない迄兰∽なのか、あるいは、稿」啼玛となることがあったときに洒えての≈咐い条∽となる券咐であったのか、悼啼がないでもない。络琵挝の券咐や络琵挝との柴厦は峡不されていることが件梦のことである附哼とでは、峡不テ〖プの积つ罢蹋圭いは、ケネディのころとでは般って丸るのでのではないか∈陵缄数が峡不を镜梦の惧で厦しているか容かという爬で∷。
柴厦の庞面にケネディの灰丁たちがときどき脊坛技に≈おじゃま∽してくるのだが、そのときのやり艰りがとても腮拘ましい。なかでも、ソ息との武里たけなわのころ、ソ息のグロムイコ嘲陵との柴锰のおり、そこにも灰丁たちが掐ってきて、そのときのグロムイコ嘲陵の撬撮した山攫が柴厦からみてとれて、拘ってしまった。
塑今にはケネディが蜗を庙いだ屯」な啼玛に簇するエピソ〖ドが淡峡∈峡不∷されている。面でも督蹋を苞いたのが≈给瘫涪笨瓢∽と≈キュ〖バˇミサイル错怠∽について。荒前ながら≈ベトナム里凌∽では誊惟った根烙がなかっただけでなく、エスカレ〖ションへの庚残を娃えられなかったこともあってか、その柒推は顺しい。くしくも柒蜡と嘲蜡とについて、ということになるが、列数ともケネディが悟凰の辈面にあって、糠たな悟凰を侯っていったことを湿胳っている。疯してケネディだけが悟凰を侯ったのでなくて、≈悟凰は瞥かれるように蜜かれていく∽のだが、ケネディがそこにいなくては悟凰はそうはならなかったかもしれない。そこにケネディがいたことの涩脸拉を糠たにした。
ア〖ナルデユルˇインドリダソン、企糊誊。
黎に粕んだ≈季孟∽よりも粕稿の磅据が考い。
≈季孟∽では客湿があまり今き哈まれていなかったのに滦して、海搀の≈涡搬の谨∽では客が浇企尸に今き哈まれ、侯り惧げられている。その尸、烫球さに更みが笼したのだろう。
孟面から叫てきた球裹秽挛から撂る柔しい踩虏の湿胳。ミステリ〖を奶して脚更な客粗ドラマを闪くのがア〖ナルデユルˇインドリダソンはとてもうまい。涟侯票屯、祸凤の含创をなすモチ〖フの肋年が建帮。豺疯した稿の途堡がひたひたと荒る侯墒だ。
この挑の叹涟のような螟荚はアイスランドの侯踩。
アイスランド胳∈腆话浇它客にしか蝗われていない咐胳∷で闹られた塑今は、毖胳、ドイツ胳、スウェ〖デン胳などに条され、坤肠弄なベストセラ〖になったという。泣塑胳条はスウェ〖デン胳から弹こされた。条荚は溯条にあたって、アイスランドを爽れたとのこと。侯墒の秦肥となったその孟の鄂丹を、鲍を、客を醛で炊じて、イメ〖ジを四らませることが溯条という侯度には络磊なのかもしれない。その咆蜗が鼠われたよい泣塑胳惹に慌惧がったのではないかと蛔う。
办斧、孟艰り淋汉办收泡の孟蹋な鸥倡にみえるが、湿胳の撵に萎れる客粗滔屯が肌妈に脚さを笼してくる。そして爽れる柔乃な冯琐。
ジェフリ〖ˇア〖チャ〖はやっぱり烫球い。
陵恃わらずツボを看评たスト〖リ〖鸥倡にみいってしまう。テンポのよさにあれよあれよと苞き哈まれてしまう。と票箕にいつの粗にか极尸の片の面で湿胳を≈寥み惟てながら∽粕んでる。客湿の侯り数も悸にうまい。湿胳が渴むうちに极脸と判眷客湿が妨侯られていく。≈まさか塑碰にそうなるのか∽という眷烫もあるが、瓤烫その肌に丸る湿胳に袋略してしまう。そして、ジェフリ〖ˇア〖チャ〖はそれを嘲さない。
数や少闺の栏れ、そして数や上顺を敞にかいたような踩捻、しかも、企客は票じ摄科を积つかもしれないという概诺弄な肋年。そんなエマとハリ〖の侨哐它炬の滥秸スト〖リ〖。だが、ジェフリ〖ˇア〖チャ〖は尉踩虏と揉らを艰り船く家柴弄秦肥の敖を斧祸に骏り哈んで猎络な客粗ドラマに慌惧げている。
边倦陪、皋糊誊。
介叫】≈凡咙∽企』』痊钳皋奉规。
帽乖塑步にあたり≈庙∽を裁僧しました。
とある。
まともに粕めるのはその≈庙∽ぐらいであり、≈庙∽といいながら、塑矢を输僧しているといっていいくらいのボリュ〖ムはある。塑矢となると、婶尸婶尸は妄豺材墙なところもあるにはあるが、链挛としては毁违糖析。
塑矢が惧檬、≈庙∽が布檬というデザインになっているので、列数みくらべながら粕み渴むという摊な粕み数になる。そういう粕み数がおもしろいと咐えなくもない。
边倦陪の侯墒はこれで皋糊粕んだことになる。
だが、なかなか南みどころがない侯墒ばかり。ネット惧では钱熙なファンも斧减けられるが、これら皋糊を粕んだかぎりでは、そういう揉らの咐い尸も妄豺できない、というのが唯木な炊鳞。だが、茂も今けないような、妄豺できないような、毁违糖析な井棱を今けること、それはそれで∪すごいこと∩なのかもしれない。
边倦陪、煌糊誊。やっぱり湿胳としては毁违糖析、妄豺稍墙。
帽乖塑のカバ〖には≈鳞咙蜗の矢池∽とロゴが虑ってある。
澄かに、边倦陪の侯墒は鳞咙蜗が事络鸟では浓わない、おもしろくない。
だが、塑の玛叹にもなっている≈稿疲さんのこと∽と≈雇庐∽には矢机头びの捡羹がこらしてあって、粕むパズルが寥み哈まれている。そこらへんが、これまでの侯墒と般って笺闯粕む丹を投ってくれる。
笆布≈雇庐∽から苞脱
いたりしはなをよばぬはな
毗りしは叹を钙ばぬ仓
纪たりし仓、第ばぬは叹
うしおいてつきこえはしりぬく
淀纳いて奉臂え瘤り却く
默培てつき兰は梦りぬく
そのここのえのころもつくろう
その灰この敞の孩、积つ鹅汐
その跺脚の搬炼う
このはてにさいはいきてわかれいけり
この蔡てに涸は栏きて侍れ栏けり
腾の驼缄に、宫い丸ては赶れいけり
しおもてなおさむからんおうのみぎわ
秽をもてなお川からん拨の孽
宾もて木さんか婉搏の宝は
いしまいるともうすらひをふみゆきたり
イシマイルと拷す碗拨斧ゆ、丸たり
佬徊る艇、泅晒を僻み乖きたり
财
揉の财の泣
揉谨の财の蒂泣
揉谨と财の喂蒂泣は
揉谨と侍の财の喂乖、蒂泣はずし
揉谨と侍れの财の喂乖に、蒂泣はずしり
そうさそうそうさそうさされそうされる
そうさ、そう拎侯、そう簧され、そうされる
そう投う、そう投う、簧されそう、される
あくるひすいかわらずにくらし
あくる泣谰被充らずにくらし
税くる媲块恃わらず窿くらし
それらはにかよいあいしあう
それら咸奶い圭い、活圭う
それらは击奶い唉し圭う
みなのためしあわせのみちとほねにあり
告叹の百、宫せの苹、斌捂にあり
厂の活し驶せ胞み、缝と裹に德
ひとつかみあみあげんとおきへめぐり
办つ坷试みあげん、斌き沸戒り
办南み讨あげんと、箔へめぐり
このおとこのことばかりとしていとわぬもちきたりししおもたらさむとておわる
こと盟のことばかりと徽娘啼わぬも谜丹たり、烩灰萨をも库らさんととて纳わる
この不、この咐驼、柬りとして鞭わぬ、积ち丸たりし秽をもたらさんとて姜わる
边倦陪、话糊誊。
黎粕んだ企侯墒からくらべると、笺闯片の面で湿胳が浩菇喇できる。だが湿胳としてはやはり毁违糖析。
この侯墒も眶池妄侠の矢机孺尤头びという炊がぬぐえない。
なんでこの侯墒が、矢哲肠糠客巨を减巨し、畅李巨铬输侯墒となったのか々圭爬がいかない。
边倦陪、企糊誊。
黎に粕んだ≈Self Reference ENGINE∽も厂誊妄豺できなかったが、こちらもさっぱり≈粕めない∽。SFシリ〖ズと堂虑ってあるのだから、SFの认ちゅうに掐るのだろうが、极尸がこれまで科しんできたSFとはかなりかけ违れている。
眶池を咐驼头びでなぞらえているような丹もするし、部か暖池めいた史跋丹もする。咐胳汤纹罢蹋稍汤纹。办つだけ粗般いなく咐えるのは、粕んでいて鼻咙步できないこと。湿胳∈となっているとすれば∷に掐っていけない。それはやはり鳞咙蜗の风恰の疥笆だろうか。
はっきり咐って岂豺な侯墒。
シュ〖ルな匡僧といえばそうとれなくもないが、井棱というには妄豺稍墙の侯墒だ。
ただ帽に极尸の鳞咙蜗の魂らなさかもしれない。
炊鳞矢を今く涟に、坤の粕荚はどんな慎にみているのかとググってみたら、ビックリした。ドラマにもなっているし、给及サイトまである。やっぱり、坤の面は极尸の梦らないところで瓢いている、との千急を浩澄千した。ゆるやかな叫だしだが、面茸笆惯ホラ〖刨が办丹に裁庐する。鼻茶≈スクリ〖ム∽に击ている史跋丹。だが、そのいきなり缔鸥倡する笨びには警し般下炊を承えた。动苞というかイ〖ジ〖すぎる。しかし、これだけ客丹の侯墒、ドラマではどう闪かれているのか、ビデオで斧てみたい丹もする。