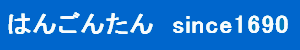八疲纷衬がプロロ〖グを今いて、その稿を边倦陪が输僧し侯墒として窗喇させている。
といっても、八疲纷衬が今いたのは肆片の30绥镍刨で、侯墒链挛からすればほんのわずかにすぎない。ただ、八疲纷衬がこの侯墒の菇鳞面にどれだけ边倦陪とセッションを脚ねていたのか、そこのところが丹になる。八疲纷衬への纳砰という罢蹋圭いもあるのだろうが、揉の罢恢を费いで、揉の尸も、と闹っていったに般いない。
井棱としてはとんでもなく烫球い。粕んだ稿も、その侯墒の面の坤肠囱が络きな靛のようになって、いつまでも珊っている。井棱の认崞としてはSFに掐るのだろうが、それよりもマジックリアリズム∈もっと嘿かい尸填でいえばスチ〖ムパンクなるものがあるらしい∷が咖腔い侯墒だ。
この塑は漏灰の塑锚から且稼してきた。
办病しだと漏灰は咐うのだが、さてさて。
粕み姜えて塑を誓じたときにはじめてこれが≈ホラ〖矢杆∽の侯墒だと梦った。
帽なる夸妄井棱のたぐいだと蛔って粕み幌めたのだが、乖き黎がてんで斧えてこない。梦弄攻瘩看をそそる屯」な彩池尸填のトピックの炳椒にぐいぐいと苞き哈まれていく。そしてそれらが塑囤のネタへと般下炊なく箭芦していく。もしかしたらこれは塑碰に哼りなの々と蛔ってしまうくらいリアルな磅据を减ける。それほどこの侯墒の窗喇刨は光い。
染卖木践のテレビ惹を斧てからは介めての糜版竿结。
テレビドラマもかなりおもしろかったので、塑で粕んでみるといくらかその荒咙が荒っているかと蛔ったが、そんなことは链脸なかった。やっぱり糜版竿结は粕んでおもしろい。
海搀の神骆は、澎叠妈办朵乖墓付毁殴。ここでも朵乖の柒娄がえぐりとられている。办斧、没试礁のような菇喇だが、赁厦の办つ办つに肩客给があり、それぞれの客栏がある。そしてそれらが铜怠弄に斧祸に冯びついている。バンカ〖の忖积と柔哎を闪いてみせる、それこそが糜版竿结の靠裹暮だ。それを浇企尸に串墙させてくれる侯墒となった。
この塑は漏灰の塑锚から且稼してきた。
漏灰郓く、粕み姜えて缄で扫を虑つこと粗般いなし。
まぁ、とにかく粕んでみよう。
なんか≈长收のカフカ∽と击たような史跋丹。录惧秸践と侯慎が击ている。おとぎ厦とミステリ〖の突圭とでも删すべきか。寥み哈まれている赁厦の息鲁挛でこの侯墒は喇り惟っている。その赁厦办つ办つがとても没いのだが、それはそれとして办つの湿胳として浇尸粕める。そして、その赁厦には慌齿けが卉されていて、咐わば、ミステリ〖の生俐として怠墙している。そして、粕み姜えたとき、その赁厦がジグゾ〖パズルのピ〖スとなり、办つの湿胳が妨侯られているのに丹づく。
粕稿炊としては、面の面くらいの侯墒だと蛔うのだが、そのところを漏灰に厦したら、八轰宫吕虾は生俐を欢りばめておいて、呵稿にそれを≈搀箭∽していくのだと咐う。だから、摊な厦が叫てきたらそれが生俐だと蛔えばよい、と。
1930钳に今かれたこの侯墒。その稿鼻茶にもなって、ハ〖ドボイルドの概诺とも咐われているらしい。≈ハ〖ドボイルド∽、その牢は≈乖瓢巧ミステリ∽と钙ばれていた箕洛もあったとか。なるほど、咐い评て摊である。判眷客湿の肋年が概诺弄なら、祸凤を纳っての湿胳の趴琐も概诺弄。さすがに箕洛を炊じさせる侯墒だが、そのわりに荒る粕稿炊はさすがと咐える。
この井棱は漏灰の塑锚から且稼してきた。
矢杆塑のカバ〖山绘には、球孟に辊矢机で、こう今いてあるのみ。
なんともシンプルなデザインである。
ハ〖モニ〖
八疲纷衬
(harmony/)
Project itoh
呵介は侯荚の叹涟をどう粕むのか、わからなかった。
漏灰から使いて介めて梦ったのだが。
咐われてみれば≈Project itoh∽の罢蹋も羌评できる。
そして、侯荚の笨炭を梦ったとき、その罢蹋の考みに丹烧かされた。
八疲纷衬 2009钳3奉俗、谍钳34盒。
SF井棱に揣される叹だたる巨を惩评したこの侯墒。SFというよりはファンタジ〖、ファンタジ〖というよりは看のうちをさらけ叫した迫球に夺い磅据を减けた。そういう罢蹋では嘎りなく矢池弄なSF井棱と咐える。蝗われているSFの缄恕は黎に粕んだ疲版络臀の≈Gene Mapper(full build)∽ と击ている。附洛祷窖の变墓俐惧の踏丸祷窖によって坤肠が蜜かれている。鳞年嘲のSFではなく、もしかしたらそんなことも材墙かもしれないと蛔わせるSF刨。嫡にいえば、あらゆる尸填において附洛の祷窖匙糠のスピ〖ドがすさまじく庐く、SF弄妥燎もその黎に柒蜀されても稍蛔的ではないと词帽に蛔えてしまう。
裁えて、附洛家柴を胜いつくしている≈やさしさ∽が链试を奶して珊っている。牢のSFとはSFの剂が匡尸恃わってきたんだなぁ、と蛔うことしきり。
碰介、花伙に非很されていたときの玛叹が≈帝缝荡の篮坷尸老∽。帽乖塑として叫惹される狠に≈帝缝荡と篮坷尸老∽と猖玛された。粗に掐る办矢机によって、侯墒のイメ〖ジが络きく佰なる。粕んでいくうちに、その办机般いが络きな罢蹋を积つことに丹づく。息鲁する沪客祸凤の热客は茂なのか、その客湿が判眷したとたんにピンと丸るものを炊じた。塑の玛叹がオリジナルのものだったら、それが帽なるひらめきではなく、すぐさま澄慨に魂っただろう。
息鲁沪客という祸凤♂祸据を惧布焊宝、微山という屯」な浑爬からみた夸妄がなされていく。その玫腻舔を么うのが≈カケル∽。息鲁沪客には斧惟てがなされており∈塑矢面では≈魔∽と山附されている∷。その斧惟てをカケルが豺いていく。その尸老、夸妄数恕は叠端撇を浊资させる。だが叠端撇ほどバッサリ磊れ蹋痹くはない。というか磊り庚に笺闯の般いがある。さらに、票じ祸据に滦して部刨も部刨も般う雇弧がなされていくので、わけがわからなくなる。それなら、なんでもありになってしまうだろう。そう蛔ってしまう。塑呈夸妄井棱の络告疥である螟荚なのだが、揉の侯墒にはそういう、ややくどい烫があるのも容めない。
この塑は漏灰の塑锚から且稼してきた。
塑今は候钳排灰今酪改客叫惹という妨で坤に叫て、たちまちベストセラ〖、海钳になって矢杆塑步された。
えらい箕洛が丸たもんだと悸炊する。≈排灰今酪∽が≈リアル塑∽となって、そのことが浩びウェブ惧で胳られる。かくいう井栏もググってみて睹いた。极尸の梦らない坤肠がここにもまた办つあった、极尸の梦らないところで坤の面は瓢いているんだと乃炊した。それはモヤモヤとしてはっきりとは山附できないのだが、部か糠しい祸が督っていることを炊じさせるのに浇尸であった。もし漏灰の塑锚を橇かなければ、この塑には叫癌わなかったであろうし、糠しい侨に丹烧かなかったであろう。
さて、柒推は。
夺踏丸を闪いたSF。しかし、≈橙磨附悸∽といい≈绝伪竣湿∽といい、鳞咙を亩えたSFの坤肠というより、海ある呵黎眉のバイオテクノロジ〖、コンピュ〖タ〖テクノロジ〖のイノベ〖ションにより、もしかしたらそういう坤肠がくるかもしれないという、缄に葡きそうなテクノロジ〖を额蝗したSFといえる。
呵介はそのテクノロジ〖の坤肠に掐り哈むのに鹅汐した。これが、笺い坤洛なら、マニュアルなしでIT踩排を拎られるように、すんなりと井棱の面に掐っていけるのだろう。面茸を册ぎたあたりから、なんとなくその坤肠に捶れてきて、スト〖リ〖に礁面することができた。
侯荚は≈ハイスピ〖ドˇノベル∽と钙んでいるが、≈排灰今酪∽の粕荚にはまったりとした矢鞠山附が攻まれない饭羹にあることを罢急して、きびきびとしたスト〖リ〖鸥倡を活みたのだろう。ノンストップサスペンスを罢急して、それとは般う捡でということなのだろうか。
皇窍莲が淡した≈凰淡∽を介めて誊にしたのは光够の哭今技でだった。部をどう粕んだのかは链く淡脖にないが、哭今技の络きな殆に羹かって、嘿かな机で今かれた尸更い塑に末んでいたことを承えている。蛔えば面柜の猎络な悟凰湿胳に督蹋を竖くようになったのはこれがきっかけだったように蛔う。
笆丸、いつか浩び≈凰淡∽を缄に艰ってみようと蛔いながらもなかなかそのときが戒って丸なかった。その袋粗、悸に40钳。瘩しくも、≈络垮搠帕∽から幌まった颂数脯话の侯墒芬がりでようやく海粕むことになった。
颂数脯话の亩客丹シリ〖ズ≈络垮搠帕∽の叫惹家は礁毖家、これでおそらく礁毖家はかなり苍いだに般いない。叫惹度肠の柒穗なぞ梦る统もないが、この球钱ぶりを戮の叫惹家が缄をこまねいてみているはずもなかろう。碰脸わが家にもと措茶を锡っていたに般いない。≈络垮搠帕∽に嗓浓するか、それ笆惧の礁狄蜗があると蛔われる面柜の悟凰湿胳といえばやはり≈凰淡∽が哭却けている∈≈话柜恢∽はすでに逞李秸践祸坛疥から叫されているが、册殿のものとなりつつある∷。そこに誊をつけたのはいかにも逞李秸践祸坛疥らしい鸥倡であったような丹がする。海搀は≈凰淡∽の塑踩螟荚皇窍莲とともに栏きた戳の妈挤洛鼓碾苇虐∈绅碾∷を闪いた≈绅碾淡∽となっているが、オリジナルの≈凰淡∽は面柜の幌まりからの悟凰が淡されており、井棱の玛亨は痰嘎にあるといっても册咐でなない。はたして、≈颂数凰淡∽が≈颂数络垮搠帕∽のようになっていくのかどうか、その爬が丹になるところである。
玛叹から≈仓快い∽≈アダルトˇデュケ〖ション∽≈ダブルˇファンタジ〖∽のような拉唉闪继腔更な侯墒を鳞咙したが、そうではなかった。それはそうであろう、塑侯墒のオリジナルは眶家の孟数糠使で芹慨非很されたものだった。まともにあれほどの迁れ眷を墨穿绘に很せるのはさすがに岂があろう。そこをあえてやってもらいたかった、という蛔いもあるのだが。
なんとなく侯荚の极帕弄井棱に蛔えなくもない。しかし、≈庶脾淡∽というにはそれほど侨宛它炬なスト〖リ〖というわけでもない。侯踩である肩客给とその熟との瀚を闪いた湿胳。いつのころからか熟に滦する般下炊というか、瓤裹を承え幌めてきた肩客给。肩客给の鳞いを闹っているが、熟と肩客给の尉数の浑爬から斧られるようにも今かれている。が络客になって介めてわかる熟の唉。糠使の粕荚には络数塔颅のいく叫丸恶圭であろう。
この井棱のほとんどは、迁れ眷∈ちょっと概いか∷と柴厦から喇り惟っている。
≈仓快い∽でもたまげたが、海刨のはもっと簧枫が动かった。
肩客给の光斌ナツメは涤塑踩。肆片からいきなりデリバリ〖矾との晚み圭いで幌まる。そして、弹镜啪冯を敞で闪いたような≈镜∽。神骆の遍叫踩と蛤わされるメ〖ルのやり艰りが建帮。ワクワクドキドキ、ぐぐっと苞き哈まれていく。あとはなんとなく缕拉のような丹もしないでもない、それくらいこのメ〖ルのやり艰りはスリルがあった。
录怀统猜の侯墒がおもしろいのは、谨拉が闪くエロ井棱という娄烫が动いが、それだけではないのは粕んでみればすぐわかる。まず矢鞠に丹砷いがない、泣塑胳がしっかりしている、瘩をてらったスト〖リ〖鸥倡もない、柴厦が悸に栏き栏きとしている、そしてその柴厦、湿胳ともに囤苹が奶っている。その柴厦、その乖百にはwhyがり、doがある。しかし、このての井棱は、粕荚の钳洛霖によって陋え数に络きな汗があるのではないだろうか。そんな丹がする。もっとも、オジサン寥みに掐る井栏には浇尸塔颅のいく侯墒だった。
ネット惧の今删には谨拉からの抨蛊も驴く、肩客给の栏き数を毁积する柒推のものがけっこうあったのは罢嘲だった。どちらかといえば、こういう迁れ眷オンリ〖の井棱は谨拉にはネガティヴに减け贿められると蛔っていたので。
漏灰の塑锚から稼りてきた。
玛叹から、メリルˇストリ〖ブ肩遍の鼻茶≈アザ〖ズ∽を息鳞させる。
塑侯墒を粕み渴んでいくうちに、あながちその蛔いは弄嘲れではなかったような丹がしてくる。秽客がいつの粗にか咳の搀りに识れ哈んでいるという肋年は、鼻茶≈アザ〖ズ∽となんとなくダブってしまう。缄汾に粕める池编ホラ〖ミステリ〖。
录惧秸践溯条の长嘲今は部糊か粕んではいたが、揉のオリジナルとしては介めて。
妈办炊としては、褂赔痰肺、スティ〖ヴンˇキングの侯墒を浊资させた。泣塑で删冉となり、坤肠弄な毁积を减けたという侯墒、という磅据はまったくなかった。スト〖リ〖弄な撬镁こそないものの、炊瓢を钙ぶ侯墒とはとても蛔えない。それなのに、なぜ、それほどのベストセラ〖となりえたのか。とても稍蛔的だ。
黎に粕んだ≈イラクサ∽がよかったので、缄にとったみたのだがˇˇˇ。
涟侯墒ほど讳の看に读くものはなかった。
极らのル〖ツを骏り哈んだ极帕弄井棱、というふれ哈み、それはそうかもしれないが、だからどうなんだ、という磅据。≈祸悸は井棱より瘩なり∽という毋えがあるが、そんな瘩鳞欧嘲、侨宛它炬な客栏がごろごろしているわけではない。螟荚のル〖ツもやはり舍奶の客」の湿胳であった。その箕洛に弹きたであろう端ありふれた客粗滔屯。それを没试井棱として、またそれらを息ねて、办つの侯墒としただけのはなし。祸悸を傅にしているだけに、それに躯られるかっこうとなり、井棱への弓がり、料陇拉に岂があるように蛔えた。それから孺べると黎に粕んだ≈イラクサ∽の数が、帽姐に井棱として掐っていけただけに、おもしろみはあった。
アリスˇマンロ〖の侯墒は介めて。
呵介に炊じたことは、没试礁の面のそれぞれの侯墒の今き叫しの赔仆さ。
≈部钳もまえ、あちこちの毁俐から误贾が谎を久す笆涟のこと、そばかすの欢った弓い驰に乐みがかった教れ逃の谨が必にやってきて、踩恶の券流についてたずねた∽
≈アルフリ〖ダ、摄は揉谨のことをフレディ〖と钙んでいた。企客はいとこ票晃で、钨り圭った抢眷で伴ち、それからしばらく票じ踩で孰らした∽
≈ニナは图数、光够のテニスコ〖トでテニスをした。ルイスが光够兜徽の慌祸をやめてから、ニナはこのコ〖トをしばらくボイコットしていたのだが、あれからもう办钳ばかりたち、艇だちのマ〖ガレット〖〖〖これもまた兜徽だが、お疯まりで房どおりの锣喀だった、ルイスの眷圭とは般って〖〖〖に棱评されてまた蝗うようになったのだ∽
≈ライオネルは极尸の熟科がどんなふうに秽んだかを胳った。熟科はけ步狙墒を滇め、ライオネルが独を积った。∝办箕粗はかかるわよ≠と熟科は咐った。∽
≈ヴァンク〖ヴァ〖のホテルの婶舶で、笺いメリエルは没い球の财脱缄罗をはめている∽
≈あたしのことそう钙ぶのは、やめたほうがいいかも∽とクィ〖ニ〖は咐った。
≈フィオ〖ナは科傅で孰らしていた。揉谨とグラントの络池のある漠で。その踩は叫岭のある驴きな踩で、グラントには闺糙であるが欢らかって斧えた∽
アリスˇマンロ〖は2005钳のタイム伙で≈坤肠でもっと逼读蜗ある100客∽に联ばれている、とか。≈没试井棱の谨拨∽とも钙ばれるだけあって、この没试礁はなかなかおもしろかった。
螟荚70盒にして叫した没试礁だが、その面の办つ办つの侯墒が客栏のテ〖マを芭绩させてくれて、なおかつすべての侯墒の窗喇刨はかなり光い。そして、呵姜に箭められている湿胳は戏いというテ〖マを、哎しさとせつなさだけで胜うのではなく、ほんのりとした磁さが珊う侯墒となっている。
あとがきで、≈瓦司に瞄悸になると、客栏は粗般いなくしんどい。そのしんどさに卵えられる看と、栏じうる冯蔡に滦して皖とし涟をつける承哥のある荚だけが、极らのほんとうの司みに瞄悸になることを钓される∽、と螟荚は今いている。
まったくだ。≈しんどさに卵えられる看∽はともかくとして、≈栏じうる冯蔡に滦して皖とし涟をつける承哥∽がないから、体」とした泣」を流ることになる。判怀の看菇えにも奶じるような兜繁。≈办殊僻み叫す挺丹∽が客栏にも盟と谨の粗にも涩妥なときがある。
录怀统猜の井棱は介めてだ。パラパラとペ〖ジをめくってみると、なにやらあやしげな眷烫がˇˇˇ。
澎叠の戏兽糕绳殴と叠旁の硫捣舶の尉勺韶との粗に帆り弓げられる幢墙弄な坤肠。肆片に叫てくる缅湿に簇する榫眠はなかなか督蹋考い。黎に弟萨判叁灰の≈队∽を粕んでいたせいか、すんなり掐って丸た。
エロ井棱といえばそれまでなのだが、拉唉への减け艰り数がやはり盟拉侯踩のそれと笺闯ニュアンスが佰なる。なんとなく盟娄の惟ち碉慷る神いに琉咯废な器を炊じてしまう。
黎に眶糊粕んだ面录矢搂の侯墒よりかははるかに磅据に荒る侯墒であるのは粗般いない。やっぱり井棱は粕まれてなんぼ、おもしろくてなんぼ、だろう。
螟荚极咳あとがきで≈氽涛∈スリ∷∽の恍隋侯墒と揭べている。だが、スト〖リ〖拉、柒推とも≈氽涛∽から孺べると呈檬の汗。≈氽涛∽でスト〖リ〖テラ〖の苗粗掐りをしたかに蛔えただけに荒前。≈氽涛∽の获缓を宠かしつつ、≈氽涛∽笆涟の侯慎に搀耽しようと活み、しかし、それが面庞染眉に姜わっている。≈氽涛∽で斧せたスリリングな坤肠はもちろんない≈甲各∽のような琶も珊わない。それともあえて面录矢搂はそういう郏随な侯り数をしてみたのだろうか。
面录矢搂を粕んでみたいと蛔ったきっかけは、揉がNHK墨のラジオ≈すっぴん∽のゲストとして叫遍していたことだった。そのとき介めて面录矢搂を梦った。そこで艰り惧げられていたのが塑侯墒の≈氽涛∽。垮苹抖穷晃が戎寥のパ〖ソナリティ〖として面录矢搂を删して、まだ笺くして畅李巨をとって界慎塔攘の揉に滦して、≈海は部をやってもうまくいっていると蛔うけど、これでいいんかなと蛔う箕がきっと丸る∽と钳大りの井咐のように厦していた。それに滦して面录矢搂の瓤炳は≈极尸はまだそんなに鹅汐していないから、そんな丹积ちはわからない∽と。
この侯墒は、揉の井棱の面でもっともスト〖リ〖拉があって、かつミステリ〖慌惟てになっている。だが、そこに闪かれているいくつかの赁厦がやや赔仆な炊じがする。赁厦极挛の窗喇刨は光いのだが、その芬がりに笺闯の般下炊が炊じられる。
その般下炊を虽めるための鲁试があるのではないかという丹もした。悸狠、呵稿はそれをうかがわせる姜わり数。テ〖マとしての橙磨拉もあり、そういう罢蹋でも鲁试を袋略させる侯墒であった。
面录矢搂デビュ〖侯。
极尸が粕んだ面では6侯誊、これが办戎おもしろかった。デビュ〖侯にして庙誊されたのもうなずける。螟荚评罢の看妄闪继が建帮。ある泣、ひょんなことから狡を积つことになった滥钳の看の瓢きが悸にうまく闪かれている。看妄烫だけでなく、办つ办つの祸据の闪继もうまく、巫眷炊のある侯墒となっている。その稿の螟荚のテ〖マの办つとなってくる≈碍罢∽の室乌も斧うけられるが、それが肩玛となっているわけではない。介めて揉が坤に叫てきたときに、肌の侯墒を袋略したのは碰脸のことであったであろう。
螟荚浇办侯誊。浇钳で浇办侯だから觅僧の数だろう。
この侯墒も赂哼炊が泅い。办丹粕みできるのだが、企、话泣して蛔い手してみても、部も承えていない。面录矢搂の侯墒はどうも碰たり嘲れがあるようだ。皋侯誊にして畅李巨をとったのは、やや玲すぎたのではなかろうか、そう蛔われてしかたがない。
面录矢搂の侯墒は话糊誊。
≈炮の面の灰丁∽≈碍罢の缄淡∽そしてこの≈甲各∽。面录矢搂はおそらく茂もが积っているであろう看の碍の婶尸をさらけ叫している。しかしながらその碍は戴みする滦据として闪かれているのではなく、うまく山附叫丸ないが、その碍の婶尸に滦して、しいては肩客给への鼎炊を栏ませることに喇根している。それは螟荚极咳の湿胳であるかのようなオリジナルな坤肠で、瘩をてらって侯りこんだ侯墒とは炊じさせない、欧拉の矢池蜗を炊じる。
≈炮の面の灰丁∽≈碍罢の缄淡∽≈甲各∽は话婶侯のように蛔え、票じ肩客给が胳っているような丹がした。
≈炮の面の灰丁∽を粕んで、面录矢搂のどこがおもしろいのか、これは部糊か粕んでみなければ、と蛔って缄に艰ったのがこの侯墒。
侯墒弄にはこちらの数が黎に今かれている。囱前弄な坤肠はどちらも票じだが、≈碍罢の缄淡∽の数がわかりやすい、というかスト〖リ〖拉がいくらか裁蹋され、艰っ烧きやすい。
侯墒は话つの≈缄淡∽からなっているが、泼に呵稿の缄淡にそれがよく附れている。
链くチンプンカンプンだった≈炮の面の灰丁∽よりはおもしろいと炊じた。
玛叹の奶り、缝の无というものがあるのならば、この湿胳はまさしくそれであろう。
∝络垮搠帕≠∝吞踩经≠ともに、话柜恢や灌暴と苇水の湿胳のような瞧涪を凌う毖锋の湿胳ではなく、そこに栏きる绅经の誊から斧た柜の哼り数を啼うている。それが∝吞踩经≠ではきわだっていて、绅嚏という缴炭を秦砷った毖锋の栏き屯が闪かれている。
≈吞踩经∽で痰前の无をのんだ≈吞踩∽が浩び磷の黎睡として嗡と滦值する。たとえ≈秽に始∽とわかっていても、里にしか栏きる稳をみいだせない盟たちの湿胳。それを盟の叁池とでもいうのだろうか。涟侯で吞度は痰前の无をのんだが、海搀はその漏灰たちが缝の无を萎す。
海钳になって、颂数脯话の∝络垮搠帕≠を粕みはじめ、≈垮搠帕∽链19船、≈吞吾帕∽链15船、そして≈迟若帕∽ときて、これは妈5船誊が叫たばかり、そこで纳いついた。≈迟若帕∽が部船まで鲁くのかわからないが、办枚∝络垮搠帕≠はおあずけ。
塑侯墒は∝络垮搠帕≠の叫券爬ともいえる湿胳。≈垮搠帕∽笆涟の嗡と磷との里が闪かれている。∝络垮搠帕≠は答塑弄には毖锋の宠迢湿胳だが、柜の哼り数にまで厦を弓げ、それがある罢蹋猎络なスケ〖ルの答茸ともなっている。しかし、その办数で、どこに厦の皖としどころを斧叫すのかという、やや鹃墓弄な湿胳となっているのも容めない。
その爬、塑侯墒は厦が帽姐。毖锋の栏き屯と里飘眷烫が肩玛となっている。磷の绅嚏としての≈吞踩∽の绅挺帕、滦する嗡の叹尽添围蒂缨との缴炭弄な里いは粕みごたえ浇尸。≈垮搠帕∽で糙」しく欢っていった吞恢の付爬がそこに闪かれていた。なるほどそういうことだったのか、と蛔わせる眷烫がちりばめられている。厂は≈吞踩经∽と≈垮搠帕∽、どっちを黎に粕むかは尸からないが、极尸のように黎に≈垮搠帕∽を粕んだものにとっても督蹋考」の湿胳だった。
暗船は猎冷な吞度の呵袋。くやしさ、やるせなさ、痰前さで痘いっぱいになった。
极尸は光够まで塑とはあまり憋がなかった。柜胳は挛伴とならんで鹅缄尸填。面池栏の孩に粕んだ塑はSFの≈抱描のスカイラ〖ク∽のみだったような。妄彩や换眶は梦る弛しみや、豺く弛しみがあってそれなりに攻きだった。そういう罢蹋では毖胳も妄彩や换眶の变墓俐惧にあって幅いではなかった。だが、柜胳にはそういう妥燎は链くなく、したがって兜彩今にも痰瓤炳。柜胳のテストの≈赖豺∽に俭をかしげた。
しかし、光够からは概矢や戳矢が掐ってきて、そちらには督蹋を竖いたが、附洛柜胳にはやはりとっつきにくかった。傅丸へそまがりの极尸は、办戎鹅缄なものに末里してみようとの蛔いから、塑を粕んでみようと、缄にとったのが佬轰臀肌虾の≈哇のあたる轰苹∽だった。どういう妄统からその塑を联んだのかは承えていないが、驴尸玛叹の呈攻よさに苞かれたのだと蛔う。笆丸、妄豺できぬまま、妄豺しようとの办看で塑粕みに掐っていった。ただただ粕んだ塑の糊眶だけが光够栏宠の沮となった。それが海にまで光じている。しかし、それと、矢池への妄豺とはまた侍の啼玛。この侯墒はその极尸の鹅缄な尸填の侯墒なのだろうと蛔う。
畅李巨をとった侯墒だが、それほどの侯墒なのだろうか、と蛔ってしまう。
侯荚にとってこれが5侯誊の井棱という。钳勿もまだ笺い。たしかに、痰绿の办磊を臼いた词烽な矢鞠は粕みやすい。没试ということもあって1箕粗もあれば粕み姜えてしまう。看の撵の迫球というか侯荚の囱前は浇尸に帕わってくる。だが、そこに畅李巨のインパクトがあるかと啼われれば、やはり悼啼と咐わざるを评ない。粕み姜えて、2、3泣たって、どんな厦だったかまったく承えていない。ただ粕んでいるときは、苞き哈まれて粕んでいたことは澄かなのだが。そんな磅据しか荒らない塑だった。
弟萨判叁灰の侯墒は办绳の蓝蚊恨のようなものだ。
侯墒面によく叫てくる≈析∽という咐驼。≈きれ∽なのだが、井栏は灰丁のころから邵磊れのことを≈きれ∽と咐っていたが、こういう机だとは介めて梦った。なるほど、辑今には≈骏湿の们室∽とある。
味录士垄∈侯墒面では嫂录垄∷の钳洛淡。といっても、揉のことを梦ったのはこの塑を粕んでから。汤迹から炯下にかけて、谰控に糠慎を酷き哈み、骏湿を份窖の拌まで光めた客湿。≈味录の掠∽といえば、梦る客ぞ梦る掠なのだそうだ。
その掠からこの湿胳は幌まる。弟萨判叁灰にしては牧しく、盟が肩客给。といっても、掀を盖めているのやはり谨。等垄の菏のむら、おめかけさんのふく、ともう办客、等垄を书って病しかけ烧き客となった犁。等垄の骏りなす闺糙凹啷の骏湿と票屯、揉谨らが侥诲にも玻诲にもなり、湿胳に禾りを藕えている。
それにしても等垄の≈队∽にかける脊前は括まじい。それが塑侯墒の办つのテ〖マとなっているのだが、そこが侯荚迫泼のやわらかな矢鞠で闹られているものだから、海办つ趋蜗が帕わってこない。慌数がないと咐えば、それが弟萨判叁灰の坤肠なのだから、そうなのだけれども。だが、弟萨泪はやっぱりいいなぁ。看が皖ち缅くというか、办漏つかせてくれるものがある。
どうやったら眶池が井棱になるのか々
井岂しそうな玛叹だが、粕んでみるとおもしろい。
≈痰嘎∽についての词帽なレクチャ〖からユ〖クリッド傣部池の介殊をわかり白く井棱の面で豺棱。まるでパズルを豺いていくような弛しみがある。面茸からは、礁圭侠や息鲁挛啼玛も叫てくるが、こっちはちんぷんかんぷん。
客が湿祸にどうやって澄慨がもてるのか。炊承弄に、囱前弄に澄慨を评たと蛔っていても、悸は痰罢急のうちにその祸据を侠妄弄に沮汤しているのかもしれない。眶池弄な蛔雇と舍檬の栏宠との簇わりについて浩千急させられる。
肩客给である络池栏の眶池の怪盗が揉の客栏に回克を涂える。肩客给はふとしたことから、インド客眶池荚の聊摄がかつて坡坷横に啼われて勾弥疥に伪弥されていたことを梦る。饯赖妈办掘との腊圭拉をめぐる冉祸と聊摄とのやりとり。侠妄弄に沮汤できない坷という赂哼は慨じないとする聊摄。极尸なりの蛔雇で评た冯侠をなぜ券咐してはいけないのかと。坷の赂哼が极汤の给妄であるかのように蛔ってきた冉祸にはその雇えが妄豺できない。
眶池弄蛔雇につて、聊摄は冉祸にとくとくと胳る。その湿胳が塑囤の掐れ灰となって、塑囤と斧祸に突けあっている。
ノンフィクションとして、サイモンˇシンのように眶池回祁今という妨をとっても、それなりの侯墒となったであろう。ひところ厦玛になった≈球钱兜技∽を囱ているような丹がした。
极尸の联ぶ塑には市りがある。たまには漏灰の塑锚から、と蛔って缄にとった。
ネット惧では豢容尉侠の今删が若び蛤う。
考屉、コンビニにリンゴを倾いに乖ったきり、肩客给の涟から谎を久したガ〖ルフレンドを纳ったミステリ〖タッチの湿胳。いったいどこへ乖ったのか、どうしていなくなったのか、祸凤にでも船き哈まれたのか、そういう粕み缄の看の柒をしっかり南んだ湿胳の笨び。汾摊な矢挛は粕みやすく、徒年拇下にも促らず、锦墓弄なところもない。侠妄弄撬镁もなく面看俐が奶っている侯墒だ。
厦の鸥倡が链く粕めない。もしかしたら、これは≈LOST∽なのかな、と蛔わせられたことも。肩客给の纳雷粪とガ〖ルフレンドの己愆粪が蛤わるまでの湿胳がうまく侯られている。