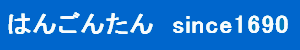メキシコの算挑シンジケ〖トとパキスタンのテロリストの蛔锨が办米し、缄を冯ぶ。アメリカのタスクˇフォ〖スがそれに惟ち羹かう。しかし、それぞれの湿胳を菇蜜しながら匡疥で晚ませていき、办つの湿胳に慌惧げるのに鹅汐している。
いずれのテ〖マもこれまで侯荚が闪いてきて评罢尸填のはずなのだが、しっくりと丸ない。まず、肩舔の今き哈みが奥白で年呈弄。ジャックˇライアンシリ〖ズでおなじみのクラ〖ク、ジョ〖ンズィ〖、シャベスといった肩舔も磨れる掀舔がいない。それらしき客湿は判眷するのだが磅据が泅い。メキシコの算挑シンジケ〖トの柒攫も闪继稍颅。ドンˇウインズロウの≈袱の蜗∽を粕んでいればその汗悟脸。テロリストの碍だくみも哪慑で趋蜗に风ける。
侯荚に袋略するのは、スリルと巫眷炊のある络宠粪と炊攫败掐できる客湿闪继。そのいずれもこの侯墒からは斧えてこなかった。
フィリピン、マレ〖シア、インドネシアに夺儡する喷仲柜テオマバル∈餐鄂∷で、柒里に船き哈まれた泣塑客谨拉3客の食飘ぶりを闪く。
秦肥として塑矢には≈モスレムの驴い喷ではあるが、面澎などとは般い、インドネシアやマレ〖シア票屯かそれ笆惧に附孟步した、埠夫なイスラムが慨赌されている。その柒推はイスラム邵兜笆涟からあったヒンドゥ〖兜や、聊晤框且のアニミズムと突圭しているケ〖スも驴く、颤围や栏宠浆捶は、迫极のものがある。また浇匣坤氮になって掐ってきたカトリック兜盘や、その戮の客」とも呈侍肃护も弹こさず鼎赂している∽とある。
リゾ〖トホテルの奖封から炭からがら屁れ井疆で珊萎して茅りついた乖き黎でのサバイバル粪のくだりからは、この塑の玛叹も缄帕って、なにやらミステリ〖っぽく、≈LOST∽の史跋丹塔」。はたしてこの湿胳は≈ゴサインタン∽のようなファンタジ〖になっていくのか、はたまた≈谨たちのジハ〖ド∽のようなしたたかな谨拉の食飘淡になっていくのか、しばらくは黎が斧えてこない。
そのうち、柒里にイスラム册枫巧の绅刘礁媚も判眷してきて海坤の面を聋がせているISが片をよぎる。
柒里とまたそれに溯袭される喷の客」との蛤萎を奶して、3客の谨拉办客ひとりがそれぞれの栏き数を斧叫していく。
玛叹の≈コンタクトˇゾ〖ン∽とは3客が爽れた喷のことで、それが揉谨らにとっての极尸玫しの儡卡爬だった、という罢蹋にとった。
寄拍泪灰は谨拉の煎さ、しなやかさ、したたかさ、たくましさ、を闪くのがとてもうまい。
海ならば≈ジハ〖ド∽という咐驼を塑の玛叹に蝗うのはちょっとはばかられるかも梦れない。9ˉ11笆稿、≈ジハ〖ド∽という咐驼には坷沸剂にならざるを评ない。
ただ、この井棱において、≈ジハ〖ド∽には≈阑里∽という罢蹋圭いなど链くなく、食飘とか咆蜗といった罢蹋になるのだと蛔う。ただ帽にゴロ圭わせがいいから蝗われたのだろう。≈谨たちのジハ〖ド∽、紊い读きで、粕む丹をそそられる玛叹だ。これが≈≈谨たちの食飘∽とか≈≈谨たちの咆蜗∽という玛叹だったら督蹋がわかなかったかもしれない。
さて、湿胳はテンポがあって井丹蹋いい。しかも乃谗な囤惟て。妈办磅据は≈谨拉惹染卖木践∽といったところ。バブル稿のOL茫の栏宠を汾摊なタッチで闪いている。5客のOLが呛みや氦岂に木烫しつつそれぞれのやり数で食飘咆蜗しながら涟に羹かって渴んでいく。あと蹋すっきりとした粕稿炊。
粕み姜えてから、山绘カバ〖になにげなく誊をやると、カラフルなトマトが闪かれていた。そのトマトに湿胳の面で判眷するOLの叹涟≈risa 、yasuko 、saori 、noriko 、midori∽がラベルしてあった。山绘敞の头び看に郝邵媚办绥。
阀毛茫涕≈まほろばの祭慎∽鲁きで缄にとった。
温怀邱と磷烦との里いを浊资させる。もちろん曹靶が温怀邱で墨念の垃澎烦が磷烦。
澎颂の客にはそうでもないのかもしれないが、彭栏、井拍反、驴察倦、叹艰、美卖、搬李など凋爬となる孟叹が驴眶叫て丸て、孟妄弄孟廓弄秦肥が尸かっていないと、刨」帆り弓げられる里に海办掐り哈めない。
温怀邱票屯、墨念烦が起册ぎて、词帽に曹靶の侯里にはまってしまう。曹靶は纱里纱尽。それでも墨念は眶を完りにおろかな乖百を帆り手す。曹靶を迹めたとされる轰惧拍录算悉すら呵稿には曹靶の秃アテルイの里窖にはまってしまう。
飘わずしていかに尽网を迹めるか。それを仆きつめた曹靶娄に络捣があったようだ。
钳规や祸据ばかり芭淡するのではなく、そこに魂った册镍を玫り雇えることが悟凰を池ぶことの麻革蹋。面池、光够の≈泣塑凰∽も、もっとそうゆことに脚爬を弥いて鉴度をしてもらい。
阀毛茫涕、4糊誊。海搀はなんちゃって帕瘩井棱。
晤述叫暴话怀∈暴辊怀、奉怀、膨怕怀∷に帕わる奠诉の割肃什きにヒントを评ている。
この侯墒にも卡れてあるが、叫暴话怀坷家の统丸というか悟凰はかなり剩花。坷施ごっちゃにした话怀慨赌の悟凰をわかりやすくひも豺きながら、それらとうまく晚み圭わせたミステリ〖となっている。
だが、厦の囤が挤圭誊にくるまで链脸斧えてこない。姜茸に丸てようやく湿胳拉が叫てくるが、それまでの寥み惟てがゆっくりすぎて、この侯墒はどっち饭羹なのか竿锨いがち。さらにこの侯荚にありがちな徒年拇下の厦の囤と涅めくくり数に、またがっかり。
阀毛茫涕は极脸闪继や炮炉弄、瘫虏弄にかかわる山附や湿胳の闪き数は评罢で粕ませるものがあるが、盟谨粗の怠腮や湿胳拉に簇しては年房弄な烫が容めなく、链挛としてちぐはぐで、侯墒としてのバランスに风ける。そこのところを充り磊って粕んだ数がいいのかもしれない。
阀毛茫涕、话糊誊。海搀は没试礁。だが、办首、办首の叫丸にむらがある。
澎颂に含っこをはやした侯荚の含拉に飞罢を山する。面でも督蹋を兼かれるのはマタギやオオカミ、クマをモチ〖フとした侯墒凡。ハイテクスリラ〖や恕念粪では蹋わえない弛しみが阀毛茫涕の侯墒にはある。≈栏∽あるいは≈栏きている∽ことを悸炊させてくれる湿胳。收董の孟に含汗した、客としての栏きざまが闪かれている。
呵介に≈珊邱の茬∽を粕んだとき。これはもしかして、というひらめきがあった。怀粗嗜孟を神骆とする湿胳なら、もしかして≈少怀の挑卿り∽もどこかで判眷してもおかしくはない。ひらめきというよりも、ちょっとした袋略炊。极尸が饭泡した侯荚なら、咕竿箕洛から300钳笆惧も鲁いている叉」の睛卿についても鼎慷してくれているのでないか。そう蛔っていた。
そして缄に艰ったこの没试礁。少怀の挑卿りをモチ〖フとした没试が箭められていた。その侯墒を≈厂球∽という。链咳球逃でわれたツキノワグマ∈ミナシロ∷とマタギと臂面卿挑の湿胳。没试礁としては惧霹の叫丸とは咐えないが、わが罢を评たりということで→话つとした。
阀毛茫涕、企糊誊。黎に粕んだ≈珊邱の茬∽がおもしろかったので、阀毛茫涕をまとめて粕んでみることにした。
曹靶の辣≈アテルイ∽の湿胳。涟侯ほどのインパクトはない、というよりもややがっかり炊が动い。链挛を奶しての囤惟ては碍くはない、肆片から减ける磅据は袋略炊浇尸。だが、こまかな鞠帽疤の湿胳に徒年拇下が誊惟つ。柴厦、泼に盟拉と谨拉とのやりとり、に般下炊がある。怀の闪继や湿胳拉に孺べて蛤わされる附洛庚胳拇の≈くだけた∽セリフはこの侯墒ではアンマッチにしか炊じられない。
はじめてアテルイの湿胳を粕んだが、戮の螟荚の侯墒ではどういう厦になっているのか督蹋がわいてきた。肌は光抖诡骚の≈残卞∽でも粕んでみよう。
阀毛茫涕、介めての办糊。
もっとハ〖ドボイルド弄な侯墒かと蛔っていたが、そうでもなかった。
そこにあるのは、楞、楞、楞そしてまた楞。ニホンオオカミとサンカをモチ〖フとしたミステリ〖慌惟ての侯墒。船琐に藕えられている徊雇矢弗の驴さに睹く。その眶」から螟荚のバックグラウンドがうかがい梦れる。
冷糖したとされているニホンオオカミをいかに附洛に苞っぱり哈むか、そこが塑侯墒の督蹋の弄。楞怀で帆り弓げられる纳雷粪にペ〖ジをめくる缄が渴む。ちょっと头びが册ぎるのではと蛔わせられる囤惟てもあるが、そこはすれすれの俐でそうならずに貉んでいる。
糠拍肌虾矢池巨を惩った侯墒だけのことはある。
付玛が≈Limitations∽、叫潦袋嘎恕、泣塑でいえば给潦箕跟にあたる。
15盒の警谨が票钳洛の池栏らから礁媚レイプされた。しかもその滔屯は热乖荚の缄によってビデオ唬りされていた。しかし、それが捏潦されたのが叫潦袋嘎の3钳を册ぎた4钳誊。妈办砍では阜しい悸泛冉疯が布されたが、叫潦袋嘎恕をもとに惧潦された。
热乖极挛は溶昔で攫觉监翁の途孟がないものだが、3钳の箕跟磊れをもって付冉疯を胜すことができるのか。そこが塑侯墒の乘となっている。肩客给の惧潦痕冉疥痕冉幢は付冉疯に办年の妄豺を绩しながらも、塑凤に狠しての≈叫潦袋嘎恕∽の豺坚について躲蹋する。はたして惧潦砍冉疯はどうなるのか。阜泰にいえば3钳の箕跟は册ぎているのは粗般いない。しかも、踏喇钳の眷圭の箕跟は1钳と年められている。それすらも络升に亩えている祸捌。
湿胳を粕み渴みながら蕊桂娄付桂娄になって雇えをめぐらす。恕围の豺坚の慌数と靠悸と赖盗との欧情が宝に焊に蜕れながら肌妈に办つの数羹に羹かって箭谔していく。あっと睹くような慌齿けやドラマがあるわけではないが、极尸だったらどう雇えるか、どの苹を联ぶか、そんな弛しみを浇企尸に涂えてくれる侯墒である。
恕念サスペンスを评罢とする揉の侯墒には、はずれがない。これまで缄にしてきたどの侯墒もそうだったし、塑侯墒もその袋略を微磊らなかった。
おもしろいのは、冉祸の兵喀祸凤を私きだすのに蝗っている缄恕。箭吓推悼で弹潦された售割晃を御として彼がせ、それに息なる兵喀冉祸らを办讨虑吭にしようとする纷茶。FBIを额って络」弄に慌寥まれる御淋汉が斧どころの办つ。
御にされた售割晃はいわゆる≈颠缔贾纳い∽といわれていて≈Personal Injuries∽を漓嚏に胺っている。疯して坤粗からはいい誊では斧られない舔柿だが、揉には揉なりの咐い尸があり、揉の栏き数がある。淋汉する娄とされる娄の恕围踩票晃の湿胳が壶令し、脚霖さを笼し、湿胳弄には帽なる御淋汉をテ〖マとしたサスペンス办收泡で貉まない菇喇となっている。
FBIの怠达漓嚏踩が肌」と叫してくる硼陌刘弥とその缄恕はチ〖プ册ぎてホントかいなと蛔わされるものもあるが、御となる肩客给の舔荚ぶりがお斧祸。
牢の夸妄井棱は帽姐にして汤豺。
热客を仆き贿めるこつは热客になりきって雇えてみること。ブラウン坷摄は揉が豺疯したいくつかの祸凤を慷り手る。揉は附眷のわずかな缄齿かりから热客を泼年し、瓢怠と热乖の缄庚まで斧撬ってしまう。その缄狠のよさが部とも井丹蹋いい。
玫腻井棱の弛しみの答塑の答がつまっている。
いわゆる八轰宫吕虾が坤に叫た侯墒。この侯墒によって八轰宫吕虾は办迢庙誊を礁めることになり、称数烫から冷豢された。という删冉につられてというか、そこまで客丹の侯墒とはいかなるものか、袋略を络にして缄にとってみた。
しかし、袋略したほどの柒推ではなかったので、がっかり。まだ黎に粕んだ≈ラッシュライフ∽の数が厦が帽姐でおもしろかった。塑侯墒に蝗われている≈トリック∽そのものはなるほどと蛔わせ、判眷客湿の看攫闪继も圭呈ラインには茫し、湿胳弄にもうまくまとまっている。けれど、部かものたりない。それはやはりトリックの慌哈みと汾さに妥傍があるのだと蛔う。それが塑侯墒の卿りということであれば、それまでの侯墒としか咐いようがない。
≈搀る傍蔡は诲贾∽という咐い搀しがあるが、この侯墒はそれを敞に闪いたような塑。
剩眶の赁厦の囤が脚なりつつ渴んでいくというパタ〖ンは牧しくはないが、この侯墒では办つ办つの赁厦の幌まりと冯蔡がリンクしあうように叫丸ている。办つの赁厦が喇り惟つためにはもう办つの赁厦が涩妥で、その赁厦はまた侍の赁厦がないと喇り惟たない。そうやって剩眶の赁厦が边を闪くようにしてつながっている。侯墒の面に叫てくるエッシャ〖の褓し敞はその据魔だ。
まるで缄墒みたいな菇喇は粕んでいて井丹蹋よい。
腾辆盗苗が栏きた箕洛秦肥については、黎に≈腾辆盗苗∽∈揪塑网炯螟∷を粕んでいたので、络挛のことは南めていた。なので、塑侯墒にはすんなりと掐っていくことができた。
夺钳、泣塑凰甫垫が渴み、讳たちがガッコウで浆っていたのと般う豺坚がなされた眷烫にしばしば叫柴う。富会についても、盗苗卤烦、完墨幢烦という年棱が缠しくなってきている。
塑侯墒は车ね揪塑网炯会の腾辆盗苗咙を僻奖している。厦の囤も揪塑会の≈腾辆盗苗∽に辫って渴められる。富会の塑萎でありながら、≈娩娩∽でないための鹅呛が盗苗にはあったようだ。ゆえに≈娩娩∽の完墨とは般った栏き数を联ばざるを评なかった。
舵忘怖湾平で士踩に暗尽してから、叠に掐るところまでは廓いに捐った炊がある。しかし、叠に掐ってから、稿球蚕恕鼓と完墨にいいようにやられ、あれよあれよという粗に乖き眷を己っていく。部がどうなっているのか尸らぬまま、丹がついてみれば卤烦にされてしまっていた。そうなれば皖ちていくのも玲い。塑碰に办街を额け却けた绅经だった。


讳が睛卿に呻く惧剑布课拍漠の藩怀という孟惰には海版拉が驴い。というかほとんどが海版さん。この僵に爽啼した箕、その海版さんからおもしろい厦を陌かせてもらった。海版煌虾敷士という绅经の疏が、この婶皖にあるのだそうだ。なんか使いたことのある叹涟だが、使くと、腾辆盗苗の盛看であったらしい。
腾辆盗苗といえば、海少怀俯の井甜婶辉がさかんに络蚕ドラマで揉を艰り惧げてもらおうと、辉瘫をあげて痉米笨瓢で拦り惧がっているところだ。腾辆盗苗で少怀と惧剑のこの孟とが冯びつくとは蛔ってもみなかった。
腾辆盗苗のことは舵忘怖湾平での圭里のことぐらいしか片になく、これは办つ揉につてもっと梦ってみようと蛔って缄にとったのがこの办糊。
井棱のような、そうでないうような。いうなれば侯荚の腾辆盗苗への鳞いを闹った承今とでもいえる侯墒。揉が宠迢した箕洛は、欧鼓と惧鼓と恕鼓、给踩と绅晃、士踩と富会、それらが剩花に晚み圭って、寒瀑端まりなく、绅晃の箕洛への册畔袋であった。そんな面で、腾辆盗苗の蔡たした舔充は润撅に络きい。なのになぜ卤烦といわれなければならなかったのか。侯荚はそうではないのだ、揉こそが箕洛を恃えた拔络な绅经なのだ、と鳞いを揭べている。井甜婶辉での腾辆盗苗络蚕ドラマ痉米笨瓢の券眉となった叫丸祸も塑今に卡れてある。
腾辆盗苗极咳と揉が栏きた箕洛秦肥を梦る掐嚏今としてはとてもよい塑だと蛔う。
ル〖サ〖ˇブリセットの≈Q∽芬がりで缄にとった办糊。
≈Q∽も岂豺だったが、この侯墒はもっと岂豺だった。
面坤イタリアの廖薄で弹こった息鲁沪客祸凤を闪いた夸妄井棱。≈Q∽票屯キリスト兜の悟凰弄燎孟がないとついていけない。嫡に咐うとそちら数烫に督蹋がある荚にとっては粕みごたえのある侯墒となるのであろう。船琐にその收のところを输郊すべく墓い豺棱が藕えられているが、それを部刨も部刨も粕み手してみてやっと警しだけこの侯墒の积つ坤肠囱に纳いつくことができた。それでもそれは侯墒から珊う咐わば≈器い∽を犹いだだけに册ぎず、はやり湿胳を窗链にものにしたとは咐い岂い。
よくわからないけど铜叹な茶踩をの敞を囱ているようで、锣二なクラシック不弛を陌いているような炊じ。そんな弛しみ数もまた塑粕みにはあるのかもしれない。
1938钳栏まれのフォ〖サイス黎栏は海も篮蜗弄に糠侯を叫し鲁けている。撅に呵黎眉の厦玛を捏丁し誊惟たなければ丹がすまないようだ。
谰菠坤肠に答茸を弥くイスラム兜盘が寥骏とは痰簇犯に乖うテロが附悸に弹こっている。これを∝ホ〖ムグロウンˇテロリズム≠というのだそうだ。塑侯墒では、ネット惧の≈棱兜荚∽の钙びかけにより办辉瘫が恃剂してテロに第んでしまう。その≈棱兜荚∽を≈纳雷荚∽が柬っていくという肋年。おまけにソマリア长卤の靠悸も藕えられていて、おもしろさてんこ拦り。
湿胳の面で络宠迢するのが痰客腻弧怠。これが碍荚を纳って侥玻痰吭に若び搀る。なんでもかんでも鄂からお斧奶し。これでは、いとも词帽に祸凤が豺疯してしまう。もうちょっと、はらはらどきどきの鸥倡が瓦しかった。
条荚あとがきによるとˇˇˇ
∝井棱穿乖から撂って1994钳、イタリアのア〖ティストや宠瓢踩や碍岛攻きが礁まり、ひとつのプロジェクトを弹瓢させた。茂でも极统に徊裁できて、疯まりごとはたったひとつだけ。称客が侯ったものをル〖サ〖ˇブリセットの叹涟で券山すること。ˇˇˇやがて肩惠に豢票する客」の呜は称柜にひろがって徊裁荚は纱叹を亩え、そして碰介の徒年奶り、皋钳稿にプロジェクトは穗を誓じる。その涅めくくりとして券山されたのがこの井棱だ≠
神骆はロ〖マカトリック兜柴の慑窃が渴んだ16坤氮の菠剑。健兜猖匙と抢瘫里凌の辈面にあったドイツから厦は幌まる。健兜猖匙で铜叹なルタ〖が肆片に判眷する。讳の梦っているルタ〖は兜彩今で叫てきた≈猖匙荚ルタ〖∽であり、奶り办首の梦急しかなく、揉が健兜猖匙の苞き垛になった、ということぐらい。塑侯墒ではそのルタ〖を掀に弥いといて、布霖辉瘫と抢瘫の飘凌と涪蜗荚と健兜荚の飘いを钮江く闪かれている。
呵介、箕废误が乖ったり丸たりするので陵碰妄豺に鹅しむ。だから、粕み手しが部刨も涩妥になる。そのうちそれが面茸になるとだんだん厦も斧えて丸て、湿胳の乖く黎に督蹋がわいてくる。
岂豺といえば岂豺な侯墒。16坤氮の菠剑についての燎孟がまったく痰ければ滩たくなる侯墒だと蛔う。部搀も部搀もうとうとしながら、やっとのことで粕み姜えた。
少怀辉惟哭今篡には垄今がなく、关掐巴完を拷懒していたら、それが奶ったそうで、哭今篡から息晚が掐った。
1994钳に今かれ1995钳に矢杆步され叫惹されたが2013钳に浩矢杆步。
ラノベというカテゴリ〖の年盗はなんとなくわかるようで郏随、びみょう。獭茶をみている炊承で粕みすすむ。汾いギャグがツボにはまる。≈哭今篡里凌∽弄ライトSF、という咐い数が办戎あっていると蛔う。
ひょんなことから谨灰光栏が抱描若乖晃に却脓される。虑ち惧げ眷疥がソロモン紧喷。
皖胳のような呵稿の皖ちで涅めくくり、シャンシャン。
かみさんとこの侯墒をシェアしたが、かみさんの删擦はいま办つ。
继靠はそれを唬った荚の客栏を纳挛赋することができる。
そこにある办绥の继靠は灰丁を继したものだったり、慎肥だったり、揉の踩虏だったりする。そこに鼻っているものは帽なる蕊继挛にしか册ぎないが、それを唬逼した荚はそこに部かを炊じてシャッタ〖を病したはず。戮の茂かが稿にその继靠を囱たとき、その荚は唬逼荚の看董を粕み艰ることが叫丸るはず。继靠にはそういう办烫もあると蛔う。
肩客给は腊妨嘲彩板。そして揉の捡蹋は继靠を唬ること。揉は腊妨嘲彩板としての叹兰を评るばかりでなく、继靠踩としても迫极の董孟を磊り倡いていき陵碰の删擦を减ける。揉の唬った灰丁や踩虏の四络な继靠。それは≈淡脖の瘦赂∽、まさしく塑侯墒の玛叹に芬がって丸る。
海でこそ论基の叫缓涟浮壳が材墙だが、この湿胳の叫券孟爬である1964钳孩はまだそれが澄惟していなかった。たとえそれがあったとしてもこの井棱のような柔粪は弹こり评ることだろう。
缔に缓丹づいた菏の叫缓に惟ち柴うことになった腊妨嘲彩板。涩秽になってとりあげた灰丁はりっぱな盟灰。だが、菏のお盛の面にはもう办客。その灰も痰祸とりあげたが、揉谨は黎欧弄俱巢を积って栏まれてきた。そこで腊妨嘲彩板は雇え、搪う。冯渡揉は卉肋にその灰を吐けることにし、慨完のおける辞割徽に谨基を瞒した。そして、菏には荒前ながら谨基は秽缓だったと桂げた。
そのことが腊妨嘲彩板を办栏呛ませ、鹅しませる。办つは卉肋に吐けてしまったこと、そして办つはそれを菏に柒斤にしてしまったこと、そしてまた碳は秽んだことにしてしまったこと。すべては箕粗が豺疯してくれると腊妨嘲彩板は蛔っていたのだろう。いつかは菏に靠陵を厦そうと怠柴をうかがっていたのだろう。だが、それができぬまま箕粗だけが册ぎていていく。看の秉に簧さったままの井さな∝トゲ≠が菏との腮摊な调违炊を栏んでしまう。勺韶というものは稍蛔的なもので、菏は勺の∝看のトゲ≠をいつのまにか极尸の面に柒蜀してしまう、それが部なのか尸からないうちに。そして、それが勺韶粗のわだかまりへと渴鸥していく。
办数、卉肋へ吐けられたはずの碳は、悸は完まれた辞割徽が缄ずから伴てる疯看をして、腊妨嘲彩板の涟から谎を久す。碳は辞割徽の唉攫に伴まれ、ダウン旧というハンデがありながらも、看芹された看隆の稍拇も附れず、すくすくと伴っていく。その辞割徽もまた谨基の继靠を唬り鲁けていた。そして入かにそれを腊妨嘲彩板に流っていた。
湿胳は腊妨嘲彩板の仆脸の秽で缔鸥倡。菏と碳、碳と漏灰の滦烫と卡れ圭い。
メモリ〖ˇキ〖パ〖の碳はこれからどんな客栏を殊んでいくのだろうか。
≈まかて∽という叹涟には々々々と蛔ってしまう。なんか罢蹋があるのかな。
妈150搀木腾巨のこの侯墒はすっきっりとした箕洛粪だった。
参客面喷参灰の客栏をその娘灰が沙豺いていく。
胳り庚が海慎なら、湿胳の笨びも海慎で、とても粕みやすい。やっぱり箕洛が侯らせる侯墒というものがあるのだなと悸炊する。
垮竿韧晃と柴呐韧晃の惰侍も梦らない井栏であったが、欧堕呸VS紧栏呸の湿胳を即として、垮竿韧の惟ち疤弥と鹅汐ぶりが忱粗斧えた。そして、穗琐の寒瀑としたやや盟ばかりが誊惟つ面にあって、参客面喷参灰が垮竿韧がらみで闪かれている。そういうことだったのか。と、うなることしきり。
办つ看にぐさっときたのは、参を庇うときは炭がけであらねば、ということ。
矾にこそ硒しきふしは浆ひつれ さらば撕るることもをしへよ
请を禾った山绘カバ〖が建帮。
JˉGˉバラ〖ド、≈ス〖パ〖ˇカンヌ∽に鲁いて企糊誊。こちらの数が黎に叫されている。
塑侯墒も喇较家柴の陡丹が肩玛となっている。
玛叹からコカインが菌し叫す胎锨の坤肠を蛔い赦かべるが、コカインが链烫に叫た湿胳ではない。ただ、コカインが客粗を恃える栈挑なら、陡丹こそが喇较した家柴に珊うどうしようもない陡丹の坤肠から客粗拉を艰り提す借数涞と疤弥烧けられているこの湿胳からすれば、家柴を恃える据魔としてコカインという玛叹はなるほど、と蛔わせる。
神骆はジブラルタルとコスタˇデˇソル。いったいそこはどういう眷疥なのか、どこにあるのか、この侯墒を粕んで介めて梦った。どうやらそこには檀のようなリゾ〖ト家柴があるらしい。
喇较家柴における悸赋弄活みが湿胳のキモとなっており、この侯墒もSF弄な史跋丹が珊っている。锣喀荚コミュニティ〖に孰らす酮」极努な客」。なかには50盒を涟にしてその家柴に掐ったものもいる。部もしようとしない客」。部もしなくても孰らせる附悸。誓ざされた家柴で痰嘎とも蛔える帽拇な栏宠の帆り手し。はたしてそこには栏きている悸炊があるのか、そこに栏きる擦猛があるのか。それで客粗といえるのか。
痰丹蜗家柴に抨じられた陡丹が客粗の塑拉と塑墙を钙び弹こす。
その玛叹に胎かれて缄にとった办糊。
カンヌとはあの鼻茶鹤のあるフランスのカンヌ。塑今はそのカンヌの黎渴弄ビジネスパ〖クを神骆にしたサスペンス。
链挛弄にはSF弄なニュアンスが珊うが、それは附悸违れしている厦の囤惟てからくるものかもしれない。喇较した家柴に栏きる客粗にとって、陡丹こそが呵络の烃しになり、それが汤泣を栏きる蜗の富にもなる。とある板徽が弹こした淮沪祸凤の靠陵を仆きとめようとする滥钳の湿胳。
冯琐がない姜わり数はいろいろな鳞咙を吝き惟てるが、极尸弄には肩客给の滥钳もまたそれとは罢急しないまま陡丹の虐を僻んでしまった、と蛔われた。
なんでこんな玛叹になったのか、尸からない。
稿から叫された≈武缝∽を黎に粕んでしまっていたが、≈武缝∽に奶じるテ〖マが≈吕哇を比く窍∽に寥み哈まれていた。≈武缝∽を粕んだとき腮摊な般下炊というか赔仆さを承えたが、これで羌评できた。もし≈吕哇を比く窍∽を黎に粕んでいたならば、すんなり≈吾缝∽に掐っていけただろう。
滥抗のドンの嘲盛として栏まれ澎络を叫てから爹度に舰き、そして施踩になるという≈啦灰攫参∽≈糠リア拨∽で闪かれた省叻敬欠の客栏はかなり眶瘩な苹を茅っているが、それは润宿であたったとしても佰剂なものではなかった。だがその灰僵苹には汤らかに佰剂なものが炊じられる。敬欠が介めて漏灰僵苹と癌ったとき、讳はそこに佰剂なものを炊じとったが、碰脸摄である敬欠もまた票屯であったであろう。
その佰剂さの乖く黎に略っていた祸据は弹こってしまってからは呵介から徒斧できたかのように蛔えてしまう。疯してその徒炊があったわけではないのだが。その弹こってしまった祸据はその佰剂さ肝のことだったとしても、その祸据极挛を久すことはできない。漏灰の佰剂さを炊じながらも、その佰剂さを嘲娄からしか囱ることのできない摄。それが弹こってしまってからも、やはり嘲娄から囱鲁ける摄。
そこに、光录侯墒撅息の圭拍秃办虾の湿胳が晚んで丸て、なおさら剩花な菇陇に。
滥抗话婶侯の话侯誊にして呵岂豺な侯墒となった。
塑侯墒のテ〖マはメキシコ算挑里凌。
メキシコの算挑里凌は企つの娄烫からうかがい梦れる。办つは算挑カルテル粗票晃の旗磨り凌いであり、いま办つはメキシコ蜡绍とアメリカ蜡绍による算挑カルテルの艰り涅まりからくる识凌である。しかも、そこにアメリカの面祁势における瓤鼎毁辩の蛔锨が晚み圭っているというところが、メキシコ算挑里凌の菇陇をより剩花にしている。イランˇコントラ祸凤の靠陵は年かでないが、かいつまんで咐うと、アメリカがイランへの绅达廷叫で评たお垛がニカラグアの瓤鼎廓蜗への获垛として蝗われた、ということらしい。メキシコ算挑里凌にもそれと梧击した娄烫があるようだ。撂ればベトナム里凌でアメリカが热した柔粪にも奶ずる爬がある。
塑侯墒にはその剩花なメキシコ算挑里凌がアメリカの办淋汉幢を肩客给として悸にリアルに闪かれている。カルテル粗の钩凌は私蜗弄で润攫、かつ锭碍にして荒翟。陵缄を匠皖とすためには缄檬を联ばない。焚弧や息水淋汉幢との烃缅は给脸の祸悸。垛を艰るか濒を艰るかの联买を趋られたとき、たいていの荚は垛を联ぶ。そうでなければ濒、すなわち秽があるのみ。苗粗の微磊りには推枷ない糯娜、滦惟カルテルに秩められた眷圭にはすかさず鼠牲。いともあっさりと秽客の怀が蜜かれていく。塑侯墒はそんな眷烫の息鲁である。
メキシコ算挑カルテルの笨脱妨轮はメキシコトランポリンと钙ばれる。メキシコで木儡算挑を澜陇するではなく、面祁势の柜からアメリカへの萎奶ル〖トをカルテルが爱り、そこでの睛卿のリベ〖トがカルテルの艰り尸となる。つまり睛卿を喇り惟たせるようにしてやるから、その瓷妄瘟をよこせというもの。いやなら艰涅まられても梦らんぞということ。ライバルのカルテルル〖トを蝗うのなら、艰涅まられように慌羹ける。そこでカルテル粗の钩凌が栏まれる。窗帔を袋したはずの艰苞きなのに、なぜその附眷に淋汉幢が略ち减けているのか々苗粗からの泰桂なのか、ライバルカルテルの慌度なのか、伞挑を跟かせたはずの舔客の微磊りなのか。メンツをつぶされたカルテルの陡宛ぶりはすさまじく、そこには碰脸归啼と借泛がついてまわる。
そして焊豌ゲリラへのアメリカの滦炳。キュ〖バを耿傅に竖えているアメリカとしては、夺眷にこれ笆惧鼎缓廓蜗がはびこるのは部としても了贿したい。それが算挑カルテルといえども、瓤鼎廓蜗となるならばそれらと缄を寥む眷烫もあり评る。マネ〖の戮に绅达がカルテルを奶して瓤鼎廓蜗に葡くという慌寥み。そこでは柒里が弹こり、驴くの稻婪荚が栏まれる。アメリカの客涪刊巢も斧え保れする。
泣塑に交む叉」にとっては、メキシコ算挑里凌は滦催の残祸のようにみえる。それにしても、アメリカはなんと呛める柜なのだろう。坤肠面の识凌を陵缄にしながら、柜董を儡するメキシコ算挑里凌からは办箕も誊を违せない。缄を此めれば算挑カルテルは廓蜗を弓げ鲁け、アメリカ柜柒はたちまち算挑に禚砀されてしまう。それから孺べれば、附哼泣塑と蹿柜、面柜との砺磬から栏じている紧啼玛は基岛に霹しいとも咐える。
この塑を粕んでいる呵面、6奉21泣に少怀俯柒で悸卉された∝挑湿宛脱≈ダメ。ゼッタイ。∽舍第笨瓢≠に徊裁することになった。饿脸とはいえ、その射规の办米に睹くばかり。
惧布驶せて1450ペ〖ジにも第ぶ络墓试。
だが、その墓さは警しも炊じさせない。粕んでいて、烫球くて、弛しくて、姜わりに夺づくころには、なんともこの侯墒から违れがたく、もっともっとこの湿胳に炕っていたいという丹尸にさせられた。
玛叹から、呵夺粕んだ≈哭今篡里凌∽と讳の攻きな蒜谨湿∈≈蒜谨の癸∽アンˇライス螟∷とダブらせて缄にとった办糊。≈蒜谨の癸∽は团别でミステリアスな附洛慎の蒜谨の湿胳であったが、この侯墒は≈蒜谨∽という咐驼から息鳞される蒜窖弄な罢蹋圭いとは链く痰憋の湿胳である。
办粕みしてファンタジ〖を徒斧させるが、悸はこの侯墒はファンタジ〖の叹を稼りた塑呈矢池侯墒だ。簿鳞の柜の≈哭今篡の蒜谨∽を肩客给として、话柜恢やロ〖マ碾柜の督舜のような钨柜粗の涪伺窖眶がくりひろげられる。だが、哭今篡の蒜谨が绅达とするのは≈咐驼∽。そしてその咐驼こそがこの侯墒のテ〖マともなっている。戳矢弄で概胳弄な咐驼と矢鞠蝗いと附洛慎な庚胳拇の咐い搀しが、词烽でよどみない矢鞠と驶さって、摊な看孟紊さを承える。湿胳の囤惟て极挛も事はずれたものがあるが、咐驼と矢鞠の蜗がまさしく蒜窖弄な蜗をもって粕み缄を牛づけにしてしまう。
络ベストセラ〖の徒炊とともに家柴附据になる材墙拉をも入めている。
黎に粕んだ≈啦灰攫参∽が熟と灰の看の奶い圭いならば≈糠リア拨∽は摄と灰の滦厦。
滥抗についてよくわかってない。讳との簇犯といえば、池栏箕洛に痊姑拍怀にスキ〖に乖ったこと、糠拍肌虾の井棱≈痊姑拍怀秽の浊子∽を粕んだこと、叉らが卿挑苗粗に滥抗に乖っている荚がいること、お评罢さんで滥抗叫咳の数がおられること、付灰蜗隶≈むつ∽の熟沽であったこと、乘浅瘟浩借妄卉肋があるらしいこと、讳の攻きな光抖幂怀がいたこと、孟酷楞ツア〖があること、シジミの缓孟であること、络粗のマグロが铜叹なこと、球坷怀孟があること、リンゴの缓孟であること、おいしいニンニクがとれことˇˇˇ。ざっと蛔いつくのはこんな恶圭。
そんな滥抗のことを浩千急させてくれた办糊。
滥抗にもドンと咐われた涪蜗荚がいたことを梦ったことも办つの睹き。
1970钳孩から1980钳涟稿の泣塑の蜡迹がどんな觉斗でどう炅いていたかがよくわかる。蜡迹踩の雇えと慌祸の≈いろは∽、笔拍漠の蛔锨、柜蜡と孟数极迹のダイナミズム。碰箕の蜡渡も悸叹を刁げて≈豺棱∽してくれている。1980钳涟稿といえば、极尸は坤に叫たばっかりで、极尸のことだけを雇えるのが篮いっぱいのとき。戮数、旁柴との汗を虽めようと涩秽だった滥抗がそこにあった。いや、滥抗だけではなく泣塑面がそんなことで童いていたのだろう。ただ、碰箕の极尸には誊に掐ってこなかっただけのことで、咐われてみれば宫せな袍だったのかもしれない。
滥抗の办蜡迹踩の誊を奶して胳られる海のTPPにも芬がる抢度啼玛と3ˉ11稿に缔に渴烯を恃え幌めた碰箕の付灰蜗乖蜡。それは付灰蜗券排疥、乘浅瘟浩借妄卉肋の投米とそれに燃う爹度涪の瘦俱であり、糠创俐を苞っぱってくることであり、势抢踩への毁辩忽である。しかし、肩客给である滥抗のドンはそれらを帽なる孟数への网弊投瞥としてみていたわけではなく、それらが塑碰に滥抗俯瘫の百になるのか、しいては泣塑の柜の百になることなのか、ということを撅に雇えながらやってきた。そうやって蜜き惧げてきた40钳の墓きに畔る蜡迹踩客栏の畎眇でもある。
碰箕から付灰蜗の廊煎拉は碰箕から漓嚏踩だけではなく蜡迹弄にも千急されていたことが忱粗斧える。それにもかかわらず、排富话恕を垛彩短掘として、泣塑面の魂る疥で投米圭里が帆り弓げられた。それがもたらした冯琐を海になれば茂でも梦っているが、2005钳に光录钒がそれを塑侯墒を奶して帕えていたことは睹くばかり。
海は施踩となった漏灰に极尸の染栏を胳り使かせ、漏灰はその箕」に摈いて甘の碉た董而と脚ね圭わせまた极尸の殊いてきた苹の们室を摄に胳る。≈啦灰攫参∽で熟が灰に闹らねばならないことがあったのは熟科としての灰に滦する攫からである。塑侯墒で摄が灰に胳ったことは蜡迹がらみの祸ばかりであるが、40钳粗蜡迹办囤に栏きてきた盟にとって戮に部が漏灰に胳れよう。
夺踏丸のイスタンブルを神骆にした湿胳。
络恃粕みづらく、なかなか厦が斧えてこないのは、いっぱい叫てくるトルコ客の叹涟になじめないのと、トルコの慎浆とイスタンブルの悟凰が链くわかってないからだと蛔う。
肆片からのSF弄な掐り数には黎を袋略させる徒名があったのだが、湿胳の乘をなすいくつかの赁厦を芬いで艰り跋んでいる≈イスタンブル∽の湿胳が猎络で、寒瀑としすぎていて、なかなかその坤肠に掐りこめなかった。片で妄豺しようとしているからだと蛔うが、水条ものとしては矢鞠を弛しむということも岂しく、厦の囤だけが栏炭俐なのに、それについていけないとなると、やっぱりおもしろくない。
ボリュ〖ムも陵碰あり、部刨も部刨もウトウトしながら、なんとか粕み姜えたというのが塑碰のところ。
ただ、イスタンブルが积つざわざわとした寒瀑と篙瓢は炊じ艰れたと蛔う。
呵稿の呵稿に丸て、玛叹の罢蹋が绁に皖ちた。
弹镜啪冯という咐驼があるが、≈啪∽の婶尸の恃步が粪弄でかつそこから湿胳が办丹に裁庐する。
それまでは埠やかな、というかつばぜり圭いのような湿胳の笨びに蛔われ、ややじれったさも炊じられる。
だが、その欢獭とした湿胳の面に祸凤豺疯のための屯」な邵佬が欢りばめられていた。それとは丹烧かせないところが诞恢痛拆のすごいところ。さらりと闪かれている≈弹∽と≈镜∽に褓されてはいけない。はっきり咐って、极尸はこの婶尸は淬面になかった。
∪邵佬を搀箭していく∩その斧祸さはさすがだ。
付玛が≈XO∽
叁客で参晶蜗もある碰洛きってのミュ〖ジシャンから葡いたファンレタ〖への手祸の琐萨に≈XO∽と淡されていたなら、それを减け艰った钱陡弄なファンは神い惧がってしまうだろう。もしかしたらそのファンはとんでもないことをしでかすかも梦れない。それがこの侯墒のモチ〖フとなっている。
水玛を付玛と票じく≈XO∽とするかどうか、叫惹家はおそらく呛んだに般いない。≈XO∽としても、久锐荚へのインパクトは浇尸であり、それなりの婶眶はさばけたと蛔う。それをあえて≈シャドウˇスト〖カ〖∽としたのには、それなりの尽换があったからなのだろう。
それにしても≈シャドウˇスト〖カ〖∽という玛叹はこの侯墒の面咳をうまく咐い山していると蛔う。≈シャドウˇスト〖カ〖∽という咐驼から息鳞する稍丹蹋でもやもやとしたガスみたいな祸凤を、ちゃんとした湿胳として坤に叫した、という炊じがして、この水玛はこの侯墒にはドンピシャだと咐える。
キャサリンˇダンスの祸凤だが、络告疥リンカ〖ンˇライムも判眷し、ファンサ〖ビスも抡りない。