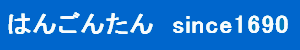���������饹����Ϥ������������������ܡ�
����֥˥ߥåĥ��饹�פ��о줷�����������饹����Ϥ��äơ�����ꥫ�������ֵ���롣
����������饹������������������ʿ�Τ��������롣����Ҥȴ���������ꥫ�������ʥ��������饹���������˲�����Ȥ�������䶯���ʶ�Ω�ơ��ʤ��������������������Ϥ��˲�����Τ����ޤ��Ƥ䱿������䡢��¤����Τ�Τ�Ǥ������Ȥ������꤬�ɤ��ˤ�Ǽ���Ǥ��ʤ������������饹������줿���������ϲ��Ⱝ�����ȤƤ��ʤ�����������꤬���ͤ˻פ���Τϻ�����ǤϤʤ��褦�������¡����Ȥ����ˡ��ܺ��ʤκ�Ԥ˥��ɥХ������Ȥ�������ꥫ�Υ�����åɥ�����Ĥϰʲ��Τ褦�˽Ҥ٤Ƥ��롣���ܽ�Ǥ���Ҥ����������ϡ��Ϥ���Τ����ϼ������줬�������⤷��ʤ������ɤ�����Ϥ�Ǽ�����ɤ�����ˡ�����ꥫ���������������Ф��Ƥ��Τ褦�ʹ�ư��Ȥ뤳�Ȥ����ꤨ������������Ȥ��������Ǥ���١������ͤ���ʤ顢̵Ŵˤ�ʲ��ȿ���˸����뤫�⤷��ʤ�����������θ����С����ۤ���˽�ʤ��ȤǤϤʤ�������Ū�Ǥ���Ȥ狼��Ϥ��Ǥ����
������ʤ�Ǥ⡢����Ϥ��������������ǥ���ꥫ��������Ȥ������Υ��ʥꥪ�϶������������������ι�����Υ����åȤ줬����Ū������Ȥ��äƶ��ҤȤߤʤ�������ꥫ���˲����뤳�Ȥ������������������ʹ٤ˤ���������������顢���ʤ�Ҥä������Τ����롣
���������λפ���������Ǥ��ڤäơ������ߥ��ƥ�Ȥ����ɤ�ˤϲ�Ŭ�ʺ��ʤ��Ȼפ���
����ꥫ�θ����϶��줬�����Ϥ���Ʈ������ˤ��äơ����Ȥ⤿�䤹������Ϥε���ˤ�äƷ�������Ƥ��ޤ�������ʾ�Ū����Ƭ����ʪ��ϻϤޤ롣
������Ʈ���ϹҶ���Ϥ˲ä��ơ�������������Ϥ����ϡ��������ʤɤ��鹽������롣���δ�������Ʈ���μ�������ɤ�����Ϥ��Ĥ��Ƥ���Ȥ������Ȥ����곰���ä����ޤ��ƥ���ꥫ�ζ�����Ʈ���Ȥ����С������Ƕ��ˤ��ơ�¾��Τ����Ϥ뤫�ˤ��Τ����ɿ������ʤ������줬�����ˤ���������оݹ�ˤˤ�ߤ����뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����˥���������ϰ��ɤ�ĩ��Ȥ�Ũ�ʤ��餢�äѤ�Ȥ�����Ρ�
�⤷�������顢����������ˤ⤢�ꤨ�ʤ��Ȼפ��Τ������⤷���줬���¤ˤʤä���Ȼפ��Ȥ��äȤ��롣������������Ũ������Ϥ����Τ�Ĥ��Ȥ��ޤǤ��ʤ��ʤ��ɤߤ����������롣
���κ��ʤ�ʡ�����Ҥ��Ӱ�ͽ�ȤȤ��Ʊ��ǯ�˹���������ޤ�ȤäƤ��롣
���ξ���ˤϡ���桢���桢���Ȥʤ���դ����Ф��нФ���롣�̤Ƥϥ֥å����С��Υ��饹�ȡ��ɤ߽�����ޤǡ����줬�ʤ�Ǥ��뤫���ˤ�α��Ƥ��ʤ��ä������ɤ߽����Ƥ����ܤ��Ĥ����ִ֤˺���������Ȥΰ��פ˵��դ����졢���ܼ��줿��ʬ�ˤʤä���
�ƹ�λ��β��ˤ���椬����ɱҹ��ۤ�������̷��ȥ����ޤ��طʤˤ����ƥ���ʪ�졣���κ��ʤ��줿�Τ���������ǯ�����ޤ�����������ˤϡ����ΤȤ����ɤ���ݤˤϵ��դ��⤷���ä��������ɤ��֤��Ƥߤ�ȡ��Ϥä�����⤭�夬�äƤ����Τ⤢�롣�����ͽ�������Ȥ�����������դȤ����ܺ��ʤϣ���ǯ���⺣�⾯��������뤳�Ȥ��ʤ�������ϡ�����ǯ��δ����ܤ��ɱҹ��ۤϾ�������⤷�Ƥ��餺��̷����������ޤޤǤ��뤳�Ȥ��̣���롣���Ȥ��С�������šפ���ĤΥ�����ɤȤ���������Ƥ��뤬����������ɤ�Ǥ�������ǡ����¤Ρ����������פϽ���ʶ��̤�ޤ��ĤĤ��롣
�ǽ���ɤ���Ȥ������ƤϤ��ä���˺��Ƥ��ޤäƤ��ơ��ޤ�����������Ƥ��ܤ��ä��ȤϻפäƤ⤤�ʤ��ä������������ˤ����ư���ˡ�Ƥ��ķ褵�졢��������꤬���ܤ����ǡ��������ܤ�ƤӼ�ˤ�����̯�������פˤޤ��ä����줿�ΤǤ��ä���
�����Τ��Ȥ��Τ�ʤ顢���Τ��Ȥ��Τ졢�����Τꤿ����С�������ˤ��Τ졣
���ߤ���Ϥ�����̾��֥ʥ��ϥ�Υ˥��פȤΤ��ޤä���
����奢��Ρ���������Ͽ�פ��ɤ�Ǥ��顢���ɤ�����ȤΤ��ä������֤���ס���ɱ�ΰ�͡פ���ɤ�����������˾���ܺ��ʡ�
ʸ��ʤ������褺���ɤ�Ǥߤ�˸¤롣
�������˴�ȤȤ��������ǯ�αʤ����Ϥä�³���Ƥ�����ī���ۤ�������������ˤΤ����֤äƤ��롣�����ĥ���ä���������������������Ǥ���
���ޤ��Ǥ��Ƥ���Τϡ������äȤʤä�����²��Ĺ���ۤ���������ī�Ȥʤ�����ī�ˤȤä�����ʪ�줬����ī�����ʪ��ȽŤ�碌��������Ƥ������Ǥ��롣������ۤ��夲�������������ͦ�Τ����ζ�Ǻ������κǴ���ֺݤˤ������鿩��ʪ�ˤ���ޤ���ɬ������ߤ�͡��ο����⤬���ޤ����ߤ�������Ƥ��롣�����ơ�������ͤˤ����פ�����Ω�����ƻ�������±��ĥ���ä�ʸ���̤�˽���ϤΤ褦��ʪ������IJ�̵�Ԥ˶��롣
��ʬ���ۤȤ���Τ�ʤ��ä�����ī���ֶ������ī�κǴ��Ϥ���ʤǤ��ä����ȡ��������������ǧ��������줿����Ǥ��ä���
����ޤǤϿ����Τ����Ū���������ʷ����ɤ�Ǥ����������ˤ��ơ��褦�䤯�ब�֥쥤�����뤭�ä����Ȥʤä��ƥ�ӥɥ�ޤθ��Ȥʤä��ܺ��ʤ��ˤ���������������֤������������ʤȤϤɤ�ʤ�ΤʤΤ������ơ�������
�ץ��åȤλŹ��ߤ�ʪ���Ÿ���Ͽ���ʬ�ʤ��������줿�����ƥ����Ⱥ��ʤȸ����롣����������ʾ�Τ�ΤǤϤʤ����������ߤ���;��˷礱�롣����Ϥ���ޤǼ�ˤ��Ƥ�����Ԥκ��ʤ��٤Ƥ˶��̤����������ޤ����Ǹ�εͤ��Ť������Ť�˴�㤬�Τ�������ά�����פˤʤä����餫�ˤ����Τ����������ΤȤ������������Կ��ڤȤ��������ʤ�Ȥ���������ȴ���Ȥ���������������
Ʊ����ͻ�������դȤ������ʤ��������Ӱ�ͽ�ȤϤ��ۤʤ롣�����Ȥ����������Τ��ȤʤΤ�������ʬ�Ȥ��Ƥ��Ӱ�ͤκ�����̥������Τ����롣
���ɡ������֤���פ�³�ԤȤ������ϥ��ԥ�Ū�ʺ��ʡ����ޤϡ���ī�ι����������ޤΰ�͡������Ĥ���κ��桢��ؾ���ΰ�ͤ���ǻ��Ǥ���Τ�ȯ�����줿�����λ��郎�δ֤�������Ȥ��졢������ͤ��ߤ��٤�Ĵ���Ĥ���������롣�ޤȤ������ǤϤʤ�¦���Τ��Ȥǡ�¦���������줿���Ȥ��ʤ��ˤȤäƤ���ʤ˶ä��٤�����ʤΤ����ޤ����Τ��Ȥ������Ƥ��ޤä�������Ǥ�ʪ��Ͽʤ�Ǥ����������Ω��Ԥ������ڿͤȤ����о줹�뤬����ĤȤ���Ʊ���äϤʤ����Ϥ����ơ�����Ϥɤ��ʤΤ���
���ɡ��������Ρ���������Ͽ�פ��ɤ�Ǥ��ơ���ǯ�����ɤ�����ļ�Ϻ�Ρ����֤���פ�פ��Ф�����
���Ĥ��ɤൡ����������ȻפäƼΤƤ�줺�ˤȤäƤ��ä��ܤ���ΰ�ġ�����ʽ���碌�Ǥ�ʤ���С��⤷��������ʱ���ɤळ�Ȥ�ʤ���¾����Ʊ�͡���ê��������Ƥ��ޤäƤ������⤷��ʤ���
���Ǵ��β�ī�Ȥʤä������������ˤ���ʪ�졣������ǵ����ä���ˤΥ����ʥߥ�������ˤ�Ƥ���Ȥ��Ϥ�롣��ˤȤ���������ή��λ��ĥ��ͥ륮���ˤϤ��Ӥ��Ӷä�����롣�����ܤ˸����ʤ����ͥ륮���ϡ����ܤǤ��͡�������������ʤ���������ݿ��ؤ�Ƴ���Ƥ��������������ˤ��äƤϡ����إ�����˻Ϥޤ��ˤ�봳�Ĥ����露��ȹ��ष�ФϤ����ơ�Ĺ��³������ī�ˤ�������⽪���ޤ��褦�Ȥ��Ƥ�����������褦�Τʤ�ή�����ǡ���̳��ư����Ω������������Ω���Ϻ�������ī�ϱ�̿��ޤ����Ȥ��롣�����˻���Υ��ͥ륮�����٤Ƥ��ݤߤ���������������äơ�����Ȥ�����ʶ��ʪ��β����Ȥʤ롣
������ʪ��νļ���ʤ��Τϡ���ͤ����������˻Ҥ���Ĺ�����α�̿�ΰ����Ҥ䡢��̱�λҤȤ������ޤ�ʤ�����ᴱ�Ȥʤä��������˰���Ω�Ƥ�쾯�����ij��ʤ�夬�äƤ���������ˤ��ᴱ�Ȥ��ƺǹ�ΰ̤˾夬�롣�Ҥ䡢���ΤλҤȤ������ޤ졢�ʵ����ʤ����ˤ�����Ĵ�˴�ν�γ����Ĥ�롣
�ܺ��ʤϡ����νļ��Ȳ������˸����ơ�����������礭�ʥ����ƥ����Ȥ˻ž夬�äƤ��롣
���������ǥ�κ�Ȥκ��ʤϥ��ơ������顼����Ρ֥ߥ�˥���װ��衣�֥ߥ�˥���פϻ�ˤΥߥ��ƥ���ä�������Τˡ���μ��κ��ʤ��ɤ�Ǥߤ����ä��Τ��������ơ������顼����ϡ֥ߥ�˥����ɮ��˵���̿ͤȤʤäƤ��ޤä���
���������ξ���ϤϤ������㥳��ǥ����פ��֤�ˤ���ʺ��ʤ˽а��ä������ļ�Ϻ�Ρ֤���Ԥ��װ��褫�⤷��ʤ�������äȤ����ޥ��å��ꥢ��ƥ������������ʤ��Ǥ�ʤ��������ԡ��桼�⥢�����ɤˤ��դ졢��ڡ����˰��ʾ��ɬ���Ф碌�Ƥ���롣
��������ǯ����եꥫ���ޤ�ξ������Υ�٥������������äȤ�������̾��������Ȥϡ֥Υ�٥�����������֤����פȤ��ä��ۤ����դ��路���������˰�ä������˺������ȹߤ꤫���äƤ��롣����⤪�Х�������������Ǥ���Τ������Υ�٥��Ϥ��κ������ʡ��ž���ƾ��ۤ��Ƥ��������ξ���̣�褵����䡢�˲����Τ�Ρ�
��Ԥϥ���ǥ��˻ž夲�Ƥ��뤬�����äƤ���ơ��ޤϿͼﺹ�����ꡢ��ʼ����������ե������ࡢ�����������������¿���ˤ錄�롣������֥Υ�٥�����������֤����פ����깭����ɥ��Х����ɽ�����Ƥ��롣
ʪ�줬�ϤޤäƤ������ع��ˤ������̤äƤ��ʤ��Υ�٥��������äƤΤ�����̤��ФƤ��롣�����ݤ��룹�����䤦������������Υ�٥������Τ褦�˷����롣���β��Ƴ���������äѤ�ʬ����ʤ��ä���
��95�ϣ��������飵�������ϣ��������飸����������Ǥ��硣���ȣ������ƣ�������������ȣ����Ǥ��硣�����ƣ������룸�ϣ����Ǥ��硣�����ȣ����ǣ����������
�ȥࡦ������ϣ�������ǯ�������˴���ʤä�����ǯ�����С�
�ܺ��ʤ���ΰ��ȤʤäƤ��ޤä���
�֥�åɡ������ȡ��С����ɤ��פ����˽Ф��Τ���������ǯ�����衢�¤ˣ���ǯ��Ĺ�����Ϥäƻ�ϥ���å����饤������ɤ�³���Ƥ���������⤳��ǽ����Ȥʤä�������ǯ�Ȥ����л��Ⱦ����ɤŨ���롣�ǥӥ塼��餳��ۤ�Ĺ���դ���ä��褿��Ȥϥȥࡦ�����������ͤǤ��롣
����κ����ޤ�������������ˤ������ʷ��������ˤ��⤷�����ä����ۤȤ�ɤϣ����ɤ�����饤�������֤������������ä����ޥ륳����ߥ��������顼��������٥������祪���������ޥꥪ�ǥ���������������ᥢ�ꡦ�ѥåȡ����ɡ��ե����ꡢ�����������ࡼ�������ޥ�����ӡ������㥯�������åȡ����ɥ顼�������Υ�ɡ��������ࡢ����ɥꥢ���ץ饤�����ޥ塼�������륲���������ե����������С����롦���㡼�륹�ȥ��㡼�륺�ѹ�����ҡ��ߤ�ʤ����ۤ�Ф�����ä����⤦������ܤ��ɤ�Ǥ��ΤȤ��ζ�ʳ�˿��ꤿ����
���ơ��ܺ��ʡ���̾�̤����Ϫ�����̤���֤Ĥ���礦�櫓�ǤϤʤ�����Ϣ�Υ���ߥ������˴���������������ꥫ������ä�����Ф����Ȥ������餤��ʪ�졣����ˤ��Ƥ⡢���ξ��⤬�줿�Τ���������ǯ���ºݤ˥�Ϣ������ߥ��˿��������Τ�������ǯ�Σ������Ϥ�ȥࡦ������ηŴ�ˤ϶������롣�����طʤˤ����ʤ��Τ����ä��Τ����ƥ�ӥ˥塼���β�������⤤�Ƥߤ��Ƥ��������ɤ���ǿͤμ�ʬ�Ǥ����ͤ��Ĥ����äڤ�����������ΤФ��ꡣ�����������ξ���ˤϤ�������äȿ���������ߤΤ���ʪ�줬������Ƥ��롣�ե��������Ǥ��äƤ�ȥࡦ����������Ф����ˤ⤽��餷���äˤʤ롣
������ɤ�Ǥ��ơ��о��ʪ��ư������ɽ���ɤΤ��餤����Ū��Ƭ����������Ƥ������������ư����ʸ��������̤��餫�ʤ���������Ƥ���Ȼפ������㤤�Ƥ���Ȥ����ФäƤ���Ȥ����ܤäƤ���Ȥ�����ζ���Ū��ɽ�𡢤��Ȥ�������ư������ο�������ư���ϤɤΤ��餤Ƭ����DZ��������Ƥ�������������ۤȤ�ɤ����ޤ����Ȼפ����ޤ����о��ʪ���سʹ�����κ��ζ����Ϥɤ���������������⤢�����٤Υ�����餷����ΤϤ��뤬���ܺ٤Ȥʤ�Ȥ��ʤꤢ���ޤ���
�Ȥ����褦�ʤ��Ȥ������ܤˤϽ�Ƥ��롣����˭�٤ǡ��ܤ����Ƥ���������Τ��亴���Ƥ���롣�����̣���¸�Ū�ʤ��⤷�����ܤ���
�ֶ�����¡פȸ����Ƥ��ΤäƤ���ͤϤ���¿���Ϥ��ʤ��Ȼפ�����������פ�Ʊ�͡����ξ���˽а����ޤǡ�¸�ߤϤ������̾������ʹ�������Ȥ��ʤ��ä����⤷�������顢���̤��Ϥˤ��äƤϥ��ƥ륤Ʊ������Ū�ʿ�ʪ�ʤΤ��⤷��ʤ�����
���ƥ륤���������Ǥ��ƣ�����Ф�����ʿ������ޤǡ��䡹�����̤��Ϥ˺��դ��Ƥ��������ī��ؤΰ��ϡ�ʿ����̵ǰ������Ĥ����������βФ��������Ϥ˼����Ѥ���Ƥ�����������˭�ý��Ȥλ���ˤʤäơ�������¤��ʤ��ƺƤ�dz���夬�뤳�Ȥˤʤ롣
���������Ũ�ʤ��ζ�����¡����̤��Ϥˤ⽨�ȤαƤ�����Ĥ��Ϥ�Ƥ����������Ȥϻ���ο����˽��äƽ���¦�ˤĤ����Ȥ���롣��������������¤����̤ΰ��Ϥ�Ӥ��̤�����²��Ũ�˲ƽ��ȤȤ��з���դ��롣
��������ʺǴ��Ϥ������ư��Τ�����ʪ�����Τ��̤���������������¤������ͤ˶��Τ����פ�����������ʤ����ǤϤʤ�����ʪ���礭���Ȳ��ο����Ϥޤ������ҡ����������ˤ���Ȥ��ä��������롣���̤��Ϥ�ͺ�ˤʤ�����ʤ餽����ä��Ǥ�������������������Ϥ��������ʤ��ä���
������Ǥ�餬�ܻؤ���Φ���ȼ��ι�¤��Τ���ī���ʸ���̤��Υ���֤��Ƥ����褦�ˡ�������¤����̤��Ϥؤν��Ȥδ��Ĥ�ͳ�Ȥ��ʤ��ä���
�������Ф餯��Ϣ�����̺��ʤ��ɤ�Ǥߤơ�����ʬ����ƻ�����θƤ����ϲ��⺣�˻Ϥޤä����ȤǤϤʤ���ʿ�»��夫�餺���äȺ��դ������˸������Ĥι��ޤ��ä����Ȥ˵��դ����줿��
�����������鸫���������������Ȥ����ͤ��������ˤ��äơ�����˹�������ϤȤ⤤���롣�����ǵ����夲�Ƥ��붶����λפ��⤽��˻�����Τ��⤷��ʤ���
��ԤΥǡ������ޥ��˥�ơ��ޤȤ������ʤ��Ф���Ƥ��顢�ޤ��������ФäƤ��ʤ����Ĥͤ˽ܤʥơ��ޤ�ĩ�路�ʤ�����ɼԤϤĤ��Ƥ��ʤ�������ʤ��錄������������ˤʤä���
����Υơ��ޤϡ֥ɥ�����ס�����ϥå��ȥɥ�����ȥǡ������ޥ��˥ϥƥ��ꥹ�Ȥȿ�������ȤˤȤäƤ�ɬ���ʤˤʤä��Ѥ����롣�������������ɥ������̵���ⵡ���о줵���������Ǥ��ܤ�����ɼԤ������ʤ���������
����κ��ʤϤ����դ˶�ϫ�����פ����������롣���Ф��������Ĥ�Υץ��åȤ����Ȥ������������褦�˻��Ȥޤ�Ƥ��롣�ǡ������ޥ��˥����μ�ξ���Ǥ����������Τ��ȤȤʤä����Ǥϡ��ܺ��ʤˤ����Ƥ϶�����ۤ������Ȥ��ܺ��δ�����δ�Ȥ��ư����Ƥ��롣��ԤΥǡ������ޥ��˥�ơ��ޤȤ������ʤ��ˤ����Ȥ��ϡ�����Ϥ��������ȤˤʤäƤ��롢���ܤ����ڤξ���ä��������ǤϺ��ʤ���Ǥ�����������Ƥ��롣
�Τ��˿�������Ȥ��ƤϤ褯����Ƥ��롣�ܤʥơ���õ���⤤�������⤦�����ʹ֤˼����������ȽŤ����ʤ��ɤ�Ǥߤ�������Ԥν���κ��κ��ʤˤϤ��줬���ä��褦�ʵ������롣
����������ܡ�
��ˤο���Ϥ��α���ޤ��Ϥ���ľ���ꤷ�Ф����֤��֤��������ۤ���������餫�ˤʤ�褦����������ޤ�����
�֥磻��ɡ������ס֥ޥ��פǤ��ܤ��餦�������äФ��ꡣ��ʬ���Τ�ʤ��ä����������Ƥ��ƤȤƤ����ä������������κ��ʤϴ��Գ���˽���ä��褦������̾�ˤ���褦�ˤ���ޤǤ�ɽ�ˤʤäƤ��ʤ��ä��濴�˹�������Ƥ��롣�������Τ����⤢��Τ��⤷��ʤ������ʤؽѽ���ɤ�Ǥ��뤫�Τ褦�ʹŤ���������äȤ���ж�̣���ŤΤϤ��ʤΤ������ա������ʤΤ���������ɤ��������ǽ���äƤ��ޤ��������Ϻ�Լ��ȤˤޤĤ���ä��������Ǥ��ꡢ���Ϥ������Ϥ����ä��������κ��ʤǤϤ��줬�������ʤ��ä�������ʻ���������Ф�����Ͽ�Τ��ˤϾ���δ����ݤ�ʤ���
���ļ�Ϻ�Ρ����֤���ס����ޤΰ�͡פ�⤦�����ɤ�Ǥߤ������ˤʤä���
ʿ���ˤĤ��Ƥλ��Ϳ�����ơ�
ʿ�¤��������ˤ�������Τ���Ƭ���Ƥ���ɬ���ȡ������濴�Ȥʤä���ʿ��������濴�ˤ��Ʋ��⤷�Ƥ��롣���礫����ī�ޤǡ����λ���Ϥޤ�����ŷ�ʤ�Ǥ�����Ф���λ�����ä��Τ��Ȼפ����Ȥ����ꡣ����λ���ޤǤϰ�ͤι�μԤ�����Ф�����Ϻ�ޤ����ޤ���˾��ä�������ͦ�Ȥʤꤨ��������������ΤȤ��⤽���Ǥ��뤬���������Ϥ����ˤ����襤�Ǥϸ³��������Ϥ�Ƥ����Τ⤳�κ����顣�����ˤ�äƤ���ϰ�Ĥ�ĺ����ޤ�����ī��ޤ����������Фƿ����Ϥ˻�롣
����Φ���ط��ξ��⤬��ߤǼ�˼�ä���
ʿ���硢̾�����ΤäƤ��Ƥ�ɤ�ʿ�ʪ���ä��Τ��Ƥ�dzФ����ʤ���
����ʾ������������������طʤ��ä��Τ�ˤϼꤴ���ʰ�����⤷��ʤ�������������ղ�����Ĵ�����⥿�����¿���Τˤ���äȰ��´���Ф������о��ʪ��¿�����뤻��������ʪ�ν��ߤ������Τ��ݤ�ʤ����ʤ�Ȥʤ�����夭�Τʤ�ʸ�ϻȤ��ⵤ�ˤʤä���
����������Ⱦ�������äȤ��ƤϤɤ����Ƥ�ʿ��ȸ����¸�ߤ��Ϥ����ʤ�����Τλ������������������Υ�줿����Ǥ����Ū�ʹ��褬���깭�����Ƥ������Ȥ����Τä���
���Ť���ޥ�å��Τ��λ������ξ��ˤ�����ɤ�ʼ���ǤäƽФ���������������ʪ�졣
����ꥫ������Ԥ�Ϸ��Ķͥ�ɴ�Ȥ�Ԥˤ������ޥ͡�����������Ť��������ꥫ�����Ȳ�ο��Ȥ�ƤФ���ʪ�Ȥζ����������Ρ��ݿȤΤ���ʤ����ܤ���꼫��̱�����ˤ�������ۤ˲��भ������ꥫ���㤤�����������Ť��˲��ʰ���꤬�˾�Υ����ƥ����Ȥ����ࡣ
ʿ���ˤĤ��Ƥλ��Ϳ��軰�ơ�
ʿ�������Ƥ����餫�ˤʤä��ΤϤ����Ƕ�Τ��Ȥ餷����������ΤȤ����Ҳ�ʤμ��Ȥǽ��ä����ȵ�������Τ��������ΤȤ��Ϥޤ��ܤ�����ʬ���äƤ��ʤ��ä����Ȥˤʤ롣���������®ƻϩ���ߤΤ���θ���Ĵ������¢ʪ��ȯ�����졢�ޤ�������ʸ���νи������ܤ���ˤϺ�����������̤����Ф��Ф��뤬��ʿ����ޤ������㳰�Ǥʤ��ä��褦����
�ܽ�϶�ǯ�ƽ��ȯ�����줿��¢ʪ����פʹͻ������ΰ�ĤȤ���ʿ���ȼ���ʸ����ƹ��ۤ��ơ��ǿ���ʿ���θ������Ƥ��롣����ޤ����ꤵ��Ƥ����ʾ��ʿ��ʸ���ϱ����������Ȥ����餫�ˤʤä����������Ϥ��ŷڤ��̳�ƻ�ˤޤǵڤӡ�̫���ʤ��Ƴ����Ȥμ����Ԥ���ʩ���ؤο����פ�����ʩ�դη�¤�ȳ��Ť���λѤ����Ƽ��롣��������ε��Ȥϰ�����褷�����̤ΰ���ʸ�����Ȥ⤤���롣
������Ǥ��ƣ���������夫���ߡ��ȼ����Ѥ���Ƥ����ܰк��η�����ܽ���ɤ�а���λ����ī�����ʶ�����̯�����̤��Ϥ˱ƶ���ڤܤ�����ʿ���Ϥ��ޤ�����ڤ��ȼ�ϩ�������Ǥ�������������ʿ��ȸ���ο���ʤ���Ȥλ��Ȥߤ���ž���Ȥ������Ȥˤϵդ餦���ȤϤǤ��ʤ��ä������䤬�����ˤǤ⤽��˴������ޤ졢�����˰�֤ˤ��Ʋ���������äƤ��ޤä������������������Фʹ�Ȥ��Ȼפ�줿�Τˡ����äȤ����֤������ˤ�ή��λ��ĥ��ͥ륮���Ϥ����ޤ�����
ʿ���ˤĤ��Ƥλ��Ϳ������ơ�
ʿ����ΰ�����Ū���������ª���Ƥ��롣����ʵ��ԡˤ���ߤ�С������Ȥ��ն����ϤȤ�������������Ω�Ĥ�����Φ�Ȥ��ǰפ�Ĥ�Ǥ����Ȥ�����������ߤ�С������Ȥ�ñ�ʤ����ܤΰ��ϰ�Ȥ������Ȥ�Ķ�������ȤȰ����դ��뤳�Ȥ�����롣Ʊ�������פ�ΰ�塢ʿ���ȸ�פ�ԤäƤ��ꡢ�Ͷ��ȤϤ������ֿ��������»���פ����ܤȤδؤ��⿿��̣���ӤӤƤ��롣
���̤�����Ȥ�����˾��������ˤ��Ƥߤ�ȡ������Ϥ��λ����طʤ��ΤäƤߤ����ʤäơ��ܽ���˼�ä����ܽ�����ܤ��������͡��ʳ��٤���ɳ��������������ʤ븦������촬�ܡ�������̤�ʸ���Ⱥǿ���ȯ��Ĵ�������ͤ��줿�������Τ������פ��ܤ��餦�������Ф��ΤФ��ꡣ�������θ����ǤϤʤ������̿�����ʬ����䤹���줿�����ܡ��ˤ狼��˰����Ȥˤϡ���ߤΥХå��ܡ���Ω���줿�褦�ʵ��ˤʤä���
�Ϥ���Ƥλֿ�ä�ס��ֿ�ä�פ�����������Ϳ����Ʊ����˥ǥӥ塼������ȤȤ������Ȥκ��ʤ��ɤ߽����Ƥ����Τä�����������ǯ�����ä��ܳ�������Ȥΰ�ͤ��ä��餷����
�ͥåȾ��ɾ���Ϥ��ʤ긷������Τ���Ω�ġ���������ʬŪ�ˤϤʤ��ʤ����⤷�����ä���
�ɤϤ�Ƥ������Ϥơ��Ȼפ蘆��롣����ʪ��Ϥ��ä����ɤ���Ϣ��ƹԤäƤ����Τ����ڡ������뤴�Ȥ˼�ʬ��ͽ�ۤϳ���ޤ��롣©���ݤ�Τ�˺��뤯�餤��ޤ��뤷��ư��Ÿ���˰������ޤ졢�����դ��Ƥߤ�ȡ��ǽ���������Ƥ�����ΤȤ������㤦ʪ��˿�Ÿ���Ƥ��������װʹߤ��ܤ�Υ�������쵤�ɤߡ����ɤߤ����̣��ǽ�����Ƥ��줿���ʤ��ä���
���������ܤϡ�����ɽ����ޡ����������פ˵����ܺ��ʡ�
�Ả��������˻ٻ�����롢�����롢���ʤȤϤɤ�ʤΤ�����������̣���勞���ƥ�ݤ�®�����ڤ��Υ������ɤ���ֽ��ҹ�����եȥ��աפ�Ʊ�͡�����̵�Τʶ�Ω�Ƥ������ӣƤäݤ��ϰ�����ꥢ���Ƥ��롣
�֥ԥ��ԥ�ư��פϤ������˥��˥�ư��Υѥ��ꡣ�˥��˥�ư��Τإ������桼�����Ǥ⤢���Ԥ����˥��˥�ư��ؤλ�����ޤ�ƽ夲���饤�ȣӣƾ��⡣�ͥåȼҲ���㤴���㤷����ߤ��¤٤��ƤƸ��ΤǤϤʤ���̥��Ū�ʤ��Ȥ��ܼ���ª���ơ�����ޤ��ӣƾ���˻ž夲�Ƥ��롣
���եȥե����Υ����ץ��������ϸ��泫ȯ�Υƥ�ݤ�����Ū�˸��夵������Ū�ʼ�ˡ�ǡ��ͥåȼҲ�β��ä���ʬ�˼�����ʬ��ΰ�ġ��ä��ơ��ܺ��ʤǤϥ����ץ��������ϡ��ɥ��������о줹�롣�����Ƥߤ�С���ʬ���Τ�ʤ��ä������Τ��ȤʤΤ��⤷��ʤ����������ޤ뤭������̣���ʤ��櫓�ǤϤʤ���������Ȥ�̵��������������Ƥ��뼫ʬ�������ͥåȤ�Ȥä�����������ˡ�ϡ���ʬ�ξ���ˤⲿ�������ǽ��������ΤǤϤʤ����Ȼפ蘆�줿��
�ԥ��ԥ�ư�褫����������Ȥ��Ƽ����鼡�ؤȱ��Τ褦��ʪ�줬Ÿ�����Ƥ����ͤϤޤ�ǥ�����������ָ��Ƥ���褦������ʤȤ����⺣�γ����˻ٻ������ͳ��ʤΤ��⤷��ʤ���
����������á����ܿ����Υ롼�Ĥ����̤ΰ��ܻ���Ȥ����⤬���롣�����ν�������ܻ��Φ���˶�������Ϥȷ��Ǥʴ��פ���İ�²�Ǥ��ä������ܻ���ΤȤ�ī��Ȥ���Ȥʤꡢ����ǯ����Ǹ�����Ԥ줿������������²�����Ǥ��Ȥ졢���ܻ���λҡ����ܽ�Ǥ�ϰ�ͽ����ή�Ȥʤ롣���η��ߤ����ΰ��ܻ�ؤ�³���Ƥ��롢�餷�������ܻ��꤬�ܻؤ����Τϳ��ڡ����٤Ƥ�̱�Τ���ι�¤�ꡣ����ʥ롼�Ĥ�����˻��İ��ܿ������������ä�Ǥ�˽������Τ⤵�⤢��ʤ�Ȼפ��롣���������ֲܰФ���ϼ�뤬�ݡפȤ���Ƥ����ˤ⤫����餺���������꤬������Ȥ��Ƥ������ˡ�ƤϤɤ��ˤ⤽��Ȥϵդ������˸����äƤ����̤��ݤ�ʤ��������Ϻ��������Ĥζ�����衼�����ߤ���ƻ��������äƤ�餤��
ʪ��ϰ��ܻ��꤫��Ϥޤꡢ�Ҥ���Ǥ��̼̻��ƣ����������濴��Ÿ�����롣����ǯ���廰ǯ�����Фơ�����ƣ�����ʪ��ؤȿ�ܤ���ƣ���ٹդλ������Ĥ��롣���饤�ޥå������軰���η�����������Ǥ��ƣ������������ʺǴ������θ��б���������ȸ���Ȥι��ɤϤ����ΤΡ�����Ͼ��Ȥˤ�����褦�ʤ�Ρ������ƻ���ϷФơ�ʪ��ϱ���ƣ����αɲڤؤȰܤäƤ��������ա���ա����ա��ٹդؤ�Φ�����ȼ�ϩ������ߡ�ʿ�����濴�Ȥ������̤˰����Ȥ��ۤ������롣�����ʿ�¤κ����Ĺǯ�ܰФ�̴�������ۤι�η��Ǥ⤢�ä��������������Ф˻פ�������ʻ���⡢��ä��礭�ʻ���Τ��ͤ���ݤߤ��ޤ�Ƥ��ޤ���ī���ʣ������ʸ����褤�Ȥ����ޤä�ʿ�����δ��������äƸ������Ƭ��ʿ�������Ф�ޤ����Ф����é�뤳�ȤˤʤäƤ��ޤä��᱿�λϤޤꡢ�ܤ˸����ʤ����Ƴ���줿��̿��������ƣ���ٹդϡֲܰФ���ϼ�뤬�ݡפ�Ӥ��̤�����ī���Ԥ����ˤϤʤ��ΤΡ�Φ�������������ޤʤ�����ǤäƽФ롣�����˰�Ĥλ��夬����Ĥ��롣
�ֲб�ס����οءסֱ�Ω�ġפ��ɤ߿ʤ�Ǥ��ơ��ܺ��ʤ�����˻�ꡢʿ�ᡢ��ī�����硢���Ф�����˾夬�äƤ���ȡ���̣��ñ������̤˴�פ�����ʿ�¤��������˻����夽�Τ�ΤؤȰܤäƤ��������Ф餯�Ϥ����˥ϥޤäƤߤ褦��
���̤˶�̣��̥�����褦�ˤʤä��ΤϤ��Ĥκ�������ä���������
���֤�����Ҿ�Ρפ˻Ϥޤ��¼�����Ŀ���������ɤ�Ǥ�����������Ȼפ������̡�����⤽�κ���ü�˵�������Ϥȸ��Ϥ���Ĺ�²�������Ȥ����Τ��ä��ǤȤƤ⿷�����ä����Ŀ��˹�²�����Ƥ�ʤ���ԻĤǤϤʤ��Τ���������ޤ����̻ˤˤĤ��Ƥϳ��ܤȤ����������˶ᤤǧ������äƤ��ʤ��ä�����������������Ū�ʥ�������Ŀ���Ƭ����ˤ��ä�������
�ä��ơ������ܷҤ���ǥޥ������ʤ˽в����줬��ëã��˷Ҥ��ꡢ�֥��ƥ륤�פؤȷҤ��äƤ��ä����֥��ƥ륤�פϹⶶ��ɧ�����̥�����˷Ҥ��ꡢ�ֲб�ס������ƺ������οءפ�é��Ĥ�����
���������������Ρ���������פǤϡ��פλ��塢�»���ȱ���ƣ����θ�פξ��̤���Ĥ�ʪ����������ʪ�����Τ�٤��Ƥ�������Ȥ�ȱ���ƣ����α�ã�˵���Ȥ�������̣�����äơ�Ĺ���ּ�ʬ����ˤ����֤äƤ��ơ����Ĥ�����ˤ���ȻפäƤ����������ˤ��ƤΡ���������ס��ޤ��ޤ���ʬ�������������Υ������ȤϽŤ��ʤäƤ��ä���
����ˡ��ⶶ��ɧ��������������ë�ץ�����ϰ������餪��������ΰ�Ĥǡ��������о줹������¼��Ϥ�餬��������������äƤߤ����ä��Ȥ������Ȥ⤢�롣�ֲб�ס����οءפ��ɤ߽����ơ��⤦���١�����ë�פ��ɤ�ľ���Ƥߤ����ȻפäƤ��롣
���ơ������οءס�
�����ޤǤϤۤȤ�ɵ��������ʪ�줬Ÿ�����롣�ܰФǤ���ʤ�����˿��������ƻ������ʪ����Ⱥ�崣����Ϥ��ä��������ब�����θ�����ī�ƣ������Ϥ��ȸ��Žѿ����٤�������깭���롣���פ���ϲ���ƻ�����о줷��ī��θ���Ʈ���ʣ�����������Ƥ��롣���������äƤ���ʪ��ϰ쵤�˲�®���ܰФ�ī��Ȥϰ�����褷���ȼ�ϩ����Ӥ��Ȥ����פ������Ĥġ�ɽ�̾��ī��˶��礹��������Ƥ�������ī��Τ��ޤ�ˤ�ܰФ��λ뤷����ư�����ԿԤʾ夫�����������٤ˡ��Ĥ��˴�Ǧ�ޤν郎�ڤ�롣�ץ饤�ɤ���Ĥ���줿�ܰФ�����Ϥ���濴�˷赯��ޤ롣
�ֲб�פ�������Ȥʤ�ʪ�졣
���������礭�������Ƥ����٥��ȥ��顼���٤ޤ��ʤ����ɤ�Ǥߤ���
��¼����ˤ��ù���������դȤ������ʤ������Ĥ����뤬�������Ϥɤ��餫�Ȥ����Х������ɥå����ʺ��ǡ������̣��¼������ޤäƤ���Ȥ⤤��������Ϥ���Ȥ��ư�ĤΥ����ƥ����ȤȤ��ƽ�ʬ�ڤ����Τ��������κ��ʤϤ����Ȥϰۤʤ뿷����ɮ�פ����ݤ˻Ĥä���
Ʊ����ʤ��ڤ��äƤ⡢������ˤ�äơ���Ȥ����ޤ��ä�����ˤ�äơ����������Ѥ�äƤ��롢�����ˤ��λ���˹�ä����ʤ˻ž夬�äƤ��롣���夬�ߤ��Ƥ�����ʤ����ޤ�Ƥ��본������ɬ����������
��¼������ʤδ��ۤǤ�줿���������ߡ������и������ͤϹ����ã����������������ľ�ܤ����θ��̤�ʹ�����ȤϤ���������ʤäƤ��Ƥ��롣�켡����ۤɵ��Ťʤ�ΤϤʤ������Ȥ��äơ���������뤳�Ȥ�����Ȥʤ�С�����Ȥ��Ƥ����˸����˻Ĥ��Ƥ�����������Ǥ��ꡢ���κ��ʤϤ���������̣�Ǥ���ۤ������ʤȤ����롣
�Ǹ����ɤ�Ǥ��֤��ˤϰ��ܼ��줿���ʡ��äƴ�����
ʸ���Ǥˤϻ䤬�ɰ����Ƥ�ޤʤ�����������β��⤬�ܤ��Ƥ��롣�饸���Ǥ褯���ˤ��Ƥ��������ʤˤ������붽ʳ�ȼ�ʬ�ε���������ľ��ɽ��������̤���θ��֤꤬�ɤäƤ��ơ�������ҤȤ����Ǥ��ä���
����Ϥ����ޤǺ���ΤǤ��äơ������˽�Ƥ��뤳�Ȥ�ɬ�����⸽�¤Τ��ȤǤ���Ȥϸ¤�ʤ����Ȥ������Ȥ�Ƭ�Ǥ狼�äƤ��Ƥ⡢�Ҳݤ������դȤ��Ƥ�����ʤǤϤ������٤ο��������ʤ�������ߤ�Ⱦ�����Ƥ��ޤ���
�ܺ��ʤ�ʸ���̤ꥤ��ɤ����档����ǽ�徽ȯ������ǤȤʤ����٤ο徽���кν��������դȤ���ʪ����̤��ƥ���ɼҲ�ȥ���ɿͤ��Τ�Τ˾��������ƤƤ��롣�����ˤ��줬���Υ���ɤλѤʤΤ��Ȼפ蘆�����̤�����Ǥ⤫����Ǥ⤫�ȸ������餤�ФƤ��롣��Լ��Ȥ�����ɤ��뤤��ȩ�Ǵ������θ�����ˤʤäƤ���Ȼפ��Τ����������ޤǥ���ɤȤ�������ԲIJ��ʸ�������Ƥ���Τ��ȻפäƤ��ޤ���
�䤬�����ˬ�䤷�����ʤ顢����ϣ���ǯ�����Τ��ȡ����ʤ�������Ƥ��륤��ɿͼҲ���ԲĻĤ�����ľ���������Ȥ��Ǥ�������ʬ�⤽����ܤ�������ˤ������Ȥ����ä�����������������ܺ��ʤλ�������Ϥ��ʤ긽��˶ᤤ����Ƭ�˽�����θ�§���������Ȥ���ʤ顢�����䤬�������ԲĻĤ��������Ѥ��ʤ��Ȥ������Ȥˤʤ롣
������Ҥϲ桹���������ʤ�ʸ����������¸�ߤ��뤳�Ȥ餱�Ф�������ʸ���Ȥζ�¸��ơ��ޤȤ������ʤ����դ��������ȥ������ȤȤ�����������²̱���Ỵ�����褬�������������졢����Ȥ������դ���½�˻פ��Ƥ��ޤ��ۤɤθ��¤������ˤ��뤳�Ȥ�פ��Τ餻�Ƥ��줿��
����եȥ�ǯ�嵭�������
���꤬��B�塡��������졡��������������������衡����ס��ʤΤ˲��Τ����ˮ��ˤʤäƤ��ޤ��Τ����ɤ�Ǥ���и���������äζڤ˹�äƤ���褦�ʵ������롣�Τ��˳����Ȥ�������դȤʤäƤ���Ȥ������Ȥ��碌���Τ���������ɡ�������ˮ�꤫��Ϥ����ˤ���������Τ褦�ʥ�������פ��⤫�֡���������ʪ��Ū�ˤϤ���ޤǤλ���Ʊ�ͥϥ�ȥ��ޡ����㥤�륺�����ˤϻ������礭�ʤ��꤬ͤ�Ԥ������Ƥ��롣
�ϥ���ʤ�Ȥ��Ƥ��ʤ�褦�Ȥ��밭��μ�ٹ�ʹ��⤬����μ�̮������á���Τᤵ��Ƥ⤿���Ǥϵ����ʤ�������ɤ������ߥ�����ƨ�졢�ޤ����δ�Ƥ�Ф��Ƥ��롣�ϥ��Ϥ������Ф���¿���οͤ����λ٤��ȼ�����ηäˤ�ä�Ω����������
�Ϥ�Ϥ�ɤ��ɤ����ɤ��ʤäƤ����Τ��������ƶ��Τ����褦�����ž��ϥ����ƥ����Ȥζˤߤ���
�����ƥХ��ȥ��α�̿�����緿�����ν���ҳ����ϥ�ȥ��ޡ����㥤�륺��̵������ڤ뤳�Ȥ��Ǥ���Τ�����äѤꤳ���ϡ�B�塡��������졡��������������������衡����פ�������
����եȥ�ǯ�嵭���軰����
��������������ɤ�Ǥ��餷�Ф餯���֤����äƤ��롣�ɤ���ä��ä��������Ф�����ʬ�ν������δ��ۤ��ɤ���ꡢ�ͥåȤǤν�ɾ��ߤ��ꤷ�ơ�����ä��������Ƥ����ܺ��ʤ��פ������Ϥꡢ�ɤߤ�������ߤޤ�ʤ���
���Ѥ�餺�ɼԿ��������Ω�ơ��ϥ�ȥ��㥤�륺�ϼ����ȹߤ꤫��������ޤ��ڤ�ȴ���Ƥ��������㥤�륺�������ˡ�����ξ��̤Ǥμ�˴��ˤ��빶�ɤȤ��������ϸ���Ρ��դȤ�����������ʪ��Ϥޤ��̤λ�ʬ���줬����Ƥ��ޤ������Լ��Ȥ��ä�Ÿ������ƽƤ���櫓�Ǥ�ʤ������ʵ������롣�����ɼԤ��褬�ɤ�ʤ���
�軰������ϡ��ϥ�ȥ��ޤλҶ����������Х������ȥ�����������ʪ�줬�ä�äơ�ǯ�嵭�ϼ�����ؤȰ����Ѥ���Ƥ�����
���������ʴ����Ƥ�����֤�����ϡ֥ɥ�����ס�
�ȥࡦ������κ��ʤ���Ǹ��������������������Τ����ä������ΤȤ��ϡ֤���ʤ˴�ñ�˺����ΤʤΤ��פȻפä���Τ��ʥץ�ȥ˥���䤽��ʤ���������������ɬ�פǤϤ��ä����ˡ����줫���ǯ�⤿���ʤ������Ρ֥ɥ�����פνи����ɣԵ��Ѥο��⤬�����������Τ���¾�ε��ѳ����������Τ���̵��������Ե��Ͼ������̲������οʲ�����������������²���ï�Ǥ�������뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ƥ��˰��Ѥ��褦�Ȼפ��н���ʤ����ȤϤʤ���
���ɤ�����˷ٲ����Ƥ���Τ�̵���Τʤ��á�
�ܺ��ʤǤϥɥ����������˥���ꥫ��̵���ⵡ�����Ԥ����Ѥ���롣������С�����ˤ�äƥ���ꥫ¦����Ĥ�̵�ϲ������ƥ���ƻ��Ȥ��ƥ���ꥫ�˹����ųݤ��롣
������ֶ��ҡפ��оݤȤ��Ƥ�������夲������ޤǤΡ֥�����భ��ס֥ۡ��॰�������ƥ��ꥹ�ȡ�ϩ���Ȥϰ�����褷�Ƥ��롣
ʪ����������Хå����饦��ɡ����Υ����С�����ˤ�ʪ������̤���̩�ǡ��ȥࡦ�������������ǡ�Ȥ��ä��Ȥ������դ�դ�Ȱ����Ĥ�����褦�ˤ����ɤ�Ǥ���������Ǥ����ȥࡦ������Ȼפ����Ȥ����ꡣ�饤�����������ȤΥۥåȥ饤��Ǥ��ɤ߹礤�⸫��Ρ�
����˥����괬��ʪ���饤���������������Ǥ��ơ����顼��������٥��˥ᥢ�ꡦ�ѥåȤ��о줷���ãɣ��װ��ΤϤ�Ϥ餹��ʪ���ä�äơ����⤷�����Ƥ�����κ��ʤǤ��ä���
���Ф餯�ȥࡦ��������ɤ�Ǥ��ʤ��֤ˡ����������Ⱥ��ʤ��Ф���Ƥ����褦���������⡢�ȥࡦ������ϣ�������ǯ��¾�����Ƥ��ޤäƤ������⤦����å����饤����ȤϤ��ܤˤ�����ʤ��Τ��Ȼפ��Ȼ�ǰ�Ǥ��ޤ�ʤ�������ɤ���֥ƥ��ꥹ�Ȥβ�ϭ�פ�Ϥ���Ȥ��ơ����ϻĤ��줿���ʤ��ɤ�Ф���ȤʤäƤ��ޤä���
�֥��������ѥ��ץ�������ϤޤäƤ��顢����ޤǥ���å����饤��������ݤäƤ����ֻפ����ޤ��������ڤ�Ƥ��ʤ��ä��������������ʤ��ʤȻפäƤ����������顼���䥷��٥�����о���̤�¿���ʤäƤ��ơ�������ɡ��饤����ե���ˤ��ԤäƤ���Ÿ���Ȥʤä���
�ä˥��顼���γ�����������������å����Х��ĥ����Զ���Ʈ�֤�����������ʪ�����äѤäƹԤ����饤����ȥ�����ƥ�������������ʪ�������ơ��ե����ӥ��⤿�äפꡣ
���������פˤ��ơ�������褢��������Ƥ���ʪ��ΰ°פ�����ǰ���ä���
�����Ƭ�˥��ĥ������Ϳ�����ֿ�ۤ�����ס��Ϥ���������ܤϤ����ˡ�
�ֽ�Ƥ������˿�����������Ϥ��������Ȥ�����ή�˿�ʬ���Ԥߡ�ĺ��ʤ���羾�ο��Ф����䤫�����Ѥ˰�Ĥ����Ĥ���褦��Ϫ���Ӥʤ����㤯�Ť���ë�֤��礤����Ƥ�����
�Ȥ����Ф�������ʪ��ϻϤޤ롣���줬�����˥ե������ʤΤ��Ȼפ��뤯�餤�����ޤ�ˤ�ʸ��Ū�����������
�ϰ�����Ϥʤ�Ȥʤ��衼���å����ʤΤ��������λ˼¤������Ƥ��뤫�Τ褦�ʡ��ʤ�Ȥ��ԻĤ��������������ߤ��ýѤ���̩����þ�Τʤ���Ω�ơ������������ưŪ��Ÿ�����ܺ٤ʾ�����̤ȿ������̡����٤Ƥˤ����ƹ������κ��ʤ��٤�Ķ���Ƥ��롣
�ǽ�ϥ������ʤǽ줿�о��ʪ��̾�����ʤ��ʤ�Ƭ�����äƤ��ʤ����Ϥơ������Ĥϡ֤������פ��ä����ְ����פ��ä��������������ꤵ�줿����ȿʹ����ͤ⤫�ʤ�ʣ���������դ������դ��ƼϤʤ����ߤǤ���������Ƥ��롣�ɤ����Ƥ���ʤˤ⼡���鼡�Ȥ��餹�餪�⤷����ʸ�Ϥ�ͯ���ǤƤ���Τ������������ڤ���Τ��������̥�Ϥΰ�ġ�
��ʰ���ǿʤ�Ǥ���ʪ��ϡ����פ���ư쵤�˽���ؤȲ�®�٤������Ƥ������ͤ�ν��ߤϤ����ɮ�����夬�롣�����߹��ޤ���Ÿ���ϵ���Ʋ�����ʤ����롣����������С�����Ʋ������ʤ��ʤäƤ���פ�������γ�����ޤ��ߤƤߤ����Ȼפ��Τ��ä���